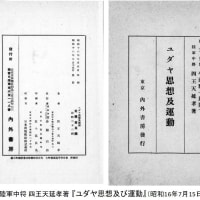大川周明 『頭山 満と近代日本』

頭山 満 (ウィキペディア)
五
明治十九年の春、頭山翁は福岡に於て荒尾精の訪問を受けだ。翁は一見して荒尾の尋常人に非ざるを知つた。翁は後年此時の会見を回想して 『当時静に思ふに、天は五百年毎に一大英傑を下すと聞いたが、 荒尾は確かに其の人物なりと信じた」 と言つて居る。
荒尾は安政五年、尾州藩士で百石取りの家に生れたが、彼の父は明治初年家族を伴ひて上京し、麹町に荒物屋を始めた。士族の商法の例に洩れず、やがて商売は悉く失敗し、其日の米塩にも窮するに至つたので、両親は妹三人を女中奉公に出し、長男精だけを連れて場末に移転することにした。然る荒尾の隣家は当時警部を勤め、後に栃木県知事となれる菅井誠美といふ薩摩人であつたが、事情を聞いて痛く同情し、精を引取りて書生とし、元園町の私塾に通はせた。
やがて菅井は本郷警察署長に栄転したが、時偶々征韓論が台頭した頃で、年少純一なる荒尾の精神も之によつて深刻なる印象を受け,夙(はや)くも此時から荒尾は支那問題の研究を志した。菅井は荒尾の志望に同感し、外国語学校に入れて支那語を学ばしめ、夜は鈴木といふ英漢数の塾に通はせ、また菅井自身が剣道の達人であつたので、熱心に撃剣を教へた。其上菅井は西郷隆盛の知己を得て居たので、西郷に依頼して荒尾を書生に置いて貰ふことにした。
荒尾が大西郷の偉大なる感化を受けたことは言ふまでもない。当時西郷は陸軍大将兼参議でありながら、其の生活は質素を極め、小さい家の屋根は所々破損し、雨降る毎に雨漏りがして居た。或夜夫人は西郷に向つて、畏(かしこ)きあたりより恩賜の金の一部で屋根の修繕をしたいと願つた時、西郷は今日本の国に雨が漏つて居る、日本の屋根を繕ふのに何程金が要るかわからんぞと言つて其願ひを斥けた。
之を聴いた荒井は電光に打たれたる如く感じ、後に此事を頭山翁にも告げて居る。西郷が征韓論に敗れて故山に帰つてから、荒尾は再び菅井の門に復つたが、明治十一年菅井の同意の下に、外国語学校を去りて陸軍教導団に入り、十三年更に陸軍士官学校に入り、十五年卒業して陸軍歩兵少尉となり、熊本鎮台第十三連隊付となつて赴任したのが、二十四歳の時である。
熊本時代の荒尾少尉については、鳥居素川が日本新聞に掲げた文章が、最も善く彼の面目を彷彿させる―― 『荒尾君その隊に在るや、勤務に精励、士卒を愛撫、最も徳義を尚び、士風を砥礪(しれい)するに努む。青年将校靡然(びぜん)その風に向ひ、各自気節を以て相戒め、遂に全連隊の美風を成すに至る。
当時さきの遣清留学生たりし御幡雅文の職を熊本鎮台に奉ずるや、荒尾君乃ち請ふて官舎を共にし、隊務の余暇支那語を学習す。
君は毎日牛豚肉一斤、酒五合を用ゐ、居常(きょじょう)木綿檳榔子(びんろうじ)染の紋付を着用、伝習録を愛読して精神を鍛錬し、また柔術及び居合術を学び、夜もその定規を廃せず、居ること二年、英名は啻に営中のみならず熊本全市に響轟し、児童走卒もまた皆君の人格を敬慕し、群児の相集りて嬉遊するや、西郷大将に擬するに非ざれば、即ち肩を張り潤歩しながら、俺は荒尾少尉ぢやぞと傲称(ごうしょう)するに至る。』
荒尾は熊本連隊に在ること二年にして、参謀本部支那課勤務を命ぜられて中央に向つた。彼は参謀本部にありて熱心に支那研究を続けたが、明治十九年四月、宿願叶ひて陸軍中尉の現職のまま参謀本部から支那に派遣された。
その頭山翁を訪ひたるは、恐らく乗船のために長崎に赴く途中である。翁は荒尾が重厚荘重なる態度風采で、沈着雄弁に東方問題を論じ、殊に西洋対東洋の問題について偉大なる抱負経論を吐露するを聞き、当時是くの如ぎ雄渾なる方策を有する者は独り此人あるのみと敬服し、爾来交りを深くするに及んで愈々其の人物に傾倒し、大西郷以後の第一人の推称した。
既に述べたる如く、近代日本の先覚者は、単に日本国内の政治的革新を以て足れりとせず、近隣諸国の改革をも実現し、相結んで復興亜細亜を建設するに非ずば、明治維新の理想は徹底すべくもないと確信して居た。
それ故に維新精神の誠実なる継承者は、実に燃ゆる熱情を以て隣邦のことを自国のことの如く考へて来た。頭山翁は 『南洲先生が生きて居られたならば、日支の提携なんぞは問題ぢやない。実に亜細亜の基礎はびくともしないものになつて居たに相違ないと思ふと、一にも二にも欧米依存で暮らしてきた昔が情ない』と長嘆したが、其の大西郷は実に下の如く言つて居た―― 『日本は支那と一緒に仕事をせねばならぬ.それには日本人が日本の着物を着て支那人の前に立つても何もならぬ。日本の優秀な人間は、どしどし支那に帰化してしまはねばならぬ。そして其等の人々によつて支那を立派に道義の国に盛り立ててやらなければ、日本と支那とが親善になることは望まれぬ。』 大西郷の此の精神を、最も誠実に継承し、また最も熱烈に実行せんとせる者は、実に荒尾精其人である。
試に下に掲ぐる荒尾の文章を読め――
『欧亜の両陸は東西文華を異にし、黄白の二色は本来その種族を同じくせず、所謂西力の東漸なるものは、直に二者の競争を意味す。されば朝鮮の貧弱は仮令朝鮮のために之を憂へざるも、深く我国のために憂へざるべからず、清国の老朽は仮令清国のために悲まざるも、痛く我国のために悲まざるべからず。
苟(いやし)くも我国にして綱紀内に張り、威信外に加はり、宇内万邦をして永く皇祖皇宗の懿徳(いとく)を矒仰(せんぎょう)せしめんと欲せば、先づこの貧弱なるものを救ひ、この老朽なるものを扶け、三国鼎峙し、輔車相倚り、進んで東亜の衰運を挽回してその声勢を恢弘(かいこう)し、西欧の虎狼を贋懲してその覬覦(きゆ)を杜絶するより急なるはなし。是れ誠に国家百年の大計にして、又目下一日も忽諸(こつしょ)に付すべからざるの急務なり。』
『顧(おも)ふに印度の一たび覆亡の禍を履(ふ)みしより、東方の故国旧邦は漸次豺狼(さいろう)の食餌となり、今や我が帝国を除くの外には、僅に支那朝鮮の二国を剰せるのみ。その貧弱を極めて未だ絶滅せず、老朽を極めて倒驚せず、尚一線一脈の気息を通じて、宗廟社稜を至危極難の境に維持しつつあるもの、抑もまた天意の東方亜細亜を厭棄せざるものありて存するに由るか。天に順ふものは存し、天に逆ふものは亡び、大に従ふものは成り、天に背くものは敗る。豈深く顧みざるべけんや。』
『何をか天意に順ふと謂ふ。曰く他なし、彼の貧弱なるものを救護して富強ならしむる是のみ。彼の老朽なるものを釐革(りかく)して壮剛ならしむる是のみ。此事や実に我が帝国の天職なり、天に順ふの責務なり。』
荒尾の是くの如き雄渾高明なる精神は、至深の感銘を頭山翁に与へたに相違ない。彼が支那に渡りて活動を開始するや、その本拠たる漢口楽善堂の二階に掲げたる綱領は、下の如くであつた。
曰く 『吾党の日的は、東洋永遠の平和を確立し、世界人類を救済するに在り。其の第一着手として支那の改造を期す』 と。 而して同志を四方に派して普く人物を萬域に求めさせるに当りては、人物を君子・豪傑・豪族・長者・侠客・富者の六類に分ち、君子を更に六等に分ちて下の如く教示した。
道を修め全地球を救ふ 第一等
道を修めて東洋を興す 第二等
国政を改良して其国を救ふ 第三等
子弟を鼓舞して道を後世に明にす 第四等
自ら朝に立ちて国を治む 第五等
独り自淑して機の至るを待つ 第六等
荒尾は是くの如き精神を以て支那に活動した。彼の同志は一切の困難を忍んで四方に旅行し、支那内地の調査に従事した。而も支那問題の解決は、少数志士の結盟だけで実現せらるべくもない。一応支那の事情を審(つまびら)かにした荒尾は、日支両国が提携して相互の富強を図り、西欧諸国に対抗するに足る実力を養ふためには、先づ両国の貿易を振興せねばならぬとし、此の目的のために日支貿易に従事すべき土魂商才の人物を養成するのが急務であると考へ、滞支三年の後、上海に日清貿易研究所を設立するの案を携へて帰朝した。
彼は啻に支那の事情に精通せるのみならず、熊本連隊時代より彼を知れる佐々友房が 『別人と思ふほど人物を上げて居た』 と感嘆したほど、滞支三年の間に人物識見は磨き上げられ、東方志士の棟梁たるべき態度風貌は一層堂々たるに至つたので、其の朝野の間に遊説するや、先づ時の首相黒田清隆、蔵相松方正義、農相岩村通俊の賛成を得、研究所創立に対する補助金を与へられることになり、次で全国に巡歴して東亜の形勢を説き、日清貿易研究所創立の趣旨を陳べて人物養成の急務を叫び、甚大なる感激を各方面に与へた。
時恰も国会開設を目前に控へ、世を挙げて政論に熱狂して、支那問題などは殆ど顧みる者なかりし頃とて、荒尾の演説は各地で異常なる反響を喚び、研究所入学を志願する青年は五百余名に達したが、詮衡(せんこう)の結果百五十名を採用することとした。
然るに一切の準備整ひて将に上海に出発するばかりになつて、政府の補助金交付困難の事情が生じ、荒尾は進退谷(きわ)まりて遂に自殺を決心したが、参謀次長川上操六の同情により、四万円の補助金を入手することが出来たので活路が開かれた。
而して川上を動かすに与つて最も力ありしは、士官学校以来彼の莫逆(ばくぎゃく)の友であり、今や軍職を辞して荒尾と行動を共にし、支那問題に一生を捧げんとする根津一の努力であつた。
かやうにして明治二十三年九月、東亜同文書院の前身たる日清貿易研究所が上海に創立されたが、開校以来常に経営のために苦心惨憺しなければならなかつた。極度に困難なる財政事情が生徒間に漏れて動揺を生じ、三十余名の生徒に退学を命じたこともあつたが、一切の苦境を切抜けて、明治二十六年六月、八十九名の卒業生を出した。而して前年には根津が編集の任に当りて、二千頁に余る清国商業総覧が発行された。
かくて研究所の価値が漸く世間に認められ、上海には日清商品陳列所の建設をも見るに至つたが、開所後一年を経ずして日清戦争の勃発を見、荒尾の事業は一時中止せねばならなかつた。
荒尾が研究所の経営に窮して金策のために上京する毎に、彼の最も障意なき相談相手は頭山翁であつた。時々は小遣にも困つて翁に無心に来た。翁は 『君の風貌は恵美須と大黒を一身に兼ねたやうであるが、恵美須や大黒にも貧乏恵美須・貧乏大黒があると見える』 と椰楡しながら欣然として用立てた。或は三千円の金が至急入用だと言つて翁を其の旅館に訪ねた。
貧乏は翁も荒尾に譲らなかつたが、いろいろ心配の結果、或る高利貸が確実な人間が連帯の印を捺すならば之に応ずるといふので、翁は鳥尾小彌太に頼むことにした。時に鳥尾は熱海に居たので、両人は東京を出立しだが、途中で鳥尾と逢つた。
よつて茶屋の二階で此事を話すと、鳥尾は金の出処が何処でもよければ、井上馨から借りてやらうと言ふ。頭山翁は、金は天下の廻りものだ、聞多の金でも何多の金でも構はないと言つて、其事を荒尾に話すと、荒尾は、井上ばかりは御免だと言つて断はつた。それは井上馨が、荒尾と別懇の間柄なる川上操六と面白からぬ関係に在つたためであつた。
曩(さき)に荒尾が日清貿易研究所創立のために帰朝して九州方面に遊説した時、筑後西郷と呼ばれし林田守隆は 『世を挙(こぞ)つて政論に熱狂しつつある時、荒尾氏が東亜の形勢を説きて之に対する国民の覚悟を促すを聞き、恰も義兵が起つて来たやうに感じた』 と言つたとの事であるが、恐らく頭山翁も同様に感じたであらう。少くとも荒尾との親交が、翁をして一層大なる関心を東亜問題に抱かしめるに至つたことは疑ふべくもない。
此の偉大なる先覚者は、日清戦争後、支那の無力一朝にして世界に暴露せられ、欧米列強の関心一に東亜に注がれ、やがて非常なる危機を招来すべぎを逸早く洞察し、此の危局に対する方策の第一着手として日清経済同盟を結ぶの必要を説き、時の松方蔵相の賛成を得て、明治二十九年一月上海に赴きて戦後の事情を視察すると共に、支那の大官巨商に経済的提携の必要なることを勧説(かんせつ)し、一旦帰朝して日本の朝野に日支提携の急務を警告し、同年八月台湾及び南支那を巡歴して将来の施設に資せんがために渡台した。
彼は新領土台湾に於て内地人と島民との融和を図るために紳商協会を創立し、将に南支那に渡りて抱負経論を行はんとしたが、乗船の前日不幸にもペストに罹り、十月三十日、その貴くして短き三十八年の生涯を了へた。彼が臨終の床上、昏々悪熱と戦ひながら遺せる最後の叫びは、実に 『ああ東洋が……東洋が……』 といふ荘厳にして悲壮なる言葉であつた。
さて頭山翁が荒尾と相識つたのは明治十九年であるが、其の前年に初めて金玉均と会ひ、爾来朝鮮問題に肝胆(かんたん)を砕くこととなつた。翁は一見して金玉均が非常の人物なることを看破し、後年彼に就て下の如く語つて居る―― 『世の多くの才子は大概身体の弱いものであるが、金玉均の如きは実に異例の傑物であつた。あれだけの才子でありながら、身体の強壮なること、その実物を見た日には、誰でも驚くのであつた。色の白い、顔の大きい、そして身丈の高さから、骨組の頑丈さからして、一見壮士の如き観があつた。その上に例の酒々落々たる風格と、滔々懸河(とうとうけんが)の弁、人を外らさぬ話術と来ては、大抵の者は屈服するのであつた。詩文・書・骨董・彫刻、何でも来いだ。趣味としては碁・玉突きなどで、碁は犬養よりも少し強かつたらう。』
明治九年江華湾条約の成立によつて、目韓両国の修好通商を見るに至つたが、彼我の国状は充分に諒解されず、相互の往来も稀であつた。当時朝鮮では閲氏一族を中心とする事大党が、支那に頼つて勢力を保持して居たが、年少気鋭の金玉均は、日本が維新の大業を成就して国運頓に興隆せるを聞き、一たび日本に渡りて其の実状を視察し、日本の援助によつて政治的革新を行ひ、多年国内に浸潤せる支那勢力を駆逐して、完全なる独立を確保したいと考へ、明治十三年の夏、初めて日本に渡来した。
彼は当時二十六歳の青年で既に内務大臣に相当する堂上戸曹判書の重職に在つたが、仏教興隆といふ名目で来たのである。東京では福澤諭吉が満腔の同情を以て親切なる指導と激励とを与へ、朝鮮復興のためには人材の養成が第一の急務なることを説いたので、金は大なる希望を鼓吹せられ、再会を約して帰国した。
彼は幾くもなく数十名の留学生を送り、その指導監督を福澤に一任し、福澤は留学生全部を自己の広尾の別邸に収容して之を指導した。而して翌年には朝鮮の官界其他より選抜された一団の人士が日本視察のために渡来し、日本の国情を見て其の進歩に驚き、帰来範を我国に採つて国政の改革を期するに至つた。
然るに翌明治十五年十月、大院君が兵士を煽動して乱を起さしめた壬午の変あり、朝鮮は日本に謝罪使を派遣することとなつたが、選ばれて使節となつだのが金の同志朴泳孝であり、金もまた一行に加つて来朝した。
彼等は正式の使命を果たすと共に、わが朝野の有力者を歴訪し、日本の援助によつて国政の革新を図り、支那勢力を朝鮮より駆逐したいといふ希望を陳べた。此の希望は少からず我が朝野の有力者を動かした。金と親交ある福澤は、彼等の運動に最も深き同情を寄せ、彼等の計画に対して種々なる助言を与へた上、彼等を後藤象二郎に紹介し、共に後援者として尽力した時の外相井上馨は、後藤・福澤等が援韓のために奔走しつつあるを見、寧ろ機先を制するに如かずとして、俄に対韓政策を定め、公使竹添進一郎をして金・朴等の独立党を庇護させ、壬午の変の償金残額四十万円を棄揖して彼等の運動に資せしめた。閲氏一族及び清国公使は之を知つて備ふる所あり、物情騒然たるに至つた。
既にして明治十七年十二月四日、金・朴等は兵を発して関一族を撃ち、王宮を擁して号令し、回天の業、朝にして成れるかの観あつたが、蓑世凱が清兵二千を率ゐて王宮に迫り、竹添公使が挙措宜しきを失つたために、独立党の事業は夢よりも果敢なき結末を告げ、金・朴等は日本に亡命した。頭山翁が金玉均と初めて会見したのは、彼等が此の甲申の変に失敗して日本に来り、金は神戸に流寓(りゅうぐう)して居た時のことである。
朝鮮の政治的改革は、日本政府の黙諾の上で行はれたものであり、金・朴等は一敗地に塗れたとは言へ、日本に亡命し来れば政府の庇護乃至厚遇を受けるものと期待して居た。然るに政府の彼等に対する態度は冷淡を極め、井上外相の如き、金が幾たび訪問しても絶対に面会を謝絶した。
此事を知りたる民間志士の同情は翕然(きゅうぜん)として彼等の上に集まり、彼等を援助して事を朝鮮に起し、其の政治的革新の志を遂げしめんとするものあるに至つた。先づ自由党員大井憲太郎・小林樟雄・新井章吾・稲垣示・磯山清兵衛等は、窃(ひそか)に資金を集め、爆弾刀剣を備へ、同志約六十人と共に渡韓して事を挙げんとしたが、明治十八年十一月、事露はれて縛に就いた。
同志の中には二十一歳の女性景山英子も居た。彼等の精神は、大井憲太郎が法廷に於てなせる陳述に尽きて居るが、彼は其中で下の如く言つて居る――『我々は日本人なるも、身を朝鮮人の位地に置き、朝鮮の社稷(しゃしょく)を危からしめんとする蠹毒(とどく)を除かんとして奮起せるものである。
成敗もと天に在り、狂と呼び愚と呼ぶも、唯だ他の評に任ずれど、我々は自ら許して義軍と称し、成敗利鈍を顧みずして、之を全国の有志に図るや、志士奮躍、袂を振つて之に投ずること、響の風に応ずる如くなりしもの、是れ真に人為の然らしむる所にあらずして、天意に出でたるものとなすも、人誰か之を不可なりとせんやである。
加ふるに有志の士はみな貴重なる生命財産を顧みざること土芥(どかい)の如く、父母兄弟を後にし、鶏林の鬼と化するを期し、三尺の剣に倚(よ)り、風粛々、易水を渡らんとす。以て此挙の不正不義に非ざるを知るべきである。』
大井・小林等が朝鮮に事を挙げんと企てて居た頃、福岡玄洋社でも同様の計画を樹てて居た。当時東京の芝公園附近に、玄洋社の青年が梁山伯を構へて、四方の同志と気脈を通じて居たが、彼等もまた朝鮮事変に対する政府の態度に憤慨し、此上は民間の志士が結束して亡命志を助け、以て朝鮮の改革を断行する以外に途なしと考へた。
そのためには玄洋社を総動員して運動の中心となし、広く同志を募りて義勇軍を組織せねばならぬといふので、頭山翁の賛成を求めるために久田金を西下させた。
久田は福岡に帰りて同志の計画を翁に告げ、その決起を懇願した。翁は之に対し、近日上京して同志と相談しようと答へたので、之を聞いた玄洋社の青年は、翁に先ち続々上京して在京社員に合流した。而して東京では熊本・金沢・青森の諸同志も此の計.画に参加し、只管翁の上京を待ち構へた。
やがて翁は京上の途に就いたが、当時金玉均が神戸に流寓して居たので、同地で金と面会した。翁は此の初対面で、金は援助するに足る人物であることを知つたが、愈々覚悟を定めて事を挙げるには充分の準備を必要とするので、持参せる千円ばかりの金を金玉均に与へ、再び福岡に引返して資金の調達に取掛かつた。恰も此時、大井憲太郎一派の対韓計画が露顕しかけ、警察側は頻りに探偵に努めて居た。再度の京上の途次、大阪で此事を知つだ翁は、斯様な時に同様の計画を進めても、徒に同志を蹉躓(さち)させるだけであると考へ、着京しても持重論を唱へて、血気に逸る同志を制止した。同志は憤激して決起を迫つたが、翁は頑として応じなかつた。
頭山翁は一方同志を慰撫して軽挙妄動を戒めると同時に、他方別個の計画を立てて其の実現に努めた。それは釜山に日清韓の三国語を教授する語学校を創立し、大陸に志ある青年を送りて大陸事情及び語学を研究させ、一朝時ある場合に此の学校を根拠地とし、此処で養成せる青年を活躍させようとする計画であつた。
此案には中江篤介、越後の赤沢常容、熊本の前田下学(かがく)等も賛成し、玄洋社員来島恒喜・的野半介等が熱心に奔走し、上京せる金玉均も時々会合に加はつた。計画は着々進み、中江が設立趣意書を執筆し、校名を善隣館と定め、資金の調達に取掛かつたが、偶々(たまたま)大井等の事件が暴露したので、其の余波を蒙りて此の計画も挫折した。之と同時に前述の対韓計画に狂奔せる青年も、大井等が一網打尽に検挙せられたのを見て、初めて翁の先見に服し、其の計画を中止した。而して金玉均は小笠原島に送られ、流罪同様の境遇に身を置くこととなつた。
【関連記事】
福澤諭吉「亞細亞諸國との和戰は我榮辱に關するなきの説」