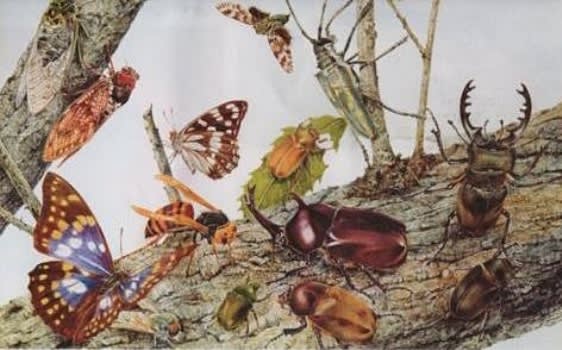雨の日に
2010-04-22 | 文芸
【日向ミズキ咲く】
雨の日は、何となく心落ち着き、自分を見つめ、取り戻すことができる様な気がする。
終日、冷たい雨降り、午前中は、普段点けているラジオを消して、昨日、寝床で読みかけのページを広げた。
中野孝次の「清貧の思想」に、三好達治の詩が取り上げられ、達治ももとより「清貧の人」であったと書かれている。
本棚から達治の詩集を手に取り、長い詩「冬の日」全文を声を出して読んだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「冬の日」 -慶州仏国寺畔にて
ああ智慧は かかる静かな冬の日に
それはふと思ひがけない時に来る
人影の絶えた堺に
山林に
たとえばかかる精舎の庭に
前触れもなくそれが汝の前に来て
かかる時 ささやく言葉に信をおけ
「静かな眼 平和な心 その外に何の宝が世にあらう」
秋は来り 秋は更け その秋は巳にかなたに歩み去る
昨日はいち日激しい風が吹きすさんでゐた
それは今日この新しい冬のはじまる一日だった
さうして日が昏れ 夜半に及んでからも 私の心は落ちつかなかった
短い夢がいく度か断れ いく度かまたはじまった
孤独な旅の空にゐて かかる客舎の夜半にも
私はつまらぬことを考へ つまらぬことになやんでゐた
さうして今朝は何という静かな朝だらう
樹木はすっかり裸になって
かささぎの巣も二つ三つそこの梢にあらはれた
ものの影はあきらかに 頭上の空は晴れきって
それらの間に遠い山脈の波うって見える
紫霞門の風雨に曝れた円柱には
それこそはまさしく冬のもの この朝の黄ばんだ日ざし
裾の方はけぢめもなくあいたいとして霞に消えた
それら遥かな頂の青い山々は
その清明な さうしてつひにはその模糊とした奥ゆきで
空間てふ 一曲の悠久の楽を奏しながら
いま地上の現を 虚空の夢幻に橋わたしてゐる
その軒端に雀の群れの喧いでゐるへん影楼の甍にうへ
さらに彼方疎林の梢に見え隠れして
そのまた先のささやかな集落の藁家の空にまで
それら高からぬまた低からぬ山々は
そこまでも遠くはてしなく
静寂をもって相応へ 寂寞をもって相呼びながら連なってゐる
そのこの朝の 何といふせう条とした
これは平和な 静謐な眺望だらう
そうして私はいまこの精舎の中心 大雄殿に縁側に
七彩の垂木の下に蹲まり
くだらない昨夜の悪夢の蟻地獄からみじめに疲れて帰ってきた
私の心を掌にとるやうに眺めてゐる
誰にも告げるかぎりではない私のこころを眺めている
眺めている―
今は空しいそこそこの礎石のまはりに咲き出でた黄菊の花を
かの石燈の灯袋にもありなしのほのかな陽炎のもえてゐるのを
ああ智慧は かかる静かな冬の日に
それはふと思ひがけない時にくる
人影の絶えた境に
山林に
たとへばかかる精舎の庭に
前触れもなくそれが汝の前にきて
かかる時 ささやく言葉に信をおけ
「静かな眼 平和な心 その外に何の宝が世にあらう」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中野孝次は、ここで達治の言う「智慧」について、
「魂に関する出来事を知覚する心の働きを的確に表現するには、この言葉しかなかったのだろう。
ここに描かれた光景は世の光景でありながらすべて魂の中の光景であった。」と述べている。
また、この達治の詩は、従然草の「一生は、雑事の小節にさへられて、むなしく暮れなん。」(第112段)の、自分の魂の平安と充実のために生きようとの心に通じると書かれていた。
私は、≪ああ智慧は かかる静かな冬の日に それはふと思ひがけない時に来る≫の一節が好きだ。
この詩を読みながら、同じような豊かな心が、今日の雨の日に、≪それはふと思いがけない時に来た≫と思った。
本当に「静かな眼 平和な心 その外に何の宝が世にあらう」と思う。
これからも、雑事の小節から離れて、時に良寛に、また藤村に、達治に触れながら静かに過ごしていきたいと思っている。 今を大切に、清貧な生活を心がけながら。
雨の日は、何となく心落ち着き、自分を見つめ、取り戻すことができる様な気がする。
終日、冷たい雨降り、午前中は、普段点けているラジオを消して、昨日、寝床で読みかけのページを広げた。
中野孝次の「清貧の思想」に、三好達治の詩が取り上げられ、達治ももとより「清貧の人」であったと書かれている。
本棚から達治の詩集を手に取り、長い詩「冬の日」全文を声を出して読んだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「冬の日」 -慶州仏国寺畔にて
ああ智慧は かかる静かな冬の日に
それはふと思ひがけない時に来る
人影の絶えた堺に
山林に
たとえばかかる精舎の庭に
前触れもなくそれが汝の前に来て
かかる時 ささやく言葉に信をおけ
「静かな眼 平和な心 その外に何の宝が世にあらう」
秋は来り 秋は更け その秋は巳にかなたに歩み去る
昨日はいち日激しい風が吹きすさんでゐた
それは今日この新しい冬のはじまる一日だった
さうして日が昏れ 夜半に及んでからも 私の心は落ちつかなかった
短い夢がいく度か断れ いく度かまたはじまった
孤独な旅の空にゐて かかる客舎の夜半にも
私はつまらぬことを考へ つまらぬことになやんでゐた
さうして今朝は何という静かな朝だらう
樹木はすっかり裸になって
かささぎの巣も二つ三つそこの梢にあらはれた
ものの影はあきらかに 頭上の空は晴れきって
それらの間に遠い山脈の波うって見える
紫霞門の風雨に曝れた円柱には
それこそはまさしく冬のもの この朝の黄ばんだ日ざし
裾の方はけぢめもなくあいたいとして霞に消えた
それら遥かな頂の青い山々は
その清明な さうしてつひにはその模糊とした奥ゆきで
空間てふ 一曲の悠久の楽を奏しながら
いま地上の現を 虚空の夢幻に橋わたしてゐる
その軒端に雀の群れの喧いでゐるへん影楼の甍にうへ
さらに彼方疎林の梢に見え隠れして
そのまた先のささやかな集落の藁家の空にまで
それら高からぬまた低からぬ山々は
そこまでも遠くはてしなく
静寂をもって相応へ 寂寞をもって相呼びながら連なってゐる
そのこの朝の 何といふせう条とした
これは平和な 静謐な眺望だらう
そうして私はいまこの精舎の中心 大雄殿に縁側に
七彩の垂木の下に蹲まり
くだらない昨夜の悪夢の蟻地獄からみじめに疲れて帰ってきた
私の心を掌にとるやうに眺めてゐる
誰にも告げるかぎりではない私のこころを眺めている
眺めている―
今は空しいそこそこの礎石のまはりに咲き出でた黄菊の花を
かの石燈の灯袋にもありなしのほのかな陽炎のもえてゐるのを
ああ智慧は かかる静かな冬の日に
それはふと思ひがけない時にくる
人影の絶えた境に
山林に
たとへばかかる精舎の庭に
前触れもなくそれが汝の前にきて
かかる時 ささやく言葉に信をおけ
「静かな眼 平和な心 その外に何の宝が世にあらう」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中野孝次は、ここで達治の言う「智慧」について、
「魂に関する出来事を知覚する心の働きを的確に表現するには、この言葉しかなかったのだろう。
ここに描かれた光景は世の光景でありながらすべて魂の中の光景であった。」と述べている。
また、この達治の詩は、従然草の「一生は、雑事の小節にさへられて、むなしく暮れなん。」(第112段)の、自分の魂の平安と充実のために生きようとの心に通じると書かれていた。
私は、≪ああ智慧は かかる静かな冬の日に それはふと思ひがけない時に来る≫の一節が好きだ。
この詩を読みながら、同じような豊かな心が、今日の雨の日に、≪それはふと思いがけない時に来た≫と思った。
本当に「静かな眼 平和な心 その外に何の宝が世にあらう」と思う。
これからも、雑事の小節から離れて、時に良寛に、また藤村に、達治に触れながら静かに過ごしていきたいと思っている。 今を大切に、清貧な生活を心がけながら。