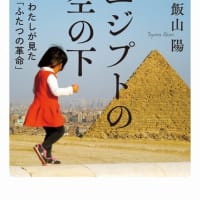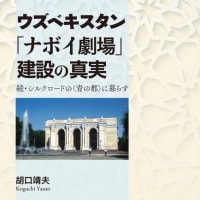「昭和天皇は戦争を選んだ!」(増田都子著 社会批評社 2015年)を読む。本書のサブタイトルには「裸の王様を賛美する育鵬社教科書を子どもたちに与えていいのか」とあり、著者の政治的立場がはっきりと示されている。
著者である増田都子氏は、東京都の中学校社会科教諭を長く勤めたが、東京都教育委員会から「偏向教育」の烙印を押され、学校現場を外され「研修所送り」になった挙句、「分限免職」の処分を受けた。こうした経歴を見ると、本書もすさまじい偏向に満ちているのかと思ったが、意外にも公開資料を丹念に読み込み、実証的な歴史教科書批判になっている。著者がもし義務教育の中学校教諭ではなく、都立高校の社会科教諭だったとしたら、これほど苛酷な処分を受けなかったのではないかと想像される。つまり、都立高校には似たような立場の教員が、何のお咎めもなく、授業を続けられるだけの「教育環境」がまだ残されているからだ。
「昭和天皇は戦争を選んだ!」(増田都子著 社会批評社 2015年)
本ブログでは、昨年7月に公にされた「昭和天皇、蒋介石支持発言」に触発されて、かなりの数の関連図書を読んできたが、究極の到達点が本書だった。著者の政治的立場は明確すぎるほど明確なので、個々の当否をあげつらうつもりは全くない。むしろ、日本近現代史のスタンダードと目される半藤一利、加藤陽子などの著作をいくら読んでも、昭和天皇の戦争責任や個人的資質の問題はよくわからない。何故なら、著者たちが「菊のタブー」には決して触れないからだ。その点においては、本書の迫力は満点だ。加藤陽子には「それでも、日本人は「戦争」を選んだ」( 朝日出版社、2009年)という著書があるから、「天皇は戦争を選んだ」という本書とは極めて対照的だ。
本書の巻頭には、二つの推薦文が寄せられている。高嶋伸欽・琉球大名誉教授の「安倍政権で勢いを増した歴史修正主義の蔓延、昭和天皇批判に腰が引けているマスコミ」と鈴木邦男・一水会顧問の「天皇制は日本に必要なのかどうか、それは堂々と論争したらいい」だ。
鈴木邦男の帯文(上記写真参照)は「もう天皇を引き込んではならない。天皇を中心にまとまって戦争する時代に戻してはならない。国論が真っ二つになった時、天皇に判断をあおぐことになってはならない。そんな時代にあこがれをもってはならない」(p.10)とし、「この本は大きな問題提起になるだろう。歴史は、失敗も暗い面も含め、すべて認め、そのうえで、天皇制は日本に必要なのかどうか。それは堂々と論争したらいい」と結ぶ。
鈴木邦男は「サヨク」に転向したのか?と思うほどの一文だが、ともあれ真っ当な結論だろうと私は思う。
昨夏、映画「日本のいちばん長い日」(半藤一利原作)がリメイク上映され、「今の平和は天皇の”ご聖断”がもたらした」というキャッチコピーが散々流された。これは本書の「昭和天皇は戦争を選んだ!」とは対極にある認識なのだが、近年公開された外交文書等の分析を見る限り、本書の方がより説得力があるのは間違いないだろう。
昭和天皇は、沖縄を二度裏切った。沖縄戦で沖縄県民を捨て石に使ったこと、さらに戦後、自己保身と引き換えに沖縄統治を米国に懇願したという事実だ。同様なことは、「大日本帝国」の「臣民」であった台湾人に対しても言える。敗戦によって棄てられた台湾の日本語世代は、昨年夏、『1971年、中国国連代表権問題で昭和天皇が佐藤栄作首相に「蒋介石を支持するように」指示したという事実』の公開で、再び昭和天皇に裏切られた事実を知らされた。1947年、蒋介石の国民党軍は、三万人もの台湾の日本語世代の知識人、リーダー層を虐殺した(二二八事件)。その後、台湾人を圧政の下で支配した独裁者・蒋介石を、自分の「命の恩人」とばかりに庇おうとした昭和天皇。このことが何を意味するのか、論評した人は寡聞にして聴かない。まさに「歴史認識」の根幹に触れる問題なのだから、見て見ぬふりは許されないはずなのに…。「臣民」、否「市民」はもっと憤りを覚えるべきだろう。
世襲(つまり萬世一系)の天皇が、後世の歴史家の批判に耐えうるような決断を次々と下せるはずなどないことは、常識でも推察できるし、また事実として、その愚かな決断によって「臣民」は「史上最大の負け戦」を戦わさせられ、甚大な被害を被った。鈴木邦男が言うように「天皇に判断を仰ぐような時代に二度とは戻ってはならない」のだ。
安保法制には賛成の私だが、近年、マスメディアで吹聴される「日本は素晴らしい」という「ホルホル番組」などを見ると、「この国」がどこに向かっているのか、不安を感じたりもする。近未来、次の大震災がおきたとき、わが「列島民族」(西部邁)はどう「脱皮」「豹変」するのか、あるいはしないのか?そのときが分水嶺となりそうだ。