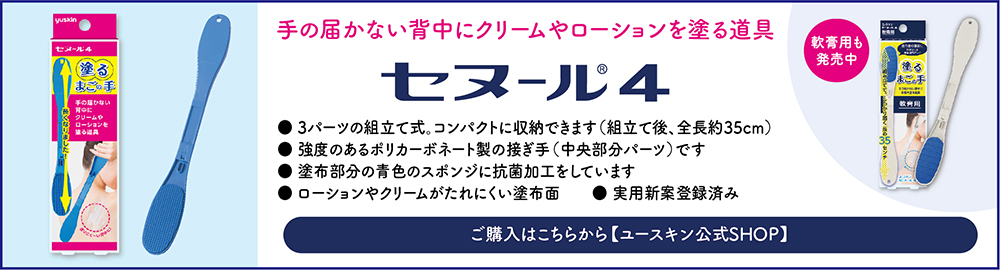『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(マッドマックス いかりのデス・ロード、原題:Mad Max: Fury Road マッド マックス: フューリー ロード)は、2015年公開のオーストラリアとアメリカの合作映画。2012年7月から12月までアフリカのナミビアで撮影された[2]。前作『マッドマックス/サンダードーム』以来、30年ぶりに製作された『マッドマックス』シリーズの第4作である。
日本では2015年6月20日に公開[3]。本作は『マッドマックス2』と同様に、英雄誕生譚(貴種流離譚)など世界各地の英雄神話を研究した神話学者ジョゼフ・キャンベルによる著書『千の顔を持つ英雄』をテーマとしている[4]。
第88回アカデミー賞では10部門にノミネートされ、最多の6部門を受賞した。
あらすじ
核兵器による大量殺戮戦争勃発後、生活環境が汚染され、生存者達は物資と資源を武力で奪い合い、文明社会が壊滅した世界を舞台とする。
砂漠化し荒廃したウェイストランド(荒野)で、元警官マックスは、過去に救えなかった命の幻覚と幻聴に煩わされ、狂気に侵されているのは世界なのか自身なのか曖昧になる中、生存本能にだけ突き動かされV8インターセプターを駆る。
流浪の途上で暴徒らの襲撃に遭い捕縛され、シタデルという砦に連行されたマックスは、インターセプターを奪われた上に身体を拘束され、環境汚染からの疾病を患う住人に供血利用される。
そこではイモータン・ジョーを首領とした独自教義を持つ好戦的な集団の支配のもと、潤沢な地下水(アクア・コーラ)と農作物栽培を牛耳ることで成り立っている独裁社会が築かれていた。
ガスタウンへと向かう取引当日、ジョーの部隊を統率するフュリオサ・ジョ・バッサ大隊長は、ジョー一族が受胎出産させることを目的として監禁していた5人の妻(ワイブズ)であるスプレンディド、トースト、ケイパブル、ダグ、フラジールの身柄を秘密裏にウォー・リグに搭乗させ、フュリオサの出生地である「緑の地」に匿う逃亡計画を、3000ガロンのガソリン(guzzoline[注釈 1])取引を隠れ蓑に東へと進路を変えて実行に移す。
部下の背任行為と、妻たちと、その胎内の我が子を奪われたと知ったジョーは配下の戦闘集団ウォーボーイズを引き連れ、友好関係にある人食い男爵と武器将軍の勢力を援軍に追走を開始する。
マックスはウォーボーイのニュークスの常備用「血液袋」として追尾車両に鎖で繋がれワイブス追走の争いに巻き込まれることになった。
追跡劇の最中に砂嵐に遭遇し、追走車両がウォー・リグの追突によって大破、手足の拘束を解くことができたマックスは、フュリオサ達を制圧する。
一人でウォー・リグに乗り込むが、フュリオサ仕様に様々な改造が施されていたため、結局は同乗する事になる。また、ジョーの直々の命令でウォー・リグに乗り込んだものの失敗した上に、ジョーのお気に入りの妻が死亡してしまったことで戻れなくなったニュークスも、ワイブズの一人であるケイパブルに啓蒙されて一行に加わることとなる。
一昼夜をかけて走破した場所でかつての仲間である鉄馬の女たちに出会うことが出来たが、土壌汚染の進行で既に目的の地は失われている事を知り、フュリオサは慟哭する。
それでもなお、ワイブスと鉄馬の女たちと共に、荒廃した地へとあてのない旅に向かおうとするフュリオサに対しマックスは、ジョーさえ除けば生きて行ける可能性の高いシタデルに戻るように諭す。
マックスの提案に同意し、主不在の砦に向かって激走するフュリオサ一行を発見し、ジョーの軍勢は追撃をかける。
犠牲も出る中、3日間に渡る逃走劇と過去の精算に決着をつけるべく、フュリオサは深手を負ったままジョーと直接対峙し、遂にジョーは倒される。そしてニュークスの捨て身の戦法で渓谷拱門の突破に成功、ジョーの配下達も排除される。フュリオサは危篤状態に陥ってしまうが、マックスはできうる限りの救命措置を施し、告げることを拒んでいた己の名前を明かす。
一行は砦に凱旋し、ジョーの圧政から解放されたことで、フュリオサは群衆に歓迎される。
人々の流れに逆らい、砦から去ろうとするマックスを見つけ、目を合わせたフュリオサは、無言の笑みをもって彼を見送るのだった。
登場人物・キャスト
主要人物
マックス(Max Rockatansky)
演 - トム・ハーディ
本名はマクシミリアン・ロカタンスキー(Maximillian Rockatansky)で、異名としてロード・ウォリアーと呼ばれることもある。元・M.F.P.(Main Force Patrol)特殊警察警官隊隊員である。
過去に目の前で散っていった命のフラッシュバックに苛まれ、高放射線に曝露された世界を旅していた。
ある日、イモータン・ジョーの武装集団ウォーボーイズに捕らえられ、放射線障害の影響により短命なウォーボーイズ構成員であるニュークスの輸血ドナーとして採血されるために拘束されていた。
逃亡したフュリオサたちの追跡を志願したニュークスにより荒地に運ばれ、自らの逃亡のため彼女達一団の砂漠横断の手助けをする。
左足に金属製歩行補助器具、右肩にFRPショルダーパッド、上下黒のレザースーツとレザーブーツ、右手にパラコードブレスレットを付けている。そのブレスレットは、前日譚コミックでグローリー・ザ・チャイルドが右の上腕に付けていたもので、彼女の形見でもある[注釈 2]。
前日譚コミック『Mad Max Fury Road Mad Max #1、#2』では、本作品は過去の映画 3部作と物語が繋がっているように描かれている。
回想シーンでは、マックスは 2作目で破壊されたV8インターセプターを再び作り直すため、略奪、ボディガード、鉱山労働、暗殺などの仕事を引き受けながら部品集めの旅をしていた事が示されている。ある場所でインターセプターを保管し修理し続けており、V8エンジンを得るべくガス・タウンのサンダードームと呼ばれる闘技場で命をかけたバトルロイヤルでの闘いの試合に参加した。
は優勝し、インターセプターを復活させようとするが、バザードという名の盗賊による襲撃で重傷を負わされ、インターセプターが奪われてしまう。
重傷を負ったマックスは謎の女性に助けられ、バザードに誘拐された娘のグローリーの救出を依頼される。前作同様、水平二連のソードオフ・ショットガンを武器[注釈 3] に、1人でバザードのアジトであるサンケンシティに乗り込み、グローリーを見つけインターセプターを取り戻し脱出しようとする。
劇中ではこの一連の出来事がマックスの幻覚の主な原因となっている。
フュリオサ大隊長(Imperator Furiosa)
演 - シャーリーズ・セロン
フュリオサ衣装
シタデルの女性大隊長。本名はフュリオサ・ジョ・バサ(Furiosa Jo Bassa)。短く刈り込んだ頭髪[注釈 4]と顔に塗った黒いグリースが特徴。左腕の前腕部から先を欠損しており、金属製義手を装着している。この義手は小型モーターを内蔵しており、人間の首すらへし折ってしまうほどの出力を備えている。
そのほか、皮革製固定ハーネスとコルセット、ショルダーパッドを身に着けている。
動作も俊敏で銃器の扱いにも長け、特に改造型SKSカービンを使った長距離射撃を得意とする他、マックスと同様のソードオフ・ショットガンやグロック17、トーラスPT99に加え、RSAF エンフィールドNo.2、ウィンチェスターM1897、リパブリックアームズ・マスラー12等も使用。本来は「緑の地」出身、スワドル・ドッグ一族の末裔で、少女期に「鉄馬の女たち」であった母マリー・ジョ・バサ(Mary Jo Bassa)と共に身柄を拐われシタデルへ連行されたが、母は3日後に落命してしまう。その後、ジョーの子産み女となるが、ジョーの怒りを買い片腕を失う[5][6][注釈 5]。
大隊長としてジョーから信用を得ながら裏では約20年間に渡り故郷へ帰る機会を窺っており、ガスタウンとの取引に向かうと見せかけて、ジョーが幽閉状態で囲っていたワイブズをウォー・タンクに匿い、フュリオサが幼少時代を過ごした故郷「緑の地」へ運ぼうとする。
名前は「激情、情熱」、または「憤怒、激怒」を表す。
前日譚コミック『Mad Max Fury Road Furiosa』によると、ジョーらの襲撃を受けて故郷「緑の地」から引き離された上に、3日後に母を失う。襲撃をかけた集団に抵抗していた少女フュリオサだったが、ジョーの下でメカニックとして働く道を選ぶ。
次第にジョーの信用を得て、大隊長の階級まで伸し上がり、「提げ爪(Bag of nails)」のニックネームで呼ばれ、気性も荒く暴力的な行動を振るうエレクタスから5人の妻の保護を任されていたが、ジョーたちの5人の妻に対する扱いに反発し、彼女らワイブズを連れて砦からの脱出を決意している。
ザ・シネマ吹替版では役名がインペラートル・フュリオサに改められている[8]。
ニュークス(Nux)
演 - ニコラス・ホルト
イモータン・ジョーの武装戦闘集団「ウォーボーイズ」のひとり。首の付根の左側に病変腫の大小2つの瘤があり、それぞれ「ラリーとバリー」と名付け友人として扱い、上半身前面にスカリフィケーションによるV8エンジンの紋様が施されている。
ルガー・バケーロを武器としており、登場時には常に輸血を必要とするほど衰弱著しい状態であったが、ジョーを狂信する彼は、栄誉ある戦死を望んでフュリオサ達の追跡隊に志願し、高品質の輸血ドナーのマックスを「輸血袋」として砂漠に連れ出たことで、マックスが追跡劇に参加する切っ掛けを作る。
ジョーとその教義を狂信し奮闘するものの目的は尽く失敗し、よりによってジョーが追い求めた妊婦スプレンディドを不注意から転落させて瀕死、死亡させてしまった事から意気消沈して自己嫌悪に陥った姿を見たケイパブルが同情と慈愛を寄せたことで彼女に恋心を抱き[5][6]、フュリオサ一行の仲間に転向。ジョー一味の追走を振り切るべくウォー・リグに同乗して、ドライビングやエンジントラブルの解消を受け持つ。名前の意味は「木の実」。
物語終盤、谷の門にてジョー達の追走から皆を守る為、ウォー・リグを自ら横転させ死亡する。
前日譚コミック『Mad Max Fury Road Nux and Immortan Joe』によると、荒廃した世界にあってもお互いに愛しみ合う両親に育てられていたが、幼い頃に母親が病死し、次いで父親も我が子のための危険な仕事に出たまま帰らず、一人きりになったところをジョーに身柄を保護され養子となる。少年時代は、「ウォーパプス」として砦にある「ブラック・サム」でメカニックとして育てられ、また優秀なドライバーでもある。
イモータン・ジョー(Immortan Joe)
演 - ヒュー・キース・バーン[注釈 6]
「シタデル」占領者で、周辺テリトリーを支配する武装集団の首領”不死身の顎”。
上半身は気腫疽らしき疾病を抱えており、それを隠す為に体を白塗りにし、両腕を包帯で覆う。健康を害する汚染された外気を避けて呼吸するための生命維持のスカルを模した特殊マスク、メダルや携帯電話の基板で装飾を施した防弾プレキシガラス・ボディーアーマーを装着している。
コルト・アナコンダとルガー・バケーロの2丁のリボルバー及び、トーラスPT99の計3丁で武装し、杖を持つ。劇中ではギガホースという1959年型キャデラックの車体を使って改造した車両に搭乗。
死後の転生を唱え、頭蓋骨とV8を奉る独自教義組織を構成、組織し、成人の「ウォーボーイズ」、子供らの「ウォーパプス」を信徒、兼、兵隊として据える。自身の子を産ませるために5人の妻をシタデルの一画に幽閉し、「ブリーダーズ(交配体)」としての待遇を妻たちに与えていたが、フュリオサが彼女らを連れて逃亡したため、自分の権利としての我が子を取り戻すために追跡することとなる。
前日譚コミック『Mad Max Fury Road Nux and Immortan Joe』によると、本名はジョー・ムーア大佐といい、石油戦争の際のベテランの軍人で、水戦争での英雄でもあった。世界の混乱後に、仲間の元軍人たちを集め、凶悪な暴走族のライダー集団「ディープドッグ」を結成し、勢力の拡大を行う途中、”太った男”(後の人食い男爵)との遭遇から、水源がある岩山の砦の情報を得て、自らの野望のために砦を占有支配していた無法者達を討ち倒し、シタデルの新たな支配者として君臨し、先住の住民達から「イモータン・ジョー」と呼ばれるようになった。
自分を神格化させ、短命な養子達には幼児期から、ジョーのために死んだら生まれ変わることができるというカルト宗教的な価値観を植え付けて手駒とし、老齢に差し掛かり若年の娘らを集め健康体の子供を産ませて子孫を残す「育種プログラム」を発案し実行に移す。
荒地で人々を捕らえては彼が根城にしている砦に連れ込んだり、人々を騙して利用している。
ワイブズ(Wives)
イモータン・ジョーにより岩山の一画に幽閉されていた健康体の妻たちで計5名。ジョーの所有物で子を産むだけの出産母体[注釈 7]という扱いに堪えかね、産まれる子供がジョーの手に渡るのを避けるため、「WE ARE NOT THINGS」「OUR BABIES WILL NOT BE WARLORDS」と部屋に書き置きし、ミス・ギディの助けを借りて、フュリオサにウォー・リグに匿われ「緑の地」への逃避行を試みる。
各人、白色の絹の衣装を纏い、それぞれの装束で着飾る。貞操帯も装着させられていたが、砂嵐を抜けた後に外している。
スプレンディド(The Splendid Angharad)
演 - ロージー・ハンティントン=ホワイトリー
5人のリーダー格で、イモータン・ジョーお気に入りの受胎母体である。ジョーの子を宿し、臨月の身体で逃亡する。名前は「見目麗しき」。逃走途中にウォー・リグから転落、ジョーの運転する車両に轢かれて瀕死となり、赤子も死亡してしまう。
ケイパブル(Capable)
演 - ライリー・キーオ
赤毛の長髪、砂嵐後から透明ゴーグルを装着。ジョーの配下だったニュークスと心を通わせ、好意を持つようになる。名前は「有能」「器用」。comic版では弦楽器を奏している。
トースト(toast the knowing)
演 - ゾーイ・クラヴィッツ
褐色肌で髪はショートカット、名前は「失意」。5人の中では一番戦う覚悟を持っている。SKSカービン及び、グロック17を武器として使用。
ダグ(The Dag)
演 - アビー・リー
細身の身体で銀の長髪。彼女もジョーの子を受胎しており葛藤がある。若干、コミックリリーフ的な一面がある。名前は「不器用、少し外れている人」を指す「Taggy」から採られている。
フラジール(Cheedo The Fragile)
演 - コートニー・イートン
名前は「華奢、儚き」。5人の中では一番若く、砦の中での生活しか知らないことも有り、過酷な道中に挫けてジョーの元に戻ろうともする。












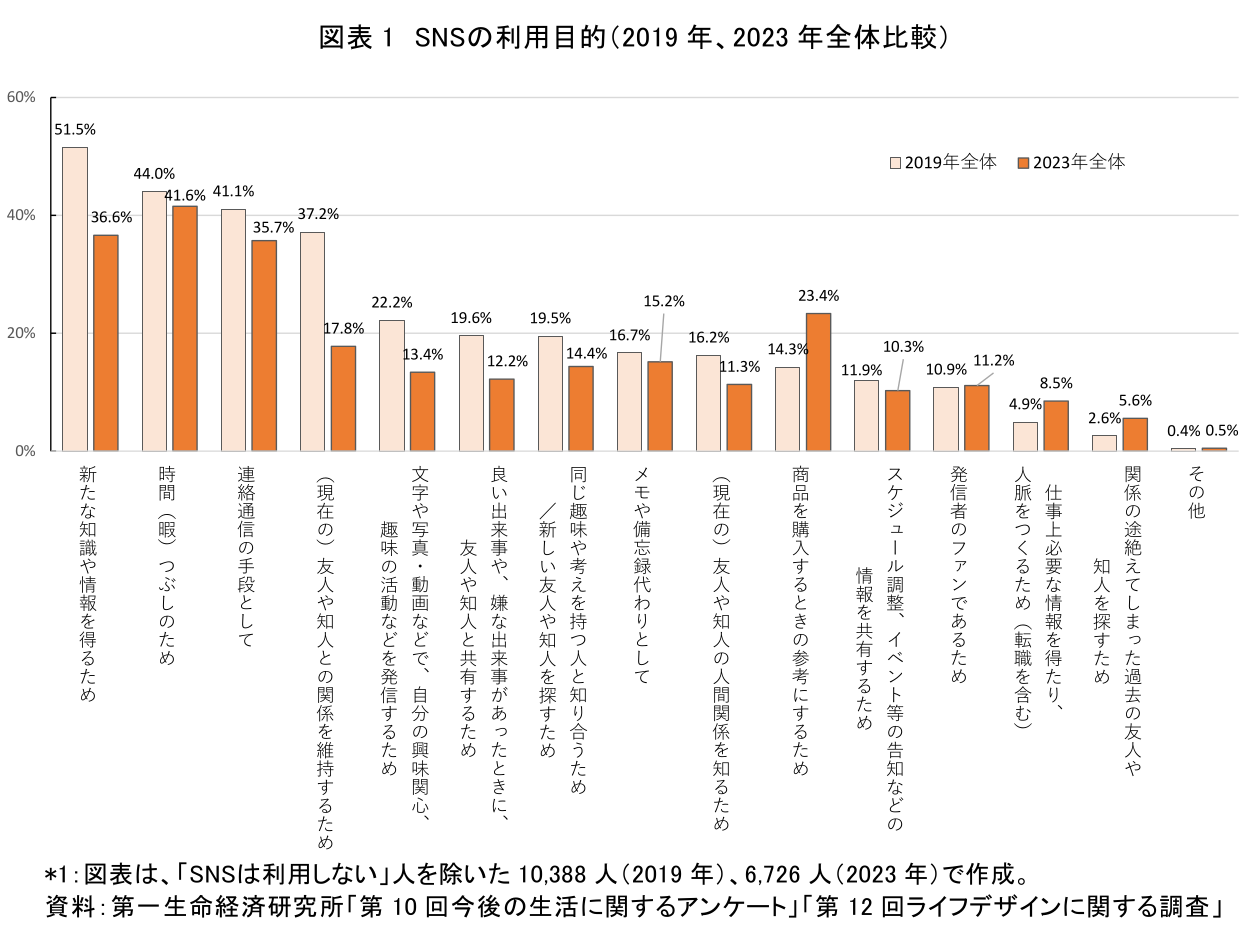
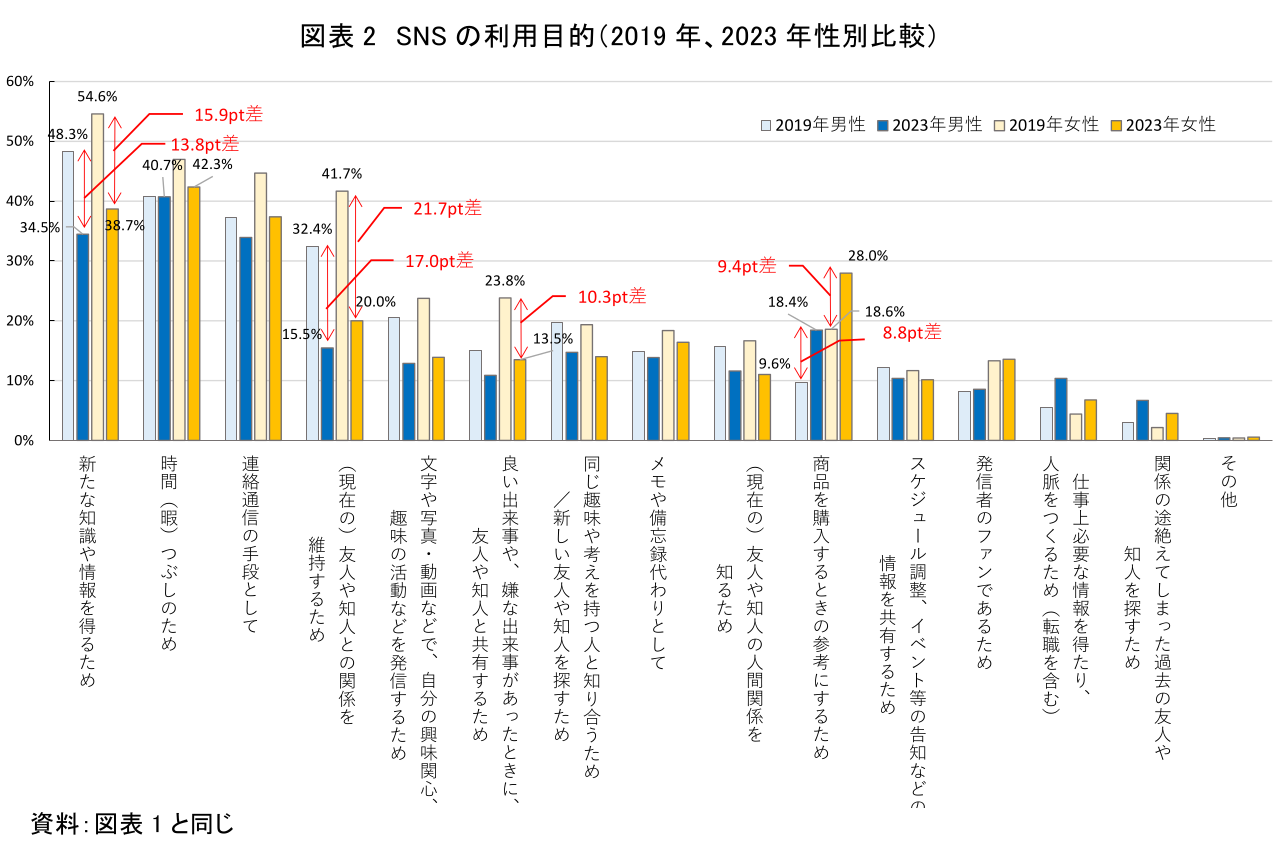
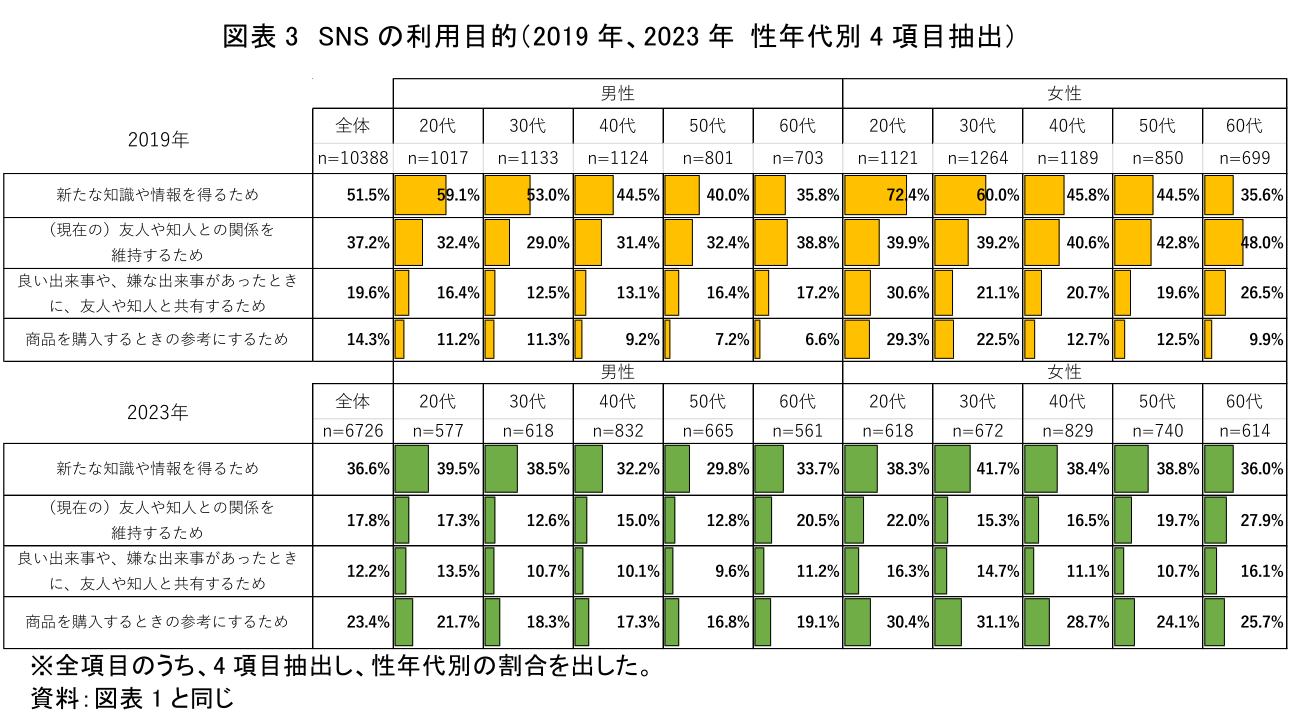
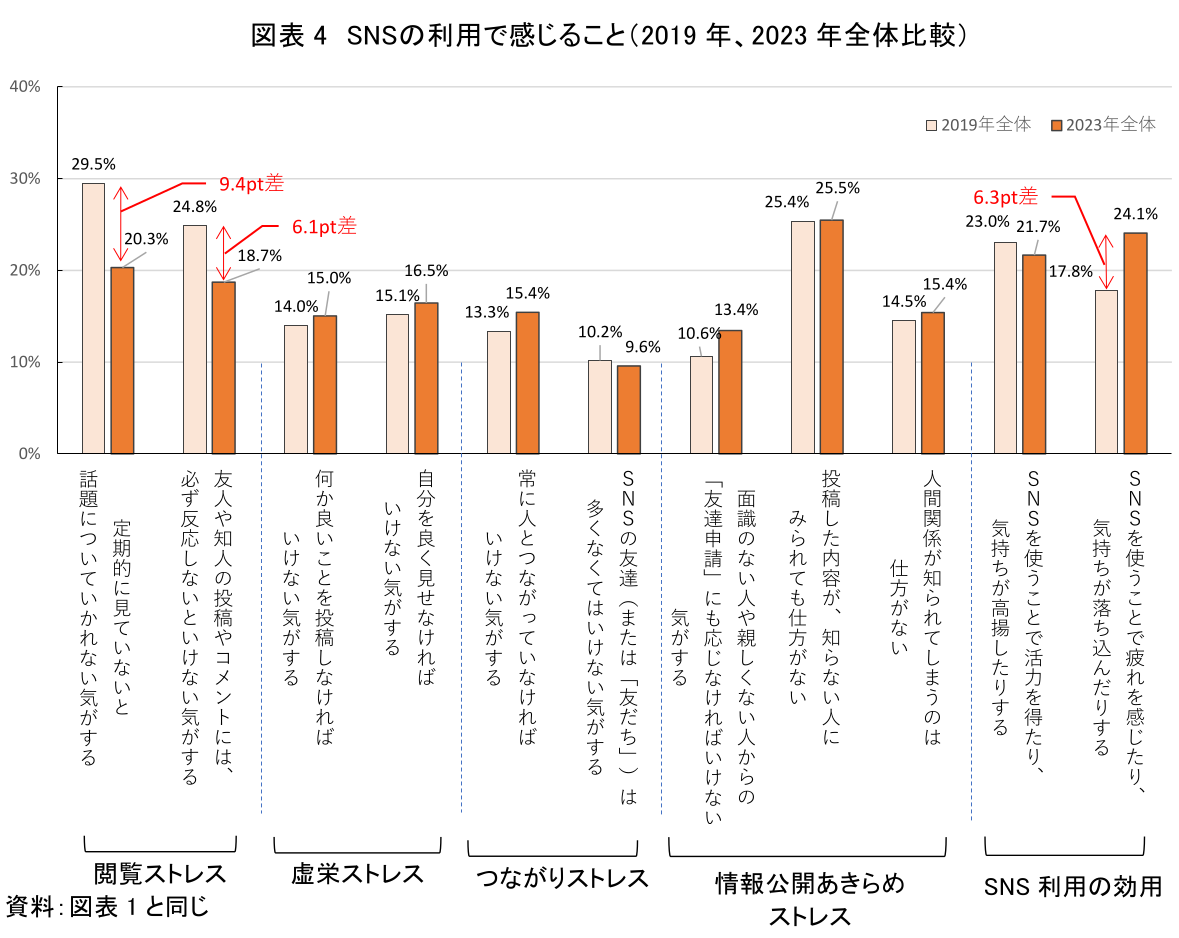
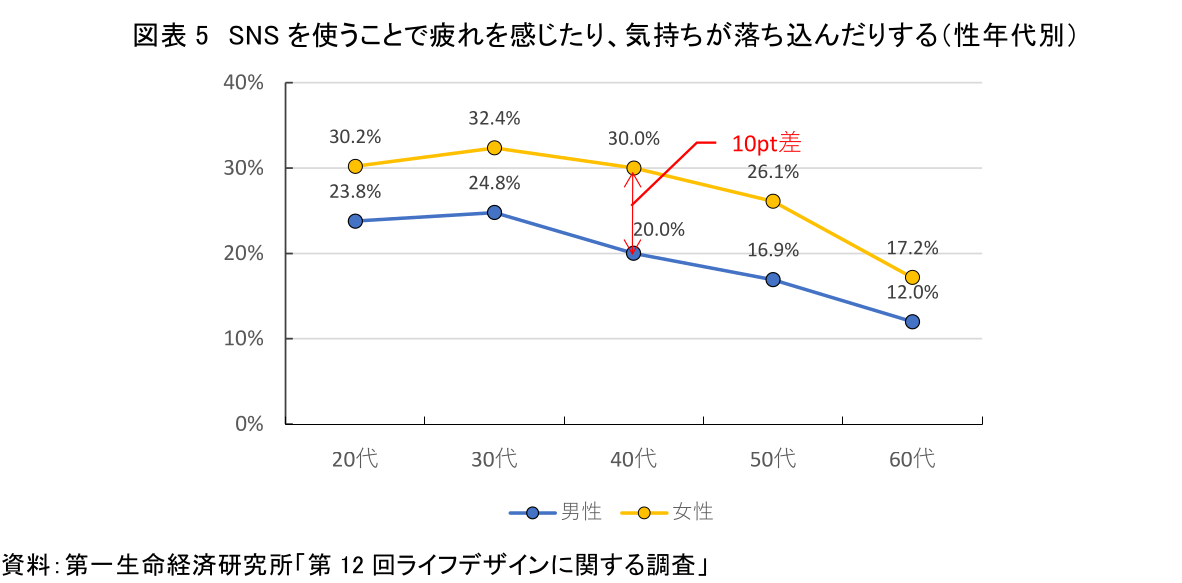










 </picture>
</picture> </button>
</button>