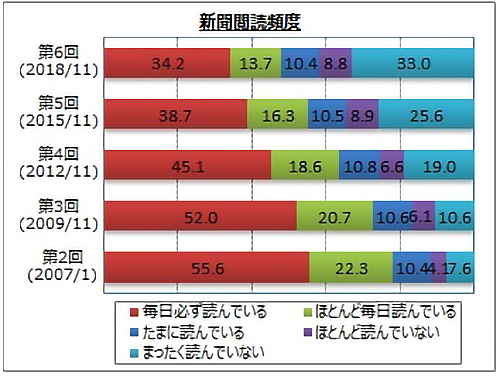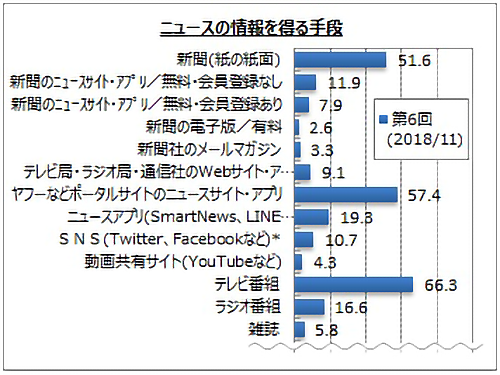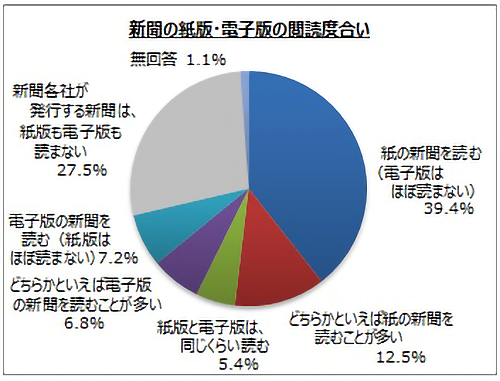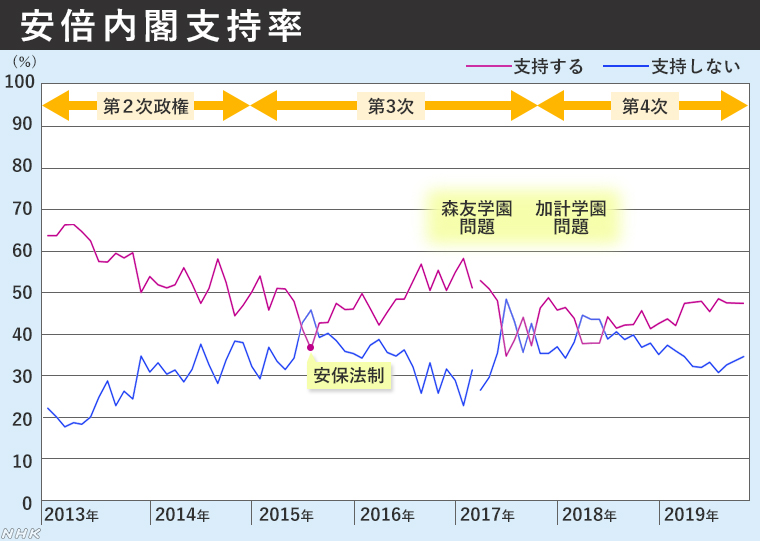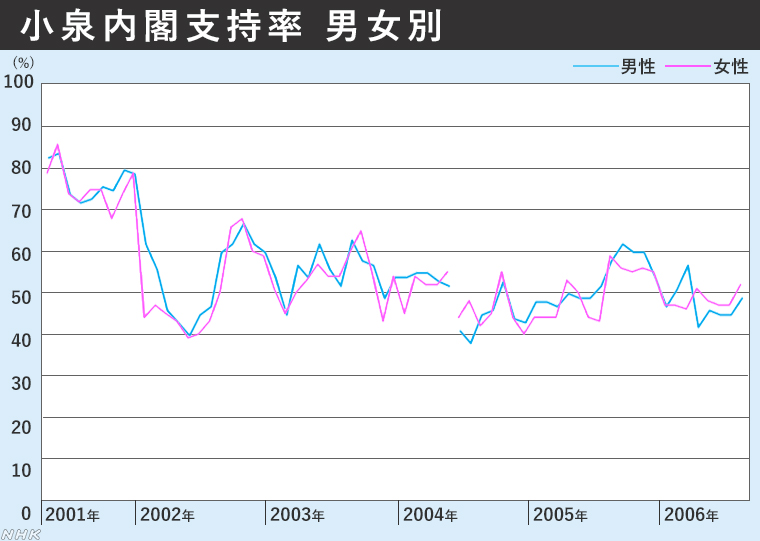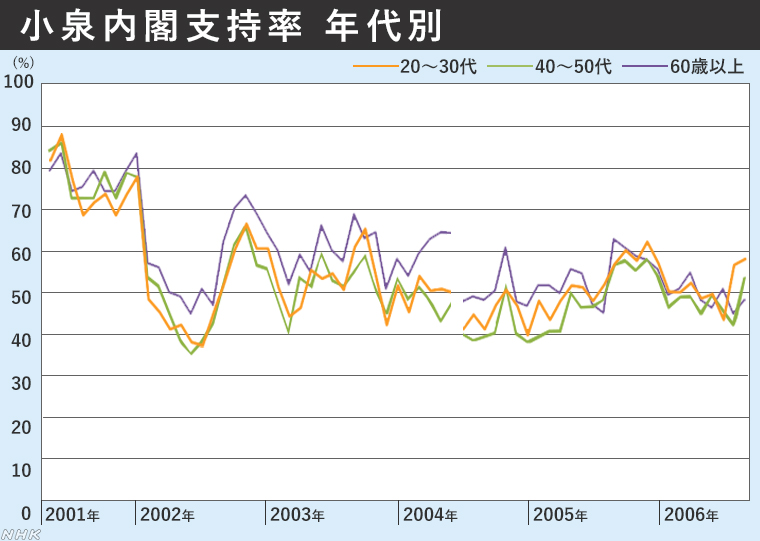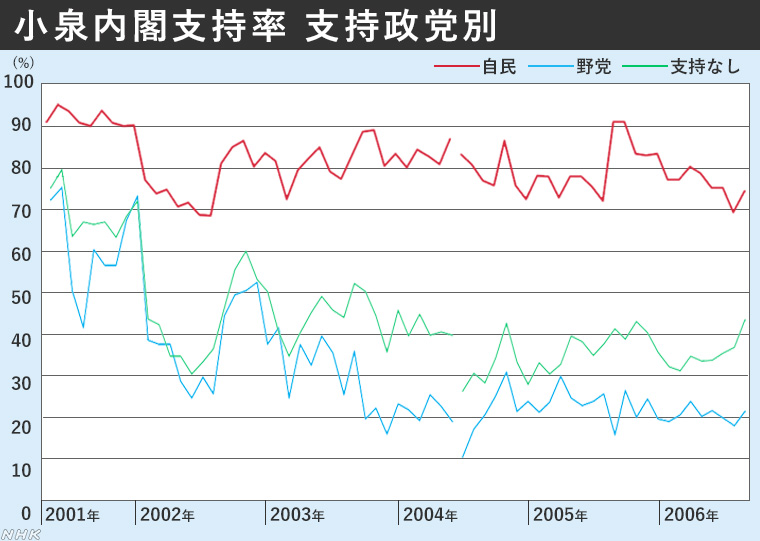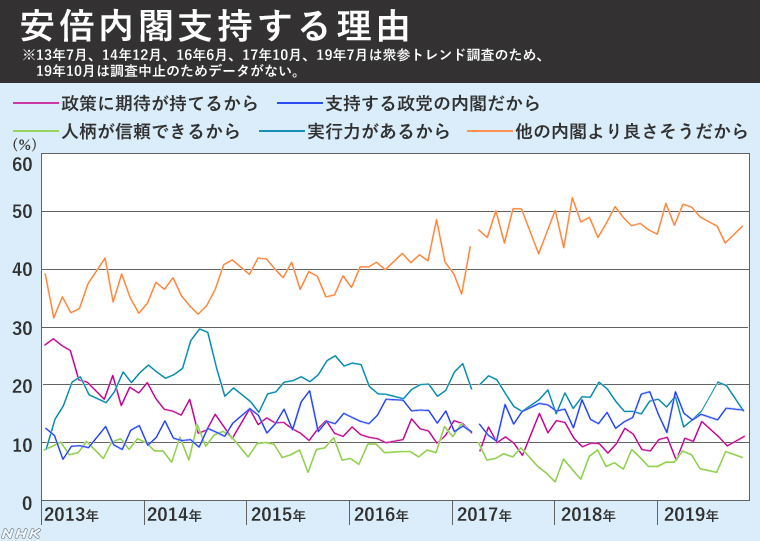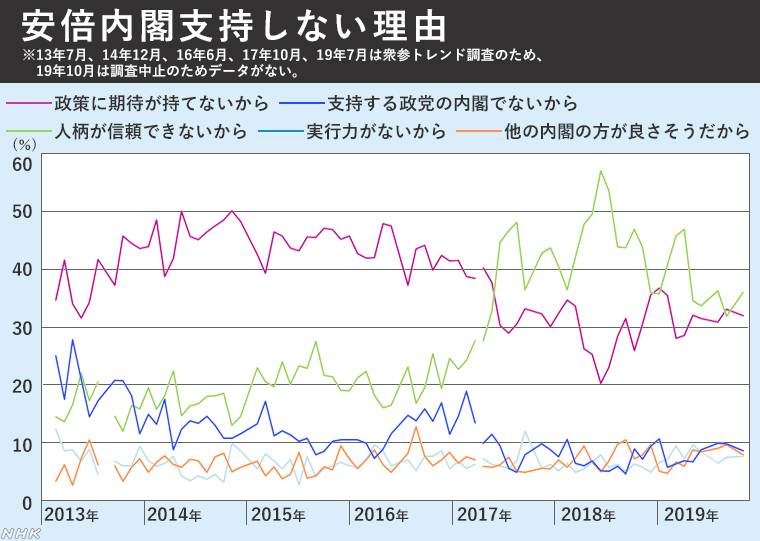国連総会は、
1999年9月13日に採択された「平和の文化に関する宣言」を受け、
2001年から2010年を「世界の子どもたちに平和と非暴力の文化をつくる国際10年」と宣言した1998年11月10日の53/25決議と、2000年を「平和の文化国際年」とした1997年11月の52/15決議を思い起こし、
平和の文化に関する以下の行動計画を採択する
A 目的とすすめ方ならびに主な担い手
1 行動計画は「平和の文化国際年」「世界の子どもたちに平和と非暴力の文化をつくる国際10年」のための基本を提供するものでなければならない。
2 国連加盟国は地域的ならびに国際的なレベルだけでなく、国内的なレベルにおいて、平和の文化を促進する行動をとることが求められる。
3 市民社会は、その地域や地方、そして全国それぞれのレベルにおいて、平和の文化に関する視野を広げるために活動領域を広げることに関わらなければならな
い。
4 国連組織は平和の文化を促進するために現在取り組んでいる努力をさらに強化しなければならない。
5 ユネスコは平和の文化を促進するために引き続いて重要な役割を果たし、そのために中心的な貢献をしなければならない。
6 平和の文化のために、宣言に述べられた担い手たちの間の協力関係が、地球的な運動のために奨励され強められなければならない。
7 平和の文化が情報の共有によって促進されるので、この点において担い手たちの主体的な活動が必要であ る。
8 行動計画の効果的な実現のために、関連する政府や各種団体、ならびに個人による、財源を含むさまざまな資源を動員する必要があ る。
B すべての関係者による国内的、地域的そして国際的なレベルでの行動を強化すること
9 教育を通じて平和の文化を育てる行動
(a) 人間的、社会的そして経済的な発達という視点をもって、また平和の文化を促進するという視点で、「全ての人に教育を」という目標を実現するために、国内的あ るいは国際的な努力を再活性化すること。
(b) 子供たちが早い時期から、あらゆる争いを平和的に、また人間の尊厳を尊重するような精神、寛容と非差別の精神をもって解決することが可能になるような価値観の形成、態度、行動の様式ならびに生き方を身につけるような教育をすすめること。
(c) 平和の文化の価値と目標が身についていく行動に、子どもたちを参加させること。
(d) 女性、特に少女達への教育への機会均等を保障すること。
(e) ユネスコが専門的な協力をした1995年の「平和、人権 、民主主義に関する行動要綱」を心に留めて、教科書を含めた教育課程の改訂を促進すること。
(f) 対話と合意形成を促進する教育と訓練をはじめ、平和の文化に役立つ価値や技能を発達させることをめざしている「平和宣言」に位置づけられたの担い手たち、とりわけユネスコの努力をはげまし強化すること。
(g) 紛争後の平和建設とともに、紛争の予防、危機管理、対立の平和的解決の分野において、適切な訓練と教育をめざしている国連機関の現在取り組んでいる努力を強めること。
(h) 国連大学、平和大学及び国連姉妹大学の計画、あ るいはユネスコの大学講座計画をはじめ、世界のあらゆる地域における高等教育組織によって行われる平和の文化促進の主体的な取り組みを拡大すること。
10 持続可能な経済的及び社会的発展を促進する行動
(a) 国際的な協調をふまえて,国内的ならびに国際的努力によって、貧困を根絶するという適切な方策と合意された目標を基礎とする、総合的な行動をすすめること。
(b) 各国における経済的、社会的不平等を軽減することをめざした政策や計画を具体化する力量を、国際的な協力を通じて強めること。
(c) 途上国の対外債務や債務返済問題に対して、効果的で公正な、開発を志向し持続性のあ る解決法を、とりわけ債務軽減によって促進すること。
(d) 持続可能な食糧の安全な確保の国家的な方策を実現するためのあ らゆるレベルの行動を強化する。その中には、国際協調を通して債務軽減から資源を生み出し、あ らゆる資源の分配と利用を、積極的かつ最も効果的にすすめる行動を発達させること。
(e) 開発の過程が参加型であり、開発の計画にすべての人々が参加することを保障するさらなる努力をすること。
(f) ジェンダーに基づくもののみかたと、女性と少女がエンパワメントすることは開発の過程の大切な一部であ る。
(g) 発展の方策は、特別な要求を持っている人々と同様に、女性や子供たちの要求に焦点を当てた特別な対策が含まれなければならない。
(h) 紛争後の状況に置ける開発の援助は、紛争に関わるすべての人々を含めて、社会復帰、 再統合そして和解の過程を強化しなければならない。
(i) 天然資源の保全と再生を含めて、持続可能な環境を確かなものとするための開発方策や計画の力量を高めること。
(j) 自決の権利を実現する上での障害を取り除くこと。特に植民地、あ るいはその他の形での外国人の支配占領、社会的経済的な発展に影響を与えている外国の占領下に生活 している人々の障害を取り除くこと。
11 あらゆる人権の尊重を促進する行動
(a) 「ウイ−ン宣言」と行動計画を完全に実施すること。
(b) あらゆる人権を促進し擁護するための国内的な行動計画の発展を奨励すること。
(c) 国の人権擁護機関をはじめとして、人権 の分野において国内の組織と力量を強めるこ と。
(d) 「発展の権利に関する宣言」と「ウイ−ン宣言」ならびに「行動計画」で確立さ
れたように、発展への権利を自覚し実施すること。
(e) 「人権教育のための国連10年(1995-2004)」の目標を達成すること。
(f) 「世界人権宣言」をあらゆるレベルで普及し促進すること。
(g) 1993年12月20日の国連総会決議48/141で確立された国連人権 高等弁務官の権限と、その後の諸決議・諸決定で決められた責任の実行を、さらにより強く支えること。
12 女性と男性の間の平等を保障する行動
(a) あらゆる国際文書の適用にあたってジェンダーの視点を貫くこと。
(b) 女性と男性の平等を促進する国際文書をさらに実現すること。
(c) 第4回世界女性会議で採択された「北京行動綱領」を、適切な資源と政治的決意をもって実施すること。とりわけ、国内行動計画を、練りあ げ、実施し、徹底しなければならない。
(d) 経済的、社会的そして政治的意志決定において女性と男性の平等を促進すること。
(e) 女性に対するあらゆる形態の差別と暴力をなくすために、国連組織の関連した部局による努力をさらに強めること。
(f) 家庭、職場そして武力紛争時をふくめて、あ らゆる形態の暴力の犠牲になっている女性への援助と支援の対策を講じること。
13 民主主義的な参加を促進する行動
(a) 民主民主主義の原則と実践を促進するあ らゆる行動を強化すること。
(b) 学校教育・社会教育・家庭教育などあ らゆる学習の場において、民主主義の原則と実践を特に強調すること。
(c) 民主主義を発展・維持させる国内的な組織と過程の強化と確立をはかること。特に公務員の訓練と力量形成が重要であ る。
(d) 関係する諸国家の要請と、関連する国連の指針に基づく、選挙の協力の準備によって、特に民主主義的な参加を強化する。
(e) テロリズム、組織犯罪、汚職・腐敗、不法な薬物の製造・密売・使用、マネーローンダリング(不正資金浄化)とたたかうこと。それらは民主主義の土台を崩して、平和の文化の十分な発展を遅らせるからであ る。
14 相互理解、寛容、連帯を促進する行動
(a) 1995年の国連寛容年の「寛容の原則に関する宣言と行動実施計画」を実行す
ること。
(b) 2001年の「国連文明間の対話年」に関連する活動を支援すること。
(c) 地域固有のあるいは先住民による対立決着と寛容促進の実践と伝統を、そこから学ぶ という目的で、さらに研究すること。
(d) 社会全体、とりわけ弱い立場の人々との相互理解と寛容と連帯を強める行動を支援すること。
(e) 「世界の先住民の国際10年」の目標の達成をさらに支援すること。
(f) 難民や避難民の自発的な帰還や社会的な統合を促進する目的を心にとめて、彼らとの寛容や連帯を促進する活動を支援すること。
(g) 移住者との寛容や連帯を促進する活動を支援すること。
(h) とりわけ新しい技術の適切な使用と情報の普及を通じて、全ての人々の間のより深い理解、寛容協力を促進すること。
(i) 人々の間と国内および国家間の相互理解、寛容、連帯、協力を促進する行動を支援すること。
15 参加型のコミュニケーションと情報や知識の自由な流れを支える行動
(a) 平和の文化を促進するメディアの重要な役割りを支持すること。
(b) 報道の自由および情報とコミュニケ−ションの自由を保障すること。
(c) 国連や関連する地域的、国内的、地方的な機構を含めて、平和の文化に関する情報の宣伝と普及のためのメディアを効果的に利用すること。
(d) さまざまなコミュニティが要求を表明し意志決定に参加することを可能にするマスコミを育てること。
(e) 新しいコミュニケーション技術とりわけインタ−ネットを含め、メディアの中の暴力問題への措置を講じること。
(f) インタ−ネットを含めた新しい情報技術についての情報の共有を促進する努力をさらにすすめること。
16 国際的な平和と安全を促進する行動
(a) 軍縮の分野での国連によって確立された優先順位を考慮しつつ、厳密で効果的な国際的なコントロ−ルのもとに、全般的完全軍縮(軍備撤廃)をすすめること。
(b) 平和の文化を推進するにあたり、できるところでは、世界のいくつかの国で取り組まれている「軍事から民事への転換」の努力に学ぶこと。
(c) 戦争による領土の獲得の不承認と、正義に基づく永遠の平和のために世界中のあ らゆ るところで働く必要性を強調すること。
(d) 交渉によって平和的な解決を導くために、信頼醸成の措置と努力を励ますこと。
(e) 不法な小火器や軽武器を製造したり売買したりさせないように手だてをとること。
(f) 紛争後の状況からおこってくる具体的な問題にたいして、国内的、地域的、国際的なレベルで自発的・積極的な構想とその実行を支えること。たとえば、軍隊の解体、戦闘員の社会復帰、難民や避難民の帰還、武器回収プログラム、情報交換、信頼構築な どがある。
(g) 国際法や国連憲章の精神に反するような一方的な措置を押さえ抑制すること。一方的措置とは、当事国に住む人々、とりわけ女性や子どもたちの経済的・社会的発達の十分な達成を遅らせるような措置であ り、人々の幸福を損ない、人権の十全な享受を妨げる。その人権には、すべての人の持つ権 利である、健康な生活のための最低基準の権利、および、食料や医療や必要な社会サ−ビスを受ける権 利がある。食料や医療の提供が政治的な圧力として使われてはならない。
(h) 国際法や国連憲章の精神である国家の政治的な独立や領土の保全に反する、軍事的・ 政治的、経済的あるいはその他いかなる形態の弾圧も、これを認めないこと。
(i) 制裁措置の民衆への影響をできるだけ小さくするという視点で、制裁における人道的に問題のあ る影響、特に女性や子どもへの影響の問題について、適切な配慮をするように勧告すること。
(j) 紛争の予防と解決に、女性のより多大な参加と活躍をすすめること。紛争後の平和の文化をすすめる行動の中では特に必要であ る。
(k) 紛争状態の中での、予防注射の促進と薬の配布キャンペ−ンための休戦日、人道的な 物資供給・配布を保障する平和の通路、病院や診療所などの健康や医療の施設の役割 を尊重する平和の聖域、などのような積極的・主体的な構想とその実行を推進するこ と。
(l) 国連や、関連する地域機構や、国連加盟国のスタッフにたいして、要請に応じ適切な場合に、紛争の理解と予防と解決のための技法のトレーニングを推進すること。
出典 http://homepage2.nifty.com/peacecom/cop/cop_actionplan.htm