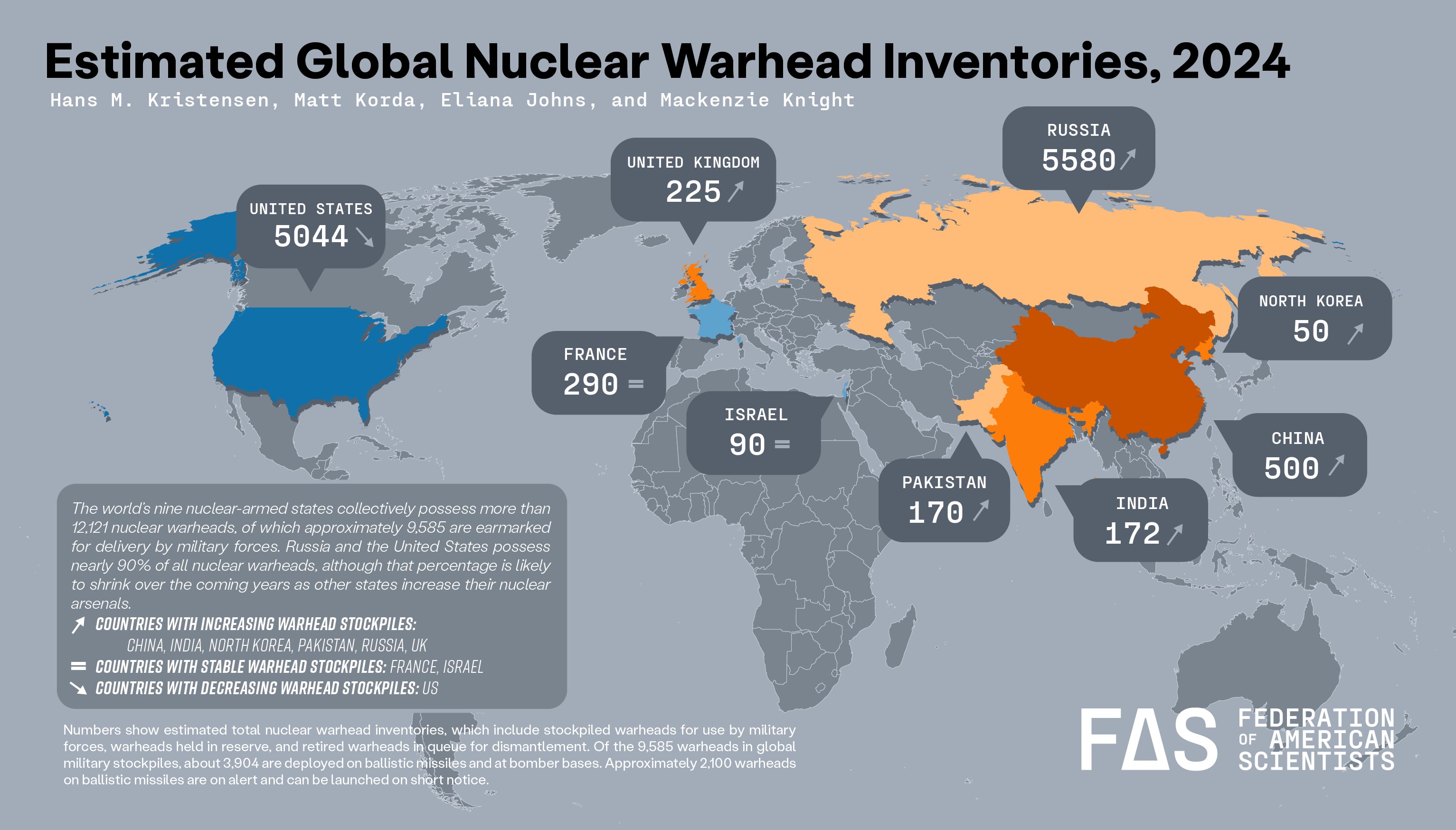「戦争ほど、残酷なものはない。戦争ほど、悲惨なものはない。だが、その戦争はまだ、つづいていた」から始まる小説『人間革命』、「平和ほど、尊きものはない。平和ほど、幸福なものはない。平和こそ、人類の進むべき、根本の第一歩であらねばならない」から始まる小説『新・人間革命』は、池田先生がつづられた創価学会の「精神の正史」です。
戸田先生と池田先生の姿を通し師弟の生き方が記された、学会員の「信心の教科書」ともいえます。
また、そこにつづられているのは、宿命の嵐と戦い、広宣流布に生き抜く、無名の庶民による人間革命の劇であり、それは、宿命を使命に転じ、蘇生した、地涌の菩薩の群像でもあります。
・『人間革命』『新・人間革命』には、学会員の生き方が描かれているんですね。
『人間革命』第1巻「はじめに」に記されている「一人の人間における偉大な人間革命は、やがて一国の宿命の転換をも成し遂げ、さらに全人類の宿命の転換をも可能にする」との主題こそ、私たち創価学会の運動が目指すものです。
『新・人間革命』第1巻「あとがき」には、こうあります。「生命の続く限り、私は書き続ける。正しい仏法とは何か。正しい人生とは何か。そして、何が歴史の『真実』か。人間にとって『正義』の戦いとは何かを。そこに、人類の未来を開く、一筋の道があるからだ」この小説に示された指針を、私たちが「精読」し「実践」することが大切といえるでしょう。
人間革命(にんげんかくめい)は、創価学会の戸田城聖(第2代会長)によって唱えられた宗教思想。その意味は、自分自身の生命や境涯をより良い方向へ変革し、人間として成長・向上を目指すということである。さらに、各個人が「人間革命」を遂げることにより、社会全体の変革さえも可能であると説かれている。
小説の『人間革命』は、この「人間革命」の思想をテーマとして、創価学会の歴史と戸田城聖の生涯を描いた長編小説。
創価学会名誉会長(第3代会長)池田大作の代表的な著作である。創価学会では教学上重要な文献とされ、「精神の正史」と位置付けられる。
池田大作(名誉会長)の小説『人間革命』は1965年(昭和40年)に聖教新聞で連載を開始し、1993年(平成5年)に完結した。続編『新・人間革命』は1993年(平成5年)に聖教新聞で連載を開始し、2018年(平成30年)に完結した。
本項では、戸田城聖が1951年に聖教新聞の創刊号で連載を開始し、1954年に完結した同名の小説『人間革命』(後に『小説 人間革命』と改題)についても併せて紹介する。
小説
小説としての『人間革命』は、戸田城聖(第2代会長)の創価教育学会再建から戸田城聖の死去までの経過と、山本伸一(池田大作の別名義)の1947年(昭和22年)の創価学会への入信から1960年(昭和35年)の第3代会長の就任までを描いている。全12巻。 続編の『新・人間革命』は、山本伸一の1960年(昭和35年)の創価学会の第3代会長就任から1991年(平成3年)の日蓮正宗(宗門)との決別までを描いている。全30巻31冊。
戸田城聖による同名の小説『人間革命』と、池田大作による同名の小説『人間革命』(英語題:"The Human Revolution")で、いずれも『聖教新聞』に連載された。戸田版は創価学会草創期のエピソードを、池田版は創価学会再建期からのエピソードなどを小説化したもの。
事実に基づいたフィクションの体裁を取るため、登場人物の氏名は変更されている。戸田版『人間革命』において、戸田城聖は主人公の「巌 九十翁(がん くつお)」の変名で登場するが、創価学会初代会長の牧口常三郎は「牧田城三郎(まきた じょうざぶろう)」の変名を使っていた。だが、平成以降の増刷版では牧口常三郎については実名表記となり、事実上ノンフィクションとなった。
池田版『人間革命』並びに『新・人間革命』に牧口常三郎と戸田城聖は実名で登場するが、主人公の池田大作(第3代会長、のちに名誉会長)は「山本伸一(やまもと しんいち)」、第4代会長の北条浩は「十条潔(じゅうじょう きよし)」、第5代会長の秋谷栄之助は「秋月英介(あきづき えいすけ)」の変名で登場する。
聖教新聞社によれば、池田版の『人間革命』とその続編『新・人間革命』(英語題:"The New Human Revolution")は、2018年9月8日の連載終了時点で7,978回(『人間革命』1,509回、『新・人間革命』6,469回)に及んでいる。日本の新聞小説の連載回数としては山岡荘八の小説『徳川家康』を上回り、史上最長とされた。
池田版には川端龍子、三芳悌吉による挿絵がある。
成立過程
戸田城聖は「妙 悟空(みょう ごくう)」というペンネーム(筆名)のもと、1951年(昭和26年)から『聖教新聞』に『人間革命』を連載して1954年(昭和29年)に完結した。1957年(昭和32年)に単行本が刊行され、1988年(平成10年)に『戸田城聖全集』の第8巻に収録された。これを引き継ぐ形で、池田大作が「法 悟空(ほう ごくう)」というペンネーム(筆名)のもと、1965年(昭和40年)から『聖教新聞』に『人間革命』を連載し、1993年(平成5年)に完結した。
戸田版は1951年(昭和26年)4月20日(『聖教新聞』創刊号)から1954年(昭和29年)8月1日までの3年4か月、池田版は1965年(昭和40年)1月1日から1993年(平成5年)2月11日まで幾度の休載を挟みながら28年1か月強連載された。その後、1993年(平成5年)11月18日から2018年(平成30年)9月8日まで続編の『新・人間革命』が24年10か月弱連載された。『新・人間革命』の単行本の最終巻となった第30巻は上下巻に分割して刊行されたため、単行本は実質的には全31冊となった。これは、単行本第1巻の前書きで「全30巻を予定している」と記したものの、第30巻が1冊で収まらなくなるほどの分量となったためである。
現在、刊行されている池田版『人間革命』は、『池田大作全集』(「全150巻に及ぶ世界最大級の個人全集である」と創価学会側は主張している)に所収(第144巻 - 第149巻に収録。全12巻を6巻分に再編し、2012年9月から2013年7月まで刊行)される際に改訂されている(これを第2版とする)。
第2版では、全集刊行委員会が修正を提案し、池田の了承を得て修正した箇所が複数ある。変更箇所は主に日蓮正宗に関連する用語などで、例えば初版では作中に登場する日蓮正宗(宗門)の僧侶を「先生」や「尊師」といった敬称で呼んでいたところを、第2版では「住職」という比較的尊敬の意味の薄い呼び方に置き換えられた。この第2版は単行本としてではなく文庫(聖教ワイド文庫)版として、全12巻が2012年12月から2013年12月にかけて刊行された。
位置付け
『人間革命』は創価学会の教学上重要な文献とされ、1977年(昭和52年)1月の第9回教学部大会での講演「仏教史観を語る」で、第3代会長池田大作は自らの『人間革命』を日蓮の遺文を集めた御書(創価学会が刊行している「新編 日蓮大聖人御書全集」または「日蓮大聖人御書全集 新版」をさす)に匹敵する書物として位置付けた。
創価学会の教学部が実施する教学試験(任用試験、3級、2級、1級の4ランクがある)を受験しようとする創価学会員には日蓮大聖人の御書に加えて、『人間革命』三部作、その中でも特に池田版『人間革命』及び『新・人間革命』を理解することが求められた。
ただし、三部作はあくまでも事実に基づいたフィクションの体裁を取っている関係で、変名を使用しない完全な事実のみを記載したという意味では、同じく創価学会が発行する月刊機関誌『大白蓮華』の巻頭企画の方が歴史的な資料性が高い。
→「大白蓮華 § 企画」、および「創価学会 § 名誉会長・歴代会長」も参照
聖教新聞社によれば、2018年時点で『新・人間革命』の累計発行部数は2400万部、『人間革命』と『新・人間革命』を合わせると5400万部である。
批判
島田裕巳は、『戸田版』が別人による代作であった可能性を示唆した。その理由として、戸田には他にまとまった著作がほとんどないことを挙げている。
→「戸田城聖 § 著作・論文」も参照
また、『池田版』にもゴーストライターが存在するという指摘が月刊ペン事件の公判で明らかにされている。
さらに、『新・人間革命』や2006年(平成18年)3月から2023年(令和5年)11月に死去するまで池田大作が機関誌『大白蓮華』に寄稿していた巻頭言についても聖教新聞社の担当職員による代作説が指摘されていた。
これらの指摘に対して創価学会側は「『池田版』の一部の原稿については、後述する理由から池田自身が執筆していない」ことを公式に認めている。理由については、「『池田版』は著者の池田大作が多忙を極める中で執筆していたほか、池田自身の体調不良によって執筆が中断することもあったため、一部の原稿については池田大作の妻・池田香峯子や聖教新聞社で『池田版』を担当していた記者による口述筆記のほか、カセットテープに録音された池田の肉声を文章化(文字起こし)する形で補っていた」と説明している。
映画
人間革命
監督 舛田利雄
脚本 橋本忍
製作 田中友幸
出演者 丹波哲郎
音楽 伊福部昭
撮影 西垣六郎
製作会社
東宝映像
シナノ企画
配給 東宝
公開 1973年10月6日
上映時間 160分
製作国 日本
言語 日本語
配給収入 13億円
続・人間革命
監督 舛田利雄
脚本 橋本忍
製作 田中友幸
出演者 丹波哲郎
音楽 伊部晴美
撮影 西垣六郎
製作会社
東宝映像
シナノ企画
配給 東宝
公開 1976年6月19日
上映時間 159分
製作国 日本
言語 日本語
配給収入 16億700万円
(1976年邦画配給収入1位)
1973年(昭和48年)9月8日に、『人間革命』のタイトルで東宝と創価学会系のシナノ企画の共同製作で映画化された。1976年(昭和51年)に、ほぼ同じスタッフ・キャストで『続・人間革命』が公開されている。スタッフ、キャストともほとんどが創価学会の外部からの豪華な俳優メンバーであり、あくまで一般映画の大作としてアピールした。
東宝映像が制作を行っていることから、1作目の『人間革命』(1973年公開)での十界論のイメージや2作目の『続・人間革命』(1976年)での日蓮大聖人の著作「立正安国論」の天変地異の描写などに特撮が用いられている。
当時は映画業界の斜陽化により特撮作品の制作も減少していたが、東宝は本作品でその存在感を知らしめ、以後キャラクター・パニックもの以外の映画やCMなどでの特撮制作の受注が増加していった[26]。
1973年の観客動員数では、『日本沈没』に次ぐ第2位となった。
2006年にシナノ企画からDVDが発売されている。2018年10月〜11月にスカパー!の日本映画専門チャンネルでテレビ初放送された。
人間革命(1973年)
キャスト
戸田城聖:丹波哲郎
牧口常三郎:芦田伸介
戸田幾枝:新珠三千代
戸田喬一:木下圭介
山平忠平:森次晃嗣
栗川:名古屋章
奥村:桑山正一
工藤:伊藤るり子
片山:伊豆肇
高島:堺左千夫
三島由造:稲葉義男
北川直作:田島義文
藤崎洋一:浜田寅彦
岩森喜造:加藤和夫
本田洋一郎:内田稔
室田日照:山谷初男
清原かつ:福田公子
泉田ため:瞳麗子
小西武雄:佐原健二
原山幸一:長谷川明男
関久男:石矢博
堀米内務部長:草川直也
渡辺弁護士:平田昭彦
ジャンパーの男:渡哲也
検事:青木義朗
看守:谷村昌彦
刑事:細井利雄
学会員:鈴木ヤスシ、塩沢とき
病気の男:佐藤允
大喧嘩をする夫婦:雪村いづみ、江角英明
銀行強盗:黒沢年男
インターン:山本豊三
サラリーマン:高松しげお
若い女性:松下ひろみ
女性の恋人:鳥居功靖
日蓮大聖人:仲代達矢
スタッフ
企画:〝人間革命〟製作委員会
製作:田中友幸
製作補:田実泰良
監督:舛田利雄
脚本:橋本忍
原作:池田大作
撮影:西垣六郎
美術:村木与四郎
録音:増尾鼎
照明:森本正邦
音楽:伊福部昭
監督助手:渥美和明
編集:黒岩義民
スチール:中山章
特殊技術:中野昭慶
特殊撮影:富岡素敬
特殊美術:井口昭彦
特殊照明:大内良雄
合成:三瓶一信
製作:シナノ企画、東宝映像
キャスト