都議会公明党の語れる実績
防災・減災
橋の耐震化、長寿命化
事業費やCO2排出を大幅削減
震災時の応急活動や避難に必要な、都内の緊急輸送道路などに架かる413橋の7割超がすでに耐震化され、3年後には、ほぼ完了する計画が進んでいます。
一方で、老朽化が進む橋の管理が課題。都によると新しく架け替えるためには、新設の約2.7倍の費用が掛かります。こうした従来の対症療法型の管理では、総事業費が今後30年間で、約1兆6000億円掛かるとともに、環境負荷も二酸化炭素(CO2)の排出量が年間で約5.3万トンに上ります。
これを、長寿命化など予防保全型の管理に転換することで、30年間の事業費は3分の1の約5000億円まで縮減できます。最新の技術により、橋を100年(一部の著名な橋は200年)以上“延命”させる事業で、CO2の排出量も3分の1以下の年間約1.6万トンに抑えられ、30年間で約110万トン削減できる計画です。
帰宅困難者対策
全国初の条例制定し、対応急ぐ
東日本大震災では、都内の帰宅困難者が300万人を超えました。これを教訓に、災害時の混乱を避け、都民の命を守るため、総合的な対策を進める都の帰宅困難者対策条例が、昨年3月に制定されました。条例化は全国初で、今年4月から施行されます。
具体的には、(1)事業者に対して一斉帰宅の抑制と従業員の3日間分の食料備蓄(2)駅や集客施設における利用者保護と、学校における児童・生徒の安全確保―などの努力義務を明記。また、官民が協力して「安否確認や災害情報を提供できる基盤の整備」や「一時滞在施設の確保」などを進めるとしています。
この条例を踏まえて都は、昨年11月に実施計画を策定。首都直下地震では、帰宅困難者は517万人に及び、一時滞在施設の需要は最低でも92万人分(東京ドーム約33個分)に上ると想定して、対応を急いでいます。
地域防災に女性の視点
都防災会議に女性委員登用など
昨年11月に修正された都地域防災計画に、女性の視点を重視した対応が盛り込まれています。
中でも、避難所の運営については、管理責任者に女性を配置することなどを明記。また、女性専用の物干し場や、更衣室、授乳室の設置に加え、生理用品や女性用下着の女性による配布も確認。パトロールの実施や照明による避難所の安全性確保など、女性や子育て家庭のニーズ(要望)に配慮した運営に努めることも盛り込まれました。帰宅困難者対策でも、一時滞在施設に授乳や女性優先のスペースを設けることが示されています。
一方、都防災会議については、これまで女性の委員がほとんど登用されていませんでした。今年1月、公明党は猪瀬直樹知事に女性委員の登用を強く要望。3月13日の都議会予算特別委員会で、公明党の質問に対して猪瀬知事は、都防災会議に「複数の女性委員を登用し、女性の防災専門家の知識を取り入れていく」と表明しました。
救命部隊が災害に威力
ハイパーレスキュー隊など活躍
東日本大震災の被災地で大活躍したハイパーレスキュー隊(消防救助機動部隊)や東京DMAT(災害医療派遣チーム)をはじめ、東京型ドクターヘリなど、全国をリードする“東京の救命部隊”が災害時に威力を発揮しています。
阪神・淡路大震災を教訓に、公明党の提案で1996年12月に発足したハイパーレスキュー隊は、通常の消防力では対応できない災害に、高度な能力を持つ隊員が、大型重機や最新の救助装備で立ち向かいます。東日本大震災では、被災した東京電力福島第1原発で決死の放水作業に挑みました。今月、新たに第9消防方面でも結成され、都内に10カ所ある消防方面本部のうち、5本部まで拡大されます。
東京DMATは、専門の医師や看護師などで編成され、大震災や交通事故などの現場へ急行し、救命処置を行います。2004年8月に7病院体制で発足。昨年3月、新たに3病院が加えられ、現在、25病院体制になっています。
また、24時間体制で患者のもとへ飛ぶ東京型ドクターヘリは、東京全域をカバーしています。
仕事・暮らし
中小企業支援
特別借換制度など資金繰り支援
中小企業金融円滑化法が3月末で期限切れとなることから、都独自の新たな融資制度「特別借換」が創設され、3月1日から受け付けが始まっています。借り換えにより月々の債務返済額を低く抑える制度で、中小企業の資金繰りを支援します。
公明党は昨年9月の都議会定例会で、「(これまで円滑化法により返済条件を変更してきた中小企業の間で)このままでは、融資が打ち切られるのではないかとの心配が広がっている」と訴え、対策を求めました。
既存の都の借換制度では、限度額が5000万円などの制限がありましたが、新制度は、借入残高の範囲内であれば限度額を設けず、複数の借入金を一本化できます。また、従業員数が20人以下の製造業(卸、小売、サービス業は5人以下)などの小規模企業者に対しては、保証料の2分の1が補助されます。
一方、地域の金融機関と連携して融資する、都独自の新保証付融資制度も、創設3年で約3000社に利用され、好評です。
東京しごとセンター
延べ100万人利用、8万人就職
若者から高齢者まで、あらゆる年齢層の就職をきめ細かなサービスで支援する「東京しごとセンター」(千代田区)が04年にオープンし、続いて「東京しごとセンター多摩」(国分寺市)が07年に開設されました。
就職のための各種支援を1カ所で提供するワンストップサービスセンターです。マンツーマンのカウンセリングでは、職務履歴の“棚卸(再確認)”や自己分析をした上で、ハローワークや民間の求人情報を利用しながら、適性に合った職業紹介が行われます。
両センターの利用者は開設以来、12年度までで延べ100万人に上り、就職に結び付いた人は8万人を超えました。
自転車安全利用で条例
点検・整備や保険加入の努力義務
自転車が関係する事故が交通事故全体に占める割合は、全国平均の20%前後に対し、都内では37.3%(11年度)に上りました。
公明党の推進により今月の都議会定例会で、自転車の安全利用を促進する都の条例が制定される見通しです。
同条例案には、利用者に対する(1)安全利用に必要な技能や知識の習得(2)安全基準に適合する自転車の利用と点検・整備(3)ヘルメットの着用(4)損害賠償保険への加入―などの努力義務を明記。都が安全利用指針を作成して公表することも盛り込まれています。また、小売業者の違法自転車の販売や、整備業者の違法な改造の禁止なども定められています。
被災地支援
都職員の長期派遣
これまで、警視庁や東京消防庁を含む3万人以上の都職員を被災地に派遣。現在も機動隊などを含む約200人が現地の復興を支えています。中でも、被災地で即戦力となる土木など技術系専門職の「任期付き職員」派遣(47人)は全国初。
応援ツアー1泊3000円補助
福島県への旅行者に1泊3000円を補助する被災地応援ツアーが、13年度も2万泊分(日帰りは1回1500円補助で1万5000回分)実施予定。11年度は被災3県へ5万泊分、12年度は福島県へ4万泊分(日帰り1万5000回分)実施されました。
ふくしまキャンペーン
鉄道事業者や区市町村などと協力し、福島県の生産物販売や観光をバックアップする「ふくしま⇔東京 キャンペーン」。JRの秋葉原や上野の駅構内での「産直市」や、各種イベントでの県産品のPRなどが展開されています。
子どものスポーツ交流
被災地では体育館や校庭が避難所などに使われ、思うように野球やサッカーができない子どもたちを都内に招き、試合やホームステイを通して交流。11年8月以来、9回開催され、東北の子どもたち180人が思い出を刻みました。
都内小売業者の現地視察
「売り手」が自信を持って福島県の農産物をPRできるように、都内の小売業者などが現地で、農産物の万全な放射線検査体制などを視察する研修会(12年10、11月実施)が好評を博しました。今後、水産物についても実施する方向です。
行政改革
全国初の新公会計制度
財政の「見える化」で隠れ借金解消
 活用できる基金残高の推移
活用できる基金残高の推移
東京都は、都議会公明党の提案を受け、2006年度に全国で初めて、企業会計の手法である「複式簿記・発生主義会計」を取り入れた「新公会計制度」を導入しました。
10年ほど前、都は深刻な財政難でしたが、当時は、現金の出入りだけを記帳する“家計簿”のような会計手法だったため、将来の負担などが不明確でした。しかし、新制度によって財政が「見える化」され、財産の状況を正確に把握できるようになった結果、都債返済のための積み立て不足など、約1兆円の“隠れ借金”が判明し、わずか2年間でほぼ解消されました。
また、税収減などに備えた“活用できる基金”の残高は、新制度の導入後、約2年間で1兆円積み増しされ、リーマン・ショックや東日本大震災後の財政需要にも、即応できるまでになっています。
さらに、新制度を活用して事業の徹底検証を行い、13年度予算案では約230億円もの財源を確保するなど、職員のコスト意識も大幅に向上しています。
都庁のスリム化進める
外郭団体を半減。職員も4分の3に
“天下りの温床”との批判もあった都の監理団体(外郭団体)。公明党が一貫して整理統合を訴えた結果、団体数はピーク時の72団体(1993年度)から、現在では33団体まで半減しました。役員退職金の廃止や役員報酬の引き下げなども断行され、99年度に2741億円だった都の財政支出は、13年度には2176億円となり、約21%も削減されています。
一方、都の職員定数は、ピーク時の78年度には22万2789人まで膨れ上がり、巨額の人件費が財政を圧迫していましたが、13年度の定数は16万5379人(予定)となり、35年前の4分の3にまで減っています。
職員の通勤定期代も、支給を1カ月単位から6カ月単位に変更することで、年間約34億円を節約しました。
環境
公共交通の利用促進
ポイントサービス「トコポ」実施
環境に優しい公共交通の利用を促す取り組みとして、11年8月から、都営交通に乗車するとポイントがたまるサービス「ToKoPo(トコポ)」が実施されています。この制度は、08年8月に公明党東京都本部青年局が都に要望し、実現したもので、都によると、現在の会員数は約7万6000人となっています。
会員になると、ICカード「PASMO(パスモ)」を使って都営地下鉄や日暮里・舎人ライナーなどに乗車した場合に、1ポイントを1円として換算できるポイントが付与されます。その上で、地下鉄からバスといった都営交通同士の乗り継ぎや、一部を除く土曜・休日の利用には、ボーナスポイントが加算されます。誰でも会員登録が可能で、入会費、年会費は無料です。
CO2削減を義務付け
大規模事業所の排出量が23%減少
 大規模事業所の温室効果ガス排出量削減実績
大規模事業所の温室効果ガス排出量削減実績
地球温暖化対策に向けて都は、10年4月から全国で初めて、大規模事業所を対象とした「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度(キャップ・アンド・トレード)」をスタート。二酸化炭素(CO2)排出量の削減に効果を挙げています。
総量削減義務では、大規模オフィスビルや商業施設、工場など1392の事業所が、02~07年度から任意で選んだ連続3カ年度の平均排出量を「基準排出量」に設定。10~14年度の5年間で、施設の内容に応じ、基準排出量の8%または6%を削減します。
排出量取引は、他者の排出削減量を購入し、自らの削減量に充当できる制度で、大規模事業所の義務超過分のほか、要件を満たす都内中小規模事業所が省エネで削減した分も、取引の対象となります。
対象事業所が前年度実績などを記載する「地球温暖化対策計画書」の集計(速報値)によると、11年度は節電の推進などにより、基準排出量と比べて23%もの削減が実現しました。
福祉・医療
バリアフリー化が拡大
駅のホームドアなど整備を推進
公明党が長年取り組んできた、バリアフリーのまちづくりが大きく進んでいます。
駅のホームからの転落を防ぐホームドアについては、都営地下鉄三田線の全駅で整備され、同大江戸線でも今年6月に整備完了の見込みです。また、国、都、区が補助を行う新たな仕組みの創設により、小田急、京王の両新宿駅、東急大井町線大井町駅にもホームドアが設置されました。一方、JR山手線では、14年度までに6割を超す駅で設置予定となっています。
さらに、各地の駅や公共施設などへのエレベーターや、身体障がい者用トイレの設置も進められているほか、地下鉄では、色覚障がい者に対応した駅名表示も実現しました。高齢者などが乗り降りしやすいノンステップバスも、全国トップクラスの導入率です。
このほか公明党は、視聴覚障がい者のために音声ガイドや字幕を付けた「バリアフリー映画」についても、積極的に上映を推進しています。
がん治療に最新技術
駒込病院に高精度の放射線機器
都民の死因第1位であり、死亡割合の3割を占める、がんについて、公明党は積極的に対策を講じてきました。
中でも、都の「がん・感染症センター」である都立駒込病院(文京区)では、11年9月のリニューアルに伴い、がん細胞にピンポイントで照射する「サイバーナイフ」など、高精度の放射線機器3台を、全国で初めて一度に導入。手術室の増設や通院治療体制の拡充、病状の進行による苦痛を和らげる「緩和ケア」病棟の設置などにより、高度ながん医療を提供しています。
このほか都内では、東邦大学医療センター大森病院(大田区)など、3カ所の病院で電話などによる休日・夜間のがん相談を行っています。
小児総合医療センター
救急など充実し子どもの命守る
10年3月にオープンした都立小児総合医療センター(府中市)。都立多摩総合医療センターと同じ建物内にあり、全国初の試みとなる「小児」と「成人」の総合医療機関の併設となっています。
特に周産期医療では、両センターが連携して重症の妊産婦患者に対応。新生児集中治療室(NICU)24床などを備えており、多摩地域の新生児救急を担っています。
また、小児救急医療では、新生児用と小児用のドクターカーを配備。全国初となる小児専門の救急治療室(ER)では、ほぼ全ての疾患の初期診療に対応し、治療の優先順位を判断する「トリアージ」によって、より病状の重い子どもから治療しています。
ひと口実績
小・中学校の教室を冷房化
公立小・中学校普通教室に冷房設備を導入する市町村に対し、2010年度から財政支援を実施。この結果、市町村での設置率は、22.5%(10年11月)から94.4%(12年度末見込み)へと上昇しました。なお、23区は100%設置済みです。
子ども医療費の助成拡充
子どもの医療費は、23区については中学3年生まで完全無料化。市町村については、入院は中学3年生まで無料、通院は就学前が無料で、小・中学生は多くの自治体が受診1件当たり200円までとなっています(一部地域では無料化)。
妊産婦救う体制を確保
脳卒中などの重症な疾患により、緊急に母体救命処置が必要な妊産婦を必ず受け入れる「スーパー総合周産期センター」として、昭和大学病院(品川区)や日本大学医学部付属板橋病院(板橋区)など都内4カ所の医療機関が指定されています。
盲ろう者に支援センター
目も耳も不自由な「盲ろう者」の支援センター(台東区)が、09年に全国で初めてオープンしました。コミュニケーションなどの訓練や各種相談、通訳・介助者の養成や派遣などの事業によって、盲ろう者の社会参加を後押ししています。
校庭芝生化が551カ所に
まちの緑を増やし、子どもの心を育む校庭の芝生化は、11年度末までに公立小・中学校275校、都立学校65校で実施され、幼稚園、保育所、私立学校についても、モデル事業として211カ所に拡大。これらを合計した551カ所の面積は約66.7ヘクタールに。
文中敬称略、肩書は当時
2013年3月25日、26日付 公明新聞
都議会公明党の語れる実績
防災・減災
橋の耐震化、長寿命化
事業費やCO2排出を大幅削減
震災時の応急活動や避難に必要な、都内の緊急輸送道路などに架かる413橋の7割超がすでに耐震化され、3年後には、ほぼ完了する計画が進んでいます。
一方で、老朽化が進む橋の管理が課題。都によると新しく架け替えるためには、新設の約2.7倍の費用が掛かります。こうした従来の対症療法型の管理では、総事業費が今後30年間で、約1兆6000億円掛かるとともに、環境負荷も二酸化炭素(CO2)の排出量が年間で約5.3万トンに上ります。
これを、長寿命化など予防保全型の管理に転換することで、30年間の事業費は3分の1の約5000億円まで縮減できます。最新の技術により、橋を100年(一部の著名な橋は200年)以上“延命”させる事業で、CO2の排出量も3分の1以下の年間約1.6万トンに抑えられ、30年間で約110万トン削減できる計画です。
帰宅困難者対策
全国初の条例制定し、対応急ぐ
東日本大震災では、都内の帰宅困難者が300万人を超えました。これを教訓に、災害時の混乱を避け、都民の命を守るため、総合的な対策を進める都の帰宅困難者対策条例が、昨年3月に制定されました。条例化は全国初で、今年4月から施行されます。
具体的には、(1)事業者に対して一斉帰宅の抑制と従業員の3日間分の食料備蓄(2)駅や集客施設における利用者保護と、学校における児童・生徒の安全確保―などの努力義務を明記。また、官民が協力して「安否確認や災害情報を提供できる基盤の整備」や「一時滞在施設の確保」などを進めるとしています。
この条例を踏まえて都は、昨年11月に実施計画を策定。首都直下地震では、帰宅困難者は517万人に及び、一時滞在施設の需要は最低でも92万人分(東京ドーム約33個分)に上ると想定して、対応を急いでいます。
地域防災に女性の視点
都防災会議に女性委員登用など
昨年11月に修正された都地域防災計画に、女性の視点を重視した対応が盛り込まれています。
中でも、避難所の運営については、管理責任者に女性を配置することなどを明記。また、女性専用の物干し場や、更衣室、授乳室の設置に加え、生理用品や女性用下着の女性による配布も確認。パトロールの実施や照明による避難所の安全性確保など、女性や子育て家庭のニーズ(要望)に配慮した運営に努めることも盛り込まれました。帰宅困難者対策でも、一時滞在施設に授乳や女性優先のスペースを設けることが示されています。
一方、都防災会議については、これまで女性の委員がほとんど登用されていませんでした。今年1月、公明党は猪瀬直樹知事に女性委員の登用を強く要望。3月13日の都議会予算特別委員会で、公明党の質問に対して猪瀬知事は、都防災会議に「複数の女性委員を登用し、女性の防災専門家の知識を取り入れていく」と表明しました。
救命部隊が災害に威力
ハイパーレスキュー隊など活躍
東日本大震災の被災地で大活躍したハイパーレスキュー隊(消防救助機動部隊)や東京DMAT(災害医療派遣チーム)をはじめ、東京型ドクターヘリなど、全国をリードする“東京の救命部隊”が災害時に威力を発揮しています。
阪神・淡路大震災を教訓に、公明党の提案で1996年12月に発足したハイパーレスキュー隊は、通常の消防力では対応できない災害に、高度な能力を持つ隊員が、大型重機や最新の救助装備で立ち向かいます。東日本大震災では、被災した東京電力福島第1原発で決死の放水作業に挑みました。今月、新たに第9消防方面でも結成され、都内に10カ所ある消防方面本部のうち、5本部まで拡大されます。
東京DMATは、専門の医師や看護師などで編成され、大震災や交通事故などの現場へ急行し、救命処置を行います。2004年8月に7病院体制で発足。昨年3月、新たに3病院が加えられ、現在、25病院体制になっています。
また、24時間体制で患者のもとへ飛ぶ東京型ドクターヘリは、東京全域をカバーしています。
仕事・暮らし
中小企業支援
特別借換制度など資金繰り支援
中小企業金融円滑化法が3月末で期限切れとなることから、都独自の新たな融資制度「特別借換」が創設され、3月1日から受け付けが始まっています。借り換えにより月々の債務返済額を低く抑える制度で、中小企業の資金繰りを支援します。
公明党は昨年9月の都議会定例会で、「(これまで円滑化法により返済条件を変更してきた中小企業の間で)このままでは、融資が打ち切られるのではないかとの心配が広がっている」と訴え、対策を求めました。
既存の都の借換制度では、限度額が5000万円などの制限がありましたが、新制度は、借入残高の範囲内であれば限度額を設けず、複数の借入金を一本化できます。また、従業員数が20人以下の製造業(卸、小売、サービス業は5人以下)などの小規模企業者に対しては、保証料の2分の1が補助されます。
一方、地域の金融機関と連携して融資する、都独自の新保証付融資制度も、創設3年で約3000社に利用され、好評です。
東京しごとセンター
延べ100万人利用、8万人就職
若者から高齢者まで、あらゆる年齢層の就職をきめ細かなサービスで支援する「東京しごとセンター」(千代田区)が04年にオープンし、続いて「東京しごとセンター多摩」(国分寺市)が07年に開設されました。
就職のための各種支援を1カ所で提供するワンストップサービスセンターです。マンツーマンのカウンセリングでは、職務履歴の“棚卸(再確認)”や自己分析をした上で、ハローワークや民間の求人情報を利用しながら、適性に合った職業紹介が行われます。
両センターの利用者は開設以来、12年度までで延べ100万人に上り、就職に結び付いた人は8万人を超えました。
自転車安全利用で条例
点検・整備や保険加入の努力義務
自転車が関係する事故が交通事故全体に占める割合は、全国平均の20%前後に対し、都内では37.3%(11年度)に上りました。
公明党の推進により今月の都議会定例会で、自転車の安全利用を促進する都の条例が制定される見通しです。
同条例案には、利用者に対する(1)安全利用に必要な技能や知識の習得(2)安全基準に適合する自転車の利用と点検・整備(3)ヘルメットの着用(4)損害賠償保険への加入―などの努力義務を明記。都が安全利用指針を作成して公表することも盛り込まれています。また、小売業者の違法自転車の販売や、整備業者の違法な改造の禁止なども定められています。
被災地支援
都職員の長期派遣
これまで、警視庁や東京消防庁を含む3万人以上の都職員を被災地に派遣。現在も機動隊などを含む約200人が現地の復興を支えています。中でも、被災地で即戦力となる土木など技術系専門職の「任期付き職員」派遣(47人)は全国初。
応援ツアー1泊3000円補助
福島県への旅行者に1泊3000円を補助する被災地応援ツアーが、13年度も2万泊分(日帰りは1回1500円補助で1万5000回分)実施予定。11年度は被災3県へ5万泊分、12年度は福島県へ4万泊分(日帰り1万5000回分)実施されました。
ふくしまキャンペーン
鉄道事業者や区市町村などと協力し、福島県の生産物販売や観光をバックアップする「ふくしま⇔東京 キャンペーン」。JRの秋葉原や上野の駅構内での「産直市」や、各種イベントでの県産品のPRなどが展開されています。
子どものスポーツ交流
被災地では体育館や校庭が避難所などに使われ、思うように野球やサッカーができない子どもたちを都内に招き、試合やホームステイを通して交流。11年8月以来、9回開催され、東北の子どもたち180人が思い出を刻みました。
都内小売業者の現地視察
「売り手」が自信を持って福島県の農産物をPRできるように、都内の小売業者などが現地で、農産物の万全な放射線検査体制などを視察する研修会(12年10、11月実施)が好評を博しました。今後、水産物についても実施する方向です。
行政改革
全国初の新公会計制度
財政の「見える化」で隠れ借金解消
 活用できる基金残高の推移
活用できる基金残高の推移
東京都は、都議会公明党の提案を受け、2006年度に全国で初めて、企業会計の手法である「複式簿記・発生主義会計」を取り入れた「新公会計制度」を導入しました。
10年ほど前、都は深刻な財政難でしたが、当時は、現金の出入りだけを記帳する“家計簿”のような会計手法だったため、将来の負担などが不明確でした。しかし、新制度によって財政が「見える化」され、財産の状況を正確に把握できるようになった結果、都債返済のための積み立て不足など、約1兆円の“隠れ借金”が判明し、わずか2年間でほぼ解消されました。
また、税収減などに備えた“活用できる基金”の残高は、新制度の導入後、約2年間で1兆円積み増しされ、リーマン・ショックや東日本大震災後の財政需要にも、即応できるまでになっています。
さらに、新制度を活用して事業の徹底検証を行い、13年度予算案では約230億円もの財源を確保するなど、職員のコスト意識も大幅に向上しています。
都庁のスリム化進める
外郭団体を半減。職員も4分の3に
“天下りの温床”との批判もあった都の監理団体(外郭団体)。公明党が一貫して整理統合を訴えた結果、団体数はピーク時の72団体(1993年度)から、現在では33団体まで半減しました。役員退職金の廃止や役員報酬の引き下げなども断行され、99年度に2741億円だった都の財政支出は、13年度には2176億円となり、約21%も削減されています。
一方、都の職員定数は、ピーク時の78年度には22万2789人まで膨れ上がり、巨額の人件費が財政を圧迫していましたが、13年度の定数は16万5379人(予定)となり、35年前の4分の3にまで減っています。
職員の通勤定期代も、支給を1カ月単位から6カ月単位に変更することで、年間約34億円を節約しました。
環境
公共交通の利用促進
ポイントサービス「トコポ」実施
環境に優しい公共交通の利用を促す取り組みとして、11年8月から、都営交通に乗車するとポイントがたまるサービス「ToKoPo(トコポ)」が実施されています。この制度は、08年8月に公明党東京都本部青年局が都に要望し、実現したもので、都によると、現在の会員数は約7万6000人となっています。
会員になると、ICカード「PASMO(パスモ)」を使って都営地下鉄や日暮里・舎人ライナーなどに乗車した場合に、1ポイントを1円として換算できるポイントが付与されます。その上で、地下鉄からバスといった都営交通同士の乗り継ぎや、一部を除く土曜・休日の利用には、ボーナスポイントが加算されます。誰でも会員登録が可能で、入会費、年会費は無料です。
CO2削減を義務付け
大規模事業所の排出量が23%減少
 大規模事業所の温室効果ガス排出量削減実績
大規模事業所の温室効果ガス排出量削減実績
地球温暖化対策に向けて都は、10年4月から全国で初めて、大規模事業所を対象とした「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度(キャップ・アンド・トレード)」をスタート。二酸化炭素(CO2)排出量の削減に効果を挙げています。
総量削減義務では、大規模オフィスビルや商業施設、工場など1392の事業所が、02~07年度から任意で選んだ連続3カ年度の平均排出量を「基準排出量」に設定。10~14年度の5年間で、施設の内容に応じ、基準排出量の8%または6%を削減します。
排出量取引は、他者の排出削減量を購入し、自らの削減量に充当できる制度で、大規模事業所の義務超過分のほか、要件を満たす都内中小規模事業所が省エネで削減した分も、取引の対象となります。
対象事業所が前年度実績などを記載する「地球温暖化対策計画書」の集計(速報値)によると、11年度は節電の推進などにより、基準排出量と比べて23%もの削減が実現しました。
福祉・医療
バリアフリー化が拡大
駅のホームドアなど整備を推進
公明党が長年取り組んできた、バリアフリーのまちづくりが大きく進んでいます。
駅のホームからの転落を防ぐホームドアについては、都営地下鉄三田線の全駅で整備され、同大江戸線でも今年6月に整備完了の見込みです。また、国、都、区が補助を行う新たな仕組みの創設により、小田急、京王の両新宿駅、東急大井町線大井町駅にもホームドアが設置されました。一方、JR山手線では、14年度までに6割を超す駅で設置予定となっています。
さらに、各地の駅や公共施設などへのエレベーターや、身体障がい者用トイレの設置も進められているほか、地下鉄では、色覚障がい者に対応した駅名表示も実現しました。高齢者などが乗り降りしやすいノンステップバスも、全国トップクラスの導入率です。
このほか公明党は、視聴覚障がい者のために音声ガイドや字幕を付けた「バリアフリー映画」についても、積極的に上映を推進しています。
がん治療に最新技術
駒込病院に高精度の放射線機器
都民の死因第1位であり、死亡割合の3割を占める、がんについて、公明党は積極的に対策を講じてきました。
中でも、都の「がん・感染症センター」である都立駒込病院(文京区)では、11年9月のリニューアルに伴い、がん細胞にピンポイントで照射する「サイバーナイフ」など、高精度の放射線機器3台を、全国で初めて一度に導入。手術室の増設や通院治療体制の拡充、病状の進行による苦痛を和らげる「緩和ケア」病棟の設置などにより、高度ながん医療を提供しています。
このほか都内では、東邦大学医療センター大森病院(大田区)など、3カ所の病院で電話などによる休日・夜間のがん相談を行っています。
小児総合医療センター
救急など充実し子どもの命守る
10年3月にオープンした都立小児総合医療センター(府中市)。都立多摩総合医療センターと同じ建物内にあり、全国初の試みとなる「小児」と「成人」の総合医療機関の併設となっています。
特に周産期医療では、両センターが連携して重症の妊産婦患者に対応。新生児集中治療室(NICU)24床などを備えており、多摩地域の新生児救急を担っています。
また、小児救急医療では、新生児用と小児用のドクターカーを配備。全国初となる小児専門の救急治療室(ER)では、ほぼ全ての疾患の初期診療に対応し、治療の優先順位を判断する「トリアージ」によって、より病状の重い子どもから治療しています。
ひと口実績
小・中学校の教室を冷房化
公立小・中学校普通教室に冷房設備を導入する市町村に対し、2010年度から財政支援を実施。この結果、市町村での設置率は、22.5%(10年11月)から94.4%(12年度末見込み)へと上昇しました。なお、23区は100%設置済みです。
子ども医療費の助成拡充
子どもの医療費は、23区については中学3年生まで完全無料化。市町村については、入院は中学3年生まで無料、通院は就学前が無料で、小・中学生は多くの自治体が受診1件当たり200円までとなっています(一部地域では無料化)。
妊産婦救う体制を確保
脳卒中などの重症な疾患により、緊急に母体救命処置が必要な妊産婦を必ず受け入れる「スーパー総合周産期センター」として、昭和大学病院(品川区)や日本大学医学部付属板橋病院(板橋区)など都内4カ所の医療機関が指定されています。
盲ろう者に支援センター
目も耳も不自由な「盲ろう者」の支援センター(台東区)が、09年に全国で初めてオープンしました。コミュニケーションなどの訓練や各種相談、通訳・介助者の養成や派遣などの事業によって、盲ろう者の社会参加を後押ししています。
校庭芝生化が551カ所に
まちの緑を増やし、子どもの心を育む校庭の芝生化は、11年度末までに公立小・中学校275校、都立学校65校で実施され、幼稚園、保育所、私立学校についても、モデル事業として211カ所に拡大。これらを合計した551カ所の面積は約66.7ヘクタールに。
文中敬称略、肩書は当時
2013年3月25日、26日付 公明新聞
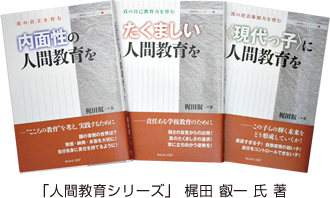 最終的には子どもたち1人ひとりが自分の人生を深く生きていくようになってほしいわけですが、人間教育のプロセスとして、子どもがどういう資質能力を身につけていったらいいか、そのためにどういう活動を準備していったらいいか、指導していったらいいか、等々を考えるために、このほど「人間教育シリーズ」の3冊を出版しました。
最終的には子どもたち1人ひとりが自分の人生を深く生きていくようになってほしいわけですが、人間教育のプロセスとして、子どもがどういう資質能力を身につけていったらいいか、そのためにどういう活動を準備していったらいいか、指導していったらいいか、等々を考えるために、このほど「人間教育シリーズ」の3冊を出版しました。









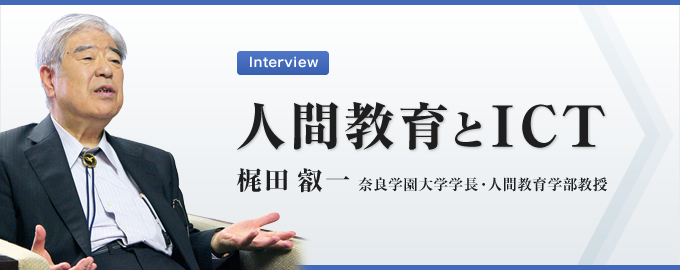
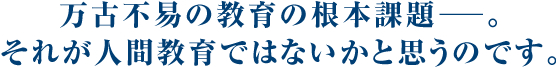
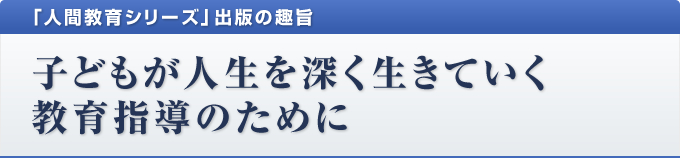

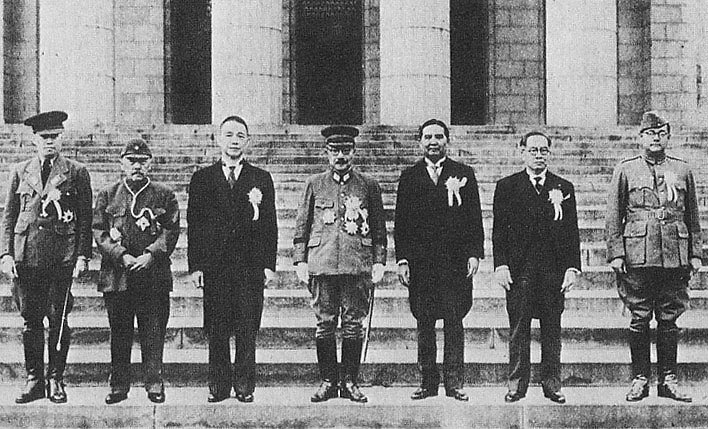
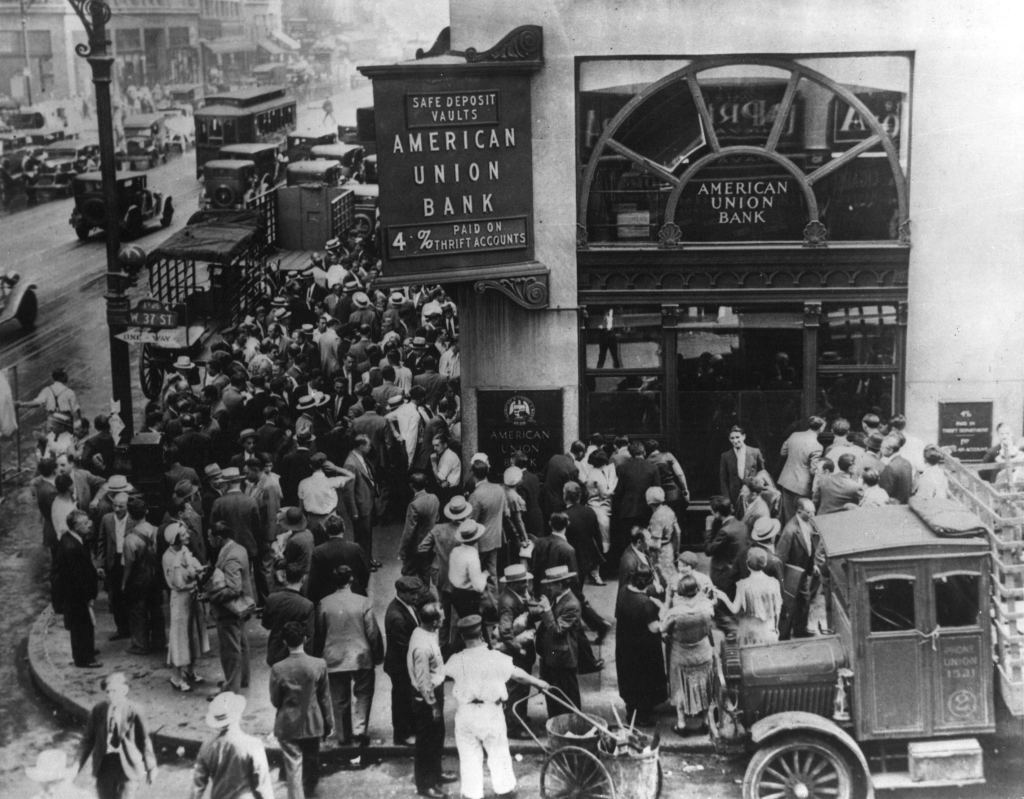
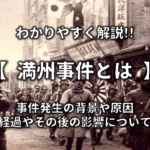
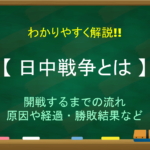
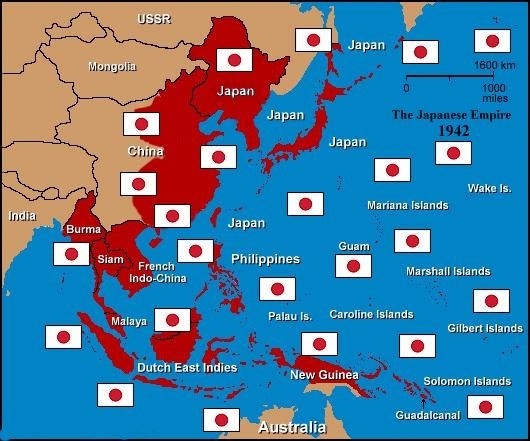

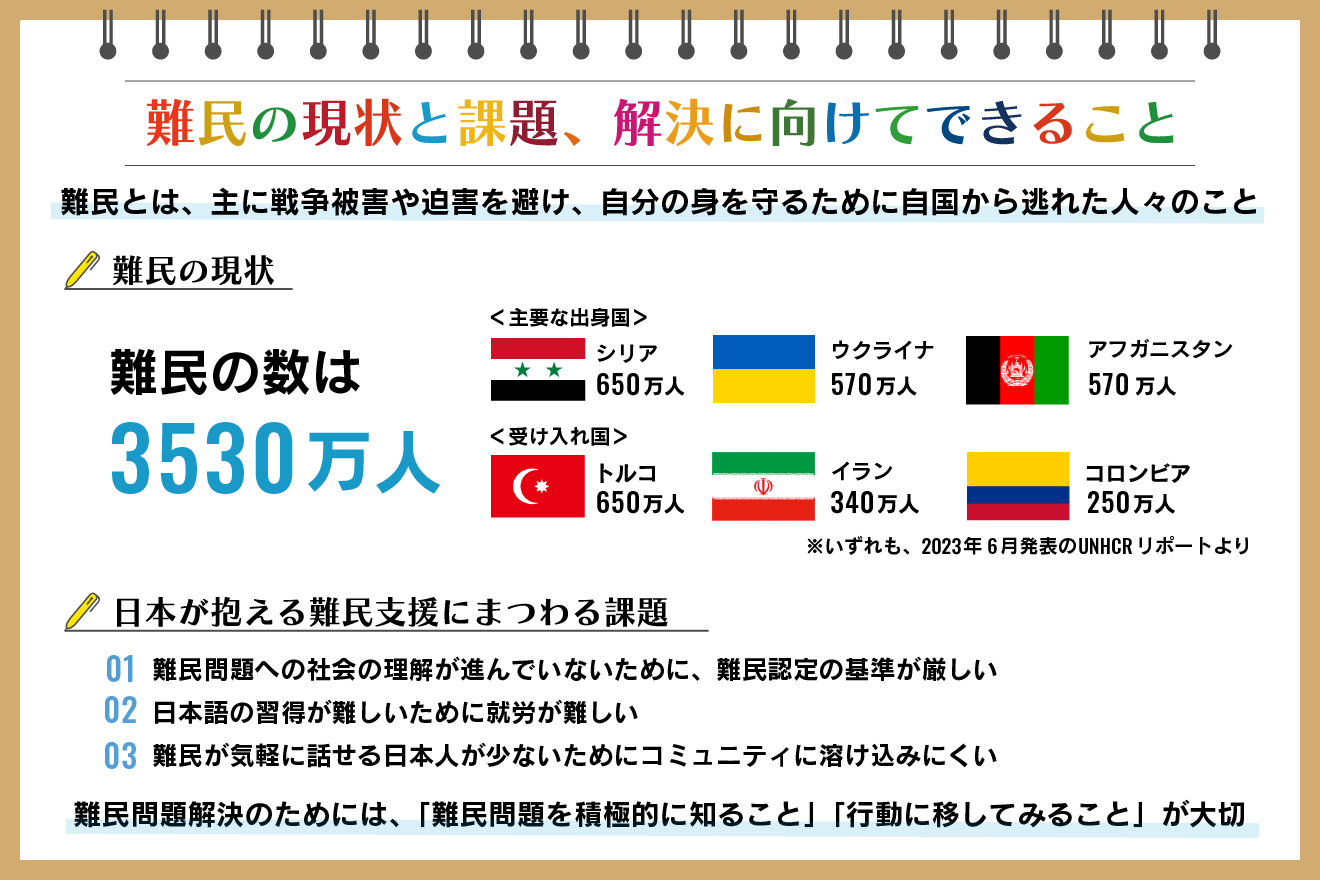




 </button>
</button>

 </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture>