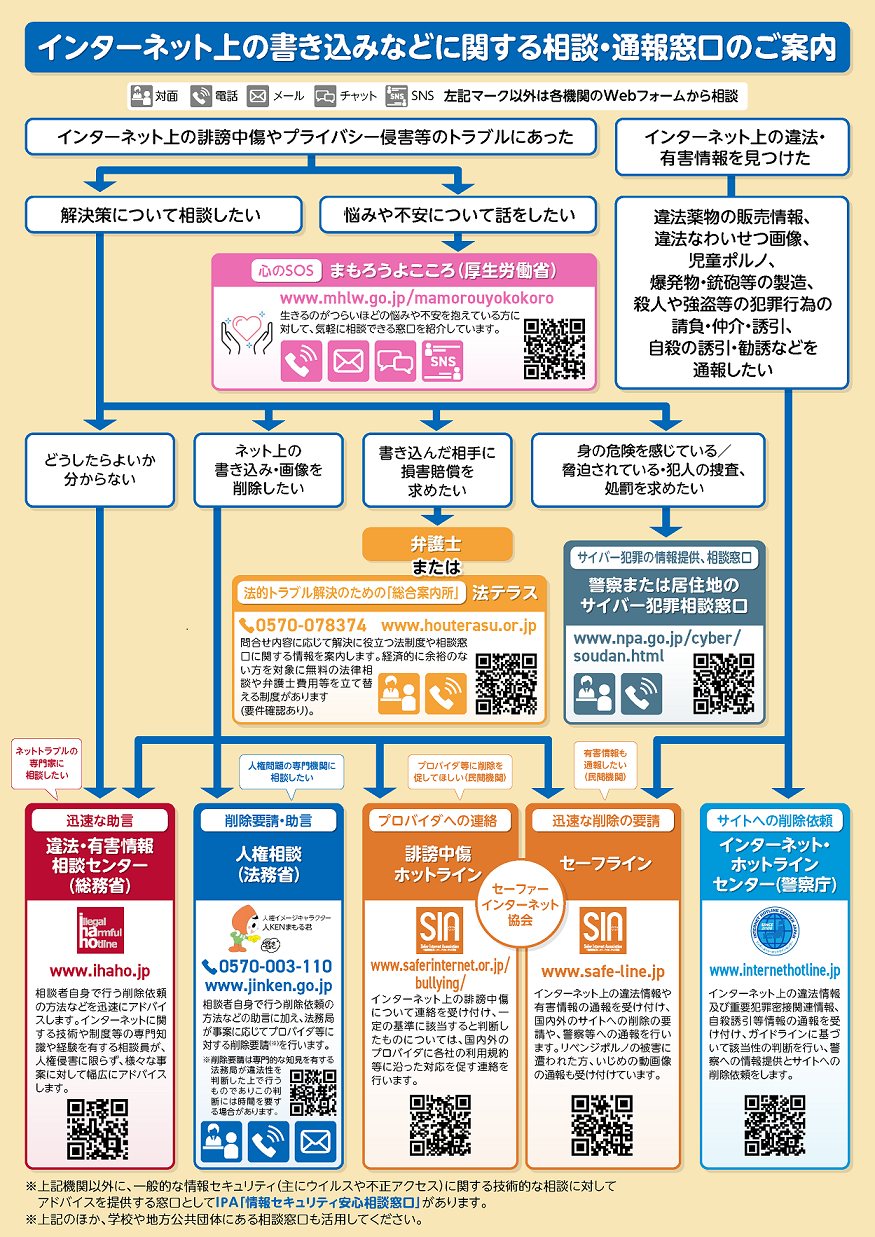【詳しく知る参議院選挙の争点】就職氷河期世代
7月20日投開票の参議院選挙で重要な論点になるとみられる政策や課題をお伝えする「争点ひとくちメモ」。
今回は「就職氷河期世代」です。

バブル経済崩壊後の雇用環境が厳しかった1993年から2004年ごろに就職活動を行っていた人たちを、国は「就職氷河期世代」としています。
全国に1700万人以上いるとされ、正社員を希望しながらかなわず不本意でアルバイトや派遣社員として働く「不本意非正規」が社会問題となり、国は2024年度までの5年間、集中的に支援しました。
内閣府によりますと、支援を始める前の2019年と去年を比較すると、この世代の人は会社役員を含めて正規雇用の労働者が975万人から31万人増えて1006万人に、「不本意非正規」は46万人から11万人減り35万人になったとしています。

一方、現在の年齢はおおむね30代後半から50代前半になり、厚生年金の加入期間が短い人がいて、上の世代に比べて金融資産が少ないというデータもあります。
また、厚生労働省の調査では若年層と比べて賃金の伸びが小さくなるなど、老後に対する不安を抱える人が少なくありません。

政府はことし6月、この世代を対象とした新たな支援プログラムの枠組みをまとめ、家計の改善や資産形成の支援に取り組むとともに、リスキリング=学び直しの支援の拡充などに取り組むことを検討しています。
今回の選挙では、就職氷河期世代の今後の支援のあり方も争点になる見通しです。
あわせて読みたい
-
-

-
【特設サイト】参院選 立候補予定者一覧 関連ニュース
7月3日公示、7月20日投開票の参議院選挙の立候補予定者一覧や関連ニュース。公示日以降は、全立候補者を掲載し、投開票日には開票速報。
-
-
-

-
参議院選挙 最新ニュース一覧・特集
参議院選挙2025の最新ニュースや特集をお伝えします。
-
-
-

-
参院選の仕組み 比例代表 特定枠 合区とは?
3年ごとに行われる参議院選挙。仕組みを詳しくお伝えします。
-
-
-

-
参院選 1人区対決 これまでの勝敗は
過去6回の参院選の1人区で、どの党派の候補者が議席を獲得したのかを選挙区ごとに一覧にしました。
-
-
-

-
【参院選前世論調査】石破内閣支持率34% 各党の支持率は
内閣支持率、政党支持率の推移は? NHK世論調査を掲載しています。
-