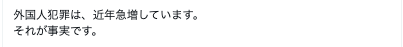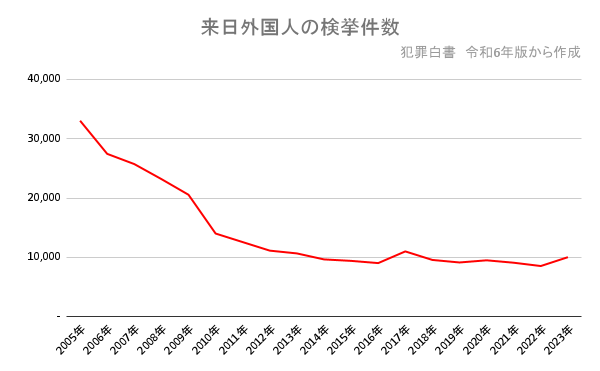立命館アジア太平洋大学客員教授 小川伸一
1.はじめに
核の「先制使用(first use)」とは、核兵器以外の手段で武力攻撃を加えてきた敵対国に対し、先んじて核兵器を使用することを意味する。他方、核の「先制不使用(no first use)」とは、核兵器を相手より先に使用することはないが、相手の核使用に対しては報復使用の選択肢を留保するというものである。
冷戦時代にあっては、核の先制使用とは、通常、武力紛争中、敵対国よりも先に核兵器を使用すること、すなわち「先行」使用を指していた。核兵器を用いて戦端を開くことも語義的には核兵器の先制使用の範疇に入るが、こうした核兵器を用いた先制核攻撃と武力紛争中の核の先制使用は区別されなければならない。しかしながら往々にして、こうした区別をせずに、核兵器を用いて戦端を開くことも核の先制使用の範疇に入れて議論される傾向がある。国際法上、他に対処手段がないことを条件に、差し迫った軍事的脅威を排除するための先制攻撃(preemptive strike)が自衛権の行使として許容されているためであろう。先制核攻撃のもう一つの形態として「ファースト・ストライク(first strike)」と呼称されるものがある。これは、先制核攻撃で敵対国の戦略核戦力に報復能力が残存しないほどの壊滅的損害を与える核攻撃で、「武装解除的ファースト・ストライク(disarming first strike)」と称されることもある。
このように核の先制使用には様々な形態があるが、核使用をめぐる政治・道義的障壁を考慮するならば、武装解除的ファースト・ストライクは勿論のこと、差し迫った軍事的脅威に直面した場合であっても核兵器による先制攻撃で戦端を開く蓋然性は極めて低い。あり得るとすれば武力衝突勃発後の戦闘作戦行動の流れを受けてやむを得ずに敵対国に先んじて核使用に走るという「先行」使用であろう。したがって本稿では、核の先制使用という場合、武力紛争中に交戦国の一方が先に核兵器の使用に踏み切ることを指すことにする。
核保有国が核の先制使用、先制不使用のいずれを採るかによって、核抑止戦略や核軍縮に大きな差異をもたらす。本稿は、核時代に入ってから今日までの核の先制使用と先制不使用をめぐる議論の流れを概観し、核の先制不使用の意義と課題を論ずることとする。
本稿で「核保有国」と称する場合、核兵器不拡散条約(NPT)上の5核兵器国に加え、NPTの枠外
で核兵器を保有するようになったインド、パキスタンのほか、同じくNPT未加盟で核兵器の保有が確か
らしいイスラエル、さらにはNPTを脱退して核爆発実験を行った北朝鮮を指している。
2.核の先制使用、先制不使用をめぐる核保有国の姿勢
(1)米国及びNATO
米国における核の先制使用、先制不使用をめぐる議論は 1950 年代の初め頃迄さかぼる。対ソ封じ込め政策に軍事的色彩を強める契機となった国家安全保障会議文書NSC-68 は 1950 年9月にトルーマン大統領によって承認されたが、その文書は、核の先制不使用政策を米国が弱体であるとか、あるいは同盟国を見捨てるとの印象を与えかねないとして明確に拒否している。アイゼンハワー政権になると、米国は核の先制使用政策を明確に打ち出すに至る。例えば 1953 年 10 月のNSC-162/2 は、ソ連あるいは中国が西側諸国に武力進攻した場合、米国は核兵器を他の兵器と同じように使用することを考慮すると述べ、通常戦力攻撃に対して核兵器を使用することを厭わない姿勢を見せている。欧州の北大西洋条約機構(NATO)諸国はこの方針を歓迎し、米国の戦術核兵器の導入を加速させていくのである。こうして旧西欧諸国には多数の米国の戦術核兵器が持ち込まれ、核の先制使用は、1950 年代の対ソ抑止の重要な柱と位置付けられたのである。例えば、アイゼンハワー政権のダレス国務長官が 1954 年1月に公表した大量報復戦略においては、核の先制使用の威嚇を前面に押し出して、通常戦力面で優位にあったソ連軍を中心とするワルシャワ条約機構(WTO)軍による西欧侵攻を抑止しようとしていた。
このように、冷戦時代の初期、戦略核戦力で圧倒的に優位にあった米国は核の先制使用の威嚇を前面に押し出す政策を採り続けたが、ソ連の対米核報復能力が整備されるにつれて、状況次第で核の先制使用もあり得るという方向に修正され、その威嚇は次第に曖昧性を帯びるようになってきた。ジョンソン政権時の 1967 年に採択され、その後長くNATOの抑止戦略として依拠された柔軟反応戦略では、通常戦力を強化するとともに、必要とあらば核の先制使用に訴えるとの方針の下で対ソ抑止を構築しようとしたのである。また、英仏も米国と同様、核の先制使用の選択肢を留保する姿勢を採った。
核の先制使用の選択肢を維持する米国の政策は、欧州のみならず、朝鮮半島及び中東においても適用されていた。米国が韓国に戦術核兵器を最初に持ち込んだのは 1957年後半から 1958 年初頭の間と言われている。
当時の南北朝鮮間の通常戦力バランスは、北朝鮮の優位にあり、この優勢な北朝鮮軍に対する抑止力の強化を狙って核兵器が配備されたのである。陸地を介して対峙していながら通常戦力バランスで劣勢にあるという状況は、当時北朝鮮が核兵器を保有していない点を除けば、旧西欧が直面した戦略環境と相通ずるものがあった。1975 年6月、日本と韓国を歴訪したシュレシンジャー米国防長官は、韓国内に核兵器を配備していることを確認するとともに、北朝鮮による対韓武力侵攻に対し、核使用の可能性を示唆したのである。このように核兵器の先制使用の可能性を打ち出して抑止力の強化を狙った点は欧州と同じであった。
また中東に関しては、ソ連によるアフガニスタン侵攻を受けて、カーター大統領が 1980年1月の一般教書演説のなかで、軍事力を含めあらゆる手段を用いてソ連の進出から湾岸地域を守るとの趣旨の「カーター・ドクトリン」を打ち出したが、この軍事的手段のなかには核兵器の先制使用も含まれると解釈されていた。
ソ連がその戦略核戦力の残存性を確保し、米国に対する報復核能力を整備するにつれて米国が宣言していた核の先制使用の信憑性に疑義が生じるようになった。米ソ間の核の投げ合いによって米国が未曾有の損害を被ることが避け難い状況になったとすれば、そうした事態につながる核の先制使用は政策としての信憑性が疑われるようになったとしても不思議ではなかった。米ソの戦略関係が1972年5月の「弾道ミサイル迎撃ミサイル(ABM)制限条約」によって法的にも確認されたいわゆる「相互確証破壊(MAD)」態勢に入ると、核の先制使用を選択肢の一つとする抑止戦略に対する批判の声が大きくなり、米国内の一部専門家や元政府関係者の間で核の先制不使用に転換することを求める声が出てきた。その論拠は次の通りである。第1に、核兵器を先に使用するか否かを曖昧にしておくとその不確かさが通常戦力による防衛態勢の構築に悪影響を与える。これに対し、明確に先制不使用を政策として採択すれば、それに応じた通常戦力の防御態勢を構築することができ、結果的にNATOの抑止力を高めることになる。
第2に、限定的な核使用であれ、一旦ソ連との間で核兵器が使用されれば、核の投げ合いを制御する術はなく、その究極は相互自殺である。そうした破滅をもたらす核の先制使用を政策の選択肢として持ち続けることには信憑性が欠如しているばかりでなく不道徳ですらある。したがって通常戦争と核戦争の敷居を高めるためにNATOの通常戦力を強化するとともに、核の先制使用を放棄して先制不使用に転換する必要がる。
しかしながら、核の先制不使用への転換を求める声は、欧州のNATO諸国、とりわけ西独からの批判や米国内の反論を受けて日の目を見ることがなかった。たとえば、ドイツ外交協会のカール・カイザーなど4名の西独人は、1982 年夏号の『フォーリン・アフェアーズ』誌において、米国が核の先制不使用政策をとれば、核の恐怖からソ連を解放することになり、ソ連の武力行使を容易にすると批判を加え、従来どおり先制
使用の選択肢を維持することを主張した12。また、当時NATO軍最高司令官の職にあったバーナード・ロジャーズは、核の先制不使用は米国の戦略核戦力を西欧の防衛から切り離すことになると批判を加えた13。
1990 年代に入ると、長年米国をして核の先制使用の選択肢を持ち続けることを余儀なくさせていた欧州の通常戦力バランスが大きく変容し始めた。1990 年 11 月には東西の通常戦力バランスを低レベルで均衡させる欧州通常戦力(CFE)条約が締結され、しかもソ連軍が東欧から撤退し始めていた。それにも拘わらず、米国及び米国の核兵器を導入している西欧諸国は、1991 年 11 月に採択されたNATOの新戦略概念
において核の先制使用の選択肢を放棄しようとしなかった。ただし、1991 年9月に打ち出されたブッシュ(父)大統領による自主的核軍縮措置の結果、欧州に配備されていた戦術核兵器の殆どが撤去され、数百発の航空機搭載自由落下核爆弾のみを残した事実にかんがみ、欧州における米国の核使用は「最後的手段(last resort)」と位置付けられるほど後景に退いたのである。
1991 年 12 月、第二次世界大戦後長年にわたって西欧に脅威を及ぼしてきたソ連が解体したが、NATOは核の先制使用の選択肢を維持したままであった。1998 年にドイツのフィッシャー外相がNATOの政策としての核の先制使用の見直しを提案した際、フランスは先制不使用を抑止政策と両立しないという理由で、また英国は潜在敵国をして我々の対応を読み切れないようにしておくには先制使用の選択肢を維持しておくべきとの理由で拒否している14。先制使用の可能性は大きく遠のいたが、この選択肢の温存は、残された自由落下核爆弾とともに米国の対欧安全保証コミットメントを示す政治的シンボルとしての役割が期待されたのであろう。
米国は、クリントン政権時の 1994 年9月とブッシュ(子)政権時の 2001 年 12 月にそれぞれの「核態勢見直し(NPR)」の一部を公表したが、核使用に関してはいずれも「意図的曖昧性(calculated ambiguity)」と称される姿勢を保ち、核の先制使用の選択肢を放棄しなかった。「意図的曖昧性」とは、米国や同盟国に対する非核攻撃、とりわけ生物・化学兵器攻撃を受けた場合に核兵器を用いて対応するか否か、すなわち
核の先制使用に踏み切るか否かを曖昧にしておき、米国の核抑止力の維持を図ろうとするものである。
しかしながら、こうした抑止政策は 1978 年の第1回国連軍縮特別総会の折に公表された米国の「消極的安全保証」宣言やNPT再検討・延長会議の直前の 1995 年4月に再度発出された消極的安全保証宣言に反するとの批判を受けていた。米国の消極的安全保証は、「核兵器不拡散条約(NPT)の締約国たる非核兵器国や核爆発装置を取得することを禁止する国際的約束の下にある非核兵器国に対しては、米国及びその同盟
国、または米国が安全保障上の約束を行っている国に対して、他の核兵器国と同盟ないし連携して攻撃を加えてこない限り、核兵器を使用しない」との趣旨であるが、この宣言の下では、非核兵器国が単独で米国や米国の同盟国に対して生物・化学兵器攻撃を加えても核兵器を使用しないことになるからである。
こうした矛盾に手当をするとともに、核の先制使用の機会を絞り込もうとしているのがオバマ政権である。2010 年4月に全文が公表されたオバマ政権のNPRは、核兵器の「基本的な役割」が米国や同盟国に対する核攻撃を抑止することにあると述べ、こうした方針に則り、NPT締約国で条約を順守している非核兵器国に対しては、そうした国がたとえ米国やその同盟国に生物・化学兵器攻撃を加えても米国は核兵器を使用しない方針を明らかにした。この結果、「意図的曖昧性」は、NPTやその他の核不拡散上の取極めを順守している非核兵器国に対しては適用されないこととなった。
ただし、生物兵器の脅威が高まった場合にはこの方針を見直すことや、核保有国やNPTを順守しない非核兵器国からの非核攻撃に核兵器で対応する可能性、すなわち核の先制使用の可能性を排除していない。しかしながら同時にオバマ政権が発表したNPRは、米国が核使用を考慮するのは「米国や同盟国・パートナー国の死活的利益(vital interests)を守るという極限状況(in extreme circumstances)においてのみ」とくぎを刺している。しかも、核兵器の「唯一の目的(sole purpose)」が核攻撃を抑止すること、すなわち核の先制不使用政策を採ることができるような状況を創り出すよう努力することを宣言しているのである16。
(2)ソ連/ロシア
ソ連は、ブレジネフ時代の 1982 年6月、一方的に核の先制不使用を宣言した。当時、この宣言の信憑性には疑問が持たれていたが、事実、欧州でNATOとWTOの間で戦端が開かれた場合、NATOが通常戦力のみを用いている段階であってもソ連は早期に核兵器や化学兵器の使用に踏み出すことを記したソ連の軍事関連文書がNATO側にわたっている17。ソ連に限らず核兵器国の核戦略には政治・外交的配慮に重きを置
いた「宣言政策(declaratory policy)」と実際の「運用政策(operational policy)」があるが、ソ連のブレジネフ時代の先制不使用宣言は宣言政策の最たるものと言えよう。
ソ連の解体後新生ロシアが誕生し、ロシアは旧ソ連の核兵器を継承したが、旧ソ連解体に伴って弱体化したロシアの通常戦力を背景に核の先制不使用宣言を見直さざる を得なくなった。こうして 1993 年 11 月、当時のロシア国防相グラチョフは、核の先制使用政策に回帰することを宣言したのである。
2010 年2月、ロシアは 2020 年ころまでを念頭に置いた新軍事ドクトリンを公表した。その中でロシアは、核兵器で対応する事態に、自国や同盟国が核攻撃その他の大量破壊兵器攻撃を受けた場合のほか、自国の存亡を危機にさらす通常戦力攻撃を受けた場合も含めている。このようにロシアは、NPTなどの国際的規範に対する国家の姿勢・行動によって差異を設けることもなく、また 1995 年4月に公表したロシアの消極的安全保証宣言に背馳する形で20、自国に大量破壊兵器攻撃や大規模通常戦力攻撃を加えてくる国家に対しては一律に核兵器を使用する意思を示している。通常戦力攻撃に関しては自国の存亡が危機にさらされるか否かを条件にしているものの、米国に比べ核の先制使用を考慮するシナリオは多いと言えよう。
(3)中国
中国は、1964 年 10 月の核実験直後から今日まで一貫して、いつ、いかなる場合においても核兵器を先に使用しないという無条件の核兵器の先制不使用を宣言している。同時に中国は、NPT上の他の核兵器国に先制不使用政策を採るよう促している。
中国が核兵器の先制不使用に固執している理由の一つは、中国が米ソ(露)のいずれかに対し核兵器を先制的に使用することは自殺行為に等しいほど中国の核戦力が劣位にあるという実際的な思惑があろう。また、無条件に核の先制不使用を宣言している国家に対して核兵器を使用することは政治的にも道義的にも難しいはずと考えるなど、核攻撃を回避する手段の一つと捉えているのかもしれない22。さらに、建国後の中国が
米国、インド、ロシア、ベトナムなどと通常戦力を用いた武力紛争を経験した事実にかんがみ、中国に対する通常戦力攻撃は核兵器を用いなくても対処できるとの自信を得ているのかもしれない23。加えて、他の核兵器国に核の先制不使用の採用を促し、 ロシアは、1995 年 4 月、「ロシア連邦は、以下の場合を除き、核兵器の不拡散に関する条約の締約国である非核兵器国に対して、核兵器を使用しない。すなわち、ロシア連邦、その準州、その軍隊若しくはその他の兵員、その同盟国、又は、ロシア連邦が安全保障上の約束を行っている国に対する侵略その他の攻撃が、核兵器国と連携し又は同盟して、当該非核兵器国により実施され又は支援される場合を除き、それらの非核兵器国に対して核兵器を使用しない」と述べ、オバマ政権が修正する前の米国の消極的安全保証宣言と同趣旨の宣言を発出している。藤田久一、浅田正彦編『軍縮条約・資料集』第二版(有信堂、1997)、107 頁。
同時に中国は、いつ、如何なる場合においても非核兵器国や非核地帯条約に加盟している非核兵器国には核攻撃を加えないとする無条件の「消極的安全保証」も宣言している。
制不使用体制の構築を訴えているのは、先制不使用が核兵器の軍事戦略上の役割を相手の核攻撃を抑止することのみに絞り込むことになることから、圧倒的に優勢な状況にある米ソ(露)の核戦力の軍事戦略上の価値を低下させることにつながると考えているのかもしれない。なお、中国は、核の先制不使用を宣言しているものの、射程の短い戦術核兵器を保有しているか否かについては明言を避けている。また、先制核攻
撃の意図がないことを示すためか、平時においては、DF-5Aなど液体燃料推進式のICBMには核弾頭を搭載していないと推定されている。DF-31Aのような固形燃料推進式のICBMについてははっきりしていないものの、おそらく同様に平時にあっては核弾頭を搭載していないものとみられている。
しかしながら、米国など一部の国の通常戦力のハイテク化など、通常戦力面での能力の格差が広がるにつれ、中国国内においては、無条件の核の先制不使用政策を再検討すべきとの意見が散見されるようになっている。これに対し、核兵器の先制不使用という考え方は、核戦力の役割を核攻撃に対する報復のみと捉える中国の考え方から論理的に導き出されるものであり、変更することはできないとの意見も見受けられる。
他方、中国政府は、2010 年NPT運用検討会議における中国代表の発言にも見られるように、従来からの無条件の核兵器の先制不使用及び消極的安全保証を堅持する意向を示し続け、変更する兆候を見せていない。しかしながら、米国が開発に着手している「即時グローバル打撃力(PGS)」など通常弾頭を搭載した戦略弾道ミサイルが本格的に配備されると、わずかな数量の中国のICBM戦力は米国の通常戦力によっ
て無力化される可能性が出てくる。こうしてみれば、米中の通常戦力の格差がさらに拡大したり、あるいは早期警戒システムの運用など中国の核戦力が充実してくれば、中国が核の先制不使用の見直しに踏み出すこともあるかもしれない。
(4)インド、パキスタン
インドは、1999 年8月に発表した核ドクトリン草案において、核兵器の目的をインドに対する「核の使用または使用の脅しを抑止すること」にあると規定し、「先に核攻撃は行わない」と述べて、広い意味での核兵器の先制不使用政策を採る意向を示していた。先制不使用を宣言した理由として、当時のジャスワント・シン外相は、インドは、NPT上の核兵器国と異なり、核兵器の主たる役割を核攻撃の抑止と位置付け、それ以上のものでないと考えているからであると説明していた29。ところが 2003 年1月になると、生物兵器や化学兵器攻撃を受けた場合、核兵器による反撃があり得ることを示唆するようになり、限定的ではあるものの核の先制使用の選択肢を保持するようになった。
他方、パキスタンに関しては、通常戦力でインドに対し劣勢にあることから、インドの優勢な通常戦力を抑止するために核の先制使用政策を採っている。1998 年5月の印パ両国の核爆発実験後にインドがパキスタンに対して核の先制不使用を呼びかけた際、これを拒否していることからもこのことは窺える31。パキスタンが核使用を決断する状況についてはあまり語られないが、2002 年の初めごろパキスタン戦略計画部長
(Chief of the Strategic Plans Division)の職にあったカリド・キドワイ中将の発言がある。キドワイ中将は、パキスタンの核兵器はインドを標的にしていると述べた後、パキスタンが核兵器を使用するケースとして次の4つのシナリオを挙げている。
第1は、インドがパキスタンに武力攻撃を加え、パキスタン領土の大部分を占領した場合である。第2は、将来の印パ戦争において、インドがパキスタン陸軍、あるいは空軍の大部分を壊滅させた場合である。第3は、インドがパキスタン経済を麻痺させた場合であり、そして第4は、インドがパキスタン国内で騒擾を引き起こすなど国内政治情勢の不安定をもたらした場合である32。パキスタンが核使用に踏み切るとするこ
れらの具体的事例から判断すると、パキスタンがインドによって軍事的に大きく追い込まれた場合や政治・経済的に危機に陥った時に核兵器に訴えることを示唆している。
こうしてみれば、パキスタンは核の先制使用政策を採りながらも、大きな国家的危機に直面した時の手段と位置付けていることが窺える。
3.核の先制使用の意義と問題点
中国を除く核保有国は、明示的に宣言する、しないにかかわらず、あるいは米国のように先制使用を考慮するシナリオを絞り込みながらも、核兵器の先制使用の選択肢を維持している。核抑止の対象に核攻撃のみならず、大規模な生物・化学兵器攻撃や通常戦力攻撃をも含めるなど、核兵器の抑止力に期待をかけているからである。圧倒的な通常戦力を保有している米国が核の先制使用の選択肢を完全に放棄できない主な理由は、多くの非核同盟国を抱え、同盟国の軍事的安全にコミットしているためである。核の先制使用の選択肢を保持していれば、同盟国に対する核攻撃のみならず、生物・化学兵器攻撃や大規模通常戦力攻撃も核抑止の対象とすることができ、様々な軍事的脅威に対して同盟国の安全を保証できることになる。しかも、こうした広範な安全保証を供与することにより、政治的に優位な立場で同盟を運営することが可能となる。
さらに、核の先制使用の効用は抑止の側面のみにとどまらない。核の先制使用政策は、生物・化学兵器攻撃も抑止の対象にできることから、生物・化学兵器の使用を難しくし、それだけ生物・化学兵器の廃絶に役立つと考えることもできる。国際社会は生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約を成立させて生物・化学兵器の廃絶に向かっているが、生物兵器禁止条約には査察・検証規定がなく33、その実効性には懸念がもた
れている。生物兵器は、化学兵器と異なり未だ本格的に兵器化されていないが、使用条件が揃えば、核兵器に匹敵する殺傷力を持つと言われている34。こうした状況にかんがみ、核兵器によって生物兵器の使用を抑止する途を残しておけば、それだけ生物兵器の開発・保有の動機も減殺されると考えることができる。
しかしながら、核の先制使用の選択肢を保持し続けることには問題点も見受けられる。第1の問題点は、安全保障上の核兵器の意義と役割をこれまで通り追認することになる。現状の追認は、核兵器の役割を狭める努力の放棄を意味し、国際社会が追求している核不拡散の目標達成を損ないかねない。非核兵器国に核兵器開発・保有の動機を与え続けるからである。NPT体制の信頼性や安定性を維持し、核軍縮を推し進めるためには、安全保障上の核兵器の意義と役割を極力低下させなければならないのである。
第2に、生物・化学兵器攻撃に対する抑止が崩れた場合の結末である。核報復の選択肢を保持することが抑止力につながるとしても、抑止は万能とは言えない。
生物兵器締約国は、追加議定書の形で検証制度を設けるべく、1994 年以降専門家会合などの場で交渉を続けてきた。しかしながら、生物兵器の開発・製造を物証によって確認することの困難さから生じる検証能力に対する疑義、さらには企業秘密や国家安全保障上の秘密保護との兼ね合いなどで合意に達することはできず、7 年後の 2001 年には追加議定書の作成は中断するに至っている。詳しくは、壊する危険は常に残っている35。しかも抑止が崩れ、実際に大規模な生物・化学兵器攻撃を受けて大きな人的被害を被った場合、選択肢として挙げていた核報復に踏み切らざるを得なくなる公算が高い。一つには、核報復を断念した場合には、核報復が有り得ることを公言していた為政者への信頼性が問われること36、さらには将来の同様のケ
ースにおける抑止の信憑性の維持・回復を考慮すれば核報復に踏み切らざるを得ないと考えるからである。しかし、核兵器の使用は、国際社会にどのような影響を与えるのであろうか。広島、長崎以降、65 年以上にも亘って使用されることのなかった核兵器が使用されれば、安全保障環境に大きなインパクトを及ぼそう。核報復によってもたらされた人的被害が予想を下回れば、核兵器に対する見方が変化し、核使用を思いとどまらせていた政治・道義的制約が弱まるとともに、核拡散を促すかもしれない。
核兵器を戦争遂行の手段と位置付ける見方が復活すれば、NPT体制に与える影響は測り知れない。
第3に、核の先制使用の選択肢を温存させるのみならず、クローズアップさせると、安全保障環境の変容次第ではそれが抑止力の一環としての役割を超え、核兵器その他の大量破壊兵器の拡散の呼び水になる恐れもある。米国のブッシュ(子)政権は、テロ組織やテロ支援国家に対処するための一つの方策として軍事力の先制使用を含む「先制行動(preemptive actions)」の必要性を強調したが、この軍事力を用いた先制行動には核使用も含まれていたと言われている37。テロ組織を抑止することは容易でないことから、こうした軍事力を用いた先制行動は対テロ対策としては一定の説得力を持っていた。しかしながら、核兵器を用いた先制攻撃の選択肢をクローズアップし且つ喧伝すれば、相手側に対してこうした核使用を抑止するために、核兵器をはじめとする大量破壊兵器の保有を促すことにもなりかねなかったのである。抑止の要諦は受動性であり、この受動性を超えて、核の先制使用に能動性や積極性を付与すれば、先制使用の負の側面を際だたせるのである。
4.核の先制不使用の意義
冷戦時代、米国の一部で核の先制不使用を唱える声があったことは既に述べたが、こうした要請の背景には、核の先制使用が米ソ両国の共倒れを招きかねないこと、そのため先制使用の威嚇が信憑性を欠いているとの認識があった。この結果、先制不使用を支持する当時の議論は、核の先制使用が孕む未曾有の危険を回避することが主たる理由となっていたのである。
しかしながら、核の先制不使用に関しては、より積極的な意義を見出すことができる。
抑止が崩壊するケースとして、例えば 冷戦時代に核の先制不使用を唱導した論者が既に示唆していたように、核の先制不使用は核軍縮を促す効果があるのである。NPT上の核兵器国も含め、総ての核保有国が中国の主張するような無条件の核の先制不使用に同意し、グローバルな核兵器の先制不使用体制を構築すれば、核兵器の役割は、単に他の核保有国の核兵器を抑止するのみとなる。核兵器の役割を他国の核使用の抑止に限定できれば、核保有国が一律に核兵器の削減に踏み切っても、安全保障上、失うものはないことになる。このように核兵器の先制不使用体制は、核軍縮を促す大きな契機となるのである。日本及びオーストラリアのイニシアティブで 2008 年7月に立ち上げられた「核不拡散・核軍縮に関する国際委員会(ICNND)」が、2009 年 12 月に発表したその報告書『核の脅威を絶つために-世界の政策立案者のための実践的な計画』のなかで、遅くとも 2025年までに総ての核保有国が明確な形で核の先制不使用を宣言することを求めている所以である。
また、核の先制不使用は非核兵器国に対する核攻撃を否定することになることから、NPT体制の基盤を強化することにつながる。NPT上の5核兵器国が合意して核の先制不使用体制を構築すれば、その副次的効果として、非核兵器国は、原則的にNPT上の5核兵器国からの核威嚇や核攻撃を恐れる必要がなくなるとともに、NPT体制の最も大きな懸案事項である核兵器国と非核兵器国の間の政治・安全保障上の不平
等性も緩和され、NPT体制の安定性や信頼性が格段に向上することになる。このように、核の先制不使用を制度化できれば、核軍縮、あるいはNPT体制の安定性や信頼性を高めることに役立つと考えられる。
さらに、核の先制不使用は、同盟国向けの核抑止の役割を限定化する効果があることは既に指摘したが、米露の相互核抑止については、あるいは将来米中が相互核抑止関係に入ると仮定すれば米中の相互核抑止についても、これを安定化させる効果を持っている。相手の核兵器運用政策が先制不使用という一定の枠組みに限定される結果、警戒態勢の緩和など、核抑止に必要な核戦力システムの整備が容易になると考えられるからである。
5.核の先制不使用体制を構築するための課題
上で述べたように、核の先制不使用は、核兵器の役割を他国の核使用を抑止することのみに極限化し、そしてそれ故に核軍縮を促進するとともにNPT体制の信頼性と安定性を高める効果がある。しかしながら、NPT上の核兵器国も含め核保有国の殆どが、濃淡の差はあれ、核の先制使用の選択肢を堅持していること、しかもそれぞれが固有の安全保障環境にあり、固有の脅威認識を持っていることを考慮すれば、当面、核保有国がこぞって核の先制不使用を宣言し、先制不使用体制の構築に向かうとは考えにくい。圧倒的な通常戦力を備えた米国でさえ、その同盟国との関係を考慮すると、核兵器の先制不使用を宣言することは、戦略的に無理があるとみる意見が多い。こうした事情の背景には、大規模な生物・化学兵器攻撃や通常戦力攻撃の抑止手段として核兵器に依存する考えを多くの国が捨てきれないでいるためである。
核の先制不使用体制の構築を妨げている要因が生物・化学兵器の脅威や大規模通常戦力の脅威であるとするならば、これらの脅威を取り除くことが不可欠となる。事実、国際社会は、生物兵器禁止条約や化学兵器禁止条約を成立させて生物・化学兵器の廃絶に向けて努力を重ねている。しかしながら、生物・化学兵器の脅威を完全になくす見通しは立っていない。両条約に背を向けている国家があることに加え、先に指摘し
たように、生物兵器の廃絶を確認する検証手段を見出していないからである。生物兵器は、ヒトに対する殺傷力の面で核兵器に匹敵する潜在力を持つと想定されているが、実際のところ、そうした規模の殺傷力をもたらす生物兵器を実用化することは容易ではない。化学兵器については過去何度も戦場で使用されたが、戦争の帰趨を決定づけるほどのインパクト、言い換えれば戦略的打撃を与えることはなかった。ヒトに対す
る生物・化学兵器の恐るべき殺傷力は、依然、潜在的なものであり続けており、今日までのところ、これらの兵器は戦争の帰趨を決定するような戦略的意義を持つまでに至っていない。また、生物・化学兵器の攻撃対象は兵士や一般市民のみであるため、生物・化学兵器を用いたカウンターフォース攻撃に限界があり、相手に戦略的打撃を与えることは容易ではない。しかも生物・化学兵器攻撃に対しては、核攻撃と異なり、
ワクチンや解毒剤、さらにはガスマスクや防護服で人的被害を抑制することも可能である。したがって、当面の生物・化学兵器対策は、生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約のさらなる普遍化を図るとともに条約の実効性を確保すべく追加的な施策を講じることであろう。
具体的に述べると、化学兵器禁止条約に関してはチャレンジ査察の実施とそのルーティン化であり43、生物兵器禁止条約に関しては、査察・検証制度の代替として現在進められている「条約強化に関連した事項44」の検討と、その検討結果を基礎にした各国間の協力体制の構築である。勿論、生物・化学兵器に対する査察・検証の難しさを思い起こせば、こうした措置を採ったとしても生物・化学兵器の廃絶に直結するとは言
最近の批判として例えば、2009 年 5 月現在、生物兵器禁止条約の締約国・地域は 163 カ国・地域、未締約国が 32 カ国(このうち署名のみで未批准の国は 13 カ国)である。化学兵器禁止条約の締約国は、2009 年 5 月現在、188 カ国であり、署名のみで未批准国はイスラエルとミャンマー、署名も批准もしていない国は、アンゴラ、エジプト、北朝鮮、ソマリア、シリアの 5 カ国である。










 </button>
</button>