アメリカで日本人が2人以上集まると必ず始まる(?)のが、アメリカ人批判。思いっ切り自己文化中心的になってアメリカ人の悪口(?)を言うのは、結構ストレス解消になるもの。
先日まで一緒だった親とわたしの間で度々話題に上ったのが、アメリカ人の汚い食べ方。紙ナプキンを何枚もくちゃくちゃにしながら口を拭き拭き食べ、食べ終わった後はそれらのナプキンを皿の上に山積みに・・・。「そんな食べ方がアメリカでは『普通』なの。それを汚いと言うあなたは自己文化中心主義者よ」と言われればそれまでだけれど・・・。それでも、紙ナプキンを使い過ぎ!
なぜアメリカ人の食べ方は汚いのか?(←それでも「汚い」と言い張るわたし )一つ考えられるのが、アメリカでは「かぶりつき」の食べ物が多いこと。ハンバーガー、サンドイッチ、ピッツア、タコス、ブリトー、それに最近多いラップ(写真)。どれもが大口を開けてかぶりついて食べていい物。かぶりついて食べているとどうなるか?かぶりつく度に「たれ」が滴り落ちるから、紙ナプキンを使用することになります。そのナプキンも、きちんと折りながら使用すればいいのに、くちゃくちゃに潰して何枚も使う・・・。
)一つ考えられるのが、アメリカでは「かぶりつき」の食べ物が多いこと。ハンバーガー、サンドイッチ、ピッツア、タコス、ブリトー、それに最近多いラップ(写真)。どれもが大口を開けてかぶりついて食べていい物。かぶりついて食べているとどうなるか?かぶりつく度に「たれ」が滴り落ちるから、紙ナプキンを使用することになります。そのナプキンも、きちんと折りながら使用すればいいのに、くちゃくちゃに潰して何枚も使う・・・。
少なくとも普段、わたしがオレゴンの下宿先で食事をするときはナプキンは不要です。ナプキンがいるような物も食べないし、食べ方もしないからです。アメリカではなぜかぶりつきの食べ物が多いのか知らないけれど、紙ナプキンを何枚も使用することを前提にした食事は見直したほうがいいのでは?
人気blogランキングへ
先日まで一緒だった親とわたしの間で度々話題に上ったのが、アメリカ人の汚い食べ方。紙ナプキンを何枚もくちゃくちゃにしながら口を拭き拭き食べ、食べ終わった後はそれらのナプキンを皿の上に山積みに・・・。「そんな食べ方がアメリカでは『普通』なの。それを汚いと言うあなたは自己文化中心主義者よ」と言われればそれまでだけれど・・・。それでも、紙ナプキンを使い過ぎ!
なぜアメリカ人の食べ方は汚いのか?(←それでも「汚い」と言い張るわたし
 )一つ考えられるのが、アメリカでは「かぶりつき」の食べ物が多いこと。ハンバーガー、サンドイッチ、ピッツア、タコス、ブリトー、それに最近多いラップ(写真)。どれもが大口を開けてかぶりついて食べていい物。かぶりついて食べているとどうなるか?かぶりつく度に「たれ」が滴り落ちるから、紙ナプキンを使用することになります。そのナプキンも、きちんと折りながら使用すればいいのに、くちゃくちゃに潰して何枚も使う・・・。
)一つ考えられるのが、アメリカでは「かぶりつき」の食べ物が多いこと。ハンバーガー、サンドイッチ、ピッツア、タコス、ブリトー、それに最近多いラップ(写真)。どれもが大口を開けてかぶりついて食べていい物。かぶりついて食べているとどうなるか?かぶりつく度に「たれ」が滴り落ちるから、紙ナプキンを使用することになります。そのナプキンも、きちんと折りながら使用すればいいのに、くちゃくちゃに潰して何枚も使う・・・。少なくとも普段、わたしがオレゴンの下宿先で食事をするときはナプキンは不要です。ナプキンがいるような物も食べないし、食べ方もしないからです。アメリカではなぜかぶりつきの食べ物が多いのか知らないけれど、紙ナプキンを何枚も使用することを前提にした食事は見直したほうがいいのでは?
人気blogランキングへ













 。(←ブルーベリーはあんたを恋人とは思っちゃいないよ)何はともあれ、わたしは正常な舌を持っているのは確かなようです。
。(←ブルーベリーはあんたを恋人とは思っちゃいないよ)何はともあれ、わたしは正常な舌を持っているのは確かなようです。

 素顔の君も、とっても素敵さ!
素顔の君も、とっても素敵さ!

 。短気のわたしは昼食後、1時間ほど冷凍したブルーベリーをさっそくデザートに。甘~くておいしい!!ブルーベリー摘みに同行した下宿先のお父様が、「商売用に大きくて見栄えがいいのを朝のうちに摘んでしまっていて、いいのが残ってなかった」とぐちっていて、そう言われてみればそうかな、とわたしも思ったけれど、それでも十分おいしい~!肥沃な土地と太陽などの、まさに自然が生んだ大傑作、"ブルブルブルーベリー"。そんなブルーベリーを食べるということは、オレゴンの自然と一体化すること!?
。短気のわたしは昼食後、1時間ほど冷凍したブルーベリーをさっそくデザートに。甘~くておいしい!!ブルーベリー摘みに同行した下宿先のお父様が、「商売用に大きくて見栄えがいいのを朝のうちに摘んでしまっていて、いいのが残ってなかった」とぐちっていて、そう言われてみればそうかな、とわたしも思ったけれど、それでも十分おいしい~!肥沃な土地と太陽などの、まさに自然が生んだ大傑作、"ブルブルブルーベリー"。そんなブルーベリーを食べるということは、オレゴンの自然と一体化すること!?





 )まあ、わたしだってフルーツ・サラダだったら作れますけどね。(←それって、いろんな果物入れて混ぜるだけ・・・
)まあ、わたしだってフルーツ・サラダだったら作れますけどね。(←それって、いろんな果物入れて混ぜるだけ・・・ )
) 国際オリンピック委員会の前会長だったサマランチさん、覚えてますか?)
国際オリンピック委員会の前会長だったサマランチさん、覚えてますか?) パック詰めよりも格安なのがうれしい!
パック詰めよりも格安なのがうれしい! 「ブルーべリーの実がなる時」を満喫します♪
「ブルーべリーの実がなる時」を満喫します♪
 にオレンジ、グレープフルーツ、
にオレンジ、グレープフルーツ、 去年食べた生のブルーベリーはそれだけ。今年は去年の欲求不満を満たすべく、ブルーベリーを食べまくり!といきたいところなんですが、わたしには安い買い物ではありません。
去年食べた生のブルーベリーはそれだけ。今年は去年の欲求不満を満たすべく、ブルーベリーを食べまくり!といきたいところなんですが、わたしには安い買い物ではありません。

 続きで夏本番!を迎えたオレゴン。毎日通る川沿いのサイクリング・ロードもすっかり夏景色に(下の写真。上が昼間で、下が夕暮れ時)。来週初めにかけて気温がどんどん上昇して月曜日には35℃を突破し、その後は30℃以下で落ち着くとか。わたしが好きな野菜や果物(トマト、スイカ、桃、ブルーベリー等など)がこれから旬を迎えるので待ち遠しい!
続きで夏本番!を迎えたオレゴン。毎日通る川沿いのサイクリング・ロードもすっかり夏景色に(下の写真。上が昼間で、下が夕暮れ時)。来週初めにかけて気温がどんどん上昇して月曜日には35℃を突破し、その後は30℃以下で落ち着くとか。わたしが好きな野菜や果物(トマト、スイカ、桃、ブルーベリー等など)がこれから旬を迎えるので待ち遠しい!


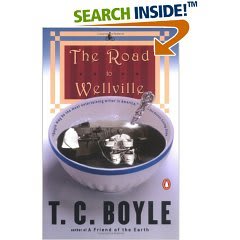


 )家庭を持ったら、ジュースは家で作って飲んでもいいのかもしれないけれど、今は時々店で購入して飲むのが、日常生活における手の届く贅沢。(←これって、スタバの売り文句だったっけ?)こんなジュースが店で手に入るなんて・・・、
)家庭を持ったら、ジュースは家で作って飲んでもいいのかもしれないけれど、今は時々店で購入して飲むのが、日常生活における手の届く贅沢。(←これって、スタバの売り文句だったっけ?)こんなジュースが店で手に入るなんて・・・、

 」
」 からたっぷりとエネルギーをもらう夏。その分食事はロー・エネルギーで十分ですね。
からたっぷりとエネルギーをもらう夏。その分食事はロー・エネルギーで十分ですね。