昨日の夜スプリング・フィールドをバスで出発し、シャンペーン(Champaign, Illinois)にやって来ました。周りをトウモロコシ畑に囲まれた、イリノイ大学所在地です。ここではちょっと豪華にモーテル(自動車旅行者用のホテル)に宿泊し、久しぶりにお風呂を堪能しました。脱塩素剤、重曹、ホホバオイル、それにローズマリーオイル入りでリラックス。(←その後、お風呂のお湯を使って洗濯しました。念のため)
久しぶりにお風呂を堪能したわたしを、更なる感動が待っていた!テレビで『クレヨンしんちゃん』を放映していたのです!(なぜかそのチャンネルは画像が悪かったけれど。)もちろん英語。しんちゃんのあの独特の言葉遣いは英語にはないけれど、声や全体の雰囲気はオリジナルのまま。ジブリ作品もそうだけれど、オリジナルの雰囲気を壊さずにうまく吹き替えをしているのに感心します。
上の画像は、「お立ち台」の上で「ゾウさんダンス」を披露するしんちゃんと、それを見て喜ぶ妹のひまわり。下の画像は、カメレオンごっこをしているしんちゃん。相変わらずおバカですね~。でも、そんなおバカな場面を写真に撮って、こうしてブログにアップするわたしはもっとおバカ!?
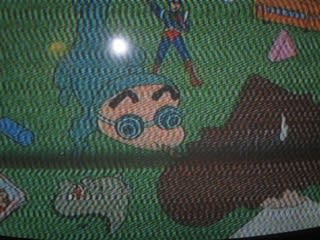
トウモロコシ畑に囲まれたアメリカのハートランドで、『クレヨンしんちゃん』をテレビで観れるとは!しんちゃんから「おバカ・パワー」をいっぱいもらったので、こらから移動が多い旅行を乗り切ります。今日の夕方、バスでオハイオ州シンシナティに向かいます。
人気blogランキングへ
久しぶりにお風呂を堪能したわたしを、更なる感動が待っていた!テレビで『クレヨンしんちゃん』を放映していたのです!(なぜかそのチャンネルは画像が悪かったけれど。)もちろん英語。しんちゃんのあの独特の言葉遣いは英語にはないけれど、声や全体の雰囲気はオリジナルのまま。ジブリ作品もそうだけれど、オリジナルの雰囲気を壊さずにうまく吹き替えをしているのに感心します。
上の画像は、「お立ち台」の上で「ゾウさんダンス」を披露するしんちゃんと、それを見て喜ぶ妹のひまわり。下の画像は、カメレオンごっこをしているしんちゃん。相変わらずおバカですね~。でも、そんなおバカな場面を写真に撮って、こうしてブログにアップするわたしはもっとおバカ!?
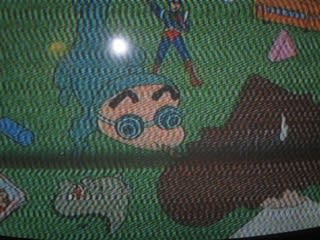
トウモロコシ畑に囲まれたアメリカのハートランドで、『クレヨンしんちゃん』をテレビで観れるとは!しんちゃんから「おバカ・パワー」をいっぱいもらったので、こらから移動が多い旅行を乗り切ります。今日の夕方、バスでオハイオ州シンシナティに向かいます。
人気blogランキングへ













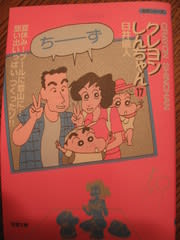
 (ちなみに、わたしのノートパソコン(laptop)の壁紙は『クレしん』です。)
(ちなみに、わたしのノートパソコン(laptop)の壁紙は『クレしん』です。)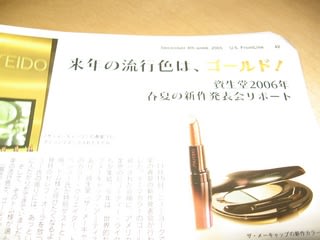
 くるものがありますね~。「ぐっと若返る」って、どの程度若返ることができるのでしょうか?80才のおばあちゃんが20代に見えるようになるっていうんだったら、わたしも買ってやってもいいけど。
くるものがありますね~。「ぐっと若返る」って、どの程度若返ることができるのでしょうか?80才のおばあちゃんが20代に見えるようになるっていうんだったら、わたしも買ってやってもいいけど。
 」
」