昨日4月28日(土)日本テレビの「世界一受けたい授業一限目体育東京大学大学院教授深代千之先生の運動神経のつくり方を見た。思わず凄いと感心した。
- 授業ではソフトボール投げ
- 縄跳びの二重とび
- 50メートル競走
- とび箱
等を最初小学生が行い、先生の訓練の後に再度上記の運動を行った。そしてその結果は全て運動能力が向上していた。元々がやる気がないような小学生と言う気もしたが、それでも結果は明らかだ。
そしていずれにしても理論的(効率的)な運動指導は、結果を残す事ができると実感した。逆を言えば、正しく(理論的)教えなければ、その運動能力は、個人が生まれもった能力となるのだろうか?
上記の訓練の中で、ボールを投げるトレーニングに登場した紙でっぽうで破裂音を出す遊び。地面にたたきつけるかるたあそび。いずれも昔当たり前に小学生の頃遊んでいた。もちろん学校の休み時間では、ボール投げなどごく普通に遊んでいた。
学校の先生が、上記体育で理論的に教えてもらった記憶はない。当たり前の遊びの一貫や個人の努力で実行していたに過ぎない。
上記のTVを見て、「今の体育は凄いね!学校でこんな事を先生が教えてくれれば、みんなできるよね!昔体育で先生は何も教えてくれなかったよ!」と言うと娘が「今でも体育は何も教えてくれないよ!」と一蹴された。
ウーンやはり、学校教育が間違っている。これは先生個人の問題ではないだろう。文部科学省の問題だろうか?日教組の問題だろうか?教育委員会の問題だろうか?
正しく教える事ができない先生に指導させると言う教育システムが間違いだ。根性論だけではだめだ。何の指導もできない先生が悪い。しかしそれを強要している仕組みが悪い。
最近の例で言うと、文部科学省が、中学校保健体育において、武道(柔道・剣道等)の必修化と言う改悪を行ったが、これなどを考えるとやはり教育の元凶は文部科学省と言う事になる。柔道を習った事がない体育の先生に体育授業で柔道を受けさせるなど論外だ。それこそ事故が起きるのは必然だ。従って事故が起きた場合は先生を訴えると言うより文部科学省を訴えるしかないのだろうか?
















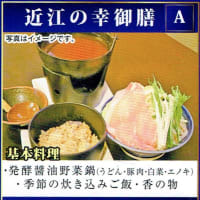
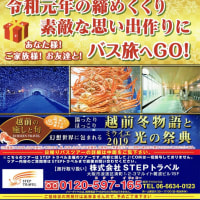


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます