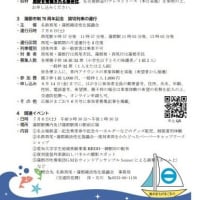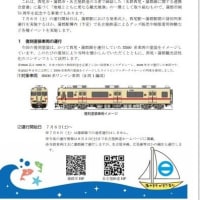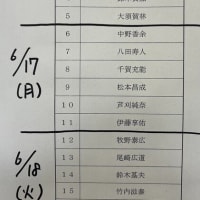令和4年5月10日(火)
お早うございます。
今日は戦後 日本の電力復興、再編成に大きく貢献した,
「元GHQ エアーズ大佐の貢献 その6」を掲載いたします。
占領軍と日本政府の間で、電力業界の再編を研究することが決まった。
その研究に当たったのは、日本政府、日本発送電、各配電、それに占領当局だった。
「占領当局の仕事はほとんど完全にエアーズ大佐とその部下に依存した。
日本政府の分担は、通産省電力局、衆参両院電力委員会、組織されたばかりの公益 委員会が受け持った。
エアーズ大佐は毎週日本の公益委員会と会った。
電力産業再編には、議会、日本発送電、それに新しい発電所建設をいつも受注している大手建設業者からの強い反対があった。
簡単に言えば、日本の電力業界の再編とは、その縄張り内に発電や送電から料金の徴収にいたるまでの機能を収め、 そのほかにもおよそあらゆる機能を押さえている日本発電と各配電を共に廃止してしまうことから成っていた。
再編の予定期日は一応1951年5月1日 だったのだが、もし日本側に主導権を全面的に渡してしまえば、この期日は守られそうになかった。
このような状況の下でエアーズ大佐は、1951年4月 17日に開いた毎週ごとの日本側公益委員会との話し合いの席上、同委員会に対し再編の長所と短所を調査・検討したこと、長所が短所を上回っており、占領軍は再編が予定通り1951年5月1日に実行に移されると考えていることを通告した。
同委員会の松本委員長・松永副委員長はエアーズ大佐の声明はまさに重大な決定を伝えたものであり、本部に持ち帰り討議したい、と述べた。

松永安左エ門(1953年頃)
松永 安左エ門(松永 安左衞門、まつなが やすざえもん、1875年(明治8年)12月1日 - 1971年(昭和46年)6月16日)は、明治末期から昭和にかけて長く日本の電力業界において活動した実業家である。
エアーズ大佐は後になって、彼らが記者団と会見し、その場でエアーズ大佐の決定を紹介したことを知った。
翌朝日本発送電の取締役三人が通訳を伴ってエ アーズ大佐の事務所を訪れ、新聞で同大佐が公益委員会に対し述べたと報じていることは、大佐が述べたことなのかどうかの確認を求めた。
彼は実質的に正 しい、と答えた。
そこで取締役たちは、再編反対を繰り返し述べた。
エアーズ 大佐は30分ばかり耳を傾けた後に、彼が決定を下す際に考慮しなかった問題 があるとの反論がなく、検討済みの反論を繰り返すことは時間の無駄だと伝え た。
両者は二言三言友好的なあいさつを交わし、取締役たちは引き上げた。
エ アーズ大佐は後になって、彼らが本社に帰ってから取締役会が招集され、これ 以上再編に抵抗せずにその実現に協力することを決めた、と教えられた。
再編 は吉田首相の承認を受けてから官報 (米国の連邦議会議事録に相当)に掲載さ れた。
これで1951年5月1日に再編が実施されることが、公布されたわけ である。
それ以後、九つの地方電力会社のそれぞれが民間所有(株式所有制) となり、所有者により支配されている。
各社が、新規の建設、発電、送電、配電のための増資から料金徴収に至る全過程について、その寡占力の乱用を阻止するための政府の規制に従うことを条件に、責任を有している。
慈悲深い専制君主の下では、短い期間であれば、きわめて大きな利点が生かされる場合もありうる。
しかし権力は腐敗を生み、絶対的権力は絶対に腐敗を生む。
エアーズ 大佐は、再編の初期段階で顧問として活躍し、特に電力各社間で電気エネルギーを融通し合い経済的な発電を最良の形で使えるようにすること、水力発電が多数あった当時にあっては乾燥期に電力を買う資金を賄うための予備基金を積み立てる こと、を勧告した。
また、実際経営のやり方の変更も勧告した。
電力各社は基礎負荷を荷うため水力発電を利用し、火力発電は最大負荷に対応する のに利用していた。しかし将来の水力発電の立地はほとんど残されておらず、建設費・利用費ともにインフレが進む中で巨額であった。
予想される電力需要賄うため高温、高圧、高能率の火力発電所を建設し、基礎負荷を担当させ、最大負荷時には貯水池式水力発電所を登場させるとの勧告が行われた。
こ のような基礎負荷向け発電所は、最良の場所を選んで建設でき、遠隔地の水カ発電所に比べ建設期間が短く済み、キロワット当たりの発電コストも同じか安いぐらいであった。
この勧告の後に (将来へのエネルギー要求が強まるにつれ)輸入石油、そして(その後)原子 エネルギー(これは大型発電施設用である)の利用が続いた。
新しい条約と占領の終結への動きが進み、日本の電力産業の再編がスムース に進展した結果、エアーズ大佐が日本に留まる必要は少なくなった。
沖縄で建設されていた全島電力網が新しい料金体系を必要とした時点で、彼はこれが電力公益事業での経験を生かす新たな機会だと考えた。
このため1952年5月 に沖縄に行き、先に概略述べたような実績をあげた。
沖縄には約四か月半滞在 し、日本には1952年8月に戻った。
一方、講和条約が批准され、占領が終結し、もはやエアーズ大佐が日本にいる必要はなくなった。
ほとんど7年近くの極東での生活を終え、同大佐は1952年8月に米国に帰国した。
彼の業績を振り返って一瞥を与えてみると、エアーズ大佐が日本の電力業界で成し遂げたこと、彼が提唱した計画や政策、その決定は適切なものであった という以外なく、また日本人はそれを実現する上で見事な手腕を発揮した。
このことは、日本の電力産業が、第二次世界大戦後の電力不足の経済状態から脱出し、今や米国とソ連に次いで、世界第三位の電力生産国になっていることに しめされている。

松永安左エ門記念館の入口付近にある路面電車と古民家
松永安左エ門記念館の敷地に入り、まず目を引くのが路面電車と木造の古民家です。
路面電車は安左エ門が1909年設立した福博電軌が最初に福岡市内に路面電車を走らせた功績を称え、実際に福岡市内を走っていた路面電車で、木造の古民家は安左エ門翁が生まれた生家です。
蒲郡市三谷町弘法山に所在する、喫茶「Hill Top ヒルトップ」 内にある、
元GHQ エアーズ大佐・感謝記念館に展示されている資料




長田 理 氏が小田原市の松永記念館に「エアーズ大佐」に関する資料を寄贈し、当時の小田原市長より感謝状を贈られる。
日本の電力業界において活動した実業家である、松永安左エ門記念館は、
生誕地である福岡市と、昭和21年に小田原へ居住してご逝去された小田原市の二ヶ所あります。
お早うございます。
今日は戦後 日本の電力復興、再編成に大きく貢献した,
「元GHQ エアーズ大佐の貢献 その6」を掲載いたします。
占領軍と日本政府の間で、電力業界の再編を研究することが決まった。
その研究に当たったのは、日本政府、日本発送電、各配電、それに占領当局だった。
「占領当局の仕事はほとんど完全にエアーズ大佐とその部下に依存した。
日本政府の分担は、通産省電力局、衆参両院電力委員会、組織されたばかりの公益 委員会が受け持った。
エアーズ大佐は毎週日本の公益委員会と会った。
電力産業再編には、議会、日本発送電、それに新しい発電所建設をいつも受注している大手建設業者からの強い反対があった。
簡単に言えば、日本の電力業界の再編とは、その縄張り内に発電や送電から料金の徴収にいたるまでの機能を収め、 そのほかにもおよそあらゆる機能を押さえている日本発電と各配電を共に廃止してしまうことから成っていた。
再編の予定期日は一応1951年5月1日 だったのだが、もし日本側に主導権を全面的に渡してしまえば、この期日は守られそうになかった。
このような状況の下でエアーズ大佐は、1951年4月 17日に開いた毎週ごとの日本側公益委員会との話し合いの席上、同委員会に対し再編の長所と短所を調査・検討したこと、長所が短所を上回っており、占領軍は再編が予定通り1951年5月1日に実行に移されると考えていることを通告した。
同委員会の松本委員長・松永副委員長はエアーズ大佐の声明はまさに重大な決定を伝えたものであり、本部に持ち帰り討議したい、と述べた。

松永安左エ門(1953年頃)
松永 安左エ門(松永 安左衞門、まつなが やすざえもん、1875年(明治8年)12月1日 - 1971年(昭和46年)6月16日)は、明治末期から昭和にかけて長く日本の電力業界において活動した実業家である。
エアーズ大佐は後になって、彼らが記者団と会見し、その場でエアーズ大佐の決定を紹介したことを知った。
翌朝日本発送電の取締役三人が通訳を伴ってエ アーズ大佐の事務所を訪れ、新聞で同大佐が公益委員会に対し述べたと報じていることは、大佐が述べたことなのかどうかの確認を求めた。
彼は実質的に正 しい、と答えた。
そこで取締役たちは、再編反対を繰り返し述べた。
エアーズ 大佐は30分ばかり耳を傾けた後に、彼が決定を下す際に考慮しなかった問題 があるとの反論がなく、検討済みの反論を繰り返すことは時間の無駄だと伝え た。
両者は二言三言友好的なあいさつを交わし、取締役たちは引き上げた。
エ アーズ大佐は後になって、彼らが本社に帰ってから取締役会が招集され、これ 以上再編に抵抗せずにその実現に協力することを決めた、と教えられた。
再編 は吉田首相の承認を受けてから官報 (米国の連邦議会議事録に相当)に掲載さ れた。
これで1951年5月1日に再編が実施されることが、公布されたわけ である。
それ以後、九つの地方電力会社のそれぞれが民間所有(株式所有制) となり、所有者により支配されている。
各社が、新規の建設、発電、送電、配電のための増資から料金徴収に至る全過程について、その寡占力の乱用を阻止するための政府の規制に従うことを条件に、責任を有している。
慈悲深い専制君主の下では、短い期間であれば、きわめて大きな利点が生かされる場合もありうる。
しかし権力は腐敗を生み、絶対的権力は絶対に腐敗を生む。
エアーズ 大佐は、再編の初期段階で顧問として活躍し、特に電力各社間で電気エネルギーを融通し合い経済的な発電を最良の形で使えるようにすること、水力発電が多数あった当時にあっては乾燥期に電力を買う資金を賄うための予備基金を積み立てる こと、を勧告した。
また、実際経営のやり方の変更も勧告した。
電力各社は基礎負荷を荷うため水力発電を利用し、火力発電は最大負荷に対応する のに利用していた。しかし将来の水力発電の立地はほとんど残されておらず、建設費・利用費ともにインフレが進む中で巨額であった。
予想される電力需要賄うため高温、高圧、高能率の火力発電所を建設し、基礎負荷を担当させ、最大負荷時には貯水池式水力発電所を登場させるとの勧告が行われた。
こ のような基礎負荷向け発電所は、最良の場所を選んで建設でき、遠隔地の水カ発電所に比べ建設期間が短く済み、キロワット当たりの発電コストも同じか安いぐらいであった。
この勧告の後に (将来へのエネルギー要求が強まるにつれ)輸入石油、そして(その後)原子 エネルギー(これは大型発電施設用である)の利用が続いた。
新しい条約と占領の終結への動きが進み、日本の電力産業の再編がスムース に進展した結果、エアーズ大佐が日本に留まる必要は少なくなった。
沖縄で建設されていた全島電力網が新しい料金体系を必要とした時点で、彼はこれが電力公益事業での経験を生かす新たな機会だと考えた。
このため1952年5月 に沖縄に行き、先に概略述べたような実績をあげた。
沖縄には約四か月半滞在 し、日本には1952年8月に戻った。
一方、講和条約が批准され、占領が終結し、もはやエアーズ大佐が日本にいる必要はなくなった。
ほとんど7年近くの極東での生活を終え、同大佐は1952年8月に米国に帰国した。
彼の業績を振り返って一瞥を与えてみると、エアーズ大佐が日本の電力業界で成し遂げたこと、彼が提唱した計画や政策、その決定は適切なものであった という以外なく、また日本人はそれを実現する上で見事な手腕を発揮した。
このことは、日本の電力産業が、第二次世界大戦後の電力不足の経済状態から脱出し、今や米国とソ連に次いで、世界第三位の電力生産国になっていることに しめされている。

松永安左エ門記念館の入口付近にある路面電車と古民家
松永安左エ門記念館の敷地に入り、まず目を引くのが路面電車と木造の古民家です。
路面電車は安左エ門が1909年設立した福博電軌が最初に福岡市内に路面電車を走らせた功績を称え、実際に福岡市内を走っていた路面電車で、木造の古民家は安左エ門翁が生まれた生家です。
蒲郡市三谷町弘法山に所在する、喫茶「Hill Top ヒルトップ」 内にある、
元GHQ エアーズ大佐・感謝記念館に展示されている資料




長田 理 氏が小田原市の松永記念館に「エアーズ大佐」に関する資料を寄贈し、当時の小田原市長より感謝状を贈られる。
日本の電力業界において活動した実業家である、松永安左エ門記念館は、
生誕地である福岡市と、昭和21年に小田原へ居住してご逝去された小田原市の二ヶ所あります。