映画評論家の筈見恒夫も名著「映画五十年史」(昭和17年 鱒書房)の「第八章 傾向映画前後(昭和2年~8年)」の中で、『生ける人形』を取り上げ、丁寧な解説を加えている。少し長いが引用しておこう。
瀬木大助という成上り者が、政界や実業界の裏面を巧みに泳ぎ廻って、虚偽と策謀を処世哲学の根本とするが、最後の一瞬には叩きのめされる。つまり瀬木の如き田舎出の青二才に切り廻されるように、今の社会は甘いものではないのだ。資本主義の機構はより巨大で、より複雑である。瀬木は、今までの映画が主人公として扱ったような正義観の持主ではない。むしろ、逆の立場にある小悪党である。しかし、当時のわれわれは、瀬木大助的な処世哲学に、一面の共感を持たぬでもなかった。『生ける人形』は、そうした現代生活と、現代人の性格に触れたものとして、特筆する価値がある。
内田吐夢は、『漕艇王』の明朗な喜活劇的構成で認められたが、『生ける人形』は彼の名を第一線的なものにした。瀬木に扮した小杉勇、軽薄でスマートな都会女に扮した入江たか子、ともに日本映画の今までに現れなかった個性であり、タイプであった。
この作品が、反響を穫ち得ると、待ち兼ねたように、各社の一流監督が轡を並べて、左翼的な題材を手がけた。
双葉十三郎もリアルタイムで『生ける人形』を観て、鮮烈な印象を受けた一人である。「日本映画 ぼくの300本」(平成16年 文春新書)の中で『生ける人形』に高い評価を加え、こんなコメントを書いている。記憶がほとんど摩滅したコメントであるが、参考までに。
後世の『悪い奴ほどよく眠る』(1960年)を思わせる社会派ドラマ。(中略)
体制や権力への批判、あるいは虐げられた者への共感、といった抵抗、抗議の傾向のある“傾向映画”が当時はやり始めていたが、この映画は現代劇におけるそのはしり。内田吐夢の演出はパンチ力があり、堂々とした作品に仕上げていた。この人の重い正統的な表現力は終生変らず。日本のキング・ヴィドア、オットー・プレミンジャーという感じだ。小杉勇は地味で美男でもないが、存在感ある俳優として数多くの佳作に出演している。また企業ものというテーマも珍しかった。
『生ける人形』については、後年内田吐夢自身が語ったコメントがあるので、紹介しておこう。(キネマ旬報 1960年12月増刊号「日本映画監督特集」)
この頃から、左翼思想を加味した「傾向映画」といわれる作品が時代劇でも現代劇でも、いくつか作られ、これが一つの流行に発展しました。これは朝日新聞に連載された小説で、一人の小市民が自分は資本主義のカラクリを利用したつもりで、最後には逆にそれにおしつぶされてしまうという筋で、傾向映画の仲間に入る作品です。しかし、左翼思想といっても今から考えるとずいぶん形式的なもので、ぼく自身ほんとうにその思想を理解していたわけではありませんでした。第一、これをつくることは会社の企画でしたし、まあ、時流に乗ったとでもいう方がいいのではないでしょうか。
しかし、ぼくとしては小林正君と組んで以来、諷刺喜劇に新しいものをねらっていましたし、その線ではある程度成功したのではないかと思います。それからもう一つ、この作品と前後してぼくの演出上の手法が変りました。非常に感覚的なものをとり入れて、映画の表現力というもの、映画の形式というものを純粋に考えるようになりました。
瀬木大助という成上り者が、政界や実業界の裏面を巧みに泳ぎ廻って、虚偽と策謀を処世哲学の根本とするが、最後の一瞬には叩きのめされる。つまり瀬木の如き田舎出の青二才に切り廻されるように、今の社会は甘いものではないのだ。資本主義の機構はより巨大で、より複雑である。瀬木は、今までの映画が主人公として扱ったような正義観の持主ではない。むしろ、逆の立場にある小悪党である。しかし、当時のわれわれは、瀬木大助的な処世哲学に、一面の共感を持たぬでもなかった。『生ける人形』は、そうした現代生活と、現代人の性格に触れたものとして、特筆する価値がある。
内田吐夢は、『漕艇王』の明朗な喜活劇的構成で認められたが、『生ける人形』は彼の名を第一線的なものにした。瀬木に扮した小杉勇、軽薄でスマートな都会女に扮した入江たか子、ともに日本映画の今までに現れなかった個性であり、タイプであった。
この作品が、反響を穫ち得ると、待ち兼ねたように、各社の一流監督が轡を並べて、左翼的な題材を手がけた。
双葉十三郎もリアルタイムで『生ける人形』を観て、鮮烈な印象を受けた一人である。「日本映画 ぼくの300本」(平成16年 文春新書)の中で『生ける人形』に高い評価を加え、こんなコメントを書いている。記憶がほとんど摩滅したコメントであるが、参考までに。
後世の『悪い奴ほどよく眠る』(1960年)を思わせる社会派ドラマ。(中略)
体制や権力への批判、あるいは虐げられた者への共感、といった抵抗、抗議の傾向のある“傾向映画”が当時はやり始めていたが、この映画は現代劇におけるそのはしり。内田吐夢の演出はパンチ力があり、堂々とした作品に仕上げていた。この人の重い正統的な表現力は終生変らず。日本のキング・ヴィドア、オットー・プレミンジャーという感じだ。小杉勇は地味で美男でもないが、存在感ある俳優として数多くの佳作に出演している。また企業ものというテーマも珍しかった。
『生ける人形』については、後年内田吐夢自身が語ったコメントがあるので、紹介しておこう。(キネマ旬報 1960年12月増刊号「日本映画監督特集」)
この頃から、左翼思想を加味した「傾向映画」といわれる作品が時代劇でも現代劇でも、いくつか作られ、これが一つの流行に発展しました。これは朝日新聞に連載された小説で、一人の小市民が自分は資本主義のカラクリを利用したつもりで、最後には逆にそれにおしつぶされてしまうという筋で、傾向映画の仲間に入る作品です。しかし、左翼思想といっても今から考えるとずいぶん形式的なもので、ぼく自身ほんとうにその思想を理解していたわけではありませんでした。第一、これをつくることは会社の企画でしたし、まあ、時流に乗ったとでもいう方がいいのではないでしょうか。
しかし、ぼくとしては小林正君と組んで以来、諷刺喜劇に新しいものをねらっていましたし、その線ではある程度成功したのではないかと思います。それからもう一つ、この作品と前後してぼくの演出上の手法が変りました。非常に感覚的なものをとり入れて、映画の表現力というもの、映画の形式というものを純粋に考えるようになりました。











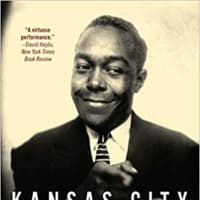

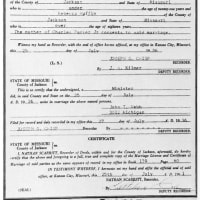







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます