今や女性脚本家が花盛りで、テレビドラマや映画の脚本は女性が書いたものが多い。で、まだテレビのない時代、映画の世界で女性脚本家と言えば、水木洋子、田中澄江、和田夏十、楠田芳子といったところだった。戦前、女流文学者はたくさん居たが、脚本家は皆無に近かった。そんな中、大正末期に21歳でデビューした日本初の女性脚本家と言われる才女がいた。水島あやめ(1903~1990)である。

水島あやめ
水島あやめという人のことを私が知ったのは、5年ほど前、無声映画鑑賞会で『明け行く空』(松竹キネマ蒲田作品、斉藤寅次郎監督 水島あやめ脚本)を観た時だった。その時、弁士の澤登翠さんが、この女性脚本家のことを紹介してくれた。
それから、ちょうど2年前、内田吐夢監督の没後40年の上映会を池袋の新文芸坐で催すことになり、企画者である私がその記念本「命一コマ 映画監督内田吐夢の全貌」という本を編集していて、その時にフィルモグラフィーを作成していたら、『極楽島の女王』とういう映画の脚本に水島あやめという名前を見つけて、あっと思った。調べてみると同一人物で、小笠原プロから松竹キネマ蒲田へ入ってたくさん脚本を書いている人だということが分った。珍しい女性がいるものだと思ってその時はそれで終ってしまったが、今になってまた水島あやめが浮上してきた。
私が今、入江たか子や小笠原プロのことを勉強しているのも、もともと内田吐夢がきっかけなのだが、その前に戻れば、子供の頃ファンだった中村錦之助の映画を、五十歳を過ぎてまた観始めたのが出発点だった。内田吐夢と水島あやめは、もしかして小笠原プロの撮影現場のどこかで顔を合わせていたかもしれない、なんて空想している。当時の内田吐夢は、ロシア人の血が混じっているのではないかと思うほど日本人離れした美男子で背も高く快活だった。ひと目見たら忘れないほど目立っていたそうだが、どうだろう。
水島あやめに関しては、「日本で初めての女性映画脚本家 水島あやめ」というホームページがあり、その中の「あやめの生涯」が詳しい。これは、因幡純雄という親族の方が月刊「シナリオ」に2006年から翌年12月まで連載した「日本初の女性脚本家 水島あやめ伝」に準拠したものだとのことだが、今度それも全部読んでみたいと思っている。また、私は寡聞にして知らなかったが、2003年7月に郷里の新潟県南魚沼市六日町で「水島あやめ生誕100年祭」があり、佐藤忠男氏の講演と、映画『明け行く空』を佐々木亜希子さんの活弁で上映したそうだ。その時のプログラムが佐々木さんのホームページに掲載されていたので、プログラムにある水島あやめの略歴なども参照した。
前置きが長くなった。
水島あやめは、1903年(明治36年)、新潟県南魚沼郡三和村大月(現・南魚沼市大月)で生まれた。本名は高野千年(ちとせ)。1921年(大正10年)、長岡高等女学校を卒業して母と上京。日本女子大学師範家政科に入り、20歳で『面白倶楽部』の懸賞小説に当選した。そして1924年(大正12年)、大学4年の時、小笠原プロで映画の脚本を手がけるようになる。
水島あやめが、なぜ小笠原プロに入って脚本を書くようになったのかは分らないが、映画化された第一作が『落葉の唄』。続いて『水兵の母』の脚本を書き、この映画は興行的に成功。大学卒業後、松竹キネマ蒲田撮影所の脚本部へ入る。小笠原プロにいた頃に書いた『極楽島の女王』の脚本が特作映画社によって製作され、帝劇で上映されるが評判はよろしからず。研修期間を経て、1926年(大正15年)、松竹に正式入社。『お坊ちゃん』を初めとして、9年間で二十数本の脚本を書く。1935 年(昭和10年)、松竹キネマが大船へ移転するのを機に退社。少女時代からの夢だった小説家に転じ、以後少女小説、翻訳児童書など数多くの作品を残した。
経歴をざっとまとめるとこんなところである。
さて、水島あやめの第一回映画化作品の『落葉の唄』のデータは以下の通り。
『落葉の唄』 1924年11月公開 浅草遊園第二館 5巻 小笠原プロ
監督:小笠原明峰 原作:国本輝堂 脚色:水島あやめ 撮影:稲見興美
セット:尾崎章太郎
出演:河井八千代(芳田君子)、沢栄子(母美保子)、北島貞子(娘道子)、児島武彦(伯父哲造)、島静二(医師立川)、三枝鏡子(道子の友)、三田文子(同)、龍田静枝(同)
原作の国本輝堂という人物は不明。セットの尾崎章太郎は、正しくは庄太郎だと思うが、大正活映からやって来た美術デザイナー。
主演の河井八千代は子役で妹役。
児島武彦は、正しくは鹿児島武彦で、日活京都の二枚目俳優から後に映画監督になった島耕二である。島耕二(1901~1986)は、長崎生まれで、長崎中学から豊国中学で学んだ後、徴兵検査で甲種合格。2年間の兵役を終え実家へ帰ると、新聞で日本映画俳優学校の開校の記事を見かけ、その生徒募集に応じて東京へ。1923年11月第一期生として入学。在校中の24年、小笠原プロの『落葉の唄』に本名で映画初出演した。

島耕二
また、その後スター女優として活躍した龍田静枝が映画初出演している。(龍田静枝については後述したい。)
この映画の内容はいわゆる「母もの」で、可憐な少女の悲しくセンティメンタルな話だったようだ。岸松雄は「日本映画監督全集」の小笠原明峰の項で、「子役の河合八千代のセンティメンタリズムに大感激した。赤坂帝国館で見た記憶がある」と書いている。
この作品から、水島あやめはペンネームを使い始めた。前掲の「水島あやめ」ホームページから転用させていただくと、彼女は、晩年、知人宛の手紙にこう書いたそうだ。
私のペンネームは、小笠原プロで、初めて作品が出来たとき、本名だと、学校を退校もなるかもしれないので(そのころの目白は、きびしくて、沢村貞子さんなど、ちょっと新劇に出て退校になった)ペンネームをつけることにし、丁度、小笠原さんの広い裏庭の池に、花しょうぶが盛りだったので、わたしはその花が好きだったし、名前を『あやめ』にして、それに似合う『水島』を姓にしたのです。
目白というのは日本女子大で、女優の沢村貞子(1908~1996)は水島あやめの後輩で、新築地劇団の芝居に出演したため日本女子大師範家政科を退学させられたという話だ。

水島あやめ
水島あやめという人のことを私が知ったのは、5年ほど前、無声映画鑑賞会で『明け行く空』(松竹キネマ蒲田作品、斉藤寅次郎監督 水島あやめ脚本)を観た時だった。その時、弁士の澤登翠さんが、この女性脚本家のことを紹介してくれた。
それから、ちょうど2年前、内田吐夢監督の没後40年の上映会を池袋の新文芸坐で催すことになり、企画者である私がその記念本「命一コマ 映画監督内田吐夢の全貌」という本を編集していて、その時にフィルモグラフィーを作成していたら、『極楽島の女王』とういう映画の脚本に水島あやめという名前を見つけて、あっと思った。調べてみると同一人物で、小笠原プロから松竹キネマ蒲田へ入ってたくさん脚本を書いている人だということが分った。珍しい女性がいるものだと思ってその時はそれで終ってしまったが、今になってまた水島あやめが浮上してきた。
私が今、入江たか子や小笠原プロのことを勉強しているのも、もともと内田吐夢がきっかけなのだが、その前に戻れば、子供の頃ファンだった中村錦之助の映画を、五十歳を過ぎてまた観始めたのが出発点だった。内田吐夢と水島あやめは、もしかして小笠原プロの撮影現場のどこかで顔を合わせていたかもしれない、なんて空想している。当時の内田吐夢は、ロシア人の血が混じっているのではないかと思うほど日本人離れした美男子で背も高く快活だった。ひと目見たら忘れないほど目立っていたそうだが、どうだろう。
水島あやめに関しては、「日本で初めての女性映画脚本家 水島あやめ」というホームページがあり、その中の「あやめの生涯」が詳しい。これは、因幡純雄という親族の方が月刊「シナリオ」に2006年から翌年12月まで連載した「日本初の女性脚本家 水島あやめ伝」に準拠したものだとのことだが、今度それも全部読んでみたいと思っている。また、私は寡聞にして知らなかったが、2003年7月に郷里の新潟県南魚沼市六日町で「水島あやめ生誕100年祭」があり、佐藤忠男氏の講演と、映画『明け行く空』を佐々木亜希子さんの活弁で上映したそうだ。その時のプログラムが佐々木さんのホームページに掲載されていたので、プログラムにある水島あやめの略歴なども参照した。
前置きが長くなった。
水島あやめは、1903年(明治36年)、新潟県南魚沼郡三和村大月(現・南魚沼市大月)で生まれた。本名は高野千年(ちとせ)。1921年(大正10年)、長岡高等女学校を卒業して母と上京。日本女子大学師範家政科に入り、20歳で『面白倶楽部』の懸賞小説に当選した。そして1924年(大正12年)、大学4年の時、小笠原プロで映画の脚本を手がけるようになる。
水島あやめが、なぜ小笠原プロに入って脚本を書くようになったのかは分らないが、映画化された第一作が『落葉の唄』。続いて『水兵の母』の脚本を書き、この映画は興行的に成功。大学卒業後、松竹キネマ蒲田撮影所の脚本部へ入る。小笠原プロにいた頃に書いた『極楽島の女王』の脚本が特作映画社によって製作され、帝劇で上映されるが評判はよろしからず。研修期間を経て、1926年(大正15年)、松竹に正式入社。『お坊ちゃん』を初めとして、9年間で二十数本の脚本を書く。1935 年(昭和10年)、松竹キネマが大船へ移転するのを機に退社。少女時代からの夢だった小説家に転じ、以後少女小説、翻訳児童書など数多くの作品を残した。
経歴をざっとまとめるとこんなところである。
さて、水島あやめの第一回映画化作品の『落葉の唄』のデータは以下の通り。
『落葉の唄』 1924年11月公開 浅草遊園第二館 5巻 小笠原プロ
監督:小笠原明峰 原作:国本輝堂 脚色:水島あやめ 撮影:稲見興美
セット:尾崎章太郎
出演:河井八千代(芳田君子)、沢栄子(母美保子)、北島貞子(娘道子)、児島武彦(伯父哲造)、島静二(医師立川)、三枝鏡子(道子の友)、三田文子(同)、龍田静枝(同)
原作の国本輝堂という人物は不明。セットの尾崎章太郎は、正しくは庄太郎だと思うが、大正活映からやって来た美術デザイナー。
主演の河井八千代は子役で妹役。
児島武彦は、正しくは鹿児島武彦で、日活京都の二枚目俳優から後に映画監督になった島耕二である。島耕二(1901~1986)は、長崎生まれで、長崎中学から豊国中学で学んだ後、徴兵検査で甲種合格。2年間の兵役を終え実家へ帰ると、新聞で日本映画俳優学校の開校の記事を見かけ、その生徒募集に応じて東京へ。1923年11月第一期生として入学。在校中の24年、小笠原プロの『落葉の唄』に本名で映画初出演した。

島耕二
また、その後スター女優として活躍した龍田静枝が映画初出演している。(龍田静枝については後述したい。)
この映画の内容はいわゆる「母もの」で、可憐な少女の悲しくセンティメンタルな話だったようだ。岸松雄は「日本映画監督全集」の小笠原明峰の項で、「子役の河合八千代のセンティメンタリズムに大感激した。赤坂帝国館で見た記憶がある」と書いている。
この作品から、水島あやめはペンネームを使い始めた。前掲の「水島あやめ」ホームページから転用させていただくと、彼女は、晩年、知人宛の手紙にこう書いたそうだ。
私のペンネームは、小笠原プロで、初めて作品が出来たとき、本名だと、学校を退校もなるかもしれないので(そのころの目白は、きびしくて、沢村貞子さんなど、ちょっと新劇に出て退校になった)ペンネームをつけることにし、丁度、小笠原さんの広い裏庭の池に、花しょうぶが盛りだったので、わたしはその花が好きだったし、名前を『あやめ』にして、それに似合う『水島』を姓にしたのです。
目白というのは日本女子大で、女優の沢村貞子(1908~1996)は水島あやめの後輩で、新築地劇団の芝居に出演したため日本女子大師範家政科を退学させられたという話だ。










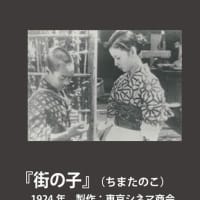



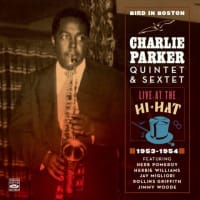
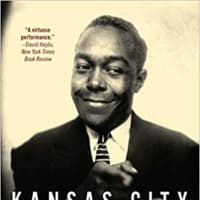

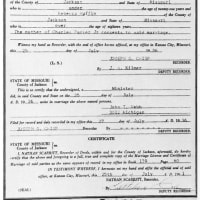



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます