 こんにちは。 今日もあったかいですね
こんにちは。 今日もあったかいですね
我が家は昨日の夜もその前も、全く暖房なしで過ごせてます。
このまま春になってしまえばいいのに

さて、【住宅ローンシリーズその⑨】です。前回のその⑧では[住宅ローン減税]についてお話ししました。
今回は[優遇金利の見方]についてです。
銀行などの住宅ローンには「店頭金利」や「基準金利」として ○% という数字の他、
「店頭金利から ○% 優遇!」といった【優遇金利】の数字が表示されていることがほとんどです。
この優遇金利とは、例えばキャンペーン期間中にローンを申し込めば金利が安くなる、
また給与振込みや、公共料金の引き落としをその銀行で行う、またその銀行のカードローンに加入する、などの条件を満たせば金利が安くなるといったものです。
この優遇金利には大きく分けて二つのパターンがあり、
「当初期間優遇タイプ」・・・金利優遇幅は 1.1~1.5% 程度と厚めになっているが優遇期間が限られているもの。期間終了後もわずかな金利優遇が続くものなどいろいろです。
「全期間一律優遇タイプ」・・・金利優遇幅は 0.7~1.0% と薄いが借り入れ期間の全期間に優遇が適用されるタイプ。
ここで注意するべきは「当初期間優遇タイプ」です。
ほとんどの場合はこのタイプで、銀行などで作ってもらう当初の返済計画もこの優遇金利が適用された返済金額が書かれているものが多いと思います。
例えばある信用金庫さんで「6年固定型住宅ローン」で2000万円を30年ローンで借りた場合、
当初の3年間は基準金利 2.70%のところ優遇金利最大1.4%引きが適用され「1.30%」となり、
月々の返済額は 59,300円 となります。
その後3年間は優遇金利幅は最大1.4%引きのままですが、基準金利が 2.95%に上がるため
適用金利も「1.55%」に上がり、返済額は 61,730円 となります。
7年目以降は変動金利に変わりますのでその時の「金利」が適用されますが、優遇金利も最大優遇期間は終わり、通常優遇金利にかわります。
この信用金庫さんの通常優遇幅は、給与振込みや公共料金引き落としなどを行った場合、
最大1.2%引きとなります。
もし基準金利が 3.00%にあがっていた場合、優遇金利 1.2%を引いた後は 「1.80%」 となり、
返済額は 64,220円となります。
ということで 7年目以降、もし金利が上がっていて優遇金利も少なくなるとすれば、月々の支払い金額も上がりますので、この点に注意が必要です。
このように「住宅ローン」を考える場合、当初の返済金額だけではなく、全期間の返済パターンを考えてプランすることが大事になってきます。
※上記返済金額は「返済額早見表」をもとに計算した概算金額なのであくまで目安です。
次回は返済方法の「元利金等返済」と、「元金均等返済」についてです。

 人気ブログランキング!参加中!
人気ブログランキング!参加中!
 ワンクリック、ご協力お願いいたしま~す
ワンクリック、ご協力お願いいたしま~す
 みなさーん、ココを押すんですよー
みなさーん、ココを押すんですよー
有難うございます。

西播地域でこだわりの家を建てるなら
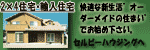
お問い合わせは
 得々情報
得々情報  まで
まで




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます