都市計画に鉄道の高架化が挙げられることは多い。選挙のポスターなどにも立体交差事業を行うという内容は見かける。
よくあげられることだけに,高架上を列車が走ることによる利点は多い。高架化が素敵なことであることがよくアピールされている現行の工事があるのでその様子を見てみたい。

(2009年6月17日撮影)
東大阪市の近鉄奈良線の約3.3kmの高架化工事。イメージキャラクターも設定されている。この工事の財源についても書かれており,大阪府と東大阪市で9割を負担しているとある。

(2009年6月17日撮影)
キャラクターは工事区ごとに設定されている。この案内も工事現場を囲む仕切に書かれている。

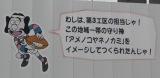

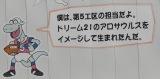
(2009年6月17日撮影)
2~5区のキャラクター。それぞれの工区の仕切に描かれている。この工事の行われている地区に由来するキャラクターで,一人称も使い分けられているようにキャラ設定もなされている。1区のキャラクターは,最初の写真に描かれているが,吹きだしの空欄には名前が入りそうだ。書かれていないのは公募中なのだろうか。
いずれにせよ,メインの工事以外にも時間と費用が投資されていそうだ。
仕切には工事やキャラクターの紹介の他にも・・・

(2009年6月17日撮影)
遺跡があった場所であることが示されたり・・・

(2009年6月17日撮影)
高架化,特に踏切がなくなることのすばらしさについて,色々な表現で紹介をしている。
そして,こんな表現も・・・

(2009年6月17日撮影)
高架化がいかに夢や希望にあふれたものだということが伝わってくる。
踏切がなくなる以外にも,高架下の空間が生まれ,別の用途に利用することができるし,駅の上下移動の回数が地下道や橋を使うよりも少なくなるなどの利点もある。
高架の存在が周囲の景観に与える影響などの問題点もないわけではないだろう。
この工事によって高架駅になる駅が3つある。それらの駅の高架化前の状況を以下で見ていきたい。
若江岩田駅

(2009年6月17日撮影)
工事が始まるまでは地下に改札のある駅だったが,工事の影響で片側のホームへは・・・

(2009年6月17日撮影)
仮駅舎の地上の改札から入るようになっている。
河内花園駅。

(2009年6月17日撮影)

(2009年6月17日撮影)
こちらもホームへは地下道を通るようになっている。

(2009年6月17日撮影)
現在のホームの後には高架橋ができている。
東花園駅。
線路の両側に駅舎がそれぞれある。

(2009年6月17日撮影)

(2009年6月17日撮影)
両方の駅舎と,その間の2つのホームは・・・

(2009年6月17日撮影)
3つの踏切でつながっている。駅郊外の隣接する踏切とは違い,電車の来る部分のみが細切れに遮断機が下りていた。上下移動がほとんどないのは楽だが,早めに駅に来ないと乗り遅れてしまうこともありそうだ。

(2009年6月17日撮影)
今の駅舎の上を高架が走っている。
工事自体はだいぶ進行していそうな印象だった。
仕切に描かれた夢の世界が実現するのもそう遠くはなさそうだ。
同じような工事現場はいくつか見たことがあるが,ここまで工事の内容のアピールに力を入れているのは初めてだった。
よくあげられることだけに,高架上を列車が走ることによる利点は多い。高架化が素敵なことであることがよくアピールされている現行の工事があるのでその様子を見てみたい。

(2009年6月17日撮影)
東大阪市の近鉄奈良線の約3.3kmの高架化工事。イメージキャラクターも設定されている。この工事の財源についても書かれており,大阪府と東大阪市で9割を負担しているとある。

(2009年6月17日撮影)
キャラクターは工事区ごとに設定されている。この案内も工事現場を囲む仕切に書かれている。

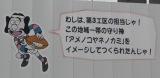

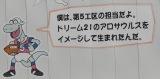
(2009年6月17日撮影)
2~5区のキャラクター。それぞれの工区の仕切に描かれている。この工事の行われている地区に由来するキャラクターで,一人称も使い分けられているようにキャラ設定もなされている。1区のキャラクターは,最初の写真に描かれているが,吹きだしの空欄には名前が入りそうだ。書かれていないのは公募中なのだろうか。
いずれにせよ,メインの工事以外にも時間と費用が投資されていそうだ。
仕切には工事やキャラクターの紹介の他にも・・・

(2009年6月17日撮影)
遺跡があった場所であることが示されたり・・・

(2009年6月17日撮影)
高架化,特に踏切がなくなることのすばらしさについて,色々な表現で紹介をしている。
そして,こんな表現も・・・

(2009年6月17日撮影)
高架化がいかに夢や希望にあふれたものだということが伝わってくる。
踏切がなくなる以外にも,高架下の空間が生まれ,別の用途に利用することができるし,駅の上下移動の回数が地下道や橋を使うよりも少なくなるなどの利点もある。
高架の存在が周囲の景観に与える影響などの問題点もないわけではないだろう。
この工事によって高架駅になる駅が3つある。それらの駅の高架化前の状況を以下で見ていきたい。
若江岩田駅

(2009年6月17日撮影)
工事が始まるまでは地下に改札のある駅だったが,工事の影響で片側のホームへは・・・

(2009年6月17日撮影)
仮駅舎の地上の改札から入るようになっている。
河内花園駅。

(2009年6月17日撮影)

(2009年6月17日撮影)
こちらもホームへは地下道を通るようになっている。

(2009年6月17日撮影)
現在のホームの後には高架橋ができている。
東花園駅。
線路の両側に駅舎がそれぞれある。

(2009年6月17日撮影)

(2009年6月17日撮影)
両方の駅舎と,その間の2つのホームは・・・

(2009年6月17日撮影)
3つの踏切でつながっている。駅郊外の隣接する踏切とは違い,電車の来る部分のみが細切れに遮断機が下りていた。上下移動がほとんどないのは楽だが,早めに駅に来ないと乗り遅れてしまうこともありそうだ。

(2009年6月17日撮影)
今の駅舎の上を高架が走っている。
工事自体はだいぶ進行していそうな印象だった。
仕切に描かれた夢の世界が実現するのもそう遠くはなさそうだ。
同じような工事現場はいくつか見たことがあるが,ここまで工事の内容のアピールに力を入れているのは初めてだった。



















































































































































