
中国では1月25日より上映が開始された、李連杰の最新作『霍元甲』。この作品は李連杰の自ら出演する最後のアクション映画になるだろうと噂され、日本でも俳優・中村獅童との共演が注目されている。
私は日本での公開を前に昨日2月7日の夜にこの映画を観に行って来た。場所はいつも映画を観に行く、広州天河城の正佳広場の中に在る飛揚影場。この映画館は新しくて豪華なソファーシートのゲストルームで映画が堪能でき、ゆったりと映画を楽しみたい人には打って付けの映画館なので、私も兼ねてから会員カードを作って、去年から『七剣』、『無極』など観たい映画がある度に足を運んでるのだ。
今回、観た『霍元甲』は最近観た中国映画の中でも群を抜いて、内容の有る作品だったと思う。
李連杰が演じる霍元甲は天津人で1869~1909年まで生きた武術の達人であり、上海に精武体操会を築き、多くの人々に慕われた人物である。彼は42歳にして持病の喀血病が悪化し死亡してしまったが、彼の武勇伝や彼の弟子たちをモチーフにした映画やドラマは数多く製作され李小龍や李連傑、ドニー・イェンなどが主演した『精武門』シリーズでは、霍元甲の弟子である陳真が日本人に毒殺された師匠の敵討ちをする作品がある。しかし、この最新作『霍元甲』を観ると霍元甲は仇打ちなんて望んでいなかったのではと感じてしまう。
以下の内容には管理人の個人的な観点やネタばれが含まれます
私がこの作品を観て感じ取った事。それは、他人を尊重すると言う事だ。ここでは、映画の見所を紹介してみたいと思う。
少年時代の元甲
このストーリーでは、霍元甲の少年時代から42歳で毒殺されるまでの成長を描いている。少年時代の元甲は肺の弱い(喘息・喀血病)、体の弱い少年だった。(良い所の坊ちゃん風で、少年元甲を演じる子役が超可愛いです。)
 大人になるのが楽しみですね。剣指の型もバッチリきまってますね。
大人になるのが楽しみですね。剣指の型もバッチリきまってますね。
体が弱い元甲少年。それ故、彼の父・霍家拳の師匠でもある恩第(邹兆龍)は全く武術を教えてはくれず、毎日、元甲に字の練習をするように命じるが、武術を身に付けて強くなりたい一心の元甲少年は、親友の農劲蓀に字の練習をさせて、自分はコッソリ武術の練習をする。しかし、父の恩第はただ字の練習をさせていた訳では無く、字の練習に使ってた本には人としての道理が書かれた本なのだが、父は人としての道理を学ばせてから武術を教えるつもりだったらしい。そんな時、父が趙家拳の趙中強と決闘する事になりますが、圧倒的優勢にも関わらず、決めてとなる一撃を寸止めした為に趙の一撃を受け、番付台から落っこちてしまいます。その試合で負けた父親に腹を立て、趙家の息子に決闘を挑みますが、武術の基礎が無い元甲はボコボコに…!そこで、復讐心が芽生え根性が捻くれてしまった元甲少年…。

傲慢な青年時代

趙家拳との試合で父が負け、自分もボコボコにされた一件以来、復讐心に燃えた元甲は武術の稽古に励み、持病の喘息も克服し、天津でも指折りの武術家に成長!しかし、青年時代の元甲はかなり調子こいてて、何か鼻につく奴である一方、大事な一人娘・翠児(ツイアル)をちやほやする親ばかな一面も持ってる。(自分の娘もあれぐらいチヤホヤしているのだろうか?)
少年時代、強さばかりを求める元甲に対し元甲の母は『恐れられる事と人から尊敬される事とは違う』と教えますが、父の言いつけを守らなかったばっかりに、成長して武術の達人となった元甲は道理を弁えない、他人を尊重する事を知らない人間になってしまい天津第一(津門第一)の座を掴む為に何人もの武術者達をぶちのめして行く。
そんな元甲は試合に勝つ度、親友の農が開いた沽月楼で祝杯を挙げ、その強さに引かれた者達がどんどん入門するが、完璧に自惚れた元甲は人を見る目がが無い為に役立たずのゴロツキ紛いの弟子までも沢山入門させてしまう。その弟子達の飲み代がかさんで多額の借金を背負った上に、とうとう家の蓄えもなくしてしまうのでした。
そんな、元甲に親友の農は何度も忠告を重るが、元甲は聞く耳を持とうとはしない。この頃の彼の道理は強い事こそが正しい事だと言う考えで、全く持って、懲りない性格なのだ。(なお、JET LIの映画『精武英雄』では元甲の死後、精武門を仕切る人物として描かれており、日本人に強い敵対心を持っている)
沽月楼の死闘

そんな中、事件が起きる。元甲の弟子がライバルの武術家・秦に痛めつけられたのだ。それを知った元甲は激怒し、秦の誕生会の席にわざと居座り酒を呑み続け嫌がらせを決行!秦の弟子が誕生会の為、沽月楼の席は貸切っているので他所に行ってくれと頼むが、怒り絶頂の彼は聞く耳を持たない。
秦に復讐するまで帰る気なんて毛頭ないのだ。農の忠告を無視し、秦と刀で斬り合い、死闘の末に元甲は秦を殺してしまう。
この戦いの様子はかつての『黄飛鴻』シリーズなども彷彿とさせる戦いぶりだ。打ち付ける刀からは火花がが飛び散り、『臥虎蔵龍』(グリーンディステニー)の酒楼での戦い如く、店の二階の吹き抜け部分を飛び回るのだ。
秦を倒したのは胸に打ち込んだ渾身の一撃だ。
その一撃を受けた秦は(恐らく肋骨が折れて心臓や肺に突き刺さって)翌日には死んでしまうのだった。この一撃は後の彼の人生を左右する一撃となる。
死闘を終えた元甲は弟子たちと祝杯を挙げるも、翌日、彼を待っていたのは秦が死んでしまったと言う悪い知らせだった。傷心の元甲が家に戻ると、皮肉な事に彼の愛する母親と娘が何者かの手によって惨殺されており、怒り狂った元甲は秦の弟子の仕業に違いないと刀を持って、秦の家に殴りこむ。
秦の弟子は母親と娘を殺した事を認め死を以って償うが、元甲は怯えた秦の妻子の様子を見て殺す事が出来ずに去って行く。
悲劇はそこで終らない。泣きっ面に蜂である。元甲に追い討ちをかけるかの様に、元甲の弟子が秦に殴られたのは秦の妾と浮気した事がばれて制裁を受けたと言う事実。傷心の元甲はその後、失踪。

放浪・農村で隠遁

心に深い傷を負った元甲は、当ての無い放浪の旅に出た。
服はボロボロ、鬚はモジャモジャ、髪の毛には白髪が混ざり、もう乞食も真っ青な汚さ!見るからに凄く臭そう。
きっと、生ゴミや何日も洗ってない靴下みたいな臭いがする元甲がたどり着いたのは美しい河が流れる山間部の村。(あんなに汚い李連杰は観た事ない。)
河で溺れた元甲を助けたのは村のお婆さんと盲目の美少女・月慈(ユエツー)だった。月慈は13歳頃から段々目が見えなくなり、ついには盲目になってしまったが、その眼は大きく美しい。料理を作ったり、田植えをしたりと、とても器量良い娘だ。彼女はよそ者の元甲を恐れず、献身的に看病し、河で頭を洗ったりと好意的に接し、元甲も段々と心を開いていく。
よく寝る元甲は村人たちから阿牛(牛さん)
 の愛称をつけられ、一緒に田植えをしたりしながら村の生活に馴染んで行くのだった。
の愛称をつけられ、一緒に田植えをしたりしながら村の生活に馴染んで行くのだった。

負けず嫌いな元甲は田植えの際に他の村人に負けじと速く苗え植えるも、苗と苗の間隔がグチャグチャで、植え直しを命じられる。

そんな折、月慈が『苗は生き物なのだから間隔を空けないと成長の邪魔になるのよ。それは、人間で言えば互いに尊重し合う事』だと言う。
その言葉に我にかえり、悟りの境地を拓いた彼は人間として大きな成長を遂げ、捻くれていた性格が一気に戻り以前よりもずっと思いやりのある人間になった。
そうして、何年かの後、元甲と月慈は互いに好意を抱きながらも、元甲は一度故郷に帰って家族の墓参りに行く事を決める。
また戻って来ると月慈に約束をして、何度も村の方を何度も振り返りながら、去って行くのだった。
帰郷と挑戦状
…とまあ、この辺までは元甲が如何にして他人を尊重できる人物になったかを語る前置き部分。あんな山奥からちゃんと天津に帰って来た元甲は家族の墓参りに行き、家に帰ると家財道具は借金のかたに取られ、残っているのは仏壇だけ。自分の誤りに気付き、慈悲の心をもった元甲の性格は人が変ったかの様に温厚でその眼光は穏やかだ。
そして白髪が混ざった辮髪姿は、非常に中年男性特有の渋みや燻し銀な雰囲気をかもし出している。今から100年近く前の中国。いくら漢方医学が素晴らしいと言っても、栄養状態や衛生状態等から考えても、昔の日本人同様に中国人の寿命も今よりずっと短かった事でしょう。日本の江戸時代の平均寿命が30代だった事を考えると、42歳という年齢ならば、早い人は天寿を真っ当していても可笑しくない年だったとも考えられる。(鄭州大学第二付属病院のレポートでは1901~1910年の中国人の平均寿命は44歳とある。)
何故なら、李小龍の映画だったか、李連杰の映画だったかで『精武門』で元甲が殺された際には、『先生も年だったからな』と言った一言が有った様な気が…。今なら42歳なんてそんなに、年と言われる程の年ではない。
さて、天津に戻り大力士を倒した後の元甲は上海に精武体操会と言う会を設し、三育(育徳、育体、育智)を目的として人材の育成に励む。しかし、打倒中国を目指す日本は、列強の各国の力を借り、日本最強の武道家・田中安野(中村獅童)を携えて、元甲に四対一の試合を申し込むのだ。流石に武道家・田中は武道の精神をちゃんと弁えた正々堂々とした武士道精神をもった素晴らしい人として演出されている。この辺は、日本人でも高尚な精神を持った人物はちゃんといて、日本人=全員悪者と言う映画のストーリーでなかったのが嬉しかった。何故なら多くの『精武門』関係の映画は日本人=悪者(陳真の恋人・山田光子は除く)と言う形が基本であり、勧善懲悪的なストーリーばかりだ。しかし、今回の『霍元甲』では、勧善懲悪を目的にしているのでは無く、己に克つといった克己の精神が描かれている。克己とは、「己に克つ事。意志の力で自分の衝動、欲望、感情を抑えること。」(広辞苑)だ。相手を尊重すると言う事は、様々な自己中心的な感情を抑え、相手の気持ちや立場になって物事を考える事だと、私は思っている。
確かに四対一の試合は不公平だと思うが、元甲は『生きて行く上で全ての事が公平だなんて事は有り得ない事だ。』と述べている。不公平な試合と知りながらも、挑戦を受けるのは、この挑戦を受けなければ中国の東亜病夫(アジアの臆病者)の汚名返上を心に決めているからだったのだろう。
田中安野との語らい
試合を前に、元甲は田中からお茶に誘われる。元甲は敢えて田中の招待に預かるが、別に田中は毒を盛ってやろうとか、そんな悪巧みはしていない。純粋にお茶に誘って、茶飲み話でもするつもりだったのだ。この時点で田中はこの対戦が四対一の戦いになるとは知らされていないので、対戦相手の人となり(為人)を観るつもりだったのではないかと思われる。
お茶に誘った田中は元甲に対して“茶葉の品質”ついて語る。彼の用意した茶葉は高級な茶葉だが、元甲は茶葉に例えて人の優劣について語るのだ。『茶は自然に生えている場合には、優劣はない。茶の品質と言うのは茶自身がそう言っている訳ではなく、優劣を決めるのは人間だ。人間も同じ様に自然に生きている状態では優劣はない。人の強弱を決めるのも人間だ。茶は品質を楽しむのでは無く、気分で楽しむ物だ。一人、一人の選択は違うものだ。』と語った。この、言葉に感銘を受けた田中はお茶で友情を深め様と語る。悪い日本人の企みで、元甲が毒殺されなければ、二人は良い友人になりえたのではと感じる。この時の中村獅童は中国語の吹き替えが入っていた為、流暢に中国語を話していた(笑)。
四対一の戦いと毒殺
1910年の上海・亞波羅影戲院(アポロ・シアター)、ここで元甲は四対一の挑戦をうける。この戦いには裏が有った。元甲のお茶の毒を盛ると言う作戦だ。これを飲んだ元甲は田中との対戦中に血を吐く(吐血?)!その血は如何にも毒を飲んだ様にどす黒く、ココアとコーヒーを混ぜたような気持ちの悪い血だ。もし、喀血なら肺から出血するので、鮮血だが、毒を飲んだ為に胃から出血した場合は胃酸の効果で血はどす黒く変色する。(余談だが私は血を吐いた経験がある。)私が血を吐いたのは、モヤモヤ病の手術後病院で飲んでいた鎮痛剤で胃がやられたせいだが、その時の血の色は元甲が毒を飲んだ後に吐いた血の色と同じだった。
しかし、ここでは元甲の毒殺について考えるが、元甲の毒殺説は嘘なのだ。元甲は幼少の頃より肺を患っており、その病状が悪化して亡くなったのが事実だ。肺を患った原因は幼少の頃に気功の練習でその呼吸法をやりすぎた為に肺を痛めてしまったのだ。そして、喀血の為に顔色が青ざめて、黄色かった為『黄面虎』と呼ばれており、恐らく顔が黄色い時点で病状は着々と進行していたと思われる。
武術の腕を見込まれて、1909年の3月に弟子の劉振声と上海の外国人租界地にやって来ますが、病状が悪化して半年後には亡くなってしまったのが事実である。毒殺されたと言うのは、後に出版された武侠小説『近代侠義英雄傳』や『大力士霍元甲傳』の影響で日本人に毒殺されたというストーリーに変えた為、それが一人歩きして映画、ドラマの影響で広まってしまったのだ。

霍元甲最期の一撃

元甲の死の真相はこんな所だが、話は映画に戻って元甲は自分が毒を飲んで助からない事を悟りながらも全力で戦う事を心に決め、血を吐きながら田中との戦いを続ける。もう幾らの力も無く、元甲は隙をついて渾身の一撃を田中の胸めがけて放つ。しかし、走馬灯の様に昔、ライバルの秦に打ち込んだ、あの一撃が頭に浮かび、昔、父が一撃を繰り出さなかった時のように寸止めをし倒れる込む。
田中に勝利を宣言させ様とするレフリーに田中は『ちょっと待てー!!!!』と叫び倒れた元甲を起して、元甲の腕を高々と挙げ彼の勝利を宣言するのであった。
死を目前にした元甲は弟子や仲間達に囲まれ、その魂は高く、高く上り、あの懐かしい農村の月滋の元へ帰って行く。満天の星空の下、白く輝く元甲が武術の型を演じる姿はとても幻想的だ。
何故、元甲が最期一撃を打ち込まなかったのか。打ち込めば田中は確実に死んでいたと思われる。しかし、元甲は田中に対して敬意を示し、武道家として高く評価していたからこそ、そんな彼の命を死に行く自分が無碍に奪ってはいけないと感じ、敢えて自分の死に際して最期の一撃を打ち込まず、相手の命を尊重したのではないだろうか。











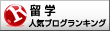




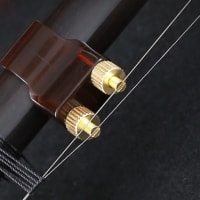




























まだ観ていないのでお書きになられた記事を拝見していませんが、
私もかなりこの作品に期待しています。
確かに近年の中国映画の中ではもっともテーマ性がある一本かもしれませんね。
李連傑の最後のアクション作品になるやもしれない作品だけあって、
彼が現代社会に生きる人たちへ伝えたかった事が全部凝縮されていそう。
公開が楽しみだな~
もう霍元甲見てこられたんですね!!う、羨ましい・・・。
ジェット・リーに限らず武術映画は大好きなのですがこういった英雄と周りに生きる人を扱う作品は特に!!かなり期待して日本での公開を待ってます^^
もちろん映画は未見なので、記事は薄目を開けて(笑)写真だけ拝見いたしました。
映画を観てから改めて、じっくり読ませていただきます。
連杰はこの映画を通して、今の若い人たちにたくさん伝えたいことがあったようです。
それで少し「説教くさい」なんていう感想を言う人もいると聞きましたが、迷の私としましては、連杰の説教を存分に心して聞きたい!
管理人様の「最近観た中国映画の中でも群を抜いて、内容の有る作品だったと思う。」とのお言葉を拝見して、とても嬉しかったです♪私も早く見たい!!
初めて書き込みをさせていただきます。
私も霍元甲を拝見しました。
やはり最後の2人のシーンには感動しました。
トドメをささなかったのは、大人になったのでしょうね。
私は、上のシーンとお墓のシーンが印象に残っています。
お墓で詫びたシーンと最後のシーンに繋がりがあるんでしょうね。
最期の一撃についてですが、あれを入れてれば田中を倒せたか…?というのは問題ではないと思います。
映画の中でも言ってましたが、武術をやる本当の目的は相手を倒すのではなく、自分自身に打ち勝つ事…まさにそれだと思います。
試合では負けても自分に勝てばそれが強さの証明である事をユアンジャは理解していたのでしょう。
そしてそれを受けた田中は、相手が武術家として自分よりも勝っていると察知して負けを認めたのだと思います。
彼が実在したのかに興味がありまして(^^;
わたしが大好きな作品の一つを紹介していただき感謝m(__)m