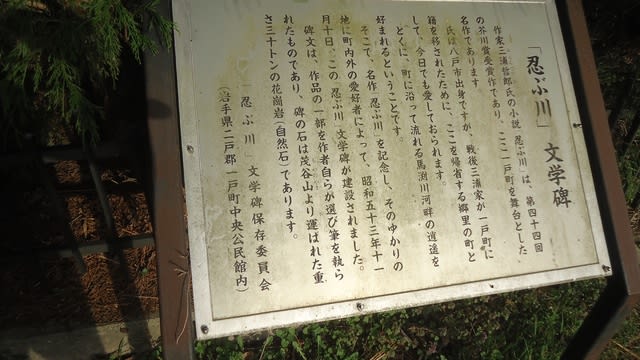藤沢周平作品より
藤沢作品には断念のあとの後悔、悔悟が描かれている。それが読む者の胸を打ち、思わず落涙することが多い。「作者の中には人間を視る目の暖かさ、深さが存在する。悲運に泣く者、その誠実さゆえに悲運に見舞われる者などが描かれる。
さまざまな人が読後感を評している。
「一話一話が二重にも三重にも趣向を凝らした、厚みのある短編だ。そして場景描写が的確である」
「暗い情念にあふれた小説だ」
「ひたひたと小さな波が打ち寄せるように、心を満たしてくれる」
「男と女の哀切な関係が描かれる」
「長い間せき止められていたものが、いっぺんに胸に溢れるのを感じる」
「人肌の温もりがある作品群」
「自然描写がたいへん美しい。そして、その美しさは、何かしら我々を望郷の想いに誘う」
「憂いを帯びた風景が過去の記憶と結びついている」
「端正な文体、悲劇的な美しさをもつ自然描写」
「日本人の心の裡にある自然の形を描いている」
「藤沢作品の魅力は、自分もそこにいる臨場感があることだ」
「藤沢作品は、人が人に抱く共感、同苦の感情によって、生き死にする瞬間が、小説のクライマックスになっている」
藤沢作品には断念のあとの後悔、悔悟が描かれている。それが読む者の胸を打ち、思わず落涙することが多い。「作者の中には人間を視る目の暖かさ、深さが存在する。悲運に泣く者、その誠実さゆえに悲運に見舞われる者などが描かれる。
さまざまな人が読後感を評している。
「一話一話が二重にも三重にも趣向を凝らした、厚みのある短編だ。そして場景描写が的確である」
「暗い情念にあふれた小説だ」
「ひたひたと小さな波が打ち寄せるように、心を満たしてくれる」
「男と女の哀切な関係が描かれる」
「長い間せき止められていたものが、いっぺんに胸に溢れるのを感じる」
「人肌の温もりがある作品群」
「自然描写がたいへん美しい。そして、その美しさは、何かしら我々を望郷の想いに誘う」
「憂いを帯びた風景が過去の記憶と結びついている」
「端正な文体、悲劇的な美しさをもつ自然描写」
「日本人の心の裡にある自然の形を描いている」
「藤沢作品の魅力は、自分もそこにいる臨場感があることだ」
「藤沢作品は、人が人に抱く共感、同苦の感情によって、生き死にする瞬間が、小説のクライマックスになっている」