前々回の記事でお伝えした軍艦島の蒟蒻煉瓦。
記事の最後でお約束した様に、ちゃんと見て来ました。
今回はそのリポートです。

これが軍艦島に残る蒟蒻煉瓦壁面の全貌です。
こうして見ると、前々回の記事でアップした、
たまたま写っていたレンガの部分が大半だったことが分かりますが、
左側は柱状の構造となっているのが分かります。
そして中央が窪んで少し面積の広い壁面、
右上には前々回の記事でも写っていた、
崩れ気味のレンガが少々あり、
更に右上に、左と同様の柱状の積み上げが少しあります。

ちなみに厚さを計ってみると、角の欠けを考慮しても、
4cm前後で、明らかに蒟蒻煉瓦だということが分かります。
また、右上の一部崩れかけのレンガの部分だけ、
おそらく天川によるつなぎが施されている様に見えます。
果たしてこの蒟蒻煉瓦が何ためのものだったのかは、今はわかりませんが、
世界遺産の認定を控え、今後の調査で明らかになっていくのかも知れません。
ちなみにこの蒟蒻煉瓦がある付近は、島の元来の岩礁の北部付近にあたり、
明治の初期に、早くから開発が始まっていた地域です。
と考えると、付近には他にも蒟蒻煉瓦が残っていてもおかしくありません。

蒟蒻煉瓦の付近を見回すと、
ありましたありました。65号棟と山道を繋ぐ空中廊下の下に、
壁面にへばりつくレンガがあります。

しかし、近づいてレンガの厚さを測ってみると、
5.5cm前後の、いわゆる豆腐煉瓦です。
下から見上げたので、厚みが圧縮され、
薄い煉瓦に見えたのですね。

豆腐煉瓦がへばりついた壁面を住宅棟側へ降りると、
五十段と呼ばれる一直線の階段のふもとへ辿り着きます。
そしてこの麓にも、以前から気になっていた煉瓦があります。
1つ前の煉瓦は鮮やかな赤色ですが、
この煉瓦は少しくすんでオレンジ色がかっています。
蒟蒻煉瓦は豆腐煉瓦より若干オレンジ色寄りなのも特徴の1つです。

円形状に並べられた煉瓦の一部と想われる遺構です。
その色や形、更には煉瓦の劣化具合から、
かなり古い時代のものであることは間違いなさそうです。
円形の外側の部分は、
画像からも分かる様にコンクリートで固められていますが、
内側の部分は土だったので、試しに掘ってみることにしました。

するとかろうじて一枚分の厚さが測れるだけ、
土を掘り起こすことができました。
早速煉瓦の厚みを測ってみると、
何と!3.8cmないし4.0cmです。
これはまぎれもない蒟蒻煉瓦ですね!
こんな所にも蒟蒻煉瓦が眠っていたんですね!
その後、島の長老で拙軍艦島の関連書籍に関しても、
いつもご意見を頂く加地氏にうかがったところ、
おそらく第一竪坑の排気竪坑の跡ではないか、
ということでした。
明治初期の頃の竪坑は、通常同じ場所に2つの穴を掘り、
一方を入気、もう片方を排気として使うのが通例で、
軍艦島の第一竪坑も当初はその作りだったのが、
三菱の操業下になって、排気竪坑を別に作った名残ではないか、
とのことでした。
しかし、三菱が本格的に操業を開始するのは明治23年のこと、
一方、蒟蒻煉瓦は、一応明治16年のド・ロ神父の救助院を最後に、
この世から姿を消すことになっています。
となると蒟蒻煉瓦で作られたこの遺構は、
明治16年以前のものということになり、
三菱操業下以前のものということになります。
謎は深まるばかりですが、
こちらも、おそらく世界遺産へむけて、
いずれは発掘調査が行なわれるものと想います。
ヴェールに包まれていたプレ三菱時代の軍艦島の姿が明らかになるのも、
そう遠くないことなのかもしれません。
◆追記 2014.05.16◆
その後、この記事にもコメントを頂いている超問さんから、
第一竪坑に付随する捲座の動力用ボイラーの煙突の基礎ではないか、
とのご意見をうかがいました。
しかし、
第一竪坑が開削されたのは明治19年と言われているので、
もしこの円形煉瓦施設が明治19年のものだとすれば、
一般的に明治16年で終わったとされる蒟蒻煉瓦の歴史を、
塗り替えることにもなります。
いずれにしても、この蒟蒻煉瓦の存在は、
軍艦島に新しい歴史の1ページを加えるものであることには
違いなさそうです。
◆シリーズ:あまり知られていない軍艦島 INDEX◆
記事の最後でお約束した様に、ちゃんと見て来ました。
今回はそのリポートです。

これが軍艦島に残る蒟蒻煉瓦壁面の全貌です。
こうして見ると、前々回の記事でアップした、
たまたま写っていたレンガの部分が大半だったことが分かりますが、
左側は柱状の構造となっているのが分かります。
そして中央が窪んで少し面積の広い壁面、
右上には前々回の記事でも写っていた、
崩れ気味のレンガが少々あり、
更に右上に、左と同様の柱状の積み上げが少しあります。

ちなみに厚さを計ってみると、角の欠けを考慮しても、
4cm前後で、明らかに蒟蒻煉瓦だということが分かります。
また、右上の一部崩れかけのレンガの部分だけ、
おそらく天川によるつなぎが施されている様に見えます。
果たしてこの蒟蒻煉瓦が何ためのものだったのかは、今はわかりませんが、
世界遺産の認定を控え、今後の調査で明らかになっていくのかも知れません。
ちなみにこの蒟蒻煉瓦がある付近は、島の元来の岩礁の北部付近にあたり、
明治の初期に、早くから開発が始まっていた地域です。
と考えると、付近には他にも蒟蒻煉瓦が残っていてもおかしくありません。

蒟蒻煉瓦の付近を見回すと、
ありましたありました。65号棟と山道を繋ぐ空中廊下の下に、
壁面にへばりつくレンガがあります。

しかし、近づいてレンガの厚さを測ってみると、
5.5cm前後の、いわゆる豆腐煉瓦です。
下から見上げたので、厚みが圧縮され、
薄い煉瓦に見えたのですね。

豆腐煉瓦がへばりついた壁面を住宅棟側へ降りると、
五十段と呼ばれる一直線の階段のふもとへ辿り着きます。
そしてこの麓にも、以前から気になっていた煉瓦があります。
1つ前の煉瓦は鮮やかな赤色ですが、
この煉瓦は少しくすんでオレンジ色がかっています。
蒟蒻煉瓦は豆腐煉瓦より若干オレンジ色寄りなのも特徴の1つです。

円形状に並べられた煉瓦の一部と想われる遺構です。
その色や形、更には煉瓦の劣化具合から、
かなり古い時代のものであることは間違いなさそうです。
円形の外側の部分は、
画像からも分かる様にコンクリートで固められていますが、
内側の部分は土だったので、試しに掘ってみることにしました。

するとかろうじて一枚分の厚さが測れるだけ、
土を掘り起こすことができました。
早速煉瓦の厚みを測ってみると、
何と!3.8cmないし4.0cmです。
これはまぎれもない蒟蒻煉瓦ですね!
こんな所にも蒟蒻煉瓦が眠っていたんですね!
その後、島の長老で拙軍艦島の関連書籍に関しても、
いつもご意見を頂く加地氏にうかがったところ、
おそらく第一竪坑の排気竪坑の跡ではないか、
ということでした。
明治初期の頃の竪坑は、通常同じ場所に2つの穴を掘り、
一方を入気、もう片方を排気として使うのが通例で、
軍艦島の第一竪坑も当初はその作りだったのが、
三菱の操業下になって、排気竪坑を別に作った名残ではないか、
とのことでした。
しかし、三菱が本格的に操業を開始するのは明治23年のこと、
一方、蒟蒻煉瓦は、一応明治16年のド・ロ神父の救助院を最後に、
この世から姿を消すことになっています。
となると蒟蒻煉瓦で作られたこの遺構は、
明治16年以前のものということになり、
三菱操業下以前のものということになります。
謎は深まるばかりですが、
こちらも、おそらく世界遺産へむけて、
いずれは発掘調査が行なわれるものと想います。
ヴェールに包まれていたプレ三菱時代の軍艦島の姿が明らかになるのも、
そう遠くないことなのかもしれません。
◆追記 2014.05.16◆
その後、この記事にもコメントを頂いている超問さんから、
第一竪坑に付随する捲座の動力用ボイラーの煙突の基礎ではないか、
とのご意見をうかがいました。
しかし、
第一竪坑が開削されたのは明治19年と言われているので、
もしこの円形煉瓦施設が明治19年のものだとすれば、
一般的に明治16年で終わったとされる蒟蒻煉瓦の歴史を、
塗り替えることにもなります。
いずれにしても、この蒟蒻煉瓦の存在は、
軍艦島に新しい歴史の1ページを加えるものであることには
違いなさそうです。
◆シリーズ:あまり知られていない軍艦島 INDEX◆













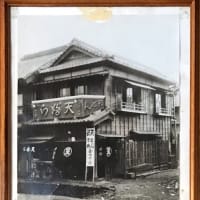




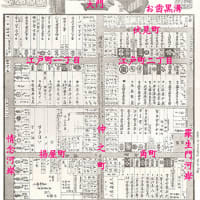
黒澤さんの行動力は、本当に羨ましい限りで、感服いた
します。
プレ三菱時代の端島の姿が、一日も早く明らかになれ
ばと願います。
すこしずつ知られざる端島が明らかになって行くのは、
楽しくもあり興味の尽きないところでもありますね。
今後共ご指導、よろしくお願いいたします!