拙ブログの軍艦島カテゴリーは、
いつのまにか軍艦島関連の情報ページになってしまいましたが、
ブログを始めた当初は『知られざる軍艦島』シリーズとして、
あまり知られていない軍艦島の情報をアップしていました。
そして今回、久しぶりの「知られざる軍艦島」です。
軍艦島が、現在、
2015年の世界遺産に推薦されているのはご存知の方も多いと想いますが、
島全体が世界遺産の対象になっているわけではありません。
軍艦島の最も軍艦島らしい住宅棟群は、大正時代からの建設なので、
「明治日本の産業革命遺産」というお題目にはそぐわなからです。
では、軍艦島に明治のものってあるの?
ということになるわけですが、

画像は観光上陸の際に、
船着場から島内へ入る時に見ることのできる、
城壁のようにも見える石積みの護岸です。
「天川(あまかわ)」と呼ばれる水に強いつなぎで天草石を積み上げた、
天川工法による石積みは、明治期に盛んに造られたものです。
この場所は石積みがそのまま残っているので分かり易いですが、
コンクリートで固められた軍艦島の堤防の殆どの箇所も、
その内側に、同様の石積みが眠っています。

画像は第三見学所から見える31号棟の、
見学所とは反対側の出入口付近ですが、
かつては、右上に見えるコンクリートの壁がもっと下まであり、
さらに下部は、コンクリで固められた地面の中でした。
しかし現在では地面と壁面が崩落し、
広範囲に渡って天川工法の石積みが露出しています。
コンクリートが瓦解してもなおしっかりと残る天川の護岸に、
明治期の土木技術の水準の高さがうかがえます。

また、画像は第二見学所の正面に見える煉瓦の壁です。
この壁は、付近にあった明治時代に造られた竪坑のための、
巻上機室の壁面の名残です。
一見、外壁の様にも見えますが、
現在見えている面は、建物の内壁にあたります。

そしてこの坑が上記の巻上機室とセットだった、
明治30年に開削された第三竪坑の穴の跡です。
これまで軍艦島に残る明治期のものといえば、
天川工法による石積み護岸と、
第三竪坑関連の遺構だけと想われていました。
しかし、最近個人的に、
実は他にも明治期と分かるものが残っているのではないか、
と漠然と想っていました。
◆

先日、上陸する機会があり、鉱業所へ足を踏み入れると、
以前は鬱蒼と茂っていた深い木々が、
世界遺産の調査のためにあらかた伐採され、
歩き易くかつ見やすくなっていました。
画像は、かつて軍艦島が軍艦の様に見える要因の1つだった、
ボイラーの高い煙突の基礎部分です。
以前は枝の硬い木々に覆い尽くされ、
近づくのも容易ではありませんでしたが、
ご覧の様にその姿を確認出来る程になっています。
しかし、
この施設をお伝えするために、この画像をアップしたわけではありません。
ファインダーをのぞいたときたまたま左にも煉瓦が見えたので、
とりあえずそれも入れ込んで撮影し、
あとで拡大しながらチェックしてみると、
画像の左端に写っている煉瓦は

蒟蒻煉瓦ではないですか──(≧∇≦)──
まさか、軍艦島に蒟蒻煉瓦が残っていたとは!
蒟蒻煉瓦に関しては以前の記事でも触れていますが、
幕末から明治初期にかけて長崎で造られた薄い煉瓦で、
その形状から蒟蒻煉瓦と呼ばれます。
蒟蒻煉瓦が最後に使われたのは、
明治16年のド・ロ様による出津救助院と言われているので、
すなわち、軍艦島に蒟蒻煉瓦があるということは、
明治16年以前に開発されていたという証拠です。
この記事の冒頭で触れた護岸と第三竪坑は、
いずれも明治23年以降の三菱の経営下になってからのものですが、
蒟蒻煉瓦の存在は、三菱以前の開発を裏付けるものとなります。
史実では残っているものの、
実際にはヴェールに包まれていた三菱以前の軍艦島を知る事ができる、
死ぬ程貴重な遺構だと想います。

画像は、軍艦島の隣の島の中ノ島に残る、
蒟蒻煉瓦で造られた壁面です。
中ノ島は軍艦島より早く開発された炭鉱の島で、
その規模は小さいながら、
岩礁の周囲を人工地盤で固めて建物を建設し、
竪坑も2本開削される等、
いわば軍艦島の雛形とでもいうべき島です。
軍艦島の蒟蒻煉瓦も壁面状に造られていることから、
おそらく、中ノ島と同様な使われ方をしていたのではないでしょうか。
残念ながら今回撮影した軍艦島の蒟蒻煉瓦の壁面は、
たまたまのこの1枚だけだったので、
次回上陸したら、しっかりと撮影して来たいと想います。
◆シリーズ:あまり知られていない軍艦島 INDEX◆
いつのまにか軍艦島関連の情報ページになってしまいましたが、
ブログを始めた当初は『知られざる軍艦島』シリーズとして、
あまり知られていない軍艦島の情報をアップしていました。
そして今回、久しぶりの「知られざる軍艦島」です。
軍艦島が、現在、
2015年の世界遺産に推薦されているのはご存知の方も多いと想いますが、
島全体が世界遺産の対象になっているわけではありません。
軍艦島の最も軍艦島らしい住宅棟群は、大正時代からの建設なので、
「明治日本の産業革命遺産」というお題目にはそぐわなからです。
では、軍艦島に明治のものってあるの?
ということになるわけですが、

画像は観光上陸の際に、
船着場から島内へ入る時に見ることのできる、
城壁のようにも見える石積みの護岸です。
「天川(あまかわ)」と呼ばれる水に強いつなぎで天草石を積み上げた、
天川工法による石積みは、明治期に盛んに造られたものです。
この場所は石積みがそのまま残っているので分かり易いですが、
コンクリートで固められた軍艦島の堤防の殆どの箇所も、
その内側に、同様の石積みが眠っています。

画像は第三見学所から見える31号棟の、
見学所とは反対側の出入口付近ですが、
かつては、右上に見えるコンクリートの壁がもっと下まであり、
さらに下部は、コンクリで固められた地面の中でした。
しかし現在では地面と壁面が崩落し、
広範囲に渡って天川工法の石積みが露出しています。
コンクリートが瓦解してもなおしっかりと残る天川の護岸に、
明治期の土木技術の水準の高さがうかがえます。

また、画像は第二見学所の正面に見える煉瓦の壁です。
この壁は、付近にあった明治時代に造られた竪坑のための、
巻上機室の壁面の名残です。
一見、外壁の様にも見えますが、
現在見えている面は、建物の内壁にあたります。

そしてこの坑が上記の巻上機室とセットだった、
明治30年に開削された第三竪坑の穴の跡です。
これまで軍艦島に残る明治期のものといえば、
天川工法による石積み護岸と、
第三竪坑関連の遺構だけと想われていました。
しかし、最近個人的に、
実は他にも明治期と分かるものが残っているのではないか、
と漠然と想っていました。
◆

先日、上陸する機会があり、鉱業所へ足を踏み入れると、
以前は鬱蒼と茂っていた深い木々が、
世界遺産の調査のためにあらかた伐採され、
歩き易くかつ見やすくなっていました。
画像は、かつて軍艦島が軍艦の様に見える要因の1つだった、
ボイラーの高い煙突の基礎部分です。
以前は枝の硬い木々に覆い尽くされ、
近づくのも容易ではありませんでしたが、
ご覧の様にその姿を確認出来る程になっています。
しかし、
この施設をお伝えするために、この画像をアップしたわけではありません。
ファインダーをのぞいたときたまたま左にも煉瓦が見えたので、
とりあえずそれも入れ込んで撮影し、
あとで拡大しながらチェックしてみると、
画像の左端に写っている煉瓦は

蒟蒻煉瓦ではないですか──(≧∇≦)──
まさか、軍艦島に蒟蒻煉瓦が残っていたとは!
蒟蒻煉瓦に関しては以前の記事でも触れていますが、
幕末から明治初期にかけて長崎で造られた薄い煉瓦で、
その形状から蒟蒻煉瓦と呼ばれます。
蒟蒻煉瓦が最後に使われたのは、
明治16年のド・ロ様による出津救助院と言われているので、
すなわち、軍艦島に蒟蒻煉瓦があるということは、
明治16年以前に開発されていたという証拠です。
この記事の冒頭で触れた護岸と第三竪坑は、
いずれも明治23年以降の三菱の経営下になってからのものですが、
蒟蒻煉瓦の存在は、三菱以前の開発を裏付けるものとなります。
史実では残っているものの、
実際にはヴェールに包まれていた三菱以前の軍艦島を知る事ができる、
死ぬ程貴重な遺構だと想います。

画像は、軍艦島の隣の島の中ノ島に残る、
蒟蒻煉瓦で造られた壁面です。
中ノ島は軍艦島より早く開発された炭鉱の島で、
その規模は小さいながら、
岩礁の周囲を人工地盤で固めて建物を建設し、
竪坑も2本開削される等、
いわば軍艦島の雛形とでもいうべき島です。
軍艦島の蒟蒻煉瓦も壁面状に造られていることから、
おそらく、中ノ島と同様な使われ方をしていたのではないでしょうか。
残念ながら今回撮影した軍艦島の蒟蒻煉瓦の壁面は、
たまたまのこの1枚だけだったので、
次回上陸したら、しっかりと撮影して来たいと想います。
◆シリーズ:あまり知られていない軍艦島 INDEX◆













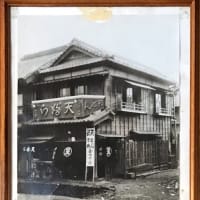




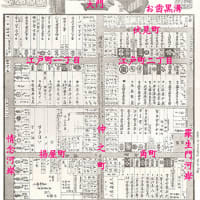
「ファインダーをのぞいたときたまたま左にも煉瓦が見えたので、とりあえずそれも入れ込んで撮影し、あとで拡大しながらチェックしてみると、画像の左端に写っている煉瓦は・・・」
羨ましい限りです。日頃の行いがよろしいのでしょうね。
これからもいろいろと教えてください。よろしくお願いします。
その場で拡大して確認すれば、すぐに蒟蒻煉瓦と分かった筈なので、
日頃の行いが悪いせいで、肝心なことを逃している証拠です(>_<)
精進いたします(笑)