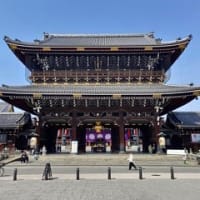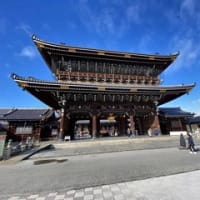今回は滋賀
MIHO MUSEUM
百の手すさび 近代の茶杓と数寄者往来
期間:10月20日(土)~12月2日(日)
前後期拝見しました。
茶杓 銘「川道㐂」千利休作
櫂先長く折撓、蟻腰の典型的な利休形の茶杓。
筒の「川道㐂」は京都の御粽司の初代・川端道喜のこと。また筒裏には「吹毛用了急須磨」と古渓宗陳が書いている。
解説には「利休の書体にはやや研究の余地を残す」とあり筒書には注意が必要だろう。
茶杓 銘「赤壁」千宗旦作
侘びた竹を用い櫂先は剣先、折撓。筒には「赤壁 不審」と宗旦が記す。
「赤壁」は中国の地名。三国志の時代「赤壁の戦い」や蘇軾が詠んだ「赤壁賦」で有名(ただし2つの場所は異なる)。宗旦は後者の意味で名付けたと思われる。
茶杓 銘「渋紙庵」小堀遠州作
露は兜巾形、折撓で節の上下に樋がある。節の上にシミが景色を成す。
「渋紙庵」とは茶人で伊達政宗の茶頭を務めた清水道閑のこと。小堀遠州から道閑に贈られた茶杓は他に数点が知られており、また手紙のやりとりも多い。伊達政宗に道閑を推挙したのも遠州である。
益田鈍翁旧蔵。
茶杓 銘「不鬼」江月宗玩作
上下片身替わりのシミ竹、丸撓の茶杓。
益田鈍翁旧蔵。
今回はなんと茶杓が100点以上も展示されている。大茶杓祭り!
ただやはり私としては近代より近世、戦国から江戸初期の茶杓がもっと見たい!!
まあ今回は近代数寄者がメインなのでしかたがありません。だから是非どこかでやってください!!!
最近の「探訪」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事