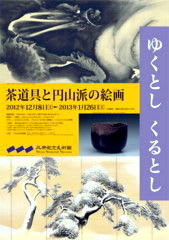三井記念美術館

「ゆくとし くるとし ―茶道具と円山派の絵画―」
期間:平成24年12月8日(土)~平成25年1月26日(土)
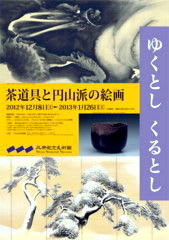 志野茶碗 銘 卯花墻
志野茶碗 銘 卯花墻
和物茶碗では光悦作の不二山と2つしかない国宝。美濃焼で作者は不明。「井」形の模様が卯の花の垣根に似ている事から銘は片桐石州が付けた。思っていたより大振りで結構ゆがんでいる。
黒楽茶碗 銘 雨雲 本阿弥光悦作
口縁と腰部の掛けはずしの景色が薄暗い雲のような見える。雨雲とはよく言ったものです。薄造りで光悦の一典型と呼べる茶碗ではないでしょうか。
赤楽茶碗 銘 鵺 道入作
のんこう七種のひとつ。赤楽の胴に黒いもやの様な部分があり、これを源頼政の鵺退治における鵺の出現する黒雲に見立てて命銘された。
粉引茶碗 銘 三好粉引
大名物。白化粧を施した上に透明釉を掛けた白茶碗で三好長慶が所持した。のちに豊臣秀吉の手に渡る。箱蓋書付は金森宗和筆。
大井戸茶碗 銘 十文字井戸
大徳寺の天祐紹杲により別銘「須弥」とも呼ばれる。古田織部が今より大きかったこの茶碗を気に入らず、十文字に割いて小さく縮めてしまった。織部独自の美学を表すエピソードです。
竹一重切花入 千少庵作
おだやかな人物であったとされる少庵らしい素朴な形の花入。
竹茶杓 歌銘 富士 織田有楽作
櫂先・露の左側がまるで刃のようで独特の存在感。茶人有楽ではなく武将有楽が顔を出したようで非常に興味深い。
なんと言っても国宝・卯花墻。志野はあまり好きではないのですが、これはてらてら感やユガミ具合が面白い。
しかし天才光悦と並ぶ国宝和物茶碗の作者が不詳なのは面白い対比ですねぇ。
十文字井戸は織部の破壊衝動がなんともはやで、有楽の茶杓は今までの有楽のイメージを覆しました(良い方に)。