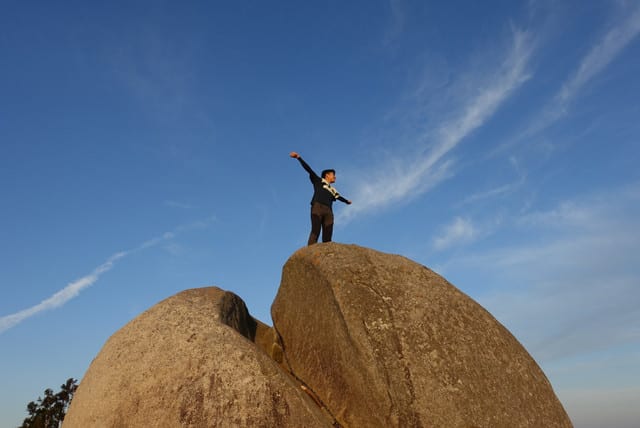記録者:齊藤(59期)
活動日時:2022年5月7~8日
どうも皆さんこんにちは。ワンゲル59期の齊藤です。
ワンゲルは1年半前に引退し、今年の春から九大の大学院に進学し、修士の一年です
まあ、引退…とはいっても、ちょくちょく一人だけ老害かまして活動に参加したり、後輩たちと結成したワンゲルトレラン部に所属して活動したりしているので、4つ下くらいまでなら結構知っている人もいるかもしれない。知ってる人、また山登ろうね!(^^)
さて、早速本題に入る。今回のブログの主題は、九大ワンゲルに代々受け継がれてきた「脊振山系全山縦走(2days)」の記録である。2020年のコロナ襲来によってしばらく活動ができずにいたため、引退後の2020年5月(当時、学部4年生)に挑戦することとなった。ずっと前から、書こう、書こう、とは思っていたものの、先延ばしにしていた。これから暇を見つけて書こうかなと思ってます。個人的には、記録係がブログを書くという文化をぜひ復活させてほしい、と思う。きっと後輩たちのためにもなるはずだ。
…話を戻しましょう。ちなみに、今回の脊振討伐では第18回目となった。
まず、この山域と縦走路についての説明を第15次隊の中島先輩の文から引用させてもらう。
--------------------------------
まずは脊振全山縦走とは何なのかを少しだけ説明する。「脊振」という響きは福岡県民や佐賀県民ならそれなりになじみがあるはず。脊振山系とは、福岡と佐賀の県境を東西50㎞にわたって走る山脈のことである。長野峠を境に西部と東部に分けられ、西部は登山者が少なく、踏み跡が不明瞭で荒れた道も多い。一方で東部は主峰・脊振山を始め、霊峰・雷山、花の都・井原山など人気の山が多く、よく整備された歩きやすいコースである。冬は日本海からの湿った季節風を一身に受け、福岡市や糸島市に雪を降らせる。脊振全山縦走はそんな脊振山地をまさしく東西に踏破する、歩行距離70㎞、累積標高6000mを優に超える山行なのである。
第15次脊振全山縦走 - 九州大学ワンダーフォーゲル部 (goo.ne.jp) より
(獲得標高に関しては、計測機器により異なり諸説。一般的には5600mほどの記載が多いよう)
----------------------------------
ワンゲラーたちは、代々この縦走にチャレンジしてきたらしく、途中の記録が曖昧な部分もあるが、57,58期の先輩方に託されたからやらないわけにはいかない(使命感)。いざ挑戦するとしても、間違いなく時期選びは大切である。どれも1000m以下の山ばかりであるので、勿論のこと日本アルプスの山脈のように涼しいなんてことは全くない。真夏には灼熱地獄と化すし、アブや蜂の襲撃を受けることになりかねない。あいつらの耳元での羽音は本当に煩わしくてキモイ。冬は当然寒いので、軽量化がカギとなるこの縦走において防寒着などの荷物が増えるのは好ましくない。つまり、日が短すぎず、かつ暑さが程よく荷物と体力と水分の消費が抑えられる「春」もしくは「秋」が適期だろう。夏合宿後で体力もついてる秋にするのもいいかもね~。今回はGWの土日を利用して挑戦した。メンバーは、何人かに声をかけてみたがそこまで乗り気では無さそうだったためソロだ。とは言っても、筆者は独り身に慣れているので、24時間近くの山行でお喋り相手がいないことなんて屁でもない。ソロなこともあって計画書はエスケープ先なども含めてきちんと作成した。
・・・それでは山行の記録に参る。

以下は持ち物だ。
ザック30L、シュラフ#3、ボトル、ポリタンク、ランシュー、帽子、ツェルト一式、グラウンドシート、銀マット、モバイルバッテリー、GoPro、エマージェンシーシート、芯抜きキジ紙、レインウェア上下、ガス缶110g、ガスヘッド、鍋、カトラリー、医療セット、緊急簡易トイレ、歯ブラシ、細引き、着替え、食糧(パン、うどん、おにぎり)、行動食(おにぎり、フルグラ、エネルギージェル、チョコレート)、非常食
軽量化のために、食糧のカロリーの大部分をフルグラにし、水は2日で4L(後述するが水は足りなかった)、2人用テントではなくツェルトとした。過去の記録では、雷山避難小屋や三瀬峠に前日のうちから荷揚げや、脊振山の自販機で飲料物の補給を行っていたが(1Dayソロトレランのセタさんは例外で(笑))、今回の目標は「単独・無補給」とした。なお、地図はGPS機能のあるスマートフォンアプリのYAMAPを使用した。
7:08 福吉駅を出発。たしか、この日は寝坊したので始発ではなかった気がする。


8:10 最初のピーク十坊山(とんぼやま)に到着。初見でこの特殊な名前読めた人いない説。途中で登りを飛ばしすぎて水を多く消費しすぎた。汗もびちゃびちゃ。反省しつつ先を急ぐ。

9:27 浮嶽に到着。補給食のフルグラがうますぎる!!!

9:55 浮嶽下り途中の展望岩的なところ。青空と新緑が鮮やかだ。

10:12 荒谷峠。写真は撮らずにスルー。
10:31 女岳着。この後、雷山方面へ向かうのだが、二丈岳へ進めば、周回型の縦走が楽しめる「糸島四座」のコンプリートとなる。特有の激しいアップダウンであるが、景色がいいし近場でよい練習になるため、休日にでも訪れてみてはどうだろうか。ただし、夏は暑い。冬は空気が澄んでいて海の沖の方まで臨むことができ、虫も少ないのでおすすめだ。

今のところ疲れも少なく快調である。
…と思ったのもつかの間、ここからが地獄だった。当時、すっかり冬は明けて春真っ只中である。暖かくなると活発になるのはなにも人間だけではない。この地域では、どうやら“蜘蛛”さんたちが多く生息しているらしく、まさにスパイダーネット地獄と化していたのだ(荒川峠⇄雷山間は特に人通りが少ないのもおそらく原因の一つ)。長い木の枝で前方を振り払いながら先を進む。腕がきつかった。それでも少なくとも100回以上は顔面に蜘蛛の巣をくらったのを覚えている。今回の縦走で一番嫌だったことだ。
道中でお会いした牛医のおじさま。どうやらコロナ時に新しい趣味として始めたらしい。とても足取りが軽い。ちなみにこの人は今でもYAMAPで繋がっている。

11:26 荒川峠。またも写真なし。
ふと足を止めた時の風景。春って新緑がとても綺麗で素敵だ。

13:12 眺望のない小さなピーク河童山に着。ご高齢の夫婦お二人に会い、激励の言葉をいただいた。先を急いではいるものの、話しかけられるのは嬉しいものだ。私もあのような老後人生を過ごしてみたい。

13:35 羽金山。珍しいことに電波基地の内部に山頂があるので、インターホンで中に入れてもらわなければならない。面倒ではあるが、整備されて綺麗だしせっかく全山縦走するなら行くことをおすすめする。ここで少し休憩。夏にみられるモクモクの雲が増えてきた。かなり暑さを感じる。行動食の炊き込みご飯おにぎりを食べた。

カメラのシャッターは半目の瞬間をとらえていた。おそらく暑い~っていう顔。

15:35 長野峠。やはり人通りが少ない区間は、荒れ気味で蜘蛛の巣も多い。ペースをあげられなかった。
16:28 我らがホームマウンテンの雷山に到着。10分休憩。蜘蛛の巣から解放された安堵感に浸りたいところだが、もうすでに16時半を回っており、幕営予定地は井原山を越えた先にある三瀬峠である。ゆっくりしたい気持ちを抑えて先を急ぐ。冨士山、本冨士山を通る井原山までの縦走路は、所々で小走りが出来ちゃうトレイルなので助かった。

ここから井原山までの道はとても歩きやすい。井原山は花の名峰と呼ばれるだけあって、どの季節にも美しい花を咲かせる。これはツツジ。

17:31 糸島ブルー。少しだけ休憩。相変わらずの眺望の良さで、とても好きな山の1つだ。

18:38 三瀬峠。本日のゴールだ。ぎりぎり日没あたりに到着できた。

上の写真の場所から登ってすぐのところに泊まる。1,2張はいける広さ。

今回持ってきたのはテントではなく簡易的なツェルトだ。無事YouTubeで勉強した通りに張れた。雨で浸水しない日、かつ寒すぎない時期だからこそ使えたが、テントの軽量化は個人的にかなりありがたい。サイズもぴったり、身長が低くて助かった。

↓↓↓ ツェルトの後方の細引きは木の幹に固定。

夕飯は僕の出身・熊本でなじみの深い五木のうどんだ(五木村がある)。小さいころ熱を出すとよくこれを食べていた時のことを思い出す。ちなみに、うどん出汁の美味しさもさることながら利便性も悪くないのでここでお勧めさせてもらう。一度茹でてあるので茹で時間はたしかほんの1分くらいでいいし、水量も他の麺類に比べてかなり少ない。常温保存での長期保存も可能なのだ。今回のように単体でも勿論おいしいが、ここにフリーズドライの牛丼や親子丼を乗せて肉うどんや親子うどんとして食べるのもめちゃくちゃウマい。これは筆者の極秘メニューであるため、情報拡散はお控え願う。


ちなみに今晩は貧相だ。普通に食事メニューみすった感があり、少し萎えた。
おやつを食べ、スマホの充電をしてから、この日は早めに寝た。
想像以上に暑かったためか、この時点で水は4Lのうち1.8Lほどまで減っていた。

4:30 暗闇の中にBTSのDynamiteのアラームが鳴り響く。昨年から僕もはまってよく聞いていたが、実家への帰省中に流していたのがきっかけで、今や筆者の母はジミン君の虜である。YouTubeをつけて鼻歌でメロディーを刻みながらノリノリで皿洗いをしているような具合である。このようにテンションの上がる曲をアラームにセットし、目が覚めてから一緒に歌いだすことで脳を起こすのが、筆者が普段より常用していた作戦である。
起きてすぐ、朝ごはんの菓子パンとフルグラを食べた。
5:10三瀬峠を出発。朝露で木々が濡れていたので上下レインウェアを着用した。雨がなくとも朝露でぬれた木沿いをレインの着用無しで進めば、ものの10mで見事にずぶ濡れなるのは必至だ。こういう縦走においては、体力のみならず気力もかなり重要であり、気分が下がるのはよくない。挑戦するつもりの君、もし100%晴れる予報だとしても、濡れるのが嫌ならレインは携行しよう。

暗い時間は他のことに気が取られないのでとても歩行がはかどる。
5:30 三瀬山。小さいピーク
6:30 金山。ここは初めて訪れたが、前後の道がとても歩きやすく、朝日に照らされる朝露と霧がなんとも幻想的だった。気持ちよくて小走りしながら時間を巻いたのをおぼえている。よくよく考えると、今トレイルランニングをやっているのは、当時この区間を走ってみたのがすごく気持ちよかったからだと思う。レインウェアを脱いだ。この後、すぐに霧が晴れて青空が広がった。

縦走路沿いの石楠花(シャクナゲ)。


つい先日、雷山で遭遇したおじさま曰はく、この年(2022年)のシャクナゲは数年に一度くらいの綺麗な咲き方だったとのこと。記憶に残るほど印象的だったので、すぐに納得がいった。
ガスに包まれたり抜けたりを繰り返した。

猟師岩山、鬼ヶ鼻岩、唐人の舞といった小さめのピークを通過
9:13 舗装路を歩いてこの山域の主峰「脊振山」に到着。
ここはキャンプ場もあれば、自衛隊のレーダー基地もある。車で山頂手前まで来れる上に、人口物や自販機もがっつりある。しっかりとした装備で矢筈峠ルートを通り下から登ってくるくると、私服を着て車で来ている人たちにめっちゃ見られて少し恥ずかしい気持ちになったことがあるのは僕だけだろうか。

楽しみにしていたランチパック(もどき)のツナマヨ味とフルグラを食べる。

ここで水が残り1Lもない。この暑さであと30㎞もあるから、確実に足りない。水が足りない場合は潔く無補給はあきらめて自販機で補給するつもりだったので、完全にコーラと水を買う脳になってお金を投入。ところがここでアクシデント。押しても出てこない。売り切れてはいないが、どうやら自販機の釣銭不足だったようだ。なんとも運が悪い。ここで断念したくもない。脊振山系は水が豊かな山域ということもあり、途中の水場をあてに先に進むことにした。

雨の土砂崩れにより崩れた道。脊振山からすぐのところは迂回ルートがあった。

10:30 蛤岳。はまぐりだけ、と読む。このあたりでとても綺麗な水流を発見したが、YAMAPの水場マーク💧はない。飲めないこともなさそうだが躊躇した。まあ、脱水になるより翌日に腹壊したほうがましだと思って飲んだ(水自体はかなり透き通っていて味もうまかった)。どうか、そこら辺の川の水を飲むようなヤバいやつだとは思わないでほしい…(笑)。

11:23 坂本峠
11:42 七曲峠
12:33 三国峠

この手前の急坂は非常にしんどかったのを覚えている。一人なので、気持ちで負けないように声に出して自分を応援した。「〇〇〇!ファイト!」みたいにどシンプルだが、これが案外効くのだ。高校のマラソン大会の時とか、沿道の人に応援されると不思議と力が湧いてきたときの感覚に似ている。
この辺りは、だいぶ急いで進んだため、写真はほとんどない。というのも、先輩と同期が貴重なGWを割いてゴール地点に駆けつけてくれるとの連絡が入ったからだ。待たせるわけにもいかないし、最初に伝えた時間を目指して進んだ。本当にありがたい。とても暑く水も足りていない状況下で原動力となっていたのは、間違いなくこの人たちの応援と密かに目論むご褒美だった。
13:15 九千部山。ゴールはもうすぐ。10分ほど休憩。

行動食スタメンの塩豆大福は潰れて変形していたが、安定のうまさだった。ちょっぴりある塩味が非常にいい。回復。水は残り300mL。

14:40 登山口まで降り、一般道路に出た。空腹で最後のフルグラをすべて掻き込んだため、僕の乾燥した口内はこれが決定打となりトドメを刺された。残り10㎞。ラストの水一口分を全て飲んだ。
ここから先はアスファルトのロード。先輩からの前情報によると、ここから足裏が逝くそうだ。一旦、登山靴のまま歩いたが、噂通り足裏へのダメージが想像以上だった。対策として持参したランシューに履き替えると、圧倒的に快適だった。数百グラムの軽量化を諦めてでも得られる効果は大きいので、ランシュー持参は必須だと個人的には思った。

15:44 基山の丘を少し下った所。暫く続いた山道も終わり、視界が一気に開けた。あの丘を登れば最後だ。その時上の方から駆け下りてくる人が見えた。過去に第16次、17次脊振全山討伐を遂げた先輩たちだった。

15:55 上には同期もいて、みんなで基山山頂にて写真撮影。わざわざ応援に来てくれたことに、この場を借りて深く感謝申し上げます。鶴さんからのマンゴープリンのプレゼントは嬉しかったけど、しばらく口が粘々になったのですぐ食べたことを後悔した。


16:52 原田駅にてゴール。駅前にある伊能忠敬さんの銅像と記念にパシャリ。日本中を歩いて地図を完成させたのだと思うと、すごすぎて自分なんかちっぽけに思えた。

なんとなく顔が瘦せているように見える(?)。なんたって2日間で1万kcalも消費したらしい。この時飲んだポカリとドデカミンの味は忘れがたいものだった。
帰り道は電車に乗り太宰府駅や博多駅を経由する際クサいままではいられないので、軽量化したい気持ちを抑えて着替えを用意していた。この選択は間違っていなかった。
19:30 マリノアシティ福岡着。姪浜駅で電車を降り徒歩で移動するなどしてまで、どうしてここへ来たのかというと、ご褒美の特大ステーキを喰らうためだ。はじめから決めていた。縦走を達成出来たら、リブロースステーキ400gを食べるのだと。ご飯も大盛り二杯食べた。これに勝る幸せはあるのだろうか(、いや無い(反語))。もし何かをするとき事前に盛大なご褒美を決めておくと、それがモチベーションになるからいいのかもしれない。身をもって体験した“肉”の力はとってもオススメだ。肉の効果は麦わらのルフィの強さが証明してくれている。

おまけ。帰りに同期がバイトするカフェに立ち寄ったらケーキとアイスコーヒーを奢ってくれた。とってもおいしかった、ありがとう!

縦走前に先輩に言われた一言、「縦走したら伊都キャンパスから見える脊振の景色が変わるはずだよ。」
GWが明けた翌日の学校で、窓の奥の方に東西にのびる稜線を見た時、その言葉をふと思い出した。
<総括>
・行動時間:21h 22min(Day1:10h 44min / Day2:10h 38min)
・総タイム:23h 14min(Day1:11h 32min / Day2:11h 41min)
・総距離:約74.7㎞
・獲得標高:約5600mD±300m程度
・総重量:約13㎏ちょっと(出発時)、うち水量4L

今回の縦走では、暑さ、飲み水、蜘蛛の巣に非常に悩まされることとなった。まず、GWは春と言えど年によってはこの日よりも3~4℃暑い場合もあるようなので油断はできない。やはり春休みか、秋の涼しい時期に攻めるのも一つの手だろう。飲み水はなるべく軽くするために4Lとしたが、自販機で買えず結果的にギリギリでとてもよろしくなかった。飲食物は、最初は重いものの消費によって軽くできるのでケチりすぎないことが大切だと思う。衣類やギア類は途中で放棄するわけにもいかないので、必要なものの吟味やグレードアップによる軽量化で対処するのがいい。蜘蛛の巣に関して言えば、仕方なイ。途中で会ったトレイルランナーによると、5月あたりから特に増えるらしいので、GW以降にいくひとは覚悟せねばならないようだ。蜘蛛が無理な人は4月までにするのが妥当だ。
縦走を終えて、今回よかったなと思う点は、(過去の先輩の助言にもあった)西側からのスタート/軽量化/モチベーションの維持だと思う。序盤に述べたように、脊振山系の西側は毎度登って降りてを繰り返す。そのため、体力の落ちた後半に西側へ挑むのは得策ではない。10㎞ほど続く最後のアスファルトも足がやられるが、むしろ、疲れていても惰性で進めばよいし、山からは降りているので安全だ。まあ、二度目に比較としてやってみるのもいいかもしれない。ちなみに、二日目は長いので三瀬峠まで進んでおくのがいいいと思う。軽量化については、高カロリーなフルグラの活用、ツェルト泊は非常に有効な手段であると思う。また、前日のうちに三瀬峠や雷山避難小屋に荷揚げする方法もある。最後に、モチベーションの維持だ。今回は数々の場面でこれが大事だったなと感じた。終盤に行くほど効果が顕著で、脊振山でのツナマヨ(反省として塩味のあるものが少なかったので、ツナマヨが食べれるのは、下界で食べるのよりも5倍は味が濃くうまかった。)、九千部山での大好物・塩豆大福、ゴール地点に待つ仲間、ご褒美のステーキ。いずれもしんどい登りでの活力となった。このような長い縦走では、やはり精神的な面がやられないのが大事だと思う。気持ちさえやられなければ、極論、時間がかかってもどこまででも進むことはできる。好きな食べ物をあえて最後まで残す作戦は、単純かつ秀逸な方法だ。また、仲間を誘って2~3人で挑戦するのもお互い助け合えるのでよいかもしれない。
たったの2日の縦走だが、行動時間も距離も長く非常に濃い山行が楽しめる。きつさもあるが、脊振山系の山々が持つ多くの魅力を感じることができて楽しい。ぜひ福岡にいるうちに歩き通してみてはいかがだろうか。また、夏の日本アルプスに向けてのトレーニングとして、二泊三日で雷山・脊振山でのテン泊縦走をするのもいいだろう。わざわざレンタカーを借りて遠くまで行かなくても、近くにこんなにいい練習コースがのだ。この伝統がこの先どうなるかは謎だが、もし引き継いでくれる人がいれば嬉しいなと思う。読んでくれたそこの君が、九大ワンゲルの意志を次いでくれることに期待しよう。
長く拙い文章にお付き合いいただきましてありがとうございました。