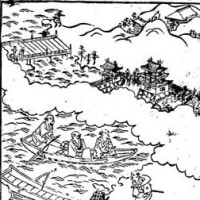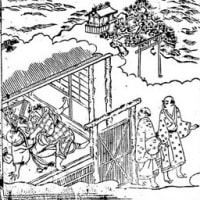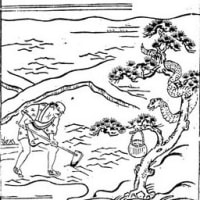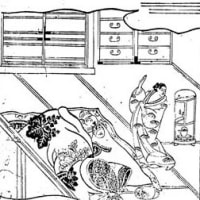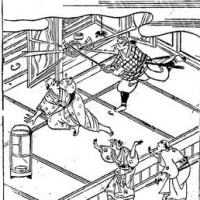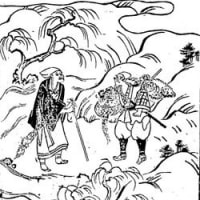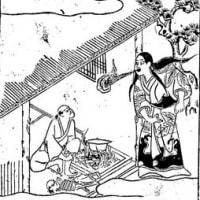ご訪問ありがとうございます→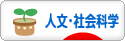 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
「法律に該当するかどうかは、併せプリズムを使うようなものだ」と、学生の頃、教わりました。
たとえば殺人では、殺害方法や動機など様々な「色(事情)」があるわけですが、それを、第1のプリズムを通して、刑法第199条殺人罪という1つの「色」に該当するかどうかを検討します。
そして、殺人罪に該当するとなったら、第2のプリズムで「各色(事情)」に分解し、動機、方法、自首や逃走、反省の程度などを勘案して、どの程度の罰が適当か、ということを決定します。
そこで五十歩百歩の故事を2つのプリズムに通してみると、まず第1のプリズムでは、「逃げた」という共通項が浮かび上がり、「卑怯者」という点では同じことだと分かります。
次に、第2のプリズムに通すと、50歩と100歩という違いが浮かび上がり、「程度」の違いによって、卑怯者の度合いに相違を認めるか否か、という問題点が浮かび上がります。
この問題に、正解というものはありません。
1歩でも逃げれば、その時点でみな「卑怯者」であり、歩数の違いは問題にならない、という考え方もありますし、戦場で50歩逃げるのと100歩逃げるのとでは雲泥の差だ、というのも間違いではありません。
(五十歩百歩の故事成語は、もっぱら前者の意味で使われていますが)
ただし後者を採用した場合、では、50歩の者がどれくらいの罪で、100歩の者がどれくらいの罪か、ということを算定しなければならず、また、51歩の者はどうか、1万歩の者はどうか、といった微妙な問題も発生します。
さて、世の中では、金銭にまつわる犯罪や、犯罪とまでは言えないけれど、道義的に見て疑問のある金銭問題は日常茶飯事です。
法令に違反したとすれば、これは言い訳のできないことであり、罪の重さに応じた罰を受けるのは当然です。
しかし法律とは切り離して、そうした者たちへの「拝金主義者」「金の亡者」といった類の、社会的な非難を考えてみるとどうでしょう?
そうした者たちに限らず、誰でもお金は大好きです。もちろん私も大好きです。
我々は、正当な労働をして得た報酬のほかに、もし、濡れ手に粟の収入があれば、大歓迎します。
そんな儚い夢を見て、庶民は、宝くじを買ったり、手軽なギャンブルをしてみたりします。
宝くじにしろ、ギャンブルにしろ、合法的ではあるけれど、正当な労働の報酬ではない点には違いはなく、また、利益を得る人がいる影には、必ず、損失を被る人がいるのも、厳然たる事実です。
また、道端で100円玉を拾ったら、たいていの人は、ポケットに入れてしまうでしょうが、これは濡れ手に粟というだけでなく、刑法第254条:遺失物等横領罪(一般的には、拾得物横領と言われています)という、まごうことなき犯罪です。
では、庶民がそのようにして儲けを得ることと、「金の亡者」が得た儲けを、プリズムに通してみたらどうでしょう。
まず第1のプリズムでは、不労所得や、微罪ながらも犯罪行為、あるいは道義的に問題がある方法によって利益を得た、という共通点が浮き彫りとなり、両者に違いはないということになります。
さらにそれを第2のプリズムに通すと、額の違いが浮かび上がります。
そう考えると、「金の亡者」と我々との間には、実は、儲けた額の違いしかありません。
これを今度は五十歩百歩の故事に当てはめてみると、不労所得を得た時点で、みな「拝金主義者」や「金の亡者」なのか、100円や庶民の小遣い程度なら良くて巨額なら悪いのか、さらに、100万円はどうか、9999万円ならどうか3億円はどうか、といった問題に行き当たります。
もちろん、正解はありません。
我々は、つい、不労所得に近い形で巨万の富を得た者に対して、やっかみ半分、悪い印象を持ってしまいがちです。
しかし、キリストは、群集が、罪を犯した女に投石で罰を与えようとしているのを制止して、「この中で、罪のない者だけが、石を拾うがよい」と言いました。
はたして我々の中に、「拝金主義者」や「金の亡者」に対して、「石を拾う」ことのできる人は、いるのでしょうか?
それとも、人間とはそもそも「餓鬼道」に堕ちるべきものなのでしょうか?
「法律に該当するかどうかは、併せプリズムを使うようなものだ」と、学生の頃、教わりました。
たとえば殺人では、殺害方法や動機など様々な「色(事情)」があるわけですが、それを、第1のプリズムを通して、刑法第199条殺人罪という1つの「色」に該当するかどうかを検討します。
そして、殺人罪に該当するとなったら、第2のプリズムで「各色(事情)」に分解し、動機、方法、自首や逃走、反省の程度などを勘案して、どの程度の罰が適当か、ということを決定します。
そこで五十歩百歩の故事を2つのプリズムに通してみると、まず第1のプリズムでは、「逃げた」という共通項が浮かび上がり、「卑怯者」という点では同じことだと分かります。
次に、第2のプリズムに通すと、50歩と100歩という違いが浮かび上がり、「程度」の違いによって、卑怯者の度合いに相違を認めるか否か、という問題点が浮かび上がります。
この問題に、正解というものはありません。
1歩でも逃げれば、その時点でみな「卑怯者」であり、歩数の違いは問題にならない、という考え方もありますし、戦場で50歩逃げるのと100歩逃げるのとでは雲泥の差だ、というのも間違いではありません。
(五十歩百歩の故事成語は、もっぱら前者の意味で使われていますが)
ただし後者を採用した場合、では、50歩の者がどれくらいの罪で、100歩の者がどれくらいの罪か、ということを算定しなければならず、また、51歩の者はどうか、1万歩の者はどうか、といった微妙な問題も発生します。
さて、世の中では、金銭にまつわる犯罪や、犯罪とまでは言えないけれど、道義的に見て疑問のある金銭問題は日常茶飯事です。
法令に違反したとすれば、これは言い訳のできないことであり、罪の重さに応じた罰を受けるのは当然です。
しかし法律とは切り離して、そうした者たちへの「拝金主義者」「金の亡者」といった類の、社会的な非難を考えてみるとどうでしょう?
そうした者たちに限らず、誰でもお金は大好きです。もちろん私も大好きです。
我々は、正当な労働をして得た報酬のほかに、もし、濡れ手に粟の収入があれば、大歓迎します。
そんな儚い夢を見て、庶民は、宝くじを買ったり、手軽なギャンブルをしてみたりします。
宝くじにしろ、ギャンブルにしろ、合法的ではあるけれど、正当な労働の報酬ではない点には違いはなく、また、利益を得る人がいる影には、必ず、損失を被る人がいるのも、厳然たる事実です。
また、道端で100円玉を拾ったら、たいていの人は、ポケットに入れてしまうでしょうが、これは濡れ手に粟というだけでなく、刑法第254条:遺失物等横領罪(一般的には、拾得物横領と言われています)という、まごうことなき犯罪です。
では、庶民がそのようにして儲けを得ることと、「金の亡者」が得た儲けを、プリズムに通してみたらどうでしょう。
まず第1のプリズムでは、不労所得や、微罪ながらも犯罪行為、あるいは道義的に問題がある方法によって利益を得た、という共通点が浮き彫りとなり、両者に違いはないということになります。
さらにそれを第2のプリズムに通すと、額の違いが浮かび上がります。
そう考えると、「金の亡者」と我々との間には、実は、儲けた額の違いしかありません。
これを今度は五十歩百歩の故事に当てはめてみると、不労所得を得た時点で、みな「拝金主義者」や「金の亡者」なのか、100円や庶民の小遣い程度なら良くて巨額なら悪いのか、さらに、100万円はどうか、9999万円ならどうか3億円はどうか、といった問題に行き当たります。
もちろん、正解はありません。
我々は、つい、不労所得に近い形で巨万の富を得た者に対して、やっかみ半分、悪い印象を持ってしまいがちです。
しかし、キリストは、群集が、罪を犯した女に投石で罰を与えようとしているのを制止して、「この中で、罪のない者だけが、石を拾うがよい」と言いました。
はたして我々の中に、「拝金主義者」や「金の亡者」に対して、「石を拾う」ことのできる人は、いるのでしょうか?
それとも、人間とはそもそも「餓鬼道」に堕ちるべきものなのでしょうか?