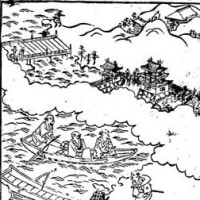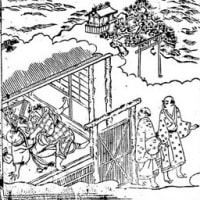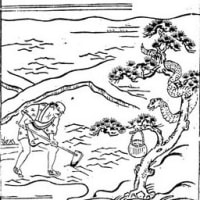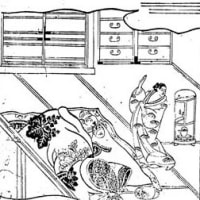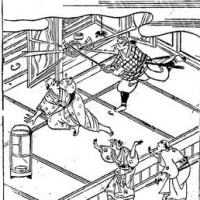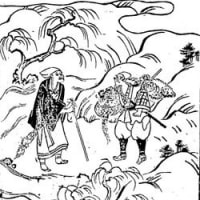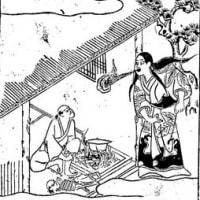ご訪問ありがとうございます→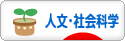 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
蛇足とは、誰でもご存知ですが、「余計なもの、要らないもの」という意味です。
ところが、つい最近知ったのですが、江戸時代の医者でもあり文学者でもあった苗村丈伯の著書「理屈物語」では、別な意味に説明しています。
<蛇足>
楚の偉い人が、召使いたちに、一杯だけ酒を与えた。召使いたちは「皆で分けて飲んでも、少しずつになってしょうがないから、地面に蛇の絵を描いて、一番先にできた者を勝者にして、そいつが酒を飲む事にしよう」と決めた。そして、中でも絵の一番うまい者が、真っ先に蛇の絵を描き上げたので、その者は酒を飲もうとしたが、他の者がまだ絵を描き上げていないのを見て、「なんだ、みな、まだ描いていないのか。私にはまだ余裕がある」と言って、蛇の絵に足を描きたした。それを見ていた一人が、彼から杯を奪い取り、酒を飲み干した。先の者が文句を言うと、酒を取った者は、「蛇に足はない。だから、お前が描いたのは、蛇ではない」と言った。
とまあ、ここまでは「理屈物語」の説話も、巷に伝えられている話と同じで、巷の話では、先に書いたように、この故事により、「蛇足」を、「余計なもの、要らないもの」という意味である、と説明しています。
ところが、「理屈物語」では、次のように続きます。
この故事から、自分のことを自慢する者を「蛇を描きて、足を添える者」という。
俄かに信じ難い俗説ならともかく、きちんとした記録に名を残す苗村丈伯が、著書の中で、明らかに間違ったことを言うとは思えません。
また、同じ「理屈物語」の中では、これもよく知られた「矛盾」「守株」「朝三暮四」「人間万事塞翁が馬」などの語源となった物語も紹介され、「・・・という話から、○○という言葉が言われるようになった」で締めており、これらの用法は今と変わりませんから、「蛇足」だけ、いい加減なことを言ったとも考えられません。
してみると、「理屈物語」が刊行された江戸時代には、「蛇足」は、上の意味で使われていたのでしょうか?
それとも、「理屈物語」の中では、この故事成語を「蛇足」とは書いておらず、「蛇を描きて、足を添える者」と書いていますから、「蛇足」という言葉自体、「理屈物語」以降の時代に成立したものなのでしょうか。
といった疑問点について、ネットなどで散々調べてみましたが、さっぱりヒットせず、調査は暗礁に乗り上げてしまいました。
今回ばかりは降参です。
駄文を読んだ諸姉諸兄、情報をお待ちしております。なにとぞ、よろしく。
蛇足とは、誰でもご存知ですが、「余計なもの、要らないもの」という意味です。
ところが、つい最近知ったのですが、江戸時代の医者でもあり文学者でもあった苗村丈伯の著書「理屈物語」では、別な意味に説明しています。
<蛇足>
楚の偉い人が、召使いたちに、一杯だけ酒を与えた。召使いたちは「皆で分けて飲んでも、少しずつになってしょうがないから、地面に蛇の絵を描いて、一番先にできた者を勝者にして、そいつが酒を飲む事にしよう」と決めた。そして、中でも絵の一番うまい者が、真っ先に蛇の絵を描き上げたので、その者は酒を飲もうとしたが、他の者がまだ絵を描き上げていないのを見て、「なんだ、みな、まだ描いていないのか。私にはまだ余裕がある」と言って、蛇の絵に足を描きたした。それを見ていた一人が、彼から杯を奪い取り、酒を飲み干した。先の者が文句を言うと、酒を取った者は、「蛇に足はない。だから、お前が描いたのは、蛇ではない」と言った。
とまあ、ここまでは「理屈物語」の説話も、巷に伝えられている話と同じで、巷の話では、先に書いたように、この故事により、「蛇足」を、「余計なもの、要らないもの」という意味である、と説明しています。
ところが、「理屈物語」では、次のように続きます。
この故事から、自分のことを自慢する者を「蛇を描きて、足を添える者」という。
俄かに信じ難い俗説ならともかく、きちんとした記録に名を残す苗村丈伯が、著書の中で、明らかに間違ったことを言うとは思えません。
また、同じ「理屈物語」の中では、これもよく知られた「矛盾」「守株」「朝三暮四」「人間万事塞翁が馬」などの語源となった物語も紹介され、「・・・という話から、○○という言葉が言われるようになった」で締めており、これらの用法は今と変わりませんから、「蛇足」だけ、いい加減なことを言ったとも考えられません。
してみると、「理屈物語」が刊行された江戸時代には、「蛇足」は、上の意味で使われていたのでしょうか?
それとも、「理屈物語」の中では、この故事成語を「蛇足」とは書いておらず、「蛇を描きて、足を添える者」と書いていますから、「蛇足」という言葉自体、「理屈物語」以降の時代に成立したものなのでしょうか。
といった疑問点について、ネットなどで散々調べてみましたが、さっぱりヒットせず、調査は暗礁に乗り上げてしまいました。
今回ばかりは降参です。
駄文を読んだ諸姉諸兄、情報をお待ちしております。なにとぞ、よろしく。