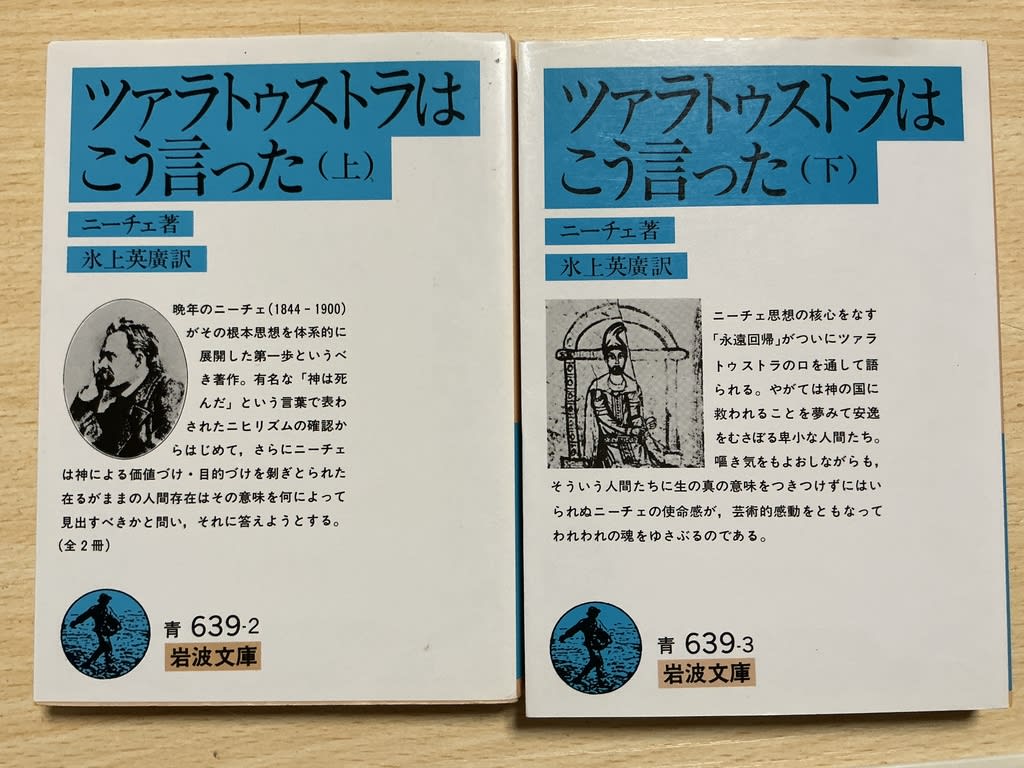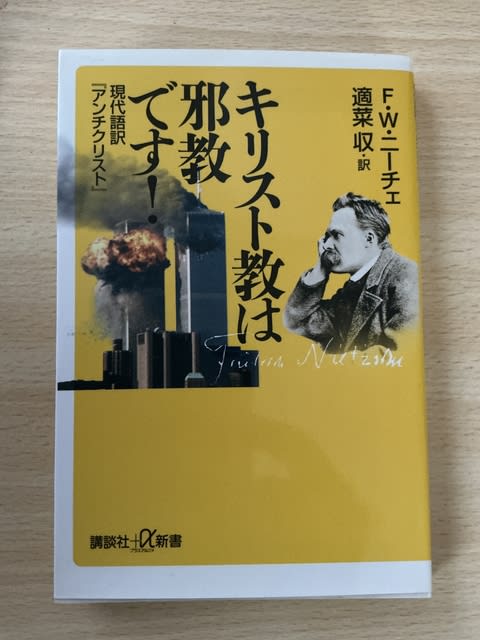昨日の最後で書いた通り、今日は「夜と霧」のまとめ。
最初に注意点その1
自分が読んだ「夜と霧」は「フランクル著作集」のうちの1冊なので単行本として出ている同名作品と違っているかもしれない。同じみすず書房からは他に2つ出版されていて、翻訳者が同じで単行本になっているものと2002年新訳のものがある。新訳とは目次が異なっているが、それが翻訳時のものなのか他の原書を用いたためかは不明。また、古い単行本に著作集のような長い刊頭解説があるのかどうかは現時点で知らない。
注意点その2
まず、本書の構成だけれど、刊頭に長い長い解説がついている。これは強制収容所でどんなことが行われていたかを出来るだけ詳細に前知識として伝えるものになっている。本文を鑑賞するためには読んでも読まなくても良いと思う。ただ、気をつけなければならないのは、たぶん出版の意図は戦争というものの悲惨さを強調したいという意図でそれを付加している。もしかするとそれが「夜と霧」を出版する意味と考えている伏しがある。これは一般的な戦争反対論の元になる思いだし、それがこうした強制収容所関係本を出版する「売り」になるのも事実だが、はっきり言って著者がこの文章を書いて意図とはズレていると考えられる。なので読んでも良いがそれにとらわれないでおくべきだろう。
本書を読むにあたって、どこから入ったかは読み方に大きな影響を与えると考えられる。1)戦争の悲惨さをこうした文章で確認する。戦争関連本を読む場合に多い読み方だが、本書はそうしたぼんやりとした感情扇動本ではないのでガッカリするかと思われる。2)癒しやセラピーを求めて読む方は多いはず。NHKで放送した「こころの時代」を観てから読むとそうなると思われる。楽になるためにはそれもアリかもしれないが、何とも言えない。世の中には別の解答もあるはずなので。3)私のように予備知識なしで読むやり方。
前置きが長くなってしまったが、本文はできるだけ簡単に短く書きたいと思う。
この文章は大きく2つの部分に分かれる。前半の強制収容所に入るところとその中での生活を書いている部分にはエピソードを交えて囚人の心の中に起きた心理的変化が主に書かれている。後半、解放の文字が現れるあたりからは著者の解釈と療法としての方法論が多く出てくる。
前半、収容され、囚人として生きる中では(当たり前だが)外部からの強制によって自己の未来を見ることができない状態(仮の存在)となり、心理的な価値低下、無感覚、自己判断を避けようとするようになる。これは強制収容所の極限状況によるものなので読んでいる自分とはかけ離れた心理状態かと考えられるのだが、どうしたわけか共感に近いものを感じてしまった。
それはこの現代(といっても数十年の間)日本の社会で、程度の違いこそあれ、我々が常に置かれている状況(外的にも心理状態としても)と似ていると思えるからだ。我々はある種の社会が求める理想像に鋳込まれるのを経験している。学校では常に教師の用意する正解があり、社会に出た時の在り方にも正解が用意されているし、仕事の課題においても生活態度においてもそうだ。そのある意味「自然」の中で我々は自己の価値低下を常に感じさせられ、多くの刺激に対して無感覚でいることを学ぶ。そうした意味で強制収容所はこの社会と相似形にあると結論することができる。
もちろん足の指が凍傷になってピンセットで抜かれるのを見ることは無いが、代わりに家の中で人知れず亡くなっている人が近所で時々発見されるのを「またか」とやり過ごしたり、職場の同僚だった者が閑職に追いやられて知らぬ間に退社していたという経験を重ねている。
さて、問題はここからだ。
では、そんな社会の中で苦しい思いをして生きていて、我々の人生には何の意味があって、何故生きているのだ?という問いに繋がる。
苦しいだけで未来に輝く未来があると保証されているわけではないのに、ただ生物として息をして食べて寝て生きている。猫であればそうしたことを何も考えず、毎日キャットフードをもらってオシッコしたら寝ていれば良い。何故か人はそこに意味を見つけたいという衝動に駆られる。
はて、その答は?
残念ながら絶対的な解答は提供されることはない。
けれども、外的に強制されて自己を守るための感情の抑制、無感覚の底においても内的な「自由」は確保され得るものだと囚人の中のいくらかの実例をあげて言っている。そこに内的な勝利の鍵があるのだと。
絶対的な答、つまり普遍的真理のようなものは結局は無いだろう。もしそれを言えるとしたらそれは宗教やスピリチュアルのような何かだろうが、それ以外でそれを言った者はいないはずだし心理学者であるフランクルに言えるはずはない。
その代わりに提供されるのはセラピーだ。ということは真理より実用性のあるものが提供されていると言える。神様がいようがいまいが救いはある。つまり方法論だ。これは工業生産において完璧に理論が確立していなくても生産してお金に換えることができるのに似ている。
その最初に来るのが前述の「自由」の行使だ。そして、真理を待っている態度から自分が人生から何を問われているかを探すという逆方向の思考へ転換することによって内的に未来を見るというやり方だ。神様が勝手に自分を照らしてくれるのではなくて、人生からの問いに自ら答えるて光を見つける。
そうすることによってたった今ここにある苦しみにも、そして先にあるかもしれない死にも意味が見出せるのだ。死、そこには単に死ぬというだけの意味以上のものがあるはずだ。例えば、何かを一所懸命やって良い結果どころか結果自体すら得られずに中途半端に終わってしまうというのも含まれる。いったい何のためにここまで努力したのか、やってきたのか?意味があったのか?というような死。だが、フランクルはそんな死にも意味を見出すことができる。むしろそれも含めて全てを統合して意味があると言う。
まさにそれはセラピーの思考だ。
もし真理を言うのであれば、無感覚な中に自己を放棄して死んでしまって人々の心や在り方にさえ何らかの意味があると言うのではないだろうか?宗教で言う「それも神のご意志」のように。だが、フランクルの場合は自己放棄させないための方法論を書いている。だからフランクルの考え方は哲学や思想とは違うセラピーなのだ。
そのセラピーをここでは強制収容所について適用しているが、ケースとして強制収容所は稀であり、囚人に特化するのであれば、それも酷い環境でとなれば次の戦争を待つことになるだろう。が、そんなわけはない。こうして極限状態で観察され考察された心理状況とそのセラピーは一般化され得たわけだから普通に日常生活を送っている人々、つまり我々にも適用できると考えなければならないだろう。
つまり、この日本の社会の中で社会の要求する型に鋳込まれるつつ生きている我々にも、ということだ。現にフランクルのセラピーを使っている方々はいるそうだ。(NHK参照)
けれども、セラピーを求めるのであれば実際ののところ他の方法も提案されている。自分にはそのあたりは何とも言えないが、ともかくフランクルの方法論を絶対視する必要はないのではなかろうか?