映画の話より先にこの題名の付け方に引かれる。
とても英語っぽい発想の名詞節になっている。そこになぜか惹かれてしまう。邦題の「かいじゅうたちのいるところ」とそれにならって付けられている。しかしWild Things を怪獣としているところは惜しい気がする。けれどもWild Thingsと言う抽象的とも言える表現を日本語にするのは難しいから仕方ない。
この映画を見るときに、ハリー・ポッターのようにあれがああしてこうなって結局そうなる的なストーリー展開を想像して見ているとかなりの拍子抜けだ。お話に一貫性があるわけでなく、テレタビーズのようにとんでもない展開、何の発展性も生産性も感じられないことが次々と行われていく。ストーリーを追って見てしまうとそれが一体何なの?あれっ、それでもう終わりなの?で終わってしまう。従って見ているこちらが見方を修正せねばならないのである。ただ、一旦修正できてしまうとなかなか別の世界が開けてきて見どころのある映画に感じられてくるのが面白い。
おとぎ話のようなストーリーではそのお話の中で遊ばされる感覚があるものがほとんどだ。主人公に成りきって感情移入してしまうとそこはもう別世界。さしずめディズニーランドのような仮想世界に遊ぶと言ったような状態となって楽しむ。子供向けのお話等では特に、その世界の仮想性だけを楽しませることでそれを夢を見る力であるとか信じる力のように言うのであるけれども、この作品の面白いところはその仮想世界を仮想世界だけの楽しみで終わらせていないところだ。
仮想世界はそのどこかに実際の世の中と対応する部分が見え隠れしている。夢の世界が理想のパラダイスを示しているだけではなく、実世界や人間の暗い部分や汚い部分をそのまま反映していてしかもそれが永遠に続くのではなくて終わりがある事さへも暗示している。さらにはそれは遊ばされるだけの出来上がった世界でもなく、自ら変化させる事も可能なものなのである。
つまりはおとぎ話の世界が実世界と地続きであって、きっと最後には子供を子供のままに停止させることなく大人に成長させる力を秘めているのだ。通常、大人の考える子供の世界は夢でありピーターパンやディズニーランドのような仮想の永遠性が前提になるのだけれども、この映画ではそれを軽々と越えて子供の生きるための実際の力を見せてくれている。そう言う羨ましいほどの豊かな発想とパワーがこの映画の裏にはあるのだ。
羨ましいと言うのはこう言うきちんとした教育的な意図を踏まえた作品は、子供を子供に育てようとする日本人的発想からはほとんど作れにないと思う、と言う意味だ。
とても英語っぽい発想の名詞節になっている。そこになぜか惹かれてしまう。邦題の「かいじゅうたちのいるところ」とそれにならって付けられている。しかしWild Things を怪獣としているところは惜しい気がする。けれどもWild Thingsと言う抽象的とも言える表現を日本語にするのは難しいから仕方ない。
この映画を見るときに、ハリー・ポッターのようにあれがああしてこうなって結局そうなる的なストーリー展開を想像して見ているとかなりの拍子抜けだ。お話に一貫性があるわけでなく、テレタビーズのようにとんでもない展開、何の発展性も生産性も感じられないことが次々と行われていく。ストーリーを追って見てしまうとそれが一体何なの?あれっ、それでもう終わりなの?で終わってしまう。従って見ているこちらが見方を修正せねばならないのである。ただ、一旦修正できてしまうとなかなか別の世界が開けてきて見どころのある映画に感じられてくるのが面白い。
おとぎ話のようなストーリーではそのお話の中で遊ばされる感覚があるものがほとんどだ。主人公に成りきって感情移入してしまうとそこはもう別世界。さしずめディズニーランドのような仮想世界に遊ぶと言ったような状態となって楽しむ。子供向けのお話等では特に、その世界の仮想性だけを楽しませることでそれを夢を見る力であるとか信じる力のように言うのであるけれども、この作品の面白いところはその仮想世界を仮想世界だけの楽しみで終わらせていないところだ。
仮想世界はそのどこかに実際の世の中と対応する部分が見え隠れしている。夢の世界が理想のパラダイスを示しているだけではなく、実世界や人間の暗い部分や汚い部分をそのまま反映していてしかもそれが永遠に続くのではなくて終わりがある事さへも暗示している。さらにはそれは遊ばされるだけの出来上がった世界でもなく、自ら変化させる事も可能なものなのである。
つまりはおとぎ話の世界が実世界と地続きであって、きっと最後には子供を子供のままに停止させることなく大人に成長させる力を秘めているのだ。通常、大人の考える子供の世界は夢でありピーターパンやディズニーランドのような仮想の永遠性が前提になるのだけれども、この映画ではそれを軽々と越えて子供の生きるための実際の力を見せてくれている。そう言う羨ましいほどの豊かな発想とパワーがこの映画の裏にはあるのだ。
羨ましいと言うのはこう言うきちんとした教育的な意図を踏まえた作品は、子供を子供に育てようとする日本人的発想からはほとんど作れにないと思う、と言う意味だ。

















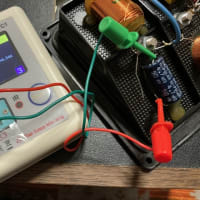
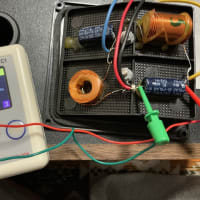

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます