一 世界同時株安
二〇〇八年、世界の株式時価総額は一年間で半減した。三〇兆ドルが吹き飛んだとされている.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003015&refer=jp_europe&sid=a_MWiGBNlQUQ
株式、不動産、商品市場から資金が一気に逃げだした。それは、まさに、ホット・マネー(hot money)(1)である。
一九九五年から〇八年に至る一〇年間、世界の名目GDPは二倍に増え、〇八年のGDPはほぼ六〇兆ドルであった。同じ期間、金融資産は二・六倍とGDPよりもはるかに速いスピードで膨張した。〇八年の世界の金融資産は約一六七兆ドルにもなっていた。金融資産は、実体経済(GDP)の二・七倍もある(三菱UFJ証券調べ)。
〇八年の世界的な株安は三つの段階を経て進行した。
第一段階は、返済に無理のある貸付、つまり、サブプライム・ローン(Subprime Loans)などを組み込んだ証券化商品保有によって、巨額の損失を抱え込んでしまった金融機関の経営不安から生じた株安。〇八年の年初から九月中旬までの期間である。〇八年三月一六日、商業銀行のJ・P・モルガン・チェース(JP Morgan Chase)が、投資銀行のベアー・スターンズ(The Bear Stearns Companies Inc.)を買収すると発表。同年七月一一日には、ニューヨーク原油先物(WTI=West Texas Intermediate)(2)が一バレル一四七・二七ドルと史上最高値をつけた。
第二段階は、米国の大手投資銀行(証券会社)であったリーマン・ブラザーズ(Lehman Brothers、同社の歴史については後述))の破綻(〇八年九月一五日)が引き起こした株安。金融機関が互いに疑心暗鬼になって、金融機関相互で短期資金を融通し合う慣行が停止し、金融市場で流動性(資金流通)が干上がってしまった。第二段階は、〇八年九月中旬から一〇月末までの期間である。九月二二日、三菱UFJがモルガン・スタンレー(Morgan Stanley)に出資すると発表した。この月の二九日、米下院で金融安定化法案(Emergency Economic Stabilization Act of 2008)がいったん否決され、そのショックで、ニューヨークのダウ工業株三〇種平均株価(3)が、史上最大幅の七七七ドルの下落をした。
第三段階は、こうした金融不安が実体経済を萎縮させることによる企業収益の圧迫からくる株安。第三段階は、〇八年一〇月末以降のことである。一〇月二七日、日経平均が二六年ぶりの安値となった。つまり、バブル崩壊前の水準に戻ったのである。そして、一一月二〇日、米国の株式市場は、パニックに陥った。ゼネラル・モーターズ(GM=general Motors)株は、一時、一ドル台、シティグループ(Citigroup)株は、四ドル台にまで売り込まれた。
ヘッジファンド(Hedge Fund)が融資回収を迫られ、資産の投げ売りに出た。空前の株高に沸いていた、ロシア、中国、パキスタン、アイスランドの株価下落幅は先進各国を上回っていた。アイスランドなどは、ピークの一〇分の一にまで下落したのである。資金は、まず弱い金融市場から逃げるものであることをこの事実は思い起こさせた。
日経平均は、一二月末で、年初来から四四%もの下落率であった。これは、戦後最大の下落率であった。米国のダウ工業株三〇種平均と英国のFTSE一〇〇種総合指数(4)は、ともに、三三%の下落率であった。つまり、金融危機の震源地である米国や英国よりも、日本の株価下落率は大きかったのである。
株価の水準の適性さを判断するのには、いくつかの指標がある。この指標のことごとくが、何十年ぶりの異常な数値を示したのが、〇八年秋の日本株暴落であった。たとえば、株価平均収益率(PER)というものがある(5)。企業の収益を発行株数で割ったものが一株当たり収益である。実際の株価が一株当たり収益の何倍になっているかの数値が株価収益率である。〇八年一〇月二七日に計算された日経平均採用二二五銘柄の予想株価収益率は九・五三倍であった。月末値比較では、この数値は一九七〇年末以来の低水準であった。三八年ぶりにこの数値が一〇を割ったのである(「〇八金融危機の軌跡1」、『讀賣新聞』二〇〇八年一二月二六日付)。
日本は、震源地の米国や、その余波で銀行倒産が相次いだヨーロッパよりも、金融被害は軽微であったとされていた。少なくとも、〇八年八月末時点では、そう信じられていた。ところが、上述のように、日本の株価下落率は米欧よりも大きかった。
その理由を『日本経済新聞』(〇八年一二月一八日付)を外需依存と株式の外資依存という日本の体質を挙げている。
第一の理由は、日本の主力企業が、グローバル展開をし、世界の需要(外需)を取り込んで成長してきたことである。外需とは米国の住宅バブルであり、急成長する新興国需要であった。そこが急転直下暗転したのである。
第二の理由は、外国人中心の日本の株式市場の構造である。外国人は日本株の三割を保有し、六割の売買シェアを持つ。こうした巨大なシェアを持つ外国人がひとたび日本株売りに転じると、買いで対抗する日本人株主は希薄である。外国人の売り越しは〇八年を通じて三・三兆円弱であった。〇七年には五兆円の買い越しだったのだから、株式環境の激変がいかに大きかったかが理解できるだろう。
日本株の売りを主導したのは、ヘッジファンドである。ヘッジファンドは、金融機関や投資家から資金回収を迫られて日本株の換金売りを加速せざるをえなかった。
株価が下がれば、それを好機として、年金基金などの機関投資家が出動するものである。この種の機関投資家は、資産に占める株式の価値が低下すると株式を買い増す傾向がある。しかし、〇八年末の株価下落の激しさが彼らを躊躇させた。底値が見えないからである。
金融機関も株式買い増しに動けない事情がある。株安で体力が奪われたからである。株価が下がれば、保有株の含み損が生じて資本不足になる。そのために増資に踏み切らざるを得ず、株式の買い増しなどできないのである。大手生命保険会社も同様である。
本山美彦氏のブログ 「消された伝統の復権」から転載
http://blog.goo.ne.jp/motoyama_2006
二〇〇八年、世界の株式時価総額は一年間で半減した。三〇兆ドルが吹き飛んだとされている.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003015&refer=jp_europe&sid=a_MWiGBNlQUQ
株式、不動産、商品市場から資金が一気に逃げだした。それは、まさに、ホット・マネー(hot money)(1)である。
一九九五年から〇八年に至る一〇年間、世界の名目GDPは二倍に増え、〇八年のGDPはほぼ六〇兆ドルであった。同じ期間、金融資産は二・六倍とGDPよりもはるかに速いスピードで膨張した。〇八年の世界の金融資産は約一六七兆ドルにもなっていた。金融資産は、実体経済(GDP)の二・七倍もある(三菱UFJ証券調べ)。
〇八年の世界的な株安は三つの段階を経て進行した。
第一段階は、返済に無理のある貸付、つまり、サブプライム・ローン(Subprime Loans)などを組み込んだ証券化商品保有によって、巨額の損失を抱え込んでしまった金融機関の経営不安から生じた株安。〇八年の年初から九月中旬までの期間である。〇八年三月一六日、商業銀行のJ・P・モルガン・チェース(JP Morgan Chase)が、投資銀行のベアー・スターンズ(The Bear Stearns Companies Inc.)を買収すると発表。同年七月一一日には、ニューヨーク原油先物(WTI=West Texas Intermediate)(2)が一バレル一四七・二七ドルと史上最高値をつけた。
第二段階は、米国の大手投資銀行(証券会社)であったリーマン・ブラザーズ(Lehman Brothers、同社の歴史については後述))の破綻(〇八年九月一五日)が引き起こした株安。金融機関が互いに疑心暗鬼になって、金融機関相互で短期資金を融通し合う慣行が停止し、金融市場で流動性(資金流通)が干上がってしまった。第二段階は、〇八年九月中旬から一〇月末までの期間である。九月二二日、三菱UFJがモルガン・スタンレー(Morgan Stanley)に出資すると発表した。この月の二九日、米下院で金融安定化法案(Emergency Economic Stabilization Act of 2008)がいったん否決され、そのショックで、ニューヨークのダウ工業株三〇種平均株価(3)が、史上最大幅の七七七ドルの下落をした。
第三段階は、こうした金融不安が実体経済を萎縮させることによる企業収益の圧迫からくる株安。第三段階は、〇八年一〇月末以降のことである。一〇月二七日、日経平均が二六年ぶりの安値となった。つまり、バブル崩壊前の水準に戻ったのである。そして、一一月二〇日、米国の株式市場は、パニックに陥った。ゼネラル・モーターズ(GM=general Motors)株は、一時、一ドル台、シティグループ(Citigroup)株は、四ドル台にまで売り込まれた。
ヘッジファンド(Hedge Fund)が融資回収を迫られ、資産の投げ売りに出た。空前の株高に沸いていた、ロシア、中国、パキスタン、アイスランドの株価下落幅は先進各国を上回っていた。アイスランドなどは、ピークの一〇分の一にまで下落したのである。資金は、まず弱い金融市場から逃げるものであることをこの事実は思い起こさせた。
日経平均は、一二月末で、年初来から四四%もの下落率であった。これは、戦後最大の下落率であった。米国のダウ工業株三〇種平均と英国のFTSE一〇〇種総合指数(4)は、ともに、三三%の下落率であった。つまり、金融危機の震源地である米国や英国よりも、日本の株価下落率は大きかったのである。
株価の水準の適性さを判断するのには、いくつかの指標がある。この指標のことごとくが、何十年ぶりの異常な数値を示したのが、〇八年秋の日本株暴落であった。たとえば、株価平均収益率(PER)というものがある(5)。企業の収益を発行株数で割ったものが一株当たり収益である。実際の株価が一株当たり収益の何倍になっているかの数値が株価収益率である。〇八年一〇月二七日に計算された日経平均採用二二五銘柄の予想株価収益率は九・五三倍であった。月末値比較では、この数値は一九七〇年末以来の低水準であった。三八年ぶりにこの数値が一〇を割ったのである(「〇八金融危機の軌跡1」、『讀賣新聞』二〇〇八年一二月二六日付)。
日本は、震源地の米国や、その余波で銀行倒産が相次いだヨーロッパよりも、金融被害は軽微であったとされていた。少なくとも、〇八年八月末時点では、そう信じられていた。ところが、上述のように、日本の株価下落率は米欧よりも大きかった。
その理由を『日本経済新聞』(〇八年一二月一八日付)を外需依存と株式の外資依存という日本の体質を挙げている。
第一の理由は、日本の主力企業が、グローバル展開をし、世界の需要(外需)を取り込んで成長してきたことである。外需とは米国の住宅バブルであり、急成長する新興国需要であった。そこが急転直下暗転したのである。
第二の理由は、外国人中心の日本の株式市場の構造である。外国人は日本株の三割を保有し、六割の売買シェアを持つ。こうした巨大なシェアを持つ外国人がひとたび日本株売りに転じると、買いで対抗する日本人株主は希薄である。外国人の売り越しは〇八年を通じて三・三兆円弱であった。〇七年には五兆円の買い越しだったのだから、株式環境の激変がいかに大きかったかが理解できるだろう。
日本株の売りを主導したのは、ヘッジファンドである。ヘッジファンドは、金融機関や投資家から資金回収を迫られて日本株の換金売りを加速せざるをえなかった。
株価が下がれば、それを好機として、年金基金などの機関投資家が出動するものである。この種の機関投資家は、資産に占める株式の価値が低下すると株式を買い増す傾向がある。しかし、〇八年末の株価下落の激しさが彼らを躊躇させた。底値が見えないからである。
金融機関も株式買い増しに動けない事情がある。株安で体力が奪われたからである。株価が下がれば、保有株の含み損が生じて資本不足になる。そのために増資に踏み切らざるを得ず、株式の買い増しなどできないのである。大手生命保険会社も同様である。
本山美彦氏のブログ 「消された伝統の復権」から転載
http://blog.goo.ne.jp/motoyama_2006


















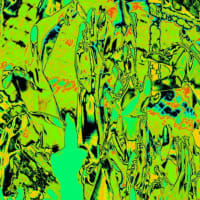
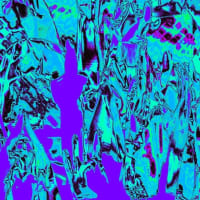
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます