
おはようございます、皆様。原田武夫です。
トルコ・イスタンブールでB20に出席し、つい先ほど成田に朝便で戻りました。
と言う中・・・実は昨日、ラウンジにて日本語の公式ブログ、アップ予約させて頂いていたのですよね~(^^♪
是非、下記ご覧ください。
色々と国際情勢について云々している人がいますが・・・
聴いていて意味があるのは当事者だけですよ!
後は…傍観者、アウトサイダーです。評論は誰でも出来る。
http://haradatakeo.com/?p=57504
https://www.facebook.com/iisia.jp/posts/832953993442490
2015年03月08日
グローバル・アジェンダが創られる現場で立ち向かうには (連載「パックス・ジャポニカへの道」)
「グローバル・リーダーシップ」を語る我が国の有識者は数多くいる。しかし私の眼から見るとこれらの有識者たちはいずれもそれを誤解しているように思えてならない。
「グローバル・リーダーシップ」とはグローバル・コミュニティにおいて共通の課題をグローバル・アジェンダとして設定し、その解決のために実効性のあるイニシアティヴを発揮することだ。しばしば我が国の、特に製造業各社においては現地法人の拠点長として現地採用職員(Locally Hired Staff, LHS)を巧みに使える能力のことをグローバル・リーダーシップだと勘違いしている向きが多い。これは完全に間違っている。
グローバル・アジェンダはグローバル・コミュニティに対していわば「宿題」として広く遍く課される課題リストだ。一度設定されてしまうと全ての国が拘束される。無論、我が国もその例外ではない。したがってまずはこのグローバル・アジェンダを創り上げる作業に積極的に参画するのが「諸国民」にとっては死活問題になる。このこともまた我が国にあてはまることだ。
ところが事このことになると、不思議なほど我が国からグローバル・アジェンダを創り上げる現場に乗り込む者はほぼ皆無なのである。たいていの場合、米国や欧州からいわば”降って来る”のを口を開けて待っているだけなのだ。テレビや新聞などでいろいろと国際情勢について「専門家」「有識者」として見解を開陳している人々がいるが、彼らの中でこうしたグローバル・アジェンダを自らの手で創り上げている者は全くいない。いや、国際社会に一歩出ればどんな「有名人」であってもたちまち”Who are you?”といわれるのがオチなのである。哀しいがこれが現実だ。
しかし嘆いてばかりいても状況は全く変わらない。私自身、これまで多くの国際的なフォーラムを行脚してきたが、この春からこれまでとは次元の違う現場に出席することした。「B20」である。
「B20」とは我が国ではほとんど聴くことのできないフォーラムである。これは政府間会合であるG20を支えるグローバル・ビジネス・コミュニティであり、そこでの議論を通じて決定される勧告(recommendations)の実に3分の1がG20、すなわち政府レヴェルで採用されてきたという実績を持つ。そしてひとたびG20で決まれば、これがG8サミットとも連動し、最終的には我が国を含めた世界各国がこれに拘束されるというわけなのである。その意味でB20こそ、グローバル・アジェンダの「源流中の源流」といっても過言ではない。

6日(イスタンブール時間)、私が属するB20「中小企業・アントレプレナーシップ」タスクフォースがキックオフ会合をトルコ・イスタンブールで開催するというので1泊3日の強行軍で参加してきた。現場には議長国トルコの経済・金融関係者を筆頭に50名近くのメンバーが出席しており、それと同時に30名ほどのメンバーが電話会議の形でオンライン出席していると聞いた。議論は実に3時間余りも続けられた。
我が国では「中小企業・アントレプレナーシップ」と聞くと余りピンと来ないかもしれない。しかしグローバル・アジェンダという観点では並み居るグローバル・カンパニー(大企業)たちよりも、倒れ掛かっている世界経済の成長を支える存在としてむしろ元気のある、出来たばかりの中小企業(Small- and Middle Sized Enterprise=SME)、しかもエマージング・マーケットのそれには大きな期待がかけられているのである。これまでB20はどちらかというと大規模なグローバル・カンパニーによる議論の場という色彩が強かった。だが、今年(2015年)の議長国トルコがそこにメスを入れたのである。そして鳴り物入りで創られたのが今回、私が所属することになった分科会であったというわけなのである。
議論は非公開であるのでここでは残念ながらその詳細を明らかに出来ないことをお赦し頂きたい。だが非常に気になったのがそもそも議論のたたき台を提供する「ナレッジ・パートナー(knowledge partner)」の役割を務めていたグローバル・コンサルティング・ファーム「アクセンチュア」の面々であった。実はこれら「アクセンチュア」の面々は実効力のあるグローバル・アジェンダの現場には必ずといって良いほど登場する。つまりところ変われど、黒子は皆一緒というわけなのである。グローバル・アジェンダがどのようにして創られているのかを知る際の大きなポイントである(ちなみにここでいう「アクセンチュア」とは日本法人を含んでいない。同名ではあってもプロセスとしては完全に疎外されていると聞いた)。
また議論の現場は正に「白兵戦」であった。積極的に発言する者は次々に指名され、その発言がナレッジ・パートナーによって記録されていく。つまり「力」ではなく、「知恵」そして「コミュニケーション能力」がモノを言う場なのである。複数回にわたり当然のように発言の機会を得る者がいる一方で、終始沈黙を続けていた者もいた。ただし、これらの者たちも少なくとも最終的には一票を入れる権利を持っているという意味では「選ばれし者」なのであるが。

かくいう私自身は、そもそも設定された「枠組み」に抜けがあるのではないかとの指摘をしておいた。「中小企業・アントレプレナーシップ」だからといってファイナンスや規制緩和の話ばかりをするが、特に製造業(manufacturing)という意味での中小企業にとって重大なのはより安くて持続可能なエネルギーをいかにして確保出来るかなのである。そのための優遇措置こそ設けられるべきである。どうも議論が「平時」ばかりを念頭に置いて行われているように見受けるが、東日本大震災(2011年)という激甚災害を経験した我が国だからこそ、「非常時」に何が起きるかを議論すべきだということを言っておきたい。気候変動(climate change)がグローバル社会における共通課題であり、それによって様々な大規模自然災害が起きていることを考えれば、今こそそうした議論が必要である。―――そう、私からは述べておいた。他の出席者たちが神妙な面持ちで聴いていたのが実に印象的であった。
議論はこの後、3月末に再び電話会議が行われ、4月には米ワシントンにて、そして6月には仏パリにて他の分科会との合同会合が開催されるといった形で続いていく。無論、私もこの源流中の源流にいることを許された事実上、唯一の日本人としてこうしたプロセスの中で大いに「暴れていく」つもりである。
世界は決して止まってなどいない。音を立てて動いている。その中で行われ続けている「未来」に向けての秩序形成にいかにして積極的に参画し、リードしていくのか。「パックス・ジャポニカ(Pax Japonica)」への道のりは今、始まったばかりである(なお、ちなみに来年(2016年)「G20=B20」の議長国は中国である。私たちがそこでのグローバル・アジェンダの形成に無関心であってはならない理由が正にここにある)。
2015年3月7日 トルコ・イスタンブールにて
原田 武夫記す
グローバル・アジェンダが創られる現場で立ち向かうには (連載「パックス・ジャポニカへの道」)
http://haradatakeo.com/?p=57504
http://haradatakeo.com/?p=57495
ここで決められたことが G20, G8 へと流れ、世界のルールになっていきます。
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/6d8a6aa08d5f1c13672d0f639a9dfbf3
想うのですが・・・「時が止まってしまった」ように感じませんか??
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/b87c8634bb2856fb7c9005126b44ff60
http://blog.goo.ne.jp/nobody-loves-you/e/d9679525ad8c7896e2efbf99bc81978e













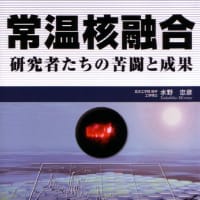





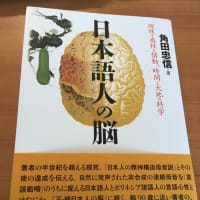
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます