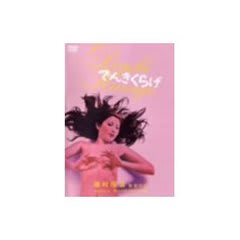園子温監督「恋の罪」を観た。
「恋の罪」などという思わせぶりなタイトルに、それが話題の監督園子温ならさぞかし女性の情感を巧みに描いてくれるのだろうと思っているのか、あるいはおそらくはじめて観るだろうR18+の映画という設定も、少し冒険してみたい気分と共振するからなのか、テアトル新宿の座席は満席で、しかも三分の一強は女性で占められていた。まるでネオンに群がる艶やかな蛾のようであり、それはそれで製作者のねらいどおりだったのかもしれない。だが、すでに日活ロマンポルノを体験している者にとっては、「恋の罪」はその延長線上の映画にすぎないし、何でもありのロマンポルノでは、こうしたエログロ・サイコサスペンスも珍しくはなかった。ならば、2時間20分という上映時間は、それだけで何か大作めいてはいるのだが、せいぜい90分にまとめられてしかるべきだろう。
冒頭の水野美紀の“インモーアル”ヌードにはじまり、主演の神楽坂恵、富樫真の3女優がいずれも裸体・インモーを晒す近頃珍しい映画で、その点は日頃「脱げなきゃ女優ではない」とおっしゃる園監督の面目躍如というところと、喝采を送りたい。だが、ここにはタイトルどおりの恋の罪など描かれていないし、少し日常を変えてみたい、危険な恋もしてみたいくらいの気持ちでこの映画に接した女性は、果たしてどんな思いで映画館を後にしたのかきいてみたいものだ。
スクリーンに映し出されるのは、男性の性のはけ口としての女体であり、性の喜びとは無縁の裸体と堕落の証しとしてのまぐわい、そして無残に切り刻まれ腐乱した女性の死体である。夫の後輩と浮気する女刑事、几帳面な夫に従順に尽くす作家の妻、昼は大学の助教授、夜は円山町の街娼である良家の女、そしてその母、いずれもがいささか劇画チックに描かれ、「服従させ・される」男女関係の中の女として立ち振る舞う。やがてこれは、東電OL殺人事件に着想を得たリアルな物語などではなく、現実を誇張したエログロ・サイコな戯画の体裁をとる極めて観念的な、言葉はいかにして肉体化できるかなどといったテーマを含む観念劇なのだと理解したくなるだろう。思うに富樫真演じる街娼のイメージはバタイユの「マダム・エドワルダ」に着想を得ているのではあるまいか。そしてスクリーンの表層にうごめく裸体など、実はどうでもよく、言葉として語られる「城」、決して行きつけない、周縁をまわり続けるしかない城に象徴されるもの、それが何かは分からないが、おそらくそういうものをこの映画のテーマにしたいのだろう。70年代風に言えば、都市の聖なる空間である皇居という「城」に、俗の象徴である円山町のアパートの「城」を対峙させ、現代の虚無を描いた物語とでもなるだろうか。
物語は、円山町という都市の異空間の磁力が3人の女を引き寄せながら展開する。フランツ・カフカの「城」が引用され、あたかも円山町、とりわけ廃墟のような安アパートが城であるかのように提示され、3人の女とそれをめぐる男たちが、その周縁をめぐっていく。街娼の女助教授は、毎日、安い料金で男とまぐわい、堕落の底を探る果てしない旅を続けている。そして金銭を介在させることで性は自由を勝ち取ることができると、堕落の入り口にいる作家の妻を堕落の深みへと誘うのである。作家の妻と街娼の女助教授が出会うのは、退屈な日常からAV撮影にかかわったことで女性性に目覚めた作家の妻が、円山町のホテルで地元のポン引きに弄ばれ後悔して彷徨っているときだった。作家の妻にとって、異彩を放つ街娼の女性性を無化するふるまいは驚愕であり、その強力な磁場に引き寄せられるのだった。街娼が向かうのは円山町の廃墟のような安アパートであり、これこそ城であると街娼はいうのである。そして、肉体を無化するまぐわいによって街娼は限りなく自由と虚無を手に入れるのだろう。
だが、こう読めばまるでダークファンタジーとして成功を収めているかに見えるが、過剰なまでの音楽や演技、使い古されたサイコ・サスペンス的な展開では、到底現代の虚無などにたどりつけない。
物語のプロットなど通俗的でかまわないとはいえ、あまりに意匠が古すぎる。この物語のコアである、街娼に堕落した女助教授も、父との近親相姦的な関係が示唆され、それに嫉妬し父の血を呪う厳格な母という、結局は家や幼児体験が歪んだ人格をつくり出したという解決の仕方であって、これでは特殊な事情を持つ異常な人間を描いたにすぎなくなってしまう。とりわけその母の異常ぶりによってよくあるサイコ・サスペンスとしての物語が補強され、それはあたかも物語の中心を放棄するふるまいであるかのようだ。だから、本来女助教授の鏡として機能すべき作家の妻の存在が宙に浮く。まだ堕落の入り口にあった作家の妻が、女助教授の堕落ぶりに魅了されるのは、同じ日常性を持っている女性がこうも変化できることへの憧憬があるからだ。だが、単なる異常者では、作家の妻がやがて同じ道を歩んでいくことの必然性へとつながらない。中心が陳腐化することで、中心としての意味を失えば、罪と知りつつSな浮気相手の無理強いを拒否できない女刑事の存在はいったい何なのか。女刑事がこの事件から何を得たのかが全く伝わらない。間に合わなかったゴミ収集車を追いかけたまま失踪してしまった主婦のエピソードをなぞるように、ラストでゴミ収集車を追いかける女刑事がたどりつくのは円山町なのだが、これは女刑事そのものが世界の迷宮に迷い込み、また入口に戻ったという城の物語の表明なのだろうか。少なくとも街娼という非日常を抱えた女が殺されたこととの関係で女刑事の不倫のその後が語られなければ、女刑事の存在そのものがただのサスペンス仕立ての道具にすぎなくなってしまう。
おもわせぶりなタイトルと同様、港町に流れ着いた作家の妻が港で子供に放尿してみせるシーンの意味は何なのか。妻は、港町の街娼に身をやつすのだが、ショバの仁義を無視してヤクザのリンチにあい、道ばたに寝ころびながら「言葉なんかおぼえるんじゃなかった」という田村隆一の詩の一節をつぶやいて映画は終わる。
この映画が着想を得たであろう「東電OL殺人事件」を書いた佐野真一さんの目的は、犯人に仕立てられたゴビンダさん救済だったが、当然ながら殺されたOLの心の闇に迫ろうとした。しかし、あまりの闇の深さにたじろぎながらも、安易にその理由を家庭環境に求めて解決しようとしなかった。それを思うとこの映画の陳腐な解決の仕方は、カフカの城も田村隆一の詩も、単なる思わせぶりな装置や道具にしか感じられないのだった。
「恋の罪」などという思わせぶりなタイトルに、それが話題の監督園子温ならさぞかし女性の情感を巧みに描いてくれるのだろうと思っているのか、あるいはおそらくはじめて観るだろうR18+の映画という設定も、少し冒険してみたい気分と共振するからなのか、テアトル新宿の座席は満席で、しかも三分の一強は女性で占められていた。まるでネオンに群がる艶やかな蛾のようであり、それはそれで製作者のねらいどおりだったのかもしれない。だが、すでに日活ロマンポルノを体験している者にとっては、「恋の罪」はその延長線上の映画にすぎないし、何でもありのロマンポルノでは、こうしたエログロ・サイコサスペンスも珍しくはなかった。ならば、2時間20分という上映時間は、それだけで何か大作めいてはいるのだが、せいぜい90分にまとめられてしかるべきだろう。
冒頭の水野美紀の“インモーアル”ヌードにはじまり、主演の神楽坂恵、富樫真の3女優がいずれも裸体・インモーを晒す近頃珍しい映画で、その点は日頃「脱げなきゃ女優ではない」とおっしゃる園監督の面目躍如というところと、喝采を送りたい。だが、ここにはタイトルどおりの恋の罪など描かれていないし、少し日常を変えてみたい、危険な恋もしてみたいくらいの気持ちでこの映画に接した女性は、果たしてどんな思いで映画館を後にしたのかきいてみたいものだ。
スクリーンに映し出されるのは、男性の性のはけ口としての女体であり、性の喜びとは無縁の裸体と堕落の証しとしてのまぐわい、そして無残に切り刻まれ腐乱した女性の死体である。夫の後輩と浮気する女刑事、几帳面な夫に従順に尽くす作家の妻、昼は大学の助教授、夜は円山町の街娼である良家の女、そしてその母、いずれもがいささか劇画チックに描かれ、「服従させ・される」男女関係の中の女として立ち振る舞う。やがてこれは、東電OL殺人事件に着想を得たリアルな物語などではなく、現実を誇張したエログロ・サイコな戯画の体裁をとる極めて観念的な、言葉はいかにして肉体化できるかなどといったテーマを含む観念劇なのだと理解したくなるだろう。思うに富樫真演じる街娼のイメージはバタイユの「マダム・エドワルダ」に着想を得ているのではあるまいか。そしてスクリーンの表層にうごめく裸体など、実はどうでもよく、言葉として語られる「城」、決して行きつけない、周縁をまわり続けるしかない城に象徴されるもの、それが何かは分からないが、おそらくそういうものをこの映画のテーマにしたいのだろう。70年代風に言えば、都市の聖なる空間である皇居という「城」に、俗の象徴である円山町のアパートの「城」を対峙させ、現代の虚無を描いた物語とでもなるだろうか。
物語は、円山町という都市の異空間の磁力が3人の女を引き寄せながら展開する。フランツ・カフカの「城」が引用され、あたかも円山町、とりわけ廃墟のような安アパートが城であるかのように提示され、3人の女とそれをめぐる男たちが、その周縁をめぐっていく。街娼の女助教授は、毎日、安い料金で男とまぐわい、堕落の底を探る果てしない旅を続けている。そして金銭を介在させることで性は自由を勝ち取ることができると、堕落の入り口にいる作家の妻を堕落の深みへと誘うのである。作家の妻と街娼の女助教授が出会うのは、退屈な日常からAV撮影にかかわったことで女性性に目覚めた作家の妻が、円山町のホテルで地元のポン引きに弄ばれ後悔して彷徨っているときだった。作家の妻にとって、異彩を放つ街娼の女性性を無化するふるまいは驚愕であり、その強力な磁場に引き寄せられるのだった。街娼が向かうのは円山町の廃墟のような安アパートであり、これこそ城であると街娼はいうのである。そして、肉体を無化するまぐわいによって街娼は限りなく自由と虚無を手に入れるのだろう。
だが、こう読めばまるでダークファンタジーとして成功を収めているかに見えるが、過剰なまでの音楽や演技、使い古されたサイコ・サスペンス的な展開では、到底現代の虚無などにたどりつけない。
物語のプロットなど通俗的でかまわないとはいえ、あまりに意匠が古すぎる。この物語のコアである、街娼に堕落した女助教授も、父との近親相姦的な関係が示唆され、それに嫉妬し父の血を呪う厳格な母という、結局は家や幼児体験が歪んだ人格をつくり出したという解決の仕方であって、これでは特殊な事情を持つ異常な人間を描いたにすぎなくなってしまう。とりわけその母の異常ぶりによってよくあるサイコ・サスペンスとしての物語が補強され、それはあたかも物語の中心を放棄するふるまいであるかのようだ。だから、本来女助教授の鏡として機能すべき作家の妻の存在が宙に浮く。まだ堕落の入り口にあった作家の妻が、女助教授の堕落ぶりに魅了されるのは、同じ日常性を持っている女性がこうも変化できることへの憧憬があるからだ。だが、単なる異常者では、作家の妻がやがて同じ道を歩んでいくことの必然性へとつながらない。中心が陳腐化することで、中心としての意味を失えば、罪と知りつつSな浮気相手の無理強いを拒否できない女刑事の存在はいったい何なのか。女刑事がこの事件から何を得たのかが全く伝わらない。間に合わなかったゴミ収集車を追いかけたまま失踪してしまった主婦のエピソードをなぞるように、ラストでゴミ収集車を追いかける女刑事がたどりつくのは円山町なのだが、これは女刑事そのものが世界の迷宮に迷い込み、また入口に戻ったという城の物語の表明なのだろうか。少なくとも街娼という非日常を抱えた女が殺されたこととの関係で女刑事の不倫のその後が語られなければ、女刑事の存在そのものがただのサスペンス仕立ての道具にすぎなくなってしまう。
おもわせぶりなタイトルと同様、港町に流れ着いた作家の妻が港で子供に放尿してみせるシーンの意味は何なのか。妻は、港町の街娼に身をやつすのだが、ショバの仁義を無視してヤクザのリンチにあい、道ばたに寝ころびながら「言葉なんかおぼえるんじゃなかった」という田村隆一の詩の一節をつぶやいて映画は終わる。
この映画が着想を得たであろう「東電OL殺人事件」を書いた佐野真一さんの目的は、犯人に仕立てられたゴビンダさん救済だったが、当然ながら殺されたOLの心の闇に迫ろうとした。しかし、あまりの闇の深さにたじろぎながらも、安易にその理由を家庭環境に求めて解決しようとしなかった。それを思うとこの映画の陳腐な解決の仕方は、カフカの城も田村隆一の詩も、単なる思わせぶりな装置や道具にしか感じられないのだった。