説明的なセリフやナレーション、過剰な感情表現の演技があふれる環境の中で、ブレッソンの映画を観ることは禊のような体験なのだった。





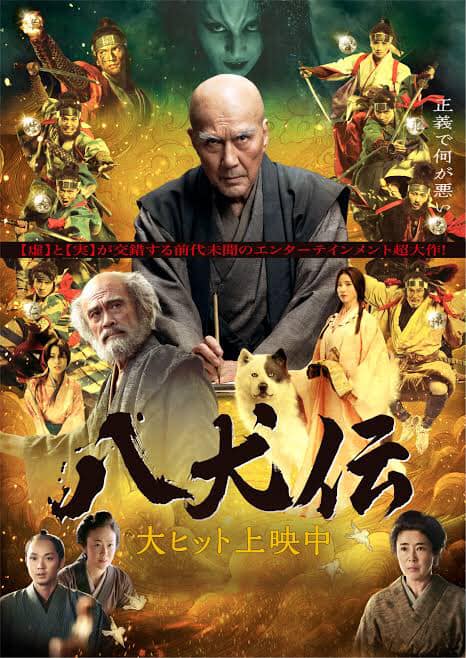




もうだいぶ前の話になるが、昨年末にテアトル新宿(だったかな)でアキ・カウリスマキの映画復帰作「枯れ葉」を観た。あまり大きなスクリーンではない上に、スタンダードサイズだったので、座る位置を間違えたと思ったのだが、さえない男女のほっこりするラブストーリーと、カウリスマキ節の健在ぶりに大いに気をよくした。ラジオから「竹田の子守歌」が日本語で流れてきたり、ハッピーエンドなラストがトリュフォーの「夜霧の恋人たち」を思わせる82分、至福の時間だった。


昨年の映画鑑賞の締めになったのがTOHOシネマ新宿で観たケリー・ライカート監督「ファースト・カウ」。西部開拓時代のオレゴンの先住民居住区が舞台。冒頭、画面の右から左へコロンビア川をゆっくりと航行する貨物船のショットできっと良い映画であると妙に確信を持った通り、少ない会話の物語を無駄のない適切なショットで組み立てていく監督の手腕に脱帽した。

中国からの移民の男ルーと、栗鼠の毛皮猟師グループの料理人だった男クッキーの二人が偶然知り合い、二人で地主が飼う、土地唯一の牛の乳を搾り盗んでドーナツを作って販売し、一儲けするという展開なのだが、二人が次第に心を通わすきっかけになるシーンがある。ルーの小屋に同居するようになったクッキーが、庭で薪割りをしているルーを窓越しに眺めているところを、カメラはクッキーの背中を手前にして納める。クッキーはしばらく薪割りを眺めているのだが、思い立って箒を取り出し家の中を掃き出すのである。これがワンショットで納められていて、ここから二人の距離がぐっと接近していくのだが、言葉や説明でなく、箒で掃くという日常的なアクションでそれを示したところが、実に映画的なのだった。この映画もスタンダードサイズだった。


気は早いが、三宅唱監督「夜明けのすべて」、ビクトル・エリセ監督「瞳をとじては」それぞれ邦画、洋画の2024年映画ベスト3に入ると断言しておく。
邦画は黒沢清監督のフランスで撮った新作が期待されるし、洋画は今後何が公開されるか分からない。それでもエリセが31年ぶりに撮った映画を無視できるわけもない。また、今日本映画界で三宅監督ほど「映画」を撮れる監督がいるだろうか。
「夜明けのすべて」も「瞳をとじて」もどちらもまなざしとみつめあうことの映画と言ってよい。みつめあう瞳と瞳をカメラは同時に写すことはできないという映画の宿命に挑んでいるのがこの2作だといえる。
「夜明けのすべて」で、いつも視線の交わらぬ横並びで画面に収まる山添君と藤沢さんが、山添君のアパートの入り口で初めて瞳を交わすショットがある。これをきっかけに二人の距離が近づいていくという重要な場面なのだが、二人を横からとらえたカメラは、一旦帰りかけた藤沢さんが振り向いて山添君に近寄りみつめあうというアクションとして映像化したみせる。生きづらさを抱える二人がお互いの支えを認め合う場面を、これほどさりげなく描ける監督はそうはいない。「カムカム」のコンビが素晴らしい。


「瞳をとじて」は文字通りまなざしの映画である。その意味は、いささか複雑な構造をもっているが、この映画では、元映画監督ミゲルが21年前に撮った映画「別れのまなざし」の映像、ミゲルの妄想シーン、「別れのまなざし」の主役で失踪したフリオを探す本編の映像というように三つの映像から成り立っている。それぞれが主題や物語の背景を補完し合うような関係にあるのだが、本編は徹底したバストアップの切替しショットによる会話シーンを中心に構成されている。後半、物語が一気に動き出すと、画面が躍動する。白いシーツがなびく中を移動カメラがくぐり塔の白壁を塗る二人の男をとらえるショットやミゲルと並んで男が海をみつめるショットが美しい。
そして「別れのまなざし」のラストシーンが古い映画館で上映されると、「別れのまなざし」の登場人物の瞳とそれをみつめるミゲルたちの瞳と、さらに私たち観客の瞳が交差しみつめ合う感動的なラストで映画は閉じる。映画の冒頭は、「別れのまなざし」の冒頭シーンで始まり、庭園のヤヌス像が映し出される。瞳を交わさないこの像は、物語の始まりと終わりの象徴として、私たちを「まなざし」の物語へと導く。しかし、私たちは最後にエリセの仕掛けた罠に、まなざしの共犯者として心地よく参加することになるだろう。

