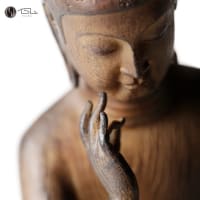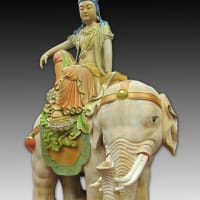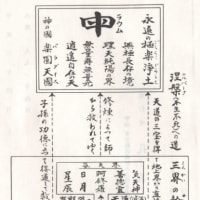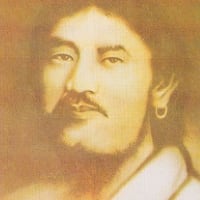2016-05-23 16:59:47
テーマ:日本の文化

古代イスラエルのユダ族(またはエフライム族)を祖とする日本最大の豪族であった秦氏、そしてその子孫と思われる秦、旗、波田、羽田、畑、端、幡多、波多、畠、幡、旛、波多野、秦野、畑野、幡野、籏野、旗野、畑中、畑山、木幡、小畑、古畑、降旗、古旗、津秦、中畑、大畑、高畑、高畠などの苗字についてはすでに紹介した。ユダ族は、ダビデ王を起点としたユダヤの王族である。今日はそれら以外の苗字、地名をご紹介したい。
「ひえだ(稗田、日枝、冷田、日江田)」「ひゅうが(日向)」「八重(やえ)」もユダ(族)から来ているとされる。日枝神社もユダ族の神社ということになる。

日枝神社
英語でユダヤ人を指す「ジュー(Jew)」も「ユダ」から来ている。さらに「ひえだ」から派生したのが「飯田」「用田」「夕田」「大田」「岩田」「岩手」「岩戸」ではなかったか。
古代イスラエルから司祭の役目を司るレビ族であるが、「良比(らび)」「日比(ひび)」はその末裔であるとされる。「賀茂」もレビ族と言われる。鰐、和仁、和邇、鰐川、鰐口、鰐洲、鰐石、鰐田、鰐部など「わに」のつく苗字は、北九州八幡付近に存在したとみられる伊都国の鰐(バニ)族の子孫と言われるが、鰐族はレビ族の末裔と考えられている。鰐というが、日本列島に実際にワニがいたわけではない。どこか南方から輸入した言葉ではなかったか。
卑弥呼時代の日本のガド族の長は「那古(なこ)」と言ったが、千葉県館山市に「那古」という地名が残っている。「なごや(那古屋、名古屋)」も同じ由来。千葉県の「上総(かずさ)国」、千葉県銚子市の「三門町」、東金市の「御門(みかど)」、山口県の「長門(ながと)」、富山県の「久戸(ぐと)」もガド族から来ているのではないか。天皇家の出自については諸説あり、エフライム族であるという説と、初代神武天皇はエフライム族だったが、日本に渡来した10代崇神天皇以降は系統が入れ替わりガド族になったという説がある。天皇のことを「ミカド」というが、これはヘブライ語で「ガド族の出自」という意味であるというのがその論拠である。
なお、旧約聖書によれば、ガド族の子孫からゼポン人の氏族が出たとされる。そしてこの「ゼポン」がなまって中国語の「日本(ジーベン)」となり、それが日本語の「ニッポン」や英語の「ジャパン」になったのではないか。
そしてダン族。「だん(弾、団、壇、弾、談、旦)」「たん(谷)→たに」という名字は、ダン族の末裔である可能性が高い。レビとダンを一緒にして「日比谷(ヒビタン→ヒビヤ)」。
次にイサカル族。「飯盛(いさかり)」「井坂」「坂」「石狩」「然別(しかりべつ)」はイサカル族に由来すると考えられる。青森の地名や苗字である「津軽(つがる)」もイサカルの「サカル」を取ったらしい。長野県の「軽井沢(かるいざわ)」も「イサ」と「カル」が倒置したものと考えられる。
ナフタリ族であるが、「田利(たり)」「ひなた(日向、日名田)」がその影響。「南部(なんぶ)」もナフタリ族の「ナフ」を取ったものと思われる。「新田(にった)」は古くは「にふた」と読まれており、「名久田(なくた)」と合わせて、ナフタリ族の流れと思われる。「ナフタリ」とはもともとヘブライ語で「イノシシ」の意味である。青森の「ねぶた」も「ナフタリ」から来ているらしい。

ねぶた祭り
次にマナセ族だが、「まなせ(曲直瀬、真瀬、間名瀬)」「まの(真野、間野、目野)」はマナセ族とされる。福岡の「宗像(むなかた)神社」であるが、これは「マナセ」と「カド」と一緒に祭った神社ではないか。

宗像神社
また古代、朝鮮半島南部の任那(みまな)に日本府(大和朝廷の出張所)があったというが、この「みまな」は「マナセ族の出自」という意味である。マナセ族は北東インドを経て渡来した可能性が高い。
薩摩島津家の家紋の十文字は、ルベン族の紋章と同じである。源頼朝とルベン族との間にもうけられた男子が島津氏となったのではないかと言われている。「阪(べん、さか)」もルベン族の末裔と言われる。

次にエフライム族。「良井(らい)」はエフライムの「ライ」を取ったとみられる。ユニコーンはエフライム族のシンボルである。「足利」「足尾」「足柄」「足寄(あしょろ)」「芦別」「尻別」「網走」「奥尻」「橋(はし)」などの地名・姓名はアシェル族から来ていると言われる。
また、「紅谷」「紅屋」「紅山」「屋見(やみ)」はベニヤミン族の末裔と言われ、「島(しま)」「住吉(すみよし)」「清水(しみず)」はシメオン族。住吉神社もこの系列である。また、「掘(ぼり)」「巽(すぶる)」はゼブルン族の子孫であると言われる。ゼブルン族はインド東部から航海して鹿児島に上陸したと言われている。
北海道の胆振(いぶり)国はヘブライ(人)、「渡島(おしま)国」はシメオン族、石狩国はイサカル族、釧路国はアシェル族、日高国はユダ族、十勝国はガド族、根室国はエフライム族、留萌(るもい)支庁はルベン族、と見事に古代イスラエルの部族ごとに配置されている。
アブラハムとはすべてのユダヤ人の祖である。

アブラハム
日本神道に古くから伝わる「神道五部書」中に「阿波羅波命(アハラハノミコト)」が出てくるが、これは「アブラハムのみこと」「アブラハム王」のことだと思われる。また、宮崎県の油津(あぶらつ)」、山形の油戸(あぶらと)、青森の油川(あぶらかわ)、福岡県の油山(あぶらやま)などはすべて「アブラハム」に由来するのではなかろうか。日本全国に「油」のつく地名は84か所あるという。「油(あぶら)」という言葉自体もここから出ているとも考えられる。いずれにしても、「油」のつく姓名・地名はこの由来である可能性が高い。
アブラハムの息子は「イサク」といい、その子孫がイサク族となった。鹿児島県の伊作(いさく)や全国各地にある「一色(いっしき)」はそこから来ていると考えられる。ヨセフはユダヤ人の祖であるヤコブの子であるが、「良須(よす)」「ひよし(日吉、日義)」はヨセフにちなんだと言われる。
「室(むろ)」「御室(おむろ)」はイスラエル北王国の首都ソムロンから来ていると言われている。「袋(だい、ふくろ)」はザブダイ族(ユダの支族)の由来と思われる。
それから以下の苗字はすべてそのままユダヤの苗字から来ていると思われる。「やない(柳井、箭内、矢内、梁井、谷内)」「いたい(板井)」「たや(田谷、田屋、多谷)」「さぎい(鷺井)」「しま(島)」「勝」(カッツ)「もりや(守屋、守谷、森谷、森屋)」「つりや(釣屋、釣谷)」、「宇治」、「秋葉」「吉屋」「三木」「菅(かん)」「古田(ふるた)」(フルダ)「子門(しもん)」「うるま(閏間、宇留間、漆間)」(ウルマン)。
以下の苗字はヘブライ語の意味を持つ。「山井」は「水夫」、「野井」は「庭」、「田丸」は「ナツメヤシ」、「砂井」は「リス」、「阿南(あなん)」は「雲」、「有江(ありえ)」は「ライオン」、「作内(さくない)」は「ペリカン」、「野賀」は「金星」、「あまみ(奄美、天海、天見)」は「大衆的な」、「渥美」は「自分自身」、「きた(北、喜多、喜田、木田)」は「教室」、「三田」は「ベッド」、「三井」は「抽出」、「あらい(荒井、新井)」は「一時的」、「とだ(戸田)」は「ありがとう」、「いかり(碇、猪狩、伊刈)」は「主要の」、「かいつ(海津)」は「夏」、「しば(芝、柴)」は「理由」、「松井」は「ありふれた」、「いとう(伊藤、伊東、井藤)」は「彼と」、「棚井」は「条件」という意味がある。さらに「羽村」「小野」「ささ(佐々、笹)」といった苗字は、どうやらヘブライ語の地名から来ているらしい。
AD