今から26年前の1984年7月、私が小学校5年の夏休みにロサンゼルス五輪が開催されました。私にとってこのロス五輪は、生まれて初めて日本選手団が夏季五輪で戦う姿を見る大会でした(ちなみに、記憶にある最初の冬季五輪は1980年のレークプラシッド五輪です)。というのも、1976年モントリオール五輪の時は如何せん3歳だったので、リアルタイムでは殆ど記憶にありません。小学校1年生だった1980年のモスクワ五輪は、日本選手団はソ連のアフガン侵攻に抗議して(というより政府の圧力で)ボイコットしました。
なので、私は生まれて最初の2回の夏季五輪は、日本選手団が活躍する姿を見ることが出来ませんでした。ただ、このロス五輪も、前回の報復で東側陣営の殆どの国がボイコットしたので、西側諸国を中心とした“片肺五輪”となり、まともな大会ではありませんでした。東西両陣営&全ての大陸が一同に揃った五輪を肉眼で初めて見るのは、中学3年の時の1988年のソウル五輪まで待たなければなりませんでした。我々の年代は、幼い頃に世界の真の実力を知らなかったので、ある意味不幸な世代なのかもしれません。
ただ、このソウル五輪も、キューバ、エチオピア、北朝鮮などがボイコットし、アパルトヘイト政策のため南アフリカも制裁措置を受けていたので参加してません。そのおかげで、ソウル五輪の陸上、ボクシング、レスリング、バレーボールなどは「真の世界一決定戦」とは呼べませんでした。なお、全ての国際オリンピック委員会(IOC)加盟国の参加が実現するのは、1996年のアトランタ五輪からです。
このロス五輪で私が最も応援したのは、男子バレーボールだった記憶があります。ちなみに私は、サウスポーで当時は珍しいジャンプサーブを操る杉本公雄が好きでしたね(徳永英明の「輝きながら」をバックに、富士フイルムのCMに出演していた選手です)。日本のバレーは男女とも1970年代が黄金時代でした。男子は1972年ミュンヘン五輪で優勝。女子は1974年世界選手権&1976年モントリオール五輪&1977年W杯を制覇し、世界三冠を達成しました。だが、日本バレーの黄金時代は、私が生まれる前、もしくは生まれて間もない頃なので、如何せんリアルタイムで見てないから殆ど記憶にありません。
なので、周りから「お前が生まれた頃の日本のバレーは、男女とも世界最強だった」と聞かされて育ちました。また、私が幼い頃に買ってもらった百科事典にも、ミュンヘン五輪で男子が優勝した写真がデカデカと掲載されていたので、小学5年生までは日本男子は本当に世界のトップクラスだと信じ込んでいました。実際に1980年代前半の日本男子は、1982年にアルゼンチンで開催された世界選手権では4位に入賞し、ニューデリーアジア大会でも優勝。翌1983年に東京で開催されたアジア選手権(兼・ロス五輪アジア予選)では中国と韓国にそれぞれフルセットの末に逆転勝利して優勝するなど、そこそこ実績はありました。そして、ロス五輪は東側諸国が多数ボイコットしたので、メディアはメダル獲得を規定路線のように煽ってました。
だが、今振り返ると、1980年代前半の日本男子が世界のトップクラスだと信じていたのは、サンタクロースの存在を信じるのと等しい行為だったと思います(笑)。というのも、ロス五輪の日本は過去最低の7位に終わりましたから。いくら7位入賞とはいえ、東側諸国が不参加なので惨敗もいいところです。日本は予選リーグでは、中国、イタリア、エジプトに3連勝して幸先の良いスタートを切ります。しかし、最終戦で、前田健(のちに、女子のイトーヨーカドー監督)が率いる新興勢力のカナダにまさかのストレートで惨敗。日本はカナダとイタリアと同じ3勝1敗で並ぶものの、セット率の差で両国を下回って予選リーグ3位に終わり、史上初めて準決勝進出を逃してメダルの夢は雲散霧消。さらに、大会中にドーピング問題も発生するなど、まさに踏んだり蹴ったりの結末でした。
あれほど煽っていた世間&メディアは、負けると一転してバッシング。ただ、気になったのは「ようやくモスクワの傷が癒えて復活したのに・・・」とメディアが表現していたことです。私はてっきり“メダル候補”の男子は、「モスクワ五輪はボイコットしたから日本はメダルを獲れなかった」という意味だと思ってました。一緒にカナダ戦をテレビ観戦していた父に事情を聞いたら愕然としましたね。というのも、モスクワ五輪は、日本男子が史上初めて予選敗退して五輪出場権を逃した事実を知りましたから。
最初それを聞いた時は本当に信じられませんでした。なにせ、日本はミュンヘン五輪で優勝していたのに、たった8年で砂上の楼閣の如く、あっけなく奈落の底に突き落とされた訳ですから。ただ、モスクワ行きを逃した事は世間一般にはあまり語られてません。今でもモスクワの日本男子は、「ボイコットによる不参加」として時々間違って伝えられてます。きっと、1970年代前半の成功体験がファンやメディアの記憶に鮮明に焼きついてるので、「無かったことにしたい過去」として扱われているからなのでしょう。なので、この事実を聞いた時の衝撃を例えるなら、「神州不滅」を信じ込んでいた軍国少年が、無条件降伏の玉音放送を聞かされた気持ちに等しいのかもしれません。
私はモスクワ五輪当時は小学校1年だったので、本大会は夏休みにテレビで見た記憶はあります。ただ、当時の私はあまりスポーツに興味がなかったし、如何せん日本選手が誰一人も参加してない大会だったので何となく見てました。せいぜい覚えているのは、ナディア・コマネチが個人総合で平均台の終盤の演技でぐらついた影響もあって、優勝を地元ソ連のエレナ・ダビドワに盗まれてしまい、激しい抗議で揉めたことぐらいでしょうか。ましてや、各競技の五輪予選のシステムや各国の勢力図なんて、幼かったのでもちろん全然知りません。
今考えると、私の知識不足というのもありましたが、生まれて最初の2回の五輪で日本選手団が活躍する姿を見たことが無かったので、男子バレーの実力を完全に見誤ってました。つまり、メディアが散々煽っていた「メダル候補」とか「世界のトップクラス」というのは、根拠が薄弱な神話だったということです。高さとパワーで見劣りした日本は、せいぜい世界のセカンドクラスでした。なので、ロス五輪のカナダ戦の惨敗は、二重にショックを受けました。
30年経った今、あらためて“日本男子バレーの黒歴史”として扱われている、モスクワ五輪世界最終予選に挑んだ代表チームを色々と調べてみると、ハッキリ言って負けるべくして負けた戦いだったと思います。敗因は、世代交代の完全な失敗、世界のさらなる大型化、そして新興勢力の台頭です。また、ルールの面でも、1977年に国際バレーボール連盟(FIVB)がラリーが続くことを目的に、ブロックのワンタッチをカウントしないルールを改正し、俊敏性で劣る大型チームに有利に傾きました。そして、日本リーグの非協力的な姿勢や協会の内紛も少なからぬ影響を及ぼしました。中でも、ミュンヘン五輪優勝監督の松平康隆が、同五輪以降、協会の要職から7年間も遠ざかったのが大きかったとも言われてます(その後の、松平の国際バレー界でのご活躍はご存知の通りです(苦笑))。
日本はモントリオール五輪では、準決勝で優勝したポーランドと2時間半にも及ぶ死闘の末にフルセットで敗れて2連覇が途絶えます。そして、キューバとの3位決定戦では主力選手を温存して若手主体で臨むものの、無気力な試合内容でストレートで惨敗。日本男子バレーは史上初めて五輪のメダルを逃しました。この敗因は、主力と控えの力量の差がありすぎる事を意味し、暗い未来を暗示しました。そして、獲れるはずだったメダルを逃した代償は、のちにたっぷりと支払うことになります。
1977年の地元開催だったW杯では、ミュンヘン五輪優勝メンバーの森田淳悟を復帰させるなど、梃入れを図って2位に入ります。しかし、時計の針を戻したような小手先なやり方では、大型化しつつある世界のバレーには通用するはずがありません。また、要となるセッターは、ベテランの猫田勝敏の後継者を必死で探すものの、アタッカーの信頼を得られず誰もが落伍。結局、「未だ猫田に及ばず」との理由で代表チームに残りますが、後継者育成の失敗は後に大きく響きます。そして、この頃から、イタリアやブラジルなど新興勢力が台頭。アジアにおいても中国と韓国が著しくレベルアップし、日本は地盤沈下しつつありました。翌1978年にその不安が現実となります。
1978年9月にイタリアで開催された世界選手権。キューバに1-3で敗れて1次リーグを2位で通過した日本は、2次リーグ(1次リーグの成績は持ち越し)では、韓国とメキシコに勝利しますが、ポーランドにフルセットで、チェコスロバキアにはストレートで敗戦。この結果、2勝3敗で6チーム中5位に終わり、9-12位決定予備戦で戦う事を余儀なくされます。そこでも、日本は東ドイツに1-3で敗れ、格下メキシコには勝ちますが1セット失うなど惨憺たる内容と結果に終わり、日本は史上最低の11位に終わります。12月のバンコクアジア大会でも、日本は韓国には勝利するものの中国に敗れてしまい、セット率の関係で優勝を韓国に奪われて2位に終わり、大会連覇も5で途絶えます。
翌1979年12月にバーレーンで開催されたアジア選手権。この大会はモスクワ五輪アジア予選を兼ねており、優勝国に五輪出場権を与えられました。しかし、日本は決勝リーグで韓国に幸先よく2セット先取するものの、第3セット以降は守勢に回って浮き足立ってしまい、大逆転負け。モスクワへの切符獲得が一気にピンチに立たされます。しかも、韓国には過去13戦全勝でしたが、敗れたのはこれが史上初めてだったので、将来を考慮しても日本は甚大な打撃を被りました。そして、次戦の中国戦も1-3で逆転負けを喰らい、史上最悪のアジア3位に転落して中国がモスクワ五輪出場権を獲得。日本は2位韓国とともに世界最終予選に回る羽目になりました。アジア選手権終了後、日本協会の専務理事になったばかりの元監督の松平が「総監督」に就任。世界最終予選では、松平が中村祐造監督に代わって実質的に指揮を執ることになります。
翌月の1980年1月、ブルガリアで開催された世界最終予選。この予選は10チームが参加し、日本は1次リーグでチェコスロバキア、ルーマニア、韓国、ハンガリーと同じB組。一方、A組はブルガリア、米国、東ドイツ、カナダ、メキシコ。予選方式は、1次リーグで各組上位2位までが決勝リーグに進出。決勝リーグ4チーム中、2位までがモスクワ五輪の出場権を得られる大変厳しい予選方式でした。また、1次リーグの成績は決勝リーグに持ち越すルールでした。このルールが、日本に微妙な影を落とします。ただ、この予選の日本の勝算は極めて低いと思われてました。やはり、世代交代が遅々として進んでなかったのが大きかったです。翌月の誕生日で36歳の猫田、同じく2月の誕生日で32歳の大古誠司、29歳の西本哲雄のミュンヘン組がレギュラーとして名を連ねているのが何よりの証拠です。
そして、この予選で日本は更なる惨状を呈します。日本は、初戦のチェコスロバキアは2-3で逆転負け。2戦目のルーマニア戦も1-3で落として連敗を喫し、この時点で自力での五輪出場権獲得が消滅。アジア選手権の時と同様に逆転負けの悪癖を繰り返します。また、いずれの試合も、日本のスパイクは高いブロックに跳ね返され、逆に相手のスパイクはブロックの上を素通りされるなど、欧州勢の高さとパワーに完敗。日本では高かった195cmの田中幹保が平凡の体格に見えたほどでした。しかも、この組はルーマニアが独走状態でした。1次リーグの成績を持ち越すルールなので、ルーマニアに負けた日本はなるべくセットを失わずに、決勝リーグを含めた残り試合を全勝する必要が生じ、絶体絶命の状態に追い詰められました。剣が峰に立たされた日本が3戦目で戦ったのは、アジア選手権で史上初の敗戦を喰らった韓国でした。
そして、ちょうど今から30年前の今日である1980年1月23日。日本は衰えを隠せなかった猫田らベテランを下げるなど、メンバーを大幅に若手に入れ替えて背水の陣で韓国戦に臨みます。しかし、気合が空転。なんと1セット目はたった11分間で失います。当時はサイドアウト制だったとはいえ、韓国に一方的に打ちまくられて、0-15と国際試合では珍しい無得点で落とします。徳俵に追い詰められた日本は、続く第2セットは猛反撃して13-8とリード。しかし、若さが裏目に出たのか、勝負所で精神的な弱さを露呈。なんとここから7連続失点を喰らって13-15と逆転され、立て続けに2セットを奪われました。そして、この時点で、セット率の関係で日本の1次リーグ3位以下が確定。試合終了を待たずして韓国に引導を渡された日本は、1964年東京五輪から続いていた五輪出場記録が4で途絶えました。
昨年11月のグラチャンバレーで日本は強豪ポーランドに接戦で勝利して3位に入り、1977年の地元開催のW杯以来、世界大会で32年ぶりとなるメダル獲得を果たしました。日本はこの大会では、イランとエジプトと対戦して接戦の末に勝利しました。ただ、日本はこの両国とは、今年9月の世界選手権で再び同組となります。日本は開催国イタリアとも同組なので、ホームアドバンテージが無いこの大会で世界における現在地や課題が浮き彫りになると思います。奇しくも、世界選手権の開催地は、32年前に奈落の底に突き落とされた同じ地であるイタリアなのも、何かの因縁を感じます。
ただ、現在のアジア王者の日本は、世代交代に関してはある程度成功していると思います。グラチャンでも分かるように、同等の国とは競り合って勝てるようになりました。しかし、ブラジルやキューバといった世界のトップクラスとは大きく水を開けられてます。なので、決して6チームしか参加してないグラチャンごときで満足はして欲しくないです。そして、五輪への道が絶たれた30年前と同じ道を辿らない為にも、代表チームの強化体制の充実やVプレミアリーグの活性化(=将来的なプロ化)に取り組むなど、しっかりと強化に邁進して欲しいです。
▼男子バレーボール・モスクワ五輪世界最終予選の日本の成績
・1次リーグB組
1980/01/20 ●2-3 チェコスロバキア
1980/01/22 ●1-3 ルーマニア
1980/01/23 ●2-3 韓国 ←この韓国戦の第2セットを落とした時点で、日本のモスクワ行きが消滅
1980/01/24 ○3-0 ハンガリー
(日本は1勝3敗で5チーム中4位で決勝リーグ進出を逃し、史上初の五輪予選敗退)
・モスクワ五輪世界最終予選の最終成績
1位・ブルガリア、2位・ルーマニア、3位・米国、4位・韓国
(ブルガリアとルーマニアがモスクワ五輪出場権を獲得)
【モスクワ五輪世界最終予選代表選手】(アジア選手権も同じメンバー)
☆大古誠司(サントリー)、☆猫田勝敏(専売広島)、小田勝美(新日鉄)、☆西本哲雄(専売広島)、花輪晴彦(日本鋼管)、岩月昇平(日本鋼管)、辻合真一郎(新日鉄)、田中幹保(新日鉄)、田中義紀(神戸製鋼)、岩田稔(新日鉄)、志水健一(松下電器)、山田修司(富士フイルム)
監督:☆中村祐造、総監督:松平康隆
☆=ミュンヘン五輪金メダリスト
松平はアジア選手権終了直後に総監督に就任。
・関連記事
男子バレーがアトランタ五輪出場を逃してから14年(上)
男子バレーがアトランタ五輪出場を逃してから14年(下)
名勝負数え歌Vol.11 「途絶えた記録(上)」
名勝負数え歌Vol.12 「途絶えた記録(下)」
女子バレーが史上初めて五輪のメダルを逃してから22年(上)
女子バレーが史上初めて五輪のメダルを逃してから22年(中)
女子バレーが史上初めて五輪のメダルを逃してから22年(下)
※アジア選手権(兼・モスクワ五輪アジア予選)の詳細の記録
モスクワ五輪世界最終予選の詳細の記録
モスクワ五輪の詳細の記録
【参考資料】読売新聞、朝日新聞、毎日新聞
なので、私は生まれて最初の2回の夏季五輪は、日本選手団が活躍する姿を見ることが出来ませんでした。ただ、このロス五輪も、前回の報復で東側陣営の殆どの国がボイコットしたので、西側諸国を中心とした“片肺五輪”となり、まともな大会ではありませんでした。東西両陣営&全ての大陸が一同に揃った五輪を肉眼で初めて見るのは、中学3年の時の1988年のソウル五輪まで待たなければなりませんでした。我々の年代は、幼い頃に世界の真の実力を知らなかったので、ある意味不幸な世代なのかもしれません。
ただ、このソウル五輪も、キューバ、エチオピア、北朝鮮などがボイコットし、アパルトヘイト政策のため南アフリカも制裁措置を受けていたので参加してません。そのおかげで、ソウル五輪の陸上、ボクシング、レスリング、バレーボールなどは「真の世界一決定戦」とは呼べませんでした。なお、全ての国際オリンピック委員会(IOC)加盟国の参加が実現するのは、1996年のアトランタ五輪からです。
このロス五輪で私が最も応援したのは、男子バレーボールだった記憶があります。ちなみに私は、サウスポーで当時は珍しいジャンプサーブを操る杉本公雄が好きでしたね(徳永英明の「輝きながら」をバックに、富士フイルムのCMに出演していた選手です)。日本のバレーは男女とも1970年代が黄金時代でした。男子は1972年ミュンヘン五輪で優勝。女子は1974年世界選手権&1976年モントリオール五輪&1977年W杯を制覇し、世界三冠を達成しました。だが、日本バレーの黄金時代は、私が生まれる前、もしくは生まれて間もない頃なので、如何せんリアルタイムで見てないから殆ど記憶にありません。
なので、周りから「お前が生まれた頃の日本のバレーは、男女とも世界最強だった」と聞かされて育ちました。また、私が幼い頃に買ってもらった百科事典にも、ミュンヘン五輪で男子が優勝した写真がデカデカと掲載されていたので、小学5年生までは日本男子は本当に世界のトップクラスだと信じ込んでいました。実際に1980年代前半の日本男子は、1982年にアルゼンチンで開催された世界選手権では4位に入賞し、ニューデリーアジア大会でも優勝。翌1983年に東京で開催されたアジア選手権(兼・ロス五輪アジア予選)では中国と韓国にそれぞれフルセットの末に逆転勝利して優勝するなど、そこそこ実績はありました。そして、ロス五輪は東側諸国が多数ボイコットしたので、メディアはメダル獲得を規定路線のように煽ってました。
だが、今振り返ると、1980年代前半の日本男子が世界のトップクラスだと信じていたのは、サンタクロースの存在を信じるのと等しい行為だったと思います(笑)。というのも、ロス五輪の日本は過去最低の7位に終わりましたから。いくら7位入賞とはいえ、東側諸国が不参加なので惨敗もいいところです。日本は予選リーグでは、中国、イタリア、エジプトに3連勝して幸先の良いスタートを切ります。しかし、最終戦で、前田健(のちに、女子のイトーヨーカドー監督)が率いる新興勢力のカナダにまさかのストレートで惨敗。日本はカナダとイタリアと同じ3勝1敗で並ぶものの、セット率の差で両国を下回って予選リーグ3位に終わり、史上初めて準決勝進出を逃してメダルの夢は雲散霧消。さらに、大会中にドーピング問題も発生するなど、まさに踏んだり蹴ったりの結末でした。
あれほど煽っていた世間&メディアは、負けると一転してバッシング。ただ、気になったのは「ようやくモスクワの傷が癒えて復活したのに・・・」とメディアが表現していたことです。私はてっきり“メダル候補”の男子は、「モスクワ五輪はボイコットしたから日本はメダルを獲れなかった」という意味だと思ってました。一緒にカナダ戦をテレビ観戦していた父に事情を聞いたら愕然としましたね。というのも、モスクワ五輪は、日本男子が史上初めて予選敗退して五輪出場権を逃した事実を知りましたから。
最初それを聞いた時は本当に信じられませんでした。なにせ、日本はミュンヘン五輪で優勝していたのに、たった8年で砂上の楼閣の如く、あっけなく奈落の底に突き落とされた訳ですから。ただ、モスクワ行きを逃した事は世間一般にはあまり語られてません。今でもモスクワの日本男子は、「ボイコットによる不参加」として時々間違って伝えられてます。きっと、1970年代前半の成功体験がファンやメディアの記憶に鮮明に焼きついてるので、「無かったことにしたい過去」として扱われているからなのでしょう。なので、この事実を聞いた時の衝撃を例えるなら、「神州不滅」を信じ込んでいた軍国少年が、無条件降伏の玉音放送を聞かされた気持ちに等しいのかもしれません。
私はモスクワ五輪当時は小学校1年だったので、本大会は夏休みにテレビで見た記憶はあります。ただ、当時の私はあまりスポーツに興味がなかったし、如何せん日本選手が誰一人も参加してない大会だったので何となく見てました。せいぜい覚えているのは、ナディア・コマネチが個人総合で平均台の終盤の演技でぐらついた影響もあって、優勝を地元ソ連のエレナ・ダビドワに盗まれてしまい、激しい抗議で揉めたことぐらいでしょうか。ましてや、各競技の五輪予選のシステムや各国の勢力図なんて、幼かったのでもちろん全然知りません。
今考えると、私の知識不足というのもありましたが、生まれて最初の2回の五輪で日本選手団が活躍する姿を見たことが無かったので、男子バレーの実力を完全に見誤ってました。つまり、メディアが散々煽っていた「メダル候補」とか「世界のトップクラス」というのは、根拠が薄弱な神話だったということです。高さとパワーで見劣りした日本は、せいぜい世界のセカンドクラスでした。なので、ロス五輪のカナダ戦の惨敗は、二重にショックを受けました。
30年経った今、あらためて“日本男子バレーの黒歴史”として扱われている、モスクワ五輪世界最終予選に挑んだ代表チームを色々と調べてみると、ハッキリ言って負けるべくして負けた戦いだったと思います。敗因は、世代交代の完全な失敗、世界のさらなる大型化、そして新興勢力の台頭です。また、ルールの面でも、1977年に国際バレーボール連盟(FIVB)がラリーが続くことを目的に、ブロックのワンタッチをカウントしないルールを改正し、俊敏性で劣る大型チームに有利に傾きました。そして、日本リーグの非協力的な姿勢や協会の内紛も少なからぬ影響を及ぼしました。中でも、ミュンヘン五輪優勝監督の松平康隆が、同五輪以降、協会の要職から7年間も遠ざかったのが大きかったとも言われてます(その後の、松平の国際バレー界でのご活躍はご存知の通りです(苦笑))。
日本はモントリオール五輪では、準決勝で優勝したポーランドと2時間半にも及ぶ死闘の末にフルセットで敗れて2連覇が途絶えます。そして、キューバとの3位決定戦では主力選手を温存して若手主体で臨むものの、無気力な試合内容でストレートで惨敗。日本男子バレーは史上初めて五輪のメダルを逃しました。この敗因は、主力と控えの力量の差がありすぎる事を意味し、暗い未来を暗示しました。そして、獲れるはずだったメダルを逃した代償は、のちにたっぷりと支払うことになります。
1977年の地元開催だったW杯では、ミュンヘン五輪優勝メンバーの森田淳悟を復帰させるなど、梃入れを図って2位に入ります。しかし、時計の針を戻したような小手先なやり方では、大型化しつつある世界のバレーには通用するはずがありません。また、要となるセッターは、ベテランの猫田勝敏の後継者を必死で探すものの、アタッカーの信頼を得られず誰もが落伍。結局、「未だ猫田に及ばず」との理由で代表チームに残りますが、後継者育成の失敗は後に大きく響きます。そして、この頃から、イタリアやブラジルなど新興勢力が台頭。アジアにおいても中国と韓国が著しくレベルアップし、日本は地盤沈下しつつありました。翌1978年にその不安が現実となります。
1978年9月にイタリアで開催された世界選手権。キューバに1-3で敗れて1次リーグを2位で通過した日本は、2次リーグ(1次リーグの成績は持ち越し)では、韓国とメキシコに勝利しますが、ポーランドにフルセットで、チェコスロバキアにはストレートで敗戦。この結果、2勝3敗で6チーム中5位に終わり、9-12位決定予備戦で戦う事を余儀なくされます。そこでも、日本は東ドイツに1-3で敗れ、格下メキシコには勝ちますが1セット失うなど惨憺たる内容と結果に終わり、日本は史上最低の11位に終わります。12月のバンコクアジア大会でも、日本は韓国には勝利するものの中国に敗れてしまい、セット率の関係で優勝を韓国に奪われて2位に終わり、大会連覇も5で途絶えます。
翌1979年12月にバーレーンで開催されたアジア選手権。この大会はモスクワ五輪アジア予選を兼ねており、優勝国に五輪出場権を与えられました。しかし、日本は決勝リーグで韓国に幸先よく2セット先取するものの、第3セット以降は守勢に回って浮き足立ってしまい、大逆転負け。モスクワへの切符獲得が一気にピンチに立たされます。しかも、韓国には過去13戦全勝でしたが、敗れたのはこれが史上初めてだったので、将来を考慮しても日本は甚大な打撃を被りました。そして、次戦の中国戦も1-3で逆転負けを喰らい、史上最悪のアジア3位に転落して中国がモスクワ五輪出場権を獲得。日本は2位韓国とともに世界最終予選に回る羽目になりました。アジア選手権終了後、日本協会の専務理事になったばかりの元監督の松平が「総監督」に就任。世界最終予選では、松平が中村祐造監督に代わって実質的に指揮を執ることになります。
翌月の1980年1月、ブルガリアで開催された世界最終予選。この予選は10チームが参加し、日本は1次リーグでチェコスロバキア、ルーマニア、韓国、ハンガリーと同じB組。一方、A組はブルガリア、米国、東ドイツ、カナダ、メキシコ。予選方式は、1次リーグで各組上位2位までが決勝リーグに進出。決勝リーグ4チーム中、2位までがモスクワ五輪の出場権を得られる大変厳しい予選方式でした。また、1次リーグの成績は決勝リーグに持ち越すルールでした。このルールが、日本に微妙な影を落とします。ただ、この予選の日本の勝算は極めて低いと思われてました。やはり、世代交代が遅々として進んでなかったのが大きかったです。翌月の誕生日で36歳の猫田、同じく2月の誕生日で32歳の大古誠司、29歳の西本哲雄のミュンヘン組がレギュラーとして名を連ねているのが何よりの証拠です。
そして、この予選で日本は更なる惨状を呈します。日本は、初戦のチェコスロバキアは2-3で逆転負け。2戦目のルーマニア戦も1-3で落として連敗を喫し、この時点で自力での五輪出場権獲得が消滅。アジア選手権の時と同様に逆転負けの悪癖を繰り返します。また、いずれの試合も、日本のスパイクは高いブロックに跳ね返され、逆に相手のスパイクはブロックの上を素通りされるなど、欧州勢の高さとパワーに完敗。日本では高かった195cmの田中幹保が平凡の体格に見えたほどでした。しかも、この組はルーマニアが独走状態でした。1次リーグの成績を持ち越すルールなので、ルーマニアに負けた日本はなるべくセットを失わずに、決勝リーグを含めた残り試合を全勝する必要が生じ、絶体絶命の状態に追い詰められました。剣が峰に立たされた日本が3戦目で戦ったのは、アジア選手権で史上初の敗戦を喰らった韓国でした。
そして、ちょうど今から30年前の今日である1980年1月23日。日本は衰えを隠せなかった猫田らベテランを下げるなど、メンバーを大幅に若手に入れ替えて背水の陣で韓国戦に臨みます。しかし、気合が空転。なんと1セット目はたった11分間で失います。当時はサイドアウト制だったとはいえ、韓国に一方的に打ちまくられて、0-15と国際試合では珍しい無得点で落とします。徳俵に追い詰められた日本は、続く第2セットは猛反撃して13-8とリード。しかし、若さが裏目に出たのか、勝負所で精神的な弱さを露呈。なんとここから7連続失点を喰らって13-15と逆転され、立て続けに2セットを奪われました。そして、この時点で、セット率の関係で日本の1次リーグ3位以下が確定。試合終了を待たずして韓国に引導を渡された日本は、1964年東京五輪から続いていた五輪出場記録が4で途絶えました。
昨年11月のグラチャンバレーで日本は強豪ポーランドに接戦で勝利して3位に入り、1977年の地元開催のW杯以来、世界大会で32年ぶりとなるメダル獲得を果たしました。日本はこの大会では、イランとエジプトと対戦して接戦の末に勝利しました。ただ、日本はこの両国とは、今年9月の世界選手権で再び同組となります。日本は開催国イタリアとも同組なので、ホームアドバンテージが無いこの大会で世界における現在地や課題が浮き彫りになると思います。奇しくも、世界選手権の開催地は、32年前に奈落の底に突き落とされた同じ地であるイタリアなのも、何かの因縁を感じます。
ただ、現在のアジア王者の日本は、世代交代に関してはある程度成功していると思います。グラチャンでも分かるように、同等の国とは競り合って勝てるようになりました。しかし、ブラジルやキューバといった世界のトップクラスとは大きく水を開けられてます。なので、決して6チームしか参加してないグラチャンごときで満足はして欲しくないです。そして、五輪への道が絶たれた30年前と同じ道を辿らない為にも、代表チームの強化体制の充実やVプレミアリーグの活性化(=将来的なプロ化)に取り組むなど、しっかりと強化に邁進して欲しいです。
▼男子バレーボール・モスクワ五輪世界最終予選の日本の成績
・1次リーグB組
1980/01/20 ●2-3 チェコスロバキア
1980/01/22 ●1-3 ルーマニア
1980/01/23 ●2-3 韓国 ←この韓国戦の第2セットを落とした時点で、日本のモスクワ行きが消滅
1980/01/24 ○3-0 ハンガリー
(日本は1勝3敗で5チーム中4位で決勝リーグ進出を逃し、史上初の五輪予選敗退)
・モスクワ五輪世界最終予選の最終成績
1位・ブルガリア、2位・ルーマニア、3位・米国、4位・韓国
(ブルガリアとルーマニアがモスクワ五輪出場権を獲得)
【モスクワ五輪世界最終予選代表選手】(アジア選手権も同じメンバー)
☆大古誠司(サントリー)、☆猫田勝敏(専売広島)、小田勝美(新日鉄)、☆西本哲雄(専売広島)、花輪晴彦(日本鋼管)、岩月昇平(日本鋼管)、辻合真一郎(新日鉄)、田中幹保(新日鉄)、田中義紀(神戸製鋼)、岩田稔(新日鉄)、志水健一(松下電器)、山田修司(富士フイルム)
監督:☆中村祐造、総監督:松平康隆
☆=ミュンヘン五輪金メダリスト
松平はアジア選手権終了直後に総監督に就任。
・関連記事
男子バレーがアトランタ五輪出場を逃してから14年(上)
男子バレーがアトランタ五輪出場を逃してから14年(下)
名勝負数え歌Vol.11 「途絶えた記録(上)」
名勝負数え歌Vol.12 「途絶えた記録(下)」
女子バレーが史上初めて五輪のメダルを逃してから22年(上)
女子バレーが史上初めて五輪のメダルを逃してから22年(中)
女子バレーが史上初めて五輪のメダルを逃してから22年(下)
※アジア選手権(兼・モスクワ五輪アジア予選)の詳細の記録
モスクワ五輪世界最終予選の詳細の記録
モスクワ五輪の詳細の記録
【参考資料】読売新聞、朝日新聞、毎日新聞
















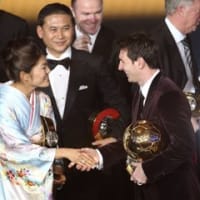


やはり松平監督がミュンヘンにピークを持って来る計画を立てて見事に取ったものの、その
ツケとして戦力の断層ができてしまったようです。
とはいえ問題は協会が それを放置して臨んだためモスクワ以降の低迷に繋がるのですが、77年のW杯でミュンヘン組を動員して銀を取ったのが道を誤った原因の1つかもしれません。
だから世界選手権の11位というのはショックでしたし、アジア大会で中国に負けたのを見て
‘モスクワ危うし’と実感したものです。
アジアでの出場権を失った時に松平氏が‘まだ最終予選がある’と言っていたので期待していたらアジア予選以上に厳しいのでダメだと思いましたよ。
モスクワ五輪ボイコットの唯一のメリットが
男子バレーの出場権獲得失敗が目立たなかった事だと当時から友人達と言ってました。
懐かしい話題を取り上げて下さりありがとうございます。
当時を全く知らないのに、僭越ながら今回書かせていただきました。
ちなみに、私がこの結果を知ったのは記述の通りに小5の時でしたが、詳しい話は今から10数年前にテレビ朝日で放送した「驚きももの木20世紀」と、日テレで放送した「知ってるつもり」で猫田さんを取り上げた時に色々と知りました。
この2つの番組を見て印象的だったのは、ミュンヘンで金メダルを獲るまでの苦労よりも、その後の苦悩の方でした。
「世界一の名セッター」猫田さんの後継者が見つからず、加齢による衰えとの戦いでした。まるでチーム全体が、偉大な栄光の呪縛に苦しめられているように感じました。
ちなみに、アジア選手権の中国戦の映像も番組で少し流してたのを覚えてます。あまりにも惨めな試合展開で、ミュンヘンの栄光との落差があり過ぎたので、正直見ていてつらいものがありました。
あと、昔の新聞を調べて分かったのは、この世界最終予選はテレビ中継がありませんでした。なので、モスクワの惨敗があまり世間に知られてないのは、おそらくこれが理由だと思われます。
記述の通りに、私は小学生時代にまともな夏の五輪を見たことが無い世代です。こーじさんの世代のように、少年時代に本物の五輪をリアルで知っているのは素直に羨ましいと思います。
こちらこそ、詳しい話を聞かせて頂いてありがとうございました。
幼いながらに覚えています
たしか猫田をコーチ兼任とし、嶋岡・丸山の2セッターで中村全日本はスタートしたと思いますが、初戦の途中ではや2セッターを見限った記憶がぼんやりとあります。
日本開催のW杯まで時間がなかったのかもしれませんが、ここをもう少し我慢できてたらなと思います
そして、世界最終予選に名前のある田中義紀!当時2部リーグに在籍していながら、彗星のように現れたアタッカーだったと思いますが、全日本での活躍も短かったのかな?
いや~、懐かしい
本当に楽しく拝読させていただきました!
このモスクワの予選を知っている人は身近にはいないので、当時をご存知の方がいらっしゃるのはとても嬉しいです。
私は80年代以降のバレーなら少しは覚えてます。1983年の秋に東京体育館で行われたアジア選手権で、中国と五輪出場権を直接争った試合に勝利した試合が異常に盛り上がっていたのも、今考えるとモスクワの出場権を逃したのが背景にあったと想像出来ますね。
この試合では途中で入った川合俊一が大活躍したのを覚えてます。
80年代は富士フイルムの黄金時代でしたけど、モスクワの最終予選の代表選手の一覧を見る限りでは70年代は新日鉄の全盛時代ですね。
こちらこそ、詳しい話を聞かせて頂いてありがとうございました。