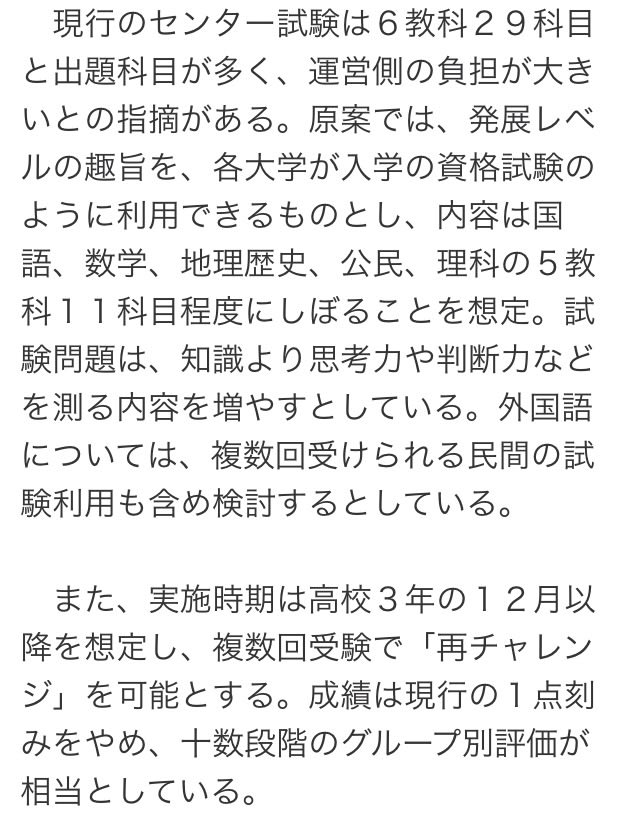アクティブラーニング入門を朝注文しました。
夜帰宅したら届いていました。
寝る前にさっと眺めましたが、とにかく
読みやすい本でした。明日からじっくり読みます。
夜帰宅したら届いていました。
寝る前にさっと眺めましたが、とにかく
読みやすい本でした。明日からじっくり読みます。
 | アクティブラーニング入門 (アクティブラーニングが授業と生徒を変える) |
| クリエーター情報なし | |
| 産業能率大学出版部 |