【修復腎移植ものがたり(14):捨てられる腎臓を!】
「先に在りしものはまた後にあるべし。先に成りしことはまた後に成るべし。日の下に新しきものあらざるなり。…前のものの事はこれを覚えることなし。後のものの事もまた後に出る者これを覚ゆることあらじ。」(『旧約聖書』「伝道の書」)
男が尿管の下部にあるがんを腎臓ごと切除し、きれいな腎臓を移植に用いることを始めたのは、呉共済病院で腎動脈瘤のある腎臓を移植に用いてから2年後、1993年4月のことだった。
話がすこし遡る。
1988年夏、男は3回目のウィスコンシン詣でをした。
今回の課題はどうしたら腎臓ドナーの供給を増やせるかということだった。東京では女子医大の太田和夫教授が中心となって、カリフォルニアからの「US腎」の輸入が続いていたが、それは宇和島には回ってこないし、来ても金を払える患者がいない。臓器保存液バイアスパンが完成してしまえば、下関の上領医師経由のウィスコンシン腎入手もできなくなる。
南伊予地方は大家族が多く、比較的濃密な親族関係が保たれているとはいうものの、いざ「生体腎移植」となったら、ドナーとして名乗り出るものは少なかった。たいていは一家を経済的に支える夫へ妻から、子供へ母親からというパターンが多かった。しかし移植された腎臓に拒絶反応がおこり、ダメになってしまうと、もう二度目はなかった。病院の屋上から飛び降り自殺したムラキサトコの悲劇を繰り返してはならない。
男は近藤院長から許可をもらって、88年7月、ウィスコンシン州マジソン市に出張した。男にとって2度目の独立記念日の花火が盛大に歓迎してくれた。この時に、香川労災病院にいた西光雄が夏休みを取って、ウィスコンシン大学に短期留学している。西は、日本でいうとワンルームマンションに相当する、男が賃借していたアパートに転がり込み、夜はリビングルームに毛布を敷いて寝た。学生時代の「なんでも見てやろう」旅行の再来だった。マジソンのセントラルパークには人を怖れない大きな鳩が沢山いた。ある日男はその一羽を捕まえ、バッグに入れてアパートに持ち帰った。男が羽をむしって調理し、二人は鳩肉を肴にささやかな宴会を楽しんだ。
解剖技師兼コーディネーターのボブ・ホフマンが大変よくしてくれて、セスナ機やヘリを使って出かける際に、脳死体から臓器を採取する現場に連れて行ってくれた。脳死体は「死体」だから、臓器を取り出すのにアメリカの医師免許はいらない。交代でボブに同行した男と西は、脳死体の腎臓の中にどれほど傷んだものがあるか、どの程度の病変までは移植に使用されるかを、実地に見聞した。
脳死体から臓器を提供してもらうには、本人または遺族の許可が要る。しかしせっかく取り出した臓器を、使えないとして廃棄するのには、別に遺族の了解は取らない。遺族は提供した臓器が役に立ったと思っている。「これは一種のサギだな」とまでは男は思わなかった。
が、ベルツァー教授が臓器の保存時間を長くするための、保存液の開発に力を入れ、腎機能の残存が見込める場合には、病変がある腎臓でもできるだけ移植に用いて、ドナーの善意を生かそうとしている姿勢には素直に感動した。
男は後に「八〇年代に米ウィスコンシン大に留学し、死体腎にがんがあっても部分切除して移植する手術を見た。それが病気腎移植に踏み切ったきっかけ」(『中国』06.11.7)と説明している。
この発言には裏付けとなる証言がなかった。だが西がある事件のことを思い出したのが、時期を特定する手がかりとなった。
「帰ってみたら潜水艦なだしおの事故のことで日本は大騒ぎになっていたが、さっぱり知らなかった」と西はいう。2001年2月に起こった宇和島水産高校の練習船「えひめ丸
が、ハワイ・オアフ島沖で米海軍原子力潜水艦「グリーンビル
と衝突して沈没した事件は、アメリカでも大きく報道された。
しかし日本の遊漁船「第一富士丸」が海上自衛隊の潜水艦「なだしお」と衝突して沈没した事件は、ウィスコンシン州では報じられなかったのだ。衝突の日は1988年7月23日で、西がこの日にマジソン市にいて、それより先に男が滞在を始めていたのは、この証言でウラが取れた。
男と西は採取してきた腎臓が、実際にどのように移植に使われるかを見学した。小さな腎腫瘍があった場合、臓器全部を廃棄するのではなく、その部分だけを切除して用いる例があった。「それを見た」という男の証言に嘘はないだろう。
だが、それを男が市立宇和島病院で実行に移すまでには、15年という歳月が経過している。91年の光畑による動脈瘤の腎臓移植が、新たなアイデアを与えたのだ。男がまず考えたのは「腎臓そのものにがんがなく、尿管にあるものなら大丈夫だろう」ということだった。
膀胱から体外につながる尿の通路を「尿道」という。これに対して腎臓から膀胱に至る尿の通路を「尿路」という。尿路の始まりは腎臓の門部をつつむ袋状の「腎盂(じんう)」だが、すぐに一本の細い管となり膀胱につながる。全長約30センチ、幅約5ミリの管、これが「尿管」である。
この尿管から生じるがんが、比較的稀な尿管がんだ。60代以降の老人に多い。多くは腎盂にまで多発性に生じるので、放置すれば尿路が詰まり、溜まった尿で腎臓が圧迫される水腎症が生じて、腎臓までダメになる。標準的治療は「腎尿管全摘」である。
尿管がんの半数以下では腎盂に病変がない。そのうち下部尿管だけに病巣が限局しているものとなると、いわゆる「尿管がん」の1割程度である。
「そういう症例なら、がんのある下部尿管を切除すれば、腎臓が移植に生かせるのではないか?」
男はそう考えた。
その発想は必ずしも突飛ではなかった。実は世界初の腎移植は、まさに下部尿管がんのために、腎尿管全摘が必要になった患者の腎臓を利用したものだった。早くも1951年に、米マサチューセッツ州スプリングフィールド病院で、下部尿管がんがある患者の腎臓を全摘して病変部を切除し、他人に移植した例がある。
世界最初に開発されたコルフ型の人工腎臓は、第二次大戦の直後にオランダからアメリカに渡ったコルフ博士によって、ボストンのピーター・ベント・ブリガム病院で改良が加えられ、1950年には実用機が製造されるようになった。この病院はハーバード大の附属病院の1つで、1980年に「ボストン婦人病院」と合併し、「ブリガム婦人病院」となった。そう、あのSTAP細胞の小保方晴子が留学した病院である。
コルフ型人工腎臓は急性腎不全の患者の治療に大活躍した。ことにこの年に始まった朝鮮戦争では、出血多量の治療に使われた乾燥血漿と並んで、砲弾爆裂により「挫滅症候群
を起こした兵士の治療に、有効な手法として利用された。しかしコルフ型は慢性腎不全患者の維持療法としては、まだ不充分だった。
けれども慢性腎不全患者を一時的に正常血液に戻すことはできる。そこに眼をつけて、患者の体液組成が正常に戻っている間に、治療として腎移植をしようと考えた医者がいる。
それが同じ州にあるスプリングフィールド病院のジェームズ・V・スコラ医師だ。
最初の患者は37歳男性で、17年前から慢性糸球体腎炎を発症し、腎不全の末期状態に近づいていた。そこで彼は患者をピーター・ベント・ブリガム病院に送り、血液透析を行ってもらった。10日間の透析で、患者の血液検査値はほぼ正常に回復し、患者は元の病院に戻った。
スコラ医師は左下部尿管がんの患者を抱えていた。腎尿管の全摘術を予定した板。腎機能は完全に正常なので、この腎臓を腎不全の患者に移植しようと考えたのだ。血液型がクロスマッチすることも調べてあった。ドナーは49歳の男性だった。
1951年3月31日に行われた手術はユニークなものだった。レシピエントの腎動脈に狭窄があるので、まず摘脾を行い、脾動脈を腹腔から後腹膜に回し、レシピエントの左腎臓を摘出し、その位置にドナーの腎臓を移植し、腎動脈をレシピエントの脾動脈に吻合した。血液凝固を防ぐためにヘパリン注射がおこなわれている。尿管を膀胱につないだのか、レシピエントの尿管につないだのかは記載がないが、腎臓の移植位置から見て後者の可能性が高い。腎臓の阻血時間は70分だった。
残念ながら当時は免疫抑制剤がなく、レシピエントには最初の数日は利尿もあったが、次第に拒絶反応が起こり、腎不全治療のためピーター・ベント・ブリガム病院に送られた。しかし3週間後の5月7日に死亡した。病理解剖の結果、移植された腎臓の周囲膿瘍と組織学的に拒絶反応の所見が認められたが、尿管がんの増生はなかった。
スコラ博士はこの貴重な経験を論文として発表しなかった。失敗に終わった「ネガティブ・データ」は一般に論文として公表されない。それでも歴史に記録されたのは、『ギブ・アンド・テイク』という臓器移植の歴史を扱った本のおかげである。著者のムーア博士はピーター・ベント・ブリガム病院の外科部長でハーバード大学医学部教授を兼ねていた。著書にはスコラ博士からの「私信
として引用してある。
スコラ医師の症例は、下部尿管がんを利用した修復腎移植が、半世紀以上前にすでに行われていたことを示している。拒絶反応を防ぐのに、最近ではレシピエントの脾臓摘出が行われること、さらに尿管がんに関する最近のがん遺伝子の知見を合わせ考えると、乳頭状移行上皮がんの形をとる下部尿管がんの治療を兼ねて、スコラ医師が腎移植と摘脾術とを同時に行ったのは、理にかなっている。感染症である腎膿瘍が起こらなければ、レシピエントはもっと長く生きられた可能性があるだろう。
ピーター・ベント・ブリガム病院で、ジョゼフ・マーレイ医師らが一卵性双生児間での腎移植に初めて成功するのは、この2年後のことだから、スコラ医師の「病腎移植(修復腎移植)」の試みの方が早い。これを一般化して述べれば、「臓器移植は修復腎移植から始まった」といえよう。
だが、この歴史を男は知るよしもなかった。空しくチャンスを待つうちに2年が過ぎた。
やがて彼の前に現れた患者はカメノという名の70歳の女性で、右の尿管下部に限局した小さながんがあった。この頃には院長の近藤俊文の要請で、愛媛大学から派遣された病理医が勤務していて、病理検査や病理解剖が院内でできるようになっていた。
1993年4月5日、カメノの腎尿管全摘術が行われ、尿管の下部を切り離した後、腎提供のドナーが親族にいなくて、人工透析を続けていた49歳のミツオに移植された。初回の腎移植である。病理診断は「乳頭状移行上皮がん、グレード1」という悪性度が低いもので、「尿管断端に浸潤なし」とあった。
移植は成功し、喜びのあまりミツオは生ビールを中ジョッキ5杯も飲み、トイレで排尿できるという、久しく忘れていた喜びを心ゆくまで味わった。
これに力をえて、男はその年の12月に、第2例目の「尿管がん修復腎移植」を行った。
患者は71歳の女性アヤノで、やはり右尿管の下部にがんがあった。レシピエントとなったツヨシは37歳の男性で、糸球体腎炎による慢性腎不全のため、1982年に母親からの腎臓移植術を受けていた
しかし植えた腎臓が9年後にダメになり、再透析の生活に戻っていた。移植でQOLを取り戻した患者ほど、腎移植への欲求がつよい。ツヨシも「がんの腎臓」であると事前に知っても、何のためらいも見せなかった。
ツヨシの場合は、移植する前に尿管がんの迅速病理診断が行われた。呉共済の光畑移植の際に、手術中に行われた、組織を瞬間凍結させて調べるあの検査である。
「術中迅速」と呼ばれるこの検査は、何しろ氷を薄切りするのだから、標本が厚くなり細胞の細かいところまでは顕微鏡でわからない。切除断端にがんがないことを確かめるのが主な目的だ。幸い尿管断端にがんはなかった。8日目に戻ってきた、パラフィン切片での最終病理診断書には「乳頭状移行上皮がん、グレード2」とあった。彼の場合も移植は成功した。
男はさらに力を得た。だが慢心は禁物である。医学部で、病理学のプレパラート試験に睾丸の組織標本を出され、「金玉、理由:見ればわかる」という答案を書いて、温厚な細川教授を「落第させる!」とカンカンに怒らせたほど、病理学の知識は乏しかった。
ほぼ1年後の1994年10月に第3例目の右尿管がん患者、65歳女性マスミの腎尿管全摘を行い、下部尿管の腫瘍を切除した後に、45歳のユキオに移植した。彼も1990年に母から腎臓をもらったが、その腎臓は3年も保たず、また透析に逆戻りしていた。
この尿管がんの場合も、術中迅速では「断端にがんフリー」であった。それで安心して移植した。が、戻ってきた最終診断は「非乳頭状移行上皮がん、グレード3>グレード2、一部SCCあり」であった。男はそのメッセージを読み落とした。がんは組織学的な形と、分化度を示すグレードにより、悪性度が異なるのだ。
ここで移行上皮がんについて少し解説をはさもう。(続)
「先に在りしものはまた後にあるべし。先に成りしことはまた後に成るべし。日の下に新しきものあらざるなり。…前のものの事はこれを覚えることなし。後のものの事もまた後に出る者これを覚ゆることあらじ。」(『旧約聖書』「伝道の書」)
男が尿管の下部にあるがんを腎臓ごと切除し、きれいな腎臓を移植に用いることを始めたのは、呉共済病院で腎動脈瘤のある腎臓を移植に用いてから2年後、1993年4月のことだった。
話がすこし遡る。
1988年夏、男は3回目のウィスコンシン詣でをした。
今回の課題はどうしたら腎臓ドナーの供給を増やせるかということだった。東京では女子医大の太田和夫教授が中心となって、カリフォルニアからの「US腎」の輸入が続いていたが、それは宇和島には回ってこないし、来ても金を払える患者がいない。臓器保存液バイアスパンが完成してしまえば、下関の上領医師経由のウィスコンシン腎入手もできなくなる。
南伊予地方は大家族が多く、比較的濃密な親族関係が保たれているとはいうものの、いざ「生体腎移植」となったら、ドナーとして名乗り出るものは少なかった。たいていは一家を経済的に支える夫へ妻から、子供へ母親からというパターンが多かった。しかし移植された腎臓に拒絶反応がおこり、ダメになってしまうと、もう二度目はなかった。病院の屋上から飛び降り自殺したムラキサトコの悲劇を繰り返してはならない。
男は近藤院長から許可をもらって、88年7月、ウィスコンシン州マジソン市に出張した。男にとって2度目の独立記念日の花火が盛大に歓迎してくれた。この時に、香川労災病院にいた西光雄が夏休みを取って、ウィスコンシン大学に短期留学している。西は、日本でいうとワンルームマンションに相当する、男が賃借していたアパートに転がり込み、夜はリビングルームに毛布を敷いて寝た。学生時代の「なんでも見てやろう」旅行の再来だった。マジソンのセントラルパークには人を怖れない大きな鳩が沢山いた。ある日男はその一羽を捕まえ、バッグに入れてアパートに持ち帰った。男が羽をむしって調理し、二人は鳩肉を肴にささやかな宴会を楽しんだ。
解剖技師兼コーディネーターのボブ・ホフマンが大変よくしてくれて、セスナ機やヘリを使って出かける際に、脳死体から臓器を採取する現場に連れて行ってくれた。脳死体は「死体」だから、臓器を取り出すのにアメリカの医師免許はいらない。交代でボブに同行した男と西は、脳死体の腎臓の中にどれほど傷んだものがあるか、どの程度の病変までは移植に使用されるかを、実地に見聞した。
脳死体から臓器を提供してもらうには、本人または遺族の許可が要る。しかしせっかく取り出した臓器を、使えないとして廃棄するのには、別に遺族の了解は取らない。遺族は提供した臓器が役に立ったと思っている。「これは一種のサギだな」とまでは男は思わなかった。
が、ベルツァー教授が臓器の保存時間を長くするための、保存液の開発に力を入れ、腎機能の残存が見込める場合には、病変がある腎臓でもできるだけ移植に用いて、ドナーの善意を生かそうとしている姿勢には素直に感動した。
男は後に「八〇年代に米ウィスコンシン大に留学し、死体腎にがんがあっても部分切除して移植する手術を見た。それが病気腎移植に踏み切ったきっかけ」(『中国』06.11.7)と説明している。
この発言には裏付けとなる証言がなかった。だが西がある事件のことを思い出したのが、時期を特定する手がかりとなった。
「帰ってみたら潜水艦なだしおの事故のことで日本は大騒ぎになっていたが、さっぱり知らなかった」と西はいう。2001年2月に起こった宇和島水産高校の練習船「えひめ丸
が、ハワイ・オアフ島沖で米海軍原子力潜水艦「グリーンビル
と衝突して沈没した事件は、アメリカでも大きく報道された。
しかし日本の遊漁船「第一富士丸」が海上自衛隊の潜水艦「なだしお」と衝突して沈没した事件は、ウィスコンシン州では報じられなかったのだ。衝突の日は1988年7月23日で、西がこの日にマジソン市にいて、それより先に男が滞在を始めていたのは、この証言でウラが取れた。
男と西は採取してきた腎臓が、実際にどのように移植に使われるかを見学した。小さな腎腫瘍があった場合、臓器全部を廃棄するのではなく、その部分だけを切除して用いる例があった。「それを見た」という男の証言に嘘はないだろう。
だが、それを男が市立宇和島病院で実行に移すまでには、15年という歳月が経過している。91年の光畑による動脈瘤の腎臓移植が、新たなアイデアを与えたのだ。男がまず考えたのは「腎臓そのものにがんがなく、尿管にあるものなら大丈夫だろう」ということだった。
膀胱から体外につながる尿の通路を「尿道」という。これに対して腎臓から膀胱に至る尿の通路を「尿路」という。尿路の始まりは腎臓の門部をつつむ袋状の「腎盂(じんう)」だが、すぐに一本の細い管となり膀胱につながる。全長約30センチ、幅約5ミリの管、これが「尿管」である。
この尿管から生じるがんが、比較的稀な尿管がんだ。60代以降の老人に多い。多くは腎盂にまで多発性に生じるので、放置すれば尿路が詰まり、溜まった尿で腎臓が圧迫される水腎症が生じて、腎臓までダメになる。標準的治療は「腎尿管全摘」である。
尿管がんの半数以下では腎盂に病変がない。そのうち下部尿管だけに病巣が限局しているものとなると、いわゆる「尿管がん」の1割程度である。
「そういう症例なら、がんのある下部尿管を切除すれば、腎臓が移植に生かせるのではないか?」
男はそう考えた。
その発想は必ずしも突飛ではなかった。実は世界初の腎移植は、まさに下部尿管がんのために、腎尿管全摘が必要になった患者の腎臓を利用したものだった。早くも1951年に、米マサチューセッツ州スプリングフィールド病院で、下部尿管がんがある患者の腎臓を全摘して病変部を切除し、他人に移植した例がある。
世界最初に開発されたコルフ型の人工腎臓は、第二次大戦の直後にオランダからアメリカに渡ったコルフ博士によって、ボストンのピーター・ベント・ブリガム病院で改良が加えられ、1950年には実用機が製造されるようになった。この病院はハーバード大の附属病院の1つで、1980年に「ボストン婦人病院」と合併し、「ブリガム婦人病院」となった。そう、あのSTAP細胞の小保方晴子が留学した病院である。
コルフ型人工腎臓は急性腎不全の患者の治療に大活躍した。ことにこの年に始まった朝鮮戦争では、出血多量の治療に使われた乾燥血漿と並んで、砲弾爆裂により「挫滅症候群
を起こした兵士の治療に、有効な手法として利用された。しかしコルフ型は慢性腎不全患者の維持療法としては、まだ不充分だった。
けれども慢性腎不全患者を一時的に正常血液に戻すことはできる。そこに眼をつけて、患者の体液組成が正常に戻っている間に、治療として腎移植をしようと考えた医者がいる。
それが同じ州にあるスプリングフィールド病院のジェームズ・V・スコラ医師だ。
最初の患者は37歳男性で、17年前から慢性糸球体腎炎を発症し、腎不全の末期状態に近づいていた。そこで彼は患者をピーター・ベント・ブリガム病院に送り、血液透析を行ってもらった。10日間の透析で、患者の血液検査値はほぼ正常に回復し、患者は元の病院に戻った。
スコラ医師は左下部尿管がんの患者を抱えていた。腎尿管の全摘術を予定した板。腎機能は完全に正常なので、この腎臓を腎不全の患者に移植しようと考えたのだ。血液型がクロスマッチすることも調べてあった。ドナーは49歳の男性だった。
1951年3月31日に行われた手術はユニークなものだった。レシピエントの腎動脈に狭窄があるので、まず摘脾を行い、脾動脈を腹腔から後腹膜に回し、レシピエントの左腎臓を摘出し、その位置にドナーの腎臓を移植し、腎動脈をレシピエントの脾動脈に吻合した。血液凝固を防ぐためにヘパリン注射がおこなわれている。尿管を膀胱につないだのか、レシピエントの尿管につないだのかは記載がないが、腎臓の移植位置から見て後者の可能性が高い。腎臓の阻血時間は70分だった。
残念ながら当時は免疫抑制剤がなく、レシピエントには最初の数日は利尿もあったが、次第に拒絶反応が起こり、腎不全治療のためピーター・ベント・ブリガム病院に送られた。しかし3週間後の5月7日に死亡した。病理解剖の結果、移植された腎臓の周囲膿瘍と組織学的に拒絶反応の所見が認められたが、尿管がんの増生はなかった。
スコラ博士はこの貴重な経験を論文として発表しなかった。失敗に終わった「ネガティブ・データ」は一般に論文として公表されない。それでも歴史に記録されたのは、『ギブ・アンド・テイク』という臓器移植の歴史を扱った本のおかげである。著者のムーア博士はピーター・ベント・ブリガム病院の外科部長でハーバード大学医学部教授を兼ねていた。著書にはスコラ博士からの「私信
として引用してある。
スコラ医師の症例は、下部尿管がんを利用した修復腎移植が、半世紀以上前にすでに行われていたことを示している。拒絶反応を防ぐのに、最近ではレシピエントの脾臓摘出が行われること、さらに尿管がんに関する最近のがん遺伝子の知見を合わせ考えると、乳頭状移行上皮がんの形をとる下部尿管がんの治療を兼ねて、スコラ医師が腎移植と摘脾術とを同時に行ったのは、理にかなっている。感染症である腎膿瘍が起こらなければ、レシピエントはもっと長く生きられた可能性があるだろう。
ピーター・ベント・ブリガム病院で、ジョゼフ・マーレイ医師らが一卵性双生児間での腎移植に初めて成功するのは、この2年後のことだから、スコラ医師の「病腎移植(修復腎移植)」の試みの方が早い。これを一般化して述べれば、「臓器移植は修復腎移植から始まった」といえよう。
だが、この歴史を男は知るよしもなかった。空しくチャンスを待つうちに2年が過ぎた。
やがて彼の前に現れた患者はカメノという名の70歳の女性で、右の尿管下部に限局した小さながんがあった。この頃には院長の近藤俊文の要請で、愛媛大学から派遣された病理医が勤務していて、病理検査や病理解剖が院内でできるようになっていた。
1993年4月5日、カメノの腎尿管全摘術が行われ、尿管の下部を切り離した後、腎提供のドナーが親族にいなくて、人工透析を続けていた49歳のミツオに移植された。初回の腎移植である。病理診断は「乳頭状移行上皮がん、グレード1」という悪性度が低いもので、「尿管断端に浸潤なし」とあった。
移植は成功し、喜びのあまりミツオは生ビールを中ジョッキ5杯も飲み、トイレで排尿できるという、久しく忘れていた喜びを心ゆくまで味わった。
これに力をえて、男はその年の12月に、第2例目の「尿管がん修復腎移植」を行った。
患者は71歳の女性アヤノで、やはり右尿管の下部にがんがあった。レシピエントとなったツヨシは37歳の男性で、糸球体腎炎による慢性腎不全のため、1982年に母親からの腎臓移植術を受けていた
しかし植えた腎臓が9年後にダメになり、再透析の生活に戻っていた。移植でQOLを取り戻した患者ほど、腎移植への欲求がつよい。ツヨシも「がんの腎臓」であると事前に知っても、何のためらいも見せなかった。
ツヨシの場合は、移植する前に尿管がんの迅速病理診断が行われた。呉共済の光畑移植の際に、手術中に行われた、組織を瞬間凍結させて調べるあの検査である。
「術中迅速」と呼ばれるこの検査は、何しろ氷を薄切りするのだから、標本が厚くなり細胞の細かいところまでは顕微鏡でわからない。切除断端にがんがないことを確かめるのが主な目的だ。幸い尿管断端にがんはなかった。8日目に戻ってきた、パラフィン切片での最終病理診断書には「乳頭状移行上皮がん、グレード2」とあった。彼の場合も移植は成功した。
男はさらに力を得た。だが慢心は禁物である。医学部で、病理学のプレパラート試験に睾丸の組織標本を出され、「金玉、理由:見ればわかる」という答案を書いて、温厚な細川教授を「落第させる!」とカンカンに怒らせたほど、病理学の知識は乏しかった。
ほぼ1年後の1994年10月に第3例目の右尿管がん患者、65歳女性マスミの腎尿管全摘を行い、下部尿管の腫瘍を切除した後に、45歳のユキオに移植した。彼も1990年に母から腎臓をもらったが、その腎臓は3年も保たず、また透析に逆戻りしていた。
この尿管がんの場合も、術中迅速では「断端にがんフリー」であった。それで安心して移植した。が、戻ってきた最終診断は「非乳頭状移行上皮がん、グレード3>グレード2、一部SCCあり」であった。男はそのメッセージを読み落とした。がんは組織学的な形と、分化度を示すグレードにより、悪性度が異なるのだ。
ここで移行上皮がんについて少し解説をはさもう。(続)












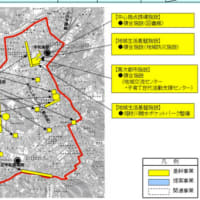
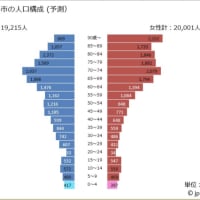



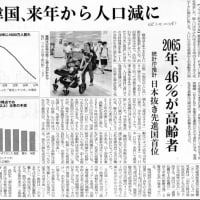










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます