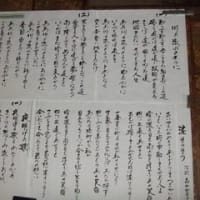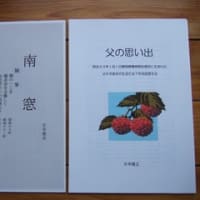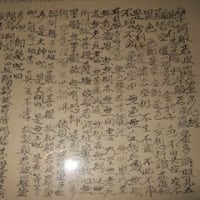今年の7月下旬だと思うが、静岡市葵区研屋町の医王山顕光院本堂でSPAC(静岡県芸術劇場)のA氏の演談を聞いた。その時この寺に、十返舎一九の子孫である重田一族の墓があり、そこには一九の戒名が刻まれた碑があることを聞いた。そのことから十返舎一九のことを調べてみた。
十返舎一九と云えば、「東海道中膝栗毛」を書いた作者である。彼は明和2年(1765年)駿河国府中(現在の静岡市葵区)で町奉行の同心の子として生まれている。本名は重田貞一と云い、通称は与七、幾五郎と云った。父親は奉行所の書記をしていて、彼も父の跡を継ぎ奉行所に勤めることになる。駿府町奉行小田切土佐守に従い、江戸に出て武家奉公をしたり、天明3年19歳のとき大阪奉行に転じた小田切直年に従い大阪に行った。しかし、ほどなく浪人してしまう。彼はかたい役人より、作家としての道を選んだのだ。その後は義太夫語りの家に寄食し、浄瑠璃作家となり、25歳のとき「近松与七」の名前で浄瑠璃『木下蔭狭間合戦』を書いている。このころ材木商家に婿入りしますが離縁されたりしている
30歳になって、また江戸へ戻り、蔦屋重三郎方に寄食して、挿絵描きなどを手伝う。その傍ら蔦屋に勧められて黄表紙『心学時計草』など出版した。、以降は生活のため20年以上にわたり、毎年20部前後の新作を書き続けた。貧乏ながら作家として生計を立てた最初の人であると云われている。この間たびたび東海道を往復し、そこから得た蓄積を、もとに書き上げたのが『東海道中膝栗毛』で、それが大ヒットを生み、洒落本作家としての地位を確立した。彼が執筆した『東海道中膝栗毛』は、最初は江戸から箱根までの初編のみで完結するつもりでいたが、2編では箱根から岡部まで、3篇は岡部から新居までと書き継がれ、8篇の大阪まで、東海道を8年がかりで完結させでいる。その後も金毘羅、宮島など参詣し江戸へ帰ってくるまで全12編20年がかりの執筆となった。
この大当たりした原因は、無邪気な飾り気のない弥次さん喜多さんと云う町人が主人公で分りやすい語り口とそして道中や宿場で起こるあらゆる人達との交流、そこで起こるアクシデントを軽快なタッチで展開していく、身分に応じた言葉使い等巧みな描写で描いている。こうした事が当時の江戸っ子をはじめとする庶民の心を捉えたと云はれる。20年にわたっての人気作家であったにもかかわらず、晩年は酒におぼれて借家住まいの貧乏世帯であったと伝えられている。しかし洒落た生き方は67歳で死ぬまで変わることなく、辞世の句は≪この世をば、どりゃおいとまに、線香の煙と共に、灰左様なら≫と詠んでいる。最期まで粋で陽気な一生を演出した人であった。