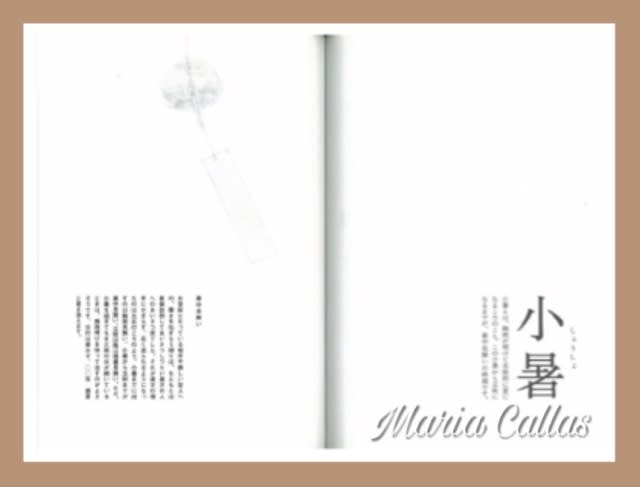今日は梅雨明けしたかのようにカラッと晴れた気持ちの良い1日でしたね☀️
朝一番でピアノの出張レッスンに来て頂いて、合間で身支度を済ませ、レッスン後にお茶のお稽古へ😊

今日は夏らしい陽気でしたので、それに合う着物をと、こちらの一揃いを選びました😊


帯はほんのりオフホワイトに染めた駒絽地に、染め疋田を取り入れた菊青海波を背景に、琵琶や笙や龍笛、そして笛袋などの古楽器を描いた、別誂えの染め名古屋帯。
帯揚げは白い絽地に濃いピンクの絞りで桔梗が表現された輪出し。
帯締めは白地に濃いピンクでワンポイントが入った夏用の組紐。
今日のお稽古は夏らしい洗い茶巾のお点前をさせて頂きました。平茶碗が苦手な私、さらに洗い茶巾は運びの際に水をこぼしそうでいつもドキドキします。
お菓子は瓢箪を模した「ひさご」で大石堂製。
お軸は珍しく歴史画で、楠木正成の桜井の別れを描いたものでした。
茶花は紫の鉄線と縞葦が活けられていました。

午後からは夫とバトンタッチ。帰宅するとちょうど宅急便が届いて、開けてみると子供たちの長靴でした。新しい長靴🥾にご満悦の息子です💕
息子は新しいもの好き、娘は物を大切に使う派なので、息子は早速新しい長靴を履き、娘はいまの長靴がキツくなるまでは取っておくそうです。同じに育てても性格によって違いが出ますね😅

夜はディナーの準備のお手伝いを子供たちがしてくれました。私の夢は子供たちが中学生くらいになったら毎週末一緒にお料理をして、成人するまでに私が習ったイタリア料理を全て受け継ぐことです✨



メインは予定を変更して、豚ヒレ肉🐖のオーブン焼き、トンナートソースです。オーブンでしっとりと焼き上げた豚肉にマヨネーズを加えたツナソースがよく合います💕