日本年金機構は、職員のパソコンに外部からウイルスメールによる不正アクセスがあり、国民年金や厚生年金などの加入者と受給者の個人情報が外部に流出したことを、昨日(6月1日)、記者会見で発表した。国民年金・厚生年金などの加入者に付与される10桁の基礎年金番号と、氏名、生年月日の3情報が約116万7000件、3情報と住所の計4情報が約5万2000件、基礎年金番号と氏名の2情報が約3万1000件の合計約125万件に上るとのことだ。
外部からのメールの添付ファイルにウイルスが入っていたのに、複数の職員が不用意にファイルを開いたこと、その後機構が「不信なメールは開けないように」との指示をしたが、その指示が徹底されず、別の職員もメールを受け取り、添付ファイルを開いてしまったことが原因だ。しかも、機構で管理する個人情報には、パスワードをかける決まりになっていたのに、半数はパスワードがかかっていなかったとのことだ。
年金業務に関して公的に管理されている個人情報が大量に流出した今回の事件は、国の情報管理システムの根幹にかかわる重大な問題だ。
私は、2010年に総務省に設置された年金業務監視委員会(国家行政組織法8条に基づく行政委員会)の委員長として、日本年金機構や厚労省年金局の年金業務を監視する職務に携わってきた。その委員会が、昨年3月末に廃止される際、「厚労省や年金機構の外部に、年金業務を監視する機関が必要である」との意見を、委員会として取りまとめ、総務大臣への意見具申も行った。(【外部機関の設置検討を 年金業務監視委が意見書】)
年金業務の監視の役割を担ってきた立場から、日本年金機構や厚労省年金局の組織の体質や業務の現状には多くの問題があり、外部機関による監視体制がなくなってしまうと、重大な問題が発生することが強く懸念されたからである。この問題については、年金業務監視委員会の設置当時の総務大臣であった原口一博議員が、監視委員会廃止直後の衆議院総務委員会で取り上げ、元委員長の私を参考人として招致し、監視委員会を廃止した政府を厳しく批判した。(原口議員の質問は、2014年4月1日総務委員会 53分30秒ころから)
総務省年金業務監視委員会が設置されていた4年間、委員会では様々な問題を取り上げてきた。2011年のサラリーマンの専業主婦にかかる年金、いわゆる「運用3号」問題、2013年の「時効特例給付に関する問題」、委員会廃止直前の2014年の「失踪宣告者に対する死亡一時金の給付に関する問題」などが、主な問題だが、いずれも、厚労省や年金機構が自主的に委員会に報告してきたものではなく、社会保険労務士等からの問題の指摘や、機構職員の内部告発など、外部からの指摘によって、委員会が問題を把握したものだった。(これらの問題の詳細については、前記衆議院総務委員会の中で(58分頃~)説明している。)
「運用3号問題」は、保険料を支払っていなかった主婦に、年金全額の支給を認めることにするという重大な事項を、厚労省は「課長通知」だけで指示をし、しかも、明らかに国民年金法に反し、重大な不公平を生じる問題であった。この問題に対して、年金業務監視委員会が総務大臣へ意見具申を行い、厚労大臣が、当時野党であった自民党から国会で厳しく追及されたことで、「運用3号」の課長通知は廃止され、新たな立法措置がとられることになった。
「時効特例給付に関する問題」と「失踪宣告者に対する死亡一時金の給付に関する問題」には共通の要因があった。年金業務の現場を担う日本年金機構の組織には「重要事項の周知徹底ができない」、「現場の問題意識が上層部に伝わらない」という重大な欠陥があり、それに起因して発生したのが、これらの問題だった。
今回の情報流出問題は、まさに、そのような機構組織の重大な欠陥によるリスクが顕在化したものである。これまで、組織の無謬性にこだわり、責任回避に終始して、そのような機構組織の問題に正面から向き合おうとしなかった厚労省にも重大な責任がある(【郷原信郎氏、激白!「誤りを認めず、無謬性にこだわる厚労省の体質が年金行政を混乱させた」(上)】【同 (下)】 ) 。
そのような日本年金機構の組織の根本的な問題や、機構を監督する立場の厚労省の組織の体質の問題を、具体的な事例を通して指摘してきたのが、外部機関としての総務省年金業務監視委員会だった。
委員会の議事はすべて公開され、マスコミにもフルオープンで行われた。そのような場で、年金問題の専門家も含む外部機関としての委員会から厳しい指摘を受けることは、厚労省や機構に緊張感を持たせることにもつながっていたであろう。
その年金業務監視委員会の設置期限は、2014年3月末と定められていた。もちろん、政令を改正すれば、設置期限の延長は可能であり、それまでの委員会での活動状況や、年金業務の実情を考えたら、当然、設置期限は延長されるべきであった。
ところが、2013年12月、総務省の行政評価局長が私の事務所を訪れて、「年金業務監視委員会は設置期限の翌年3月末で廃止し、それ以降は厚労省の社会保障審議会の中に部会として第三者機関を作り、そこで年金業務について審議してもらう。年金記録第三者委員会も廃止し、総務省は年金問題から手を引く。」ということを伝えてきた。
ほぼ終息しつつあった年金記録回復に関する「年金記録第三者委員会」をどうするかはともかく、現に多くの問題が発生していた年金業務については、年金業務監視委員会が、継続して問題を指摘し続けていた。「厚労省の審議会などという身内同然の組織の中に、第三者による審議機関を設けても、厚労省外に独立した組織として設置されてきた年金業務監視委員会の機能を代替することには全くならない」と私の意見を述べたが、総務省と厚労省との間の協議で既にその方針は決まっており、官邸の了承も得ているということだった。行政評価局長は明確には言わなかったが、省庁間の問題なので、総理官邸の意向が強く働いているということのようだった。
その1年前に発足した第二次安倍政権は、アベノミクスによる円安、株高によって支持率も高く、安定政権として基盤を形成しようとしている時だった。安倍首相にとっては、第一次安倍政権の際に、「消えた年金問題」が発端で政権が崩壊した悪夢から、「年金は鬼門」との認識があったのだろう。それだけに、総務省年金業務監視委員会が厚労省年金局や年金機構の問題を厳しく追及する中で、また年金に関する重大な問題が露見することは避けたいという思いがあったのかもしれない。
実際に、民主党政権下で立ち上げられた年金業務監視委員会による問題の指摘が、「運用3号問題」では、当時の民主党政権にとっての重大なリスクにつながった。参議院予算委員会で民主党の細川大臣を厳しく追及したのが、現在、総理官邸で官房副長官を務める世耕弘成参議院議員だった。当時野党議員であった世耕議員は、年金業務監視委員会での厚労省追及の一部始終を傍聴し、それを材料に、国会での追及を行ったものだった。(当時の細川厚労大臣は、違法な課長通知の責任を問われ、辞任(ダウン)寸前まで追い込まれたが、その直後の3月11日に東日本大震災が発生したことで、かろうじてゴングで救われた形になった。)
しかし、それは本末転倒の考え方だ。総務省という外部に設置された組織による監視機能も確保し、年金業務の適正化に万全を期すことが、政権として年金問題によるリスクを最小化する方法だったはずだ。
今回の個人情報の大量流出は、まさに機構の組織の構造に関わる問題であり、それを防止できなかったことには厚労省に重大な責任がある。1年余り前、総務省年金業務監視委員会が廃止される直前まで、外部機関による年金業務監視の必要性を訴え続けてきた私の懸念が現実の問題になってしまったことは誠に残念だ(ビデオニュース【年金業務監視委員会を廃止して日本の年金は本当に大丈夫なのか】)。
政府は、国民にとって重大な関心事である年金業務について、厚労省年金局と、日本年金機構の現状にいかなる問題があるのかについて調査し、監視体制の整備を早急に行うべきだ。構造的な問題を抱えた日本年金機構、そして、無謬性にこだわり根本的な問題解決を行おうとしない厚労省に委ねていたのでは、今回の問題からの信頼回復はあり得ない。
(2015年6月2日「郷原信郎が斬る」より転載)

















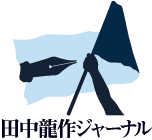 http://tanakaryusaku.jp/2015/06/00011318
http://tanakaryusaku.jp/2015/06/00011318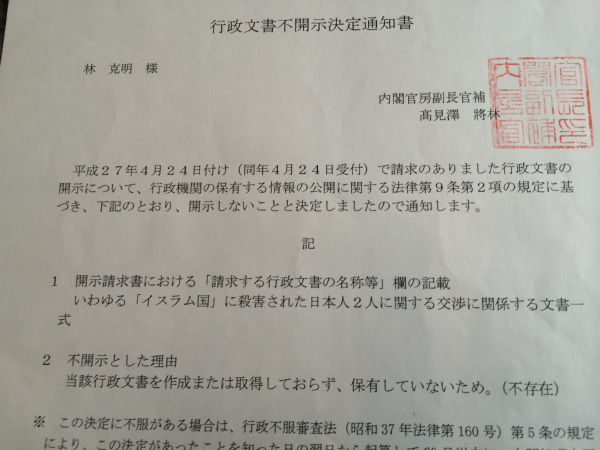

 http://dot.asahi.com/wa/2015060200096.html
http://dot.asahi.com/wa/2015060200096.html