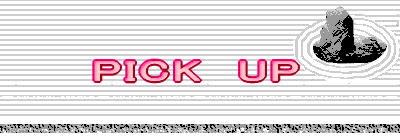
ブログ「晴れのち平安」へようこそ!
当ブログのカテゴリー「PICK UP」から移動 は私がかつて運営していたwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内のコンテンツ「PICK UP」で紹介していた内容をブログ記事へ移動させたものです。
(webサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』と「PICK UP」はともにホームページサービス終了により閲覧不可能となりました。)
私が今まで訪れた地の歴史や伝承のうち特に興味のある場所をおおまかな時代順にご紹介しています。
以下、ブログ「晴れのち平安」での各ページへのリンクです。
★ 「金印」出土の志賀島と志賀海神社 <福岡市東区>
★ 斉明女帝の朝倉橘広庭宮と木の丸殿 <福岡県朝倉市>
★ 水城と大宰府 <福岡県太宰府市>
★ 古代の迎賓館 鴻臚館 <福岡市中央区>
★ 河原左大臣 源融を祀る 融神社 <滋賀県大津市>
★ 藤原高藤と宮道列子のロマンスの地 山科 <京都市山科区>
★ 『東風吹かば…』飛梅伝説を追え! <京都市・福岡県太宰府市>
★ 熊本に平安時代の歌人・清原元輔をたずねる <熊本市西区・熊本市中央区>
★ 『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く <京都市下京区>
★ 『源氏物語』ちはやぶる金の岬 織幡神社 <福岡県宗像市>




























 『枕草子』第九十五段の一部より
『枕草子』第九十五段の一部より