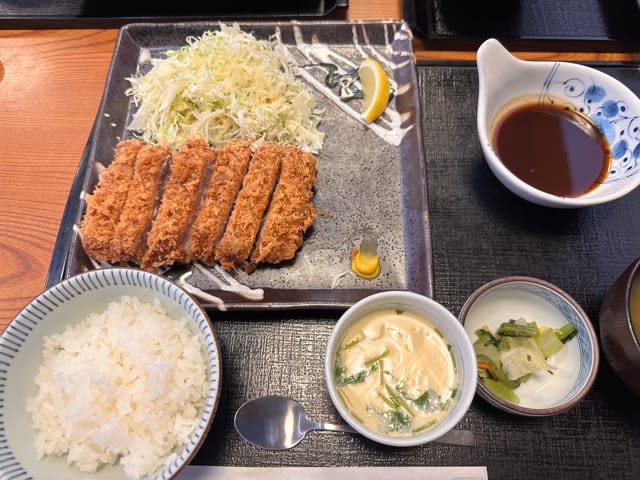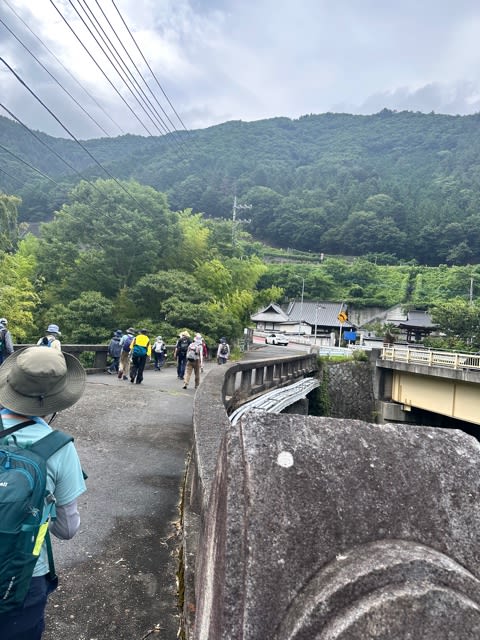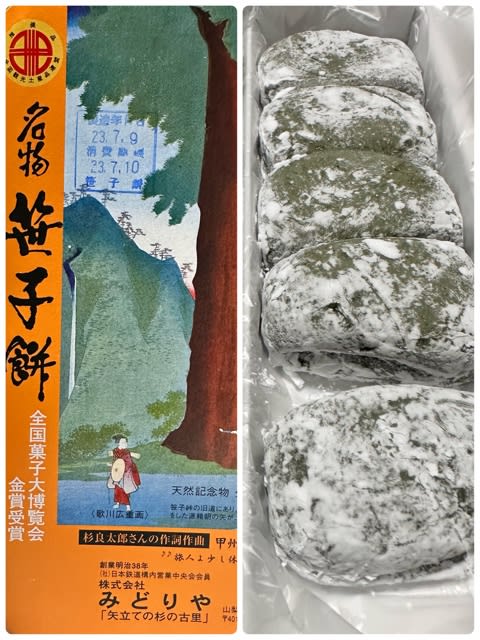10月14・15日
甲州街道を歩く13回 石和から韮崎まで
1泊2日です
7:30分 新宿駅集合です
7時には新宿駅に着いていなくては
なりません
新幹線使いませんのでね
最寄りの駅を5:30の電車に乗らなくちゃ
間に合わないのよ
新宿駅をバスで出発
高速道路を2時間ほど走り
1日目のスタート地点に着きました
なんだか歩き始める前に
疲れてしまいました
10:42 石和八幡宮
武田家の氏神
1582年織田軍に焼かれましたが
翌年徳川家康によって再建されてます
ここから250mほど先までが石和宿

10:50 笛吹市から甲府市に入りました

街道には丸い道祖神が・・・
山梨の道祖神は丸いのが特徴のようです

1石六地蔵
1つの石に6体のお地蔵さんが彫ってあります

三差路交差点
青梅街道と合流

11:40 山崎刑場跡
300年前に
切り捨て場2か所
首洗い井戸4か所
骨捨て井戸1か所があったと伝えられている
明治5年の処刑を最後に今は跡形もなく
供養塔のみ
甲府城下の入り口にあたり
「南無妙法蓮華経」と刻まれている

街道沿いに山梨学園大学ありました
箱根駅伝の常連校よね

12:00 酒折宮
祭神は日本武尊
古事記・日本書記によると
日本武尊が東征の帰りに立ちより
老人と歌問答を交わした伝説があり
連歌発祥の地とされている
最近の朝ドラ「舞い上がれ」で和歌の
やり取りの連歌って見た気がします

石川家住宅
江戸時代から金物屋・まゆ問屋などを営んでいた旧家

12:50 天尊躰寺
「目に青葉 やまほととぎす 初鰹」を歌った
山口素堂の墓がある

街道沿いに印伝の店舗
甲府で400年以上にわたって作られている
伝統工芸品
鹿革に漆で模様をつけた工芸品です
バックとか財布とか小物入れが
あるのよね
でもすごくお高いのです
私は小さなバッグを1個持ってます
自分で買ったのではありません
先輩からいただきました

13:10 ちょっと遅めのお昼ご飯

食後に
お好きなアイスをどうぞ・・・って
山梨の有名なあのケーキ屋さんのアイスです
ただし1個だけよ
ものおじしない昔のお嬢さん方は
1個って言っておかないと
何個でも食べちゃうからね

甲府柳町宿
本陣1軒
脇本陣1軒
旅籠 21軒
今の甲府市街は信玄の父が石和から移って
躑躅ヶ崎館に居館を構えたのが始まり
14:10 舞鶴城公園
自然丘陵の城跡が舞鶴城公園となっている

甲府城跡
武田氏滅亡後、甲斐国は織田信長の領地となり
本能寺の変後は徳川家康の支配下となり
家康の命で築城されました

街道歩き始めてから
「街道歩き友」がたくさんできました
還暦過ぎてから新しい友ができるって
すごいと思います
毎回、今回はどなたと会えるかなぁ~~って
楽しみです
甲府城百名城の1つだった
100名城の本持ってこなかった
残念・・・
また判子をもらいに来なくちゃ

15:40 武田神社
東西280m南北190mの土塁に囲まれた武田氏の本拠
躑躅が崎館跡
信玄の父が石和から居を移し
以後信玄・勝頼と60年間武田氏の住居と政庁を兼ねた
本拠地・・・

大河ドラマで
阿部寛、信玄が
「この地に米と塩があったならもっと強くなれたのに・・・」
とか、言ってたよね
この館でそんなこと言ってたのよね
カッコよかったね阿部寛,信玄・・・

神社の前に信玄ミュージアムってのがありました
特別展示は有料なのですが
常設展示は無料だったので
さらっと見てきました
松潤の家康~~
最初は全くピント来ませんでしたが
最近、なじんできました
岡田准一の信長はカッコよかったねぇ~~
家康の耳舐めた時は気持ち悪かったけどね・・・
秀吉役のムロツヨシも最後の死ぬシーンは
迫力あったね
信玄役の阿部寛はもちろんカッコよかった
大きな体にあの重たそうな衣装がさらに
大きく見えて迫力がありました
ミュージアムでどうする家康の皆さんと
パチリ
私・・・ミーハーなんでこういった
写真は好きです笑笑

16:20 甲州善行寺
なになに、善行寺って長野にもありますよ
甲州にもあるの???
信玄が川中島の合戦で善行寺が戦火にさらされるのを
恐れて、本尊以下、諸仏、寺宝をこの地に移し
供養をしていたそうです
武田氏滅亡後は岐阜・尾張・京都・浜松などの寺を50年めぐって
信濃善光寺に戻ったそうです
ふおえぇ~~
そうだったんだぁ~~
信濃善光寺の御本尊様が
そんな旅をしていたなんて
知らなんだわぁ~~
次郎嫁は長野県人なんで
聞いてみよ
知らなかったら
「長野善行寺のご本尊様って、疎開の旅に50年以上もでていたのよぉ~~」って
鼻高で語ってあげよう~~っと

甲斐善光寺の今のご本尊は
信濃善光寺の前立仏の善光寺如来だって
ここの御開帳も信濃善光寺と同じ7年に1度だって

甲州街道を歩く13回
石和から韮崎までの1日目はここまで

バスに乗ってホテルに向かいました



































 像
像