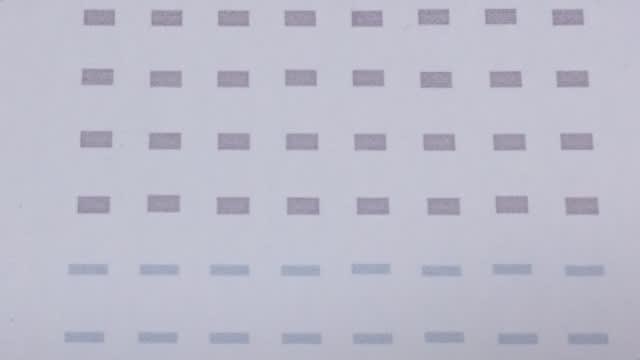TOMYTEC製京浜急行1000形1005F冷房改造車(1005F)はプロトタイプが崩れています。
デハ1005+デハ1006用OK-18台車を京成1000形1037F-3前期仕様へ転用しました。
現在両車にはTS-310台車を廻しています。

京浜急行1000形1005F 冷房改造車。
[1005F]:1005-1006-1007-1008。
グリーンマックス製OKタイプ台車(5014)でOK-18台車を代用する手段もありました。
しかしOK-18台車とOK-18台車では外観差異が大きく気乗りしませんでした。
そこでTS-310台車のまま京成1000形1029F後期仕様(1029F-3)への改装が浮上しています。

入工中のデハ1005。
4両編成分割後の京成1000形は貫通扉種別表示窓追設とアーマープレート切除が行われました。
これらを再現するには車体への加工が避けられません。
先ずデハ1005を入場させ無理のない範囲で後期仕様らしくできるか試してみました。

整形箇所を塗装したデハ1005。
貫通扉桟板モールドは全て削り取ります。
アーマープレートはアンチクライマー端部から1mmだけ残しました。
何れもクラフトナイフを滑らせながら処理しています。

塗装を終えたデハ1005。
どうにか切除できましたが貫通幌座を失ってしまいました。
マスキングテープで保護していましたが粘着力が勝ったようです。
従ってモールド切除箇所の塗装に加え貫通幌座モールドの補修が発生しました。

デハ1005 [■ 15 ■]:アーマープレート切除車。
GMカラー#29(バーミリオンA)を吹き付けましたが色温度差は隠せません。
事業者限定品ならもう少し差が縮まっていたと思います。
一方貫通幌座は油性ペイントリムーバーながら馴染んでくれました。

京成1000形モハ1029 [普通 B 7 ■ 津田沼]:貫通扉種別板表示窓追設車。
改番は[1005]標記印刷を流用する節約式です。
[1005]標記印刷はラプロス#3000で消去しました。
そして[1029]標記インレタを追加転写しています。
行先表示類は[普通 B 7 ■ 津田沼]で全て自作ステッカーを貼り付けました。
なお少しでも切除痕を隠すため[■]表示は一回り大きくしています。

モハ1029,モハ1029 (1029F-1,1029F-3)。
最後に全高が揃っていなかったクーラーキセを修正しました。
原因は湯口跡で一度全台を取り外し調整しています。
遂にモハ1029後期仕様(1029F-3)が竣工しました。
予想よりもアーマープレート切除が効果的に見えました。
●1000形
※改訂:2024年7月8日
デハ1005+デハ1006用OK-18台車を京成1000形1037F-3前期仕様へ転用しました。
現在両車にはTS-310台車を廻しています。

京浜急行1000形1005F 冷房改造車。
[1005F]:1005-1006-1007-1008。
グリーンマックス製OKタイプ台車(5014)でOK-18台車を代用する手段もありました。
しかしOK-18台車とOK-18台車では外観差異が大きく気乗りしませんでした。
そこでTS-310台車のまま京成1000形1029F後期仕様(1029F-3)への改装が浮上しています。

入工中のデハ1005。
4両編成分割後の京成1000形は貫通扉種別表示窓追設とアーマープレート切除が行われました。
これらを再現するには車体への加工が避けられません。
先ずデハ1005を入場させ無理のない範囲で後期仕様らしくできるか試してみました。

整形箇所を塗装したデハ1005。
貫通扉桟板モールドは全て削り取ります。
アーマープレートはアンチクライマー端部から1mmだけ残しました。
何れもクラフトナイフを滑らせながら処理しています。

塗装を終えたデハ1005。
どうにか切除できましたが貫通幌座を失ってしまいました。
マスキングテープで保護していましたが粘着力が勝ったようです。
従ってモールド切除箇所の塗装に加え貫通幌座モールドの補修が発生しました。

デハ1005 [■ 15 ■]:アーマープレート切除車。
GMカラー#29(バーミリオンA)を吹き付けましたが色温度差は隠せません。
事業者限定品ならもう少し差が縮まっていたと思います。
一方貫通幌座は油性ペイントリムーバーながら馴染んでくれました。

京成1000形モハ1029 [普通 B 7 ■ 津田沼]:貫通扉種別板表示窓追設車。
改番は[1005]標記印刷を流用する節約式です。
[1005]標記印刷はラプロス#3000で消去しました。
そして[1029]標記インレタを追加転写しています。
行先表示類は[普通 B 7 ■ 津田沼]で全て自作ステッカーを貼り付けました。
なお少しでも切除痕を隠すため[■]表示は一回り大きくしています。

モハ1029,モハ1029 (1029F-1,1029F-3)。
最後に全高が揃っていなかったクーラーキセを修正しました。
原因は湯口跡で一度全台を取り外し調整しています。
遂にモハ1029後期仕様(1029F-3)が竣工しました。
予想よりもアーマープレート切除が効果的に見えました。
●1000形
※改訂:2024年7月8日