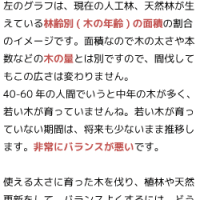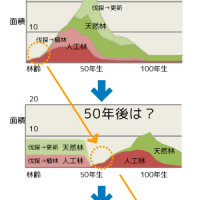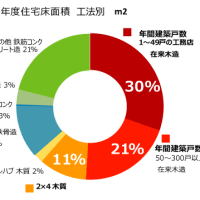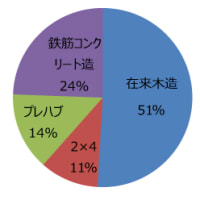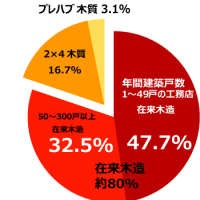今日、例の本が届いた。
詳細は また書きますが学会では「異端」とされながらも
自ら現状に接し「松枯れ」をなんとかしたいと信じる道を
進んでこられたのだと感服ました。
前の天皇とのエピソードもあり、土壌と菌類と樹の関係が
こんなにも密接だったのかとわかり 読み応えがありそうです。
その中にも出てきますが 樹の樹液というのは栄養分も運ぶが
外敵から身を守る為、また 傷ついた我が身を治す為にも使われてる。
去年の夏 アリが樹液をすっているとこを見つけて写真を撮った。

拡大

この木は 直径60cm位の杉なんだけど わけあって2月末に伐った。
新月伐採や旬伐りには、少し遅い。
旧暦でなんでくそ寒い2月のあたまが正月で立春なんだろと思ってたけど
二月の最初の新月から、植物は秘かに春に備えての準備を始めるらしい。
11月に伐った木からは ほとんど樹液は出ていない。
10月に伐った木は、秋の活動の後なので樹液が出ていた形跡がある。
接写モードのやり方がわからず 少しボケたけど
すごく綺麗で 宝石のような樹液でしょ。
同じ木なのに いろんな色があって ちょうど木酢液の原液から
蒸留した製品までの色と一緒だ。
そんな事に気がついてから 丸太を見る目が
セリに並ぶ マグロの尻尾の切り口を見るがごとくになってきた。
樹液の具合で、製品の良し悪しが判断できないだろうか…。
ネットで調べてみたが 研究している人は見つからなかった。
京大の先生にも聞いてみたが、学会的には興味の対象から
はずれることのようだ。
この木は、倒れた時に傷がついたのかもしれないし
伐り旬の違いかもしれない。
製材してしまうと わからない。
この樹液が見られるのも 山で葉枯らしをして 天然乾燥を
しているからだ。
今は、伐り旬も関係なく伐採し 伐採したらすぐに運び出され
製材されて乾燥機に入れられ出荷される木材が多い。
合理的ではあるし、ニーズに応える為にも商売の為にも
スピードは必要だし 一年中出荷しないと業者としては
成り立たないのもわかる。
国際競争力の名の元に、コストダウンと含水率 安定供給が
優先される。プレカットにするには、何らかの方法で
木事体も安定させなければならないので 人工的に乾燥させる。
オブラートに包んだ言い方をすると つまり少し細胞をいじる事になる。
この樹液に含まれる成分が、ある段階では虫や菌を防御してくれる成分の元にもなり、餌にもなるのである。
松枯れも、その防御する成分が少なくなった時に虫にやられるらしい。
偶然というか必然というか 今日 地松を売って頂けるかもしれない話が突然、舞い込んだ。このまま、ほっておけば 虫にやられるのは目に見えているという感じでもあった。
「古来 クロマツ アカマツは日本の暮らしと共に育ち 資源林として大きな価値があった。また 資源がなくなる時がきたら頼ることになる。自然の成り行きだと諦めてしまってよいのか・・・」
という 本の一説が 心に響いた。
詳細は また書きますが学会では「異端」とされながらも
自ら現状に接し「松枯れ」をなんとかしたいと信じる道を
進んでこられたのだと感服ました。
前の天皇とのエピソードもあり、土壌と菌類と樹の関係が
こんなにも密接だったのかとわかり 読み応えがありそうです。
その中にも出てきますが 樹の樹液というのは栄養分も運ぶが
外敵から身を守る為、また 傷ついた我が身を治す為にも使われてる。
去年の夏 アリが樹液をすっているとこを見つけて写真を撮った。

拡大

この木は 直径60cm位の杉なんだけど わけあって2月末に伐った。
新月伐採や旬伐りには、少し遅い。
旧暦でなんでくそ寒い2月のあたまが正月で立春なんだろと思ってたけど
二月の最初の新月から、植物は秘かに春に備えての準備を始めるらしい。
11月に伐った木からは ほとんど樹液は出ていない。
10月に伐った木は、秋の活動の後なので樹液が出ていた形跡がある。
接写モードのやり方がわからず 少しボケたけど
すごく綺麗で 宝石のような樹液でしょ。
同じ木なのに いろんな色があって ちょうど木酢液の原液から
蒸留した製品までの色と一緒だ。
そんな事に気がついてから 丸太を見る目が
セリに並ぶ マグロの尻尾の切り口を見るがごとくになってきた。
樹液の具合で、製品の良し悪しが判断できないだろうか…。
ネットで調べてみたが 研究している人は見つからなかった。
京大の先生にも聞いてみたが、学会的には興味の対象から
はずれることのようだ。
この木は、倒れた時に傷がついたのかもしれないし
伐り旬の違いかもしれない。
製材してしまうと わからない。
この樹液が見られるのも 山で葉枯らしをして 天然乾燥を
しているからだ。
今は、伐り旬も関係なく伐採し 伐採したらすぐに運び出され
製材されて乾燥機に入れられ出荷される木材が多い。
合理的ではあるし、ニーズに応える為にも商売の為にも
スピードは必要だし 一年中出荷しないと業者としては
成り立たないのもわかる。
国際競争力の名の元に、コストダウンと含水率 安定供給が
優先される。プレカットにするには、何らかの方法で
木事体も安定させなければならないので 人工的に乾燥させる。
オブラートに包んだ言い方をすると つまり少し細胞をいじる事になる。
この樹液に含まれる成分が、ある段階では虫や菌を防御してくれる成分の元にもなり、餌にもなるのである。
松枯れも、その防御する成分が少なくなった時に虫にやられるらしい。
偶然というか必然というか 今日 地松を売って頂けるかもしれない話が突然、舞い込んだ。このまま、ほっておけば 虫にやられるのは目に見えているという感じでもあった。
「古来 クロマツ アカマツは日本の暮らしと共に育ち 資源林として大きな価値があった。また 資源がなくなる時がきたら頼ることになる。自然の成り行きだと諦めてしまってよいのか・・・」
という 本の一説が 心に響いた。