
中世を旅する人びと ヨーロッパ庶民生活点描
阿部謹也 著
ちくま学芸文庫
2008年7月10日 第一刷発行
Ⅰ 道・川・橋
1 村の道と街道
道の霊をめぐる信仰や慣行は十字路に最も際立った形で集中していた。十字路は良き霊と悪しき霊が集まるところとして、いろいろな迷信の対象となっていた。p20
2 川と橋
12、3世紀には河川が重要な交通手段として浮かび上がってきた。各種の平底船や引き綱船が開発され、大量の商品の輸送が可能になってきた。引き綱船のための堤防には家などを建てることは禁じられてきた。p34
橋梁建設技術が未熟で財政も不十分であったため、中世の橋は今日のわれわれが現代の橋について感じているように堅固で恒久的なものではなく、一人一人が支えなければ維持しえないものと考えられていた。
財政面での助力はいうまでもなく、河の霊や水の精をなだめたり、橋のたもとに小聖堂を建てて神に祈ることによって、辛うじて橋を維持しうると考えられていたのである。p43
Ⅱ 旅と定住の間に
3 渡し守
街道や河川、橋と違って、渡し守は常に人間(渡し守)によって運営されねばならなかった点で、前述の三つの交通手段とは異なった性格を持っていた。つまり最初から「法的制度」として発展してきたのである。
公的な街道においては渡し場を設ける権利も国王の大権に属していた。しかし渡し舟の実際の運用は、この大権を手に入れた修道院や都市、諸侯から臣下などに委ねられていた。p46
4 居酒屋・旅籠
エラスムスの『対話集』(1523年版)に収録されている「旅籠についての対話」でドイツの宿について述べられている。
この男は黙って皆を見渡して頭数を数える。数が多ければ、その分だけ暖炉に火をくべる。たとえ温度が高くてもそうするのだ。連中には皆が汗をぐっしょりかけば、厚くもてなしたことになるのさ。
(柳田國男の「清光館哀史」で、旅籠に到着した時、夏にもかかわらず火を起こして客をもてなしたという一節がありました)
いずれにせよ旅をすみかとしたようなエラスムスが、ドイツのどこかの宿で腹を減らして食事を今か今かと不機嫌な顔をして待っていた様子を想像すると、ホルバインの描く謹厳なエラスムス像などと重ね合わせてなんとも親しみがわいてくる。それがドイツ人論までゆきかねないのだから、やはり食物の恨みはおそろしいというべきか。p72
Ⅲ 定住者の世界
5 農民
6 共同浴場
農民戦争の敗北と前後して都市の共同浴場は急速に姿を消していった。
その原因については、木材(燃料)の価格が騰貴したこと、梅毒の流行、浴場が堕落頽廃したこと、浴場での治療が禁じられたこと、浴場が教会と国家に対する反体制派の溜まり場になったこと、などの原因が絡み合ったためといわれる。p116
7 粉ひき・水車小屋
水車が一般に普及したのはまさに中世になってからである。豊かな奴隷労働力を持っていた古代世界においては人力を節約する必要は全くなく、むしろ飢えた大衆に仕事を与えなければらなかったから、せっかくの(水車の発明も)実用化の社会的需要を持っていなかったのである。p125
水車使用強制権という悪法に対して、ヨーロッパの庶民はいたるところで自家用の手回し碾臼を使って抵抗した。p133
8 パンの世界
キリスト教がヨーロッパに普及していく以前から穀物とパンとは、われわれにとっての米と餅のような、あるいはそれ以上の役割をヨーロッパの人々の生活の中で果たしていた。













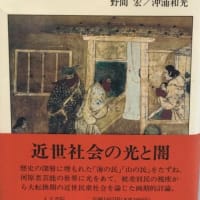






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます