面構えのりりしい営団05系

ウィキさんによれば
1988年(昭和63年)11月16日より営業運転を開始した帝都高速度交通営団(営団)の通勤形電車
2004年(平成16年)4月の営団民営化にともない、東京地下鉄(東京メトロ)に継承された
当初は東西線用として製造され、2014年(平成26年)4月28日からは千代田線北綾瀬支線(綾瀬駅 - 北綾瀬駅間)でも運用されている
とのこと
こいつで前面展望をしたいときには、ちょっと注意が必要だ
先頭車に乗り込むと

乗務員室とのしきり窓の中央がなぜかオレンジ色なのだ
そこから覗くと、まるでアニメに出てきそうな夕景だ

この色の景色を見ていると、昼でもお家に帰りたくなってくるから不思議だ
しかたなく右の窓から覗くと、視野が狭く気分がもやもやする

このオレンジ窓が使用されているのは9次車まで
2001年度製造の10次車以降はグレーの着色ガラスが使用されている
グレーならオレンジよりはまだましだ
見分け方は、おでこの真ん中の数字05に続く部分が031以降であればグレーのガラスになっている

前面展望もなかなか面倒だな
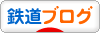 にほんブログ村
にほんブログ村
 鉄道ランキング
鉄道ランキング

ウィキさんによれば
1988年(昭和63年)11月16日より営業運転を開始した帝都高速度交通営団(営団)の通勤形電車
2004年(平成16年)4月の営団民営化にともない、東京地下鉄(東京メトロ)に継承された
当初は東西線用として製造され、2014年(平成26年)4月28日からは千代田線北綾瀬支線(綾瀬駅 - 北綾瀬駅間)でも運用されている
とのこと
こいつで前面展望をしたいときには、ちょっと注意が必要だ
先頭車に乗り込むと

乗務員室とのしきり窓の中央がなぜかオレンジ色なのだ
そこから覗くと、まるでアニメに出てきそうな夕景だ

この色の景色を見ていると、昼でもお家に帰りたくなってくるから不思議だ
しかたなく右の窓から覗くと、視野が狭く気分がもやもやする

このオレンジ窓が使用されているのは9次車まで
2001年度製造の10次車以降はグレーの着色ガラスが使用されている
グレーならオレンジよりはまだましだ
見分け方は、おでこの真ん中の数字05に続く部分が031以降であればグレーのガラスになっている

前面展望もなかなか面倒だな
 鉄道ランキング
鉄道ランキング
電車の中から電車や駅を撮影してみよう
今回は三鷹駅から中野駅までの直線区間

三鷹駅を出発
線路は左から順に中央線上り、下り、総武線上り、下り

直線区間らしいまっすぐな線路が東に向かって延びている
沿線では人気のオシャレな町、吉祥寺駅

線路が曲がりながらホームへと続いている
これで直線区間なのかという疑問が湧くが、4本の線路を構成する敷地の中央を結ぶと直線ということらしい
なんかだまされているような気がするが、先へと進む
西荻窪から出てきたE233系

ホームで待ちながら撮影している時に比べ、こちらが移動しているので電車との遭遇率は格段に跳ね上がる
荻窪駅

荻窪を出て見えるのは青梅街道の天沼陸橋

この陸橋が出来たのが1955年
2年後に中央線・総武線の高架化工事が始まったときに、この陸橋が邪魔になり荻窪駅は高架化されなかったという、涙の黒歴史があるそうな
ひところは漫画家が多く住んでいた阿佐ヶ谷

今でも住んでいるのかな、漫画家
阿佐ヶ谷を出るとE257 特急あずさが来た
うりゃ

シャッタースピードを1/500にしてみたらLED表示がちゃんと写っていた
阿佐ヶ谷を出ると大きく下る
線路が曲がっているよなあ

高円寺から出てきたE233

どんどん電車がやって来るな
高円寺、
音楽関係者やプロレスラーの多い町だと聞いている

このあたりの駅間は狭い
そもそも中野から境(現在の中央線武蔵境駅)の間に駅はなかった
以下中央線の駅だが、開業順に
1891年 荻窪
1899年 吉祥寺
1906年 柏木(現在の東中野駅)
1922年になってやっと高円寺駅・阿佐ヶ谷駅・西荻窪駅が開業
三鷹駅の開業は、1930年になってやっとなのはびっくりだ
さて高円寺駅・阿佐ヶ谷駅・西荻窪駅の三駅だが鉄道会社と地域との駆け引きの中で誕生したようだ
おそらく地域住民がおらが町に駅をということで、互いに一歩も譲らなかったのだろう
ちなみに三駅の開業日は7月15日で全く同じ年同じ日なのだそうな
さて、中野駅が見えてきた

中野ブロードウェイには「まんだらけ」の本社をはじめとして、様々なマニアックアイテムを扱っている店が多いので、第二の秋葉原として注目されているぞ
下りのE231系とすれ違い

中野駅は1889年に甲武鉄道の新宿駅 - 立川駅間開通と同時に開業した由緒ある駅だ

ここまでが直線区間
この先はカーブも多く高低差もある表情豊かな前面展望になる
それはまた後日に
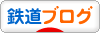 にほんブログ村
にほんブログ村
 鉄道ランキング
鉄道ランキング
今回は三鷹駅から中野駅までの直線区間

三鷹駅を出発
線路は左から順に中央線上り、下り、総武線上り、下り

直線区間らしいまっすぐな線路が東に向かって延びている
沿線では人気のオシャレな町、吉祥寺駅

線路が曲がりながらホームへと続いている
これで直線区間なのかという疑問が湧くが、4本の線路を構成する敷地の中央を結ぶと直線ということらしい
なんかだまされているような気がするが、先へと進む
西荻窪から出てきたE233系

ホームで待ちながら撮影している時に比べ、こちらが移動しているので電車との遭遇率は格段に跳ね上がる
荻窪駅

荻窪を出て見えるのは青梅街道の天沼陸橋

この陸橋が出来たのが1955年
2年後に中央線・総武線の高架化工事が始まったときに、この陸橋が邪魔になり荻窪駅は高架化されなかったという、涙の黒歴史があるそうな
ひところは漫画家が多く住んでいた阿佐ヶ谷

今でも住んでいるのかな、漫画家
阿佐ヶ谷を出るとE257 特急あずさが来た
うりゃ

シャッタースピードを1/500にしてみたらLED表示がちゃんと写っていた
阿佐ヶ谷を出ると大きく下る
線路が曲がっているよなあ

高円寺から出てきたE233

どんどん電車がやって来るな
高円寺、
音楽関係者やプロレスラーの多い町だと聞いている

このあたりの駅間は狭い
そもそも中野から境(現在の中央線武蔵境駅)の間に駅はなかった
以下中央線の駅だが、開業順に
1891年 荻窪
1899年 吉祥寺
1906年 柏木(現在の東中野駅)
1922年になってやっと高円寺駅・阿佐ヶ谷駅・西荻窪駅が開業
三鷹駅の開業は、1930年になってやっとなのはびっくりだ
さて高円寺駅・阿佐ヶ谷駅・西荻窪駅の三駅だが鉄道会社と地域との駆け引きの中で誕生したようだ
おそらく地域住民がおらが町に駅をということで、互いに一歩も譲らなかったのだろう
ちなみに三駅の開業日は7月15日で全く同じ年同じ日なのだそうな
さて、中野駅が見えてきた

中野ブロードウェイには「まんだらけ」の本社をはじめとして、様々なマニアックアイテムを扱っている店が多いので、第二の秋葉原として注目されているぞ
下りのE231系とすれ違い

中野駅は1889年に甲武鉄道の新宿駅 - 立川駅間開通と同時に開業した由緒ある駅だ

ここまでが直線区間
この先はカーブも多く高低差もある表情豊かな前面展望になる
それはまた後日に
 鉄道ランキング
鉄道ランキング
線路際やホームから撮影してきたが、どうももどかしい
できるだけ近くから、生き生きとした電車の姿を撮影してみたいという思いが日に日に強くなってきた
ではどうしたらそんな写真が撮れるのか
電車が最も輝いて見えるのは線路を走っている時だろう
では走行中の電車の中から撮影してみたらどうだろう
どんな撮影になるか分からないが、ものは試しだ
というわけで地下鉄東西線に乗ってみた
東西線は地下鉄ではあるが地上区間がやたらと長い
路線距離30.8km中13.8kmが地上区間だ
地上に出て早速来たのは東京メトロ15000系
最近は桁の多い型番の電車が多いのな

連写でうりゃ

揺れる電車の中での望遠なので構図を決めづらいが、なかなかいいんでないかい
ブレを抑えるためにシャッタースピードを上げたせいでLED表示がうまいこと写っていないのは今後の課題だな
乗ったのはこちら 東西線との直通仕様のE231系

撮影を続ける
東葉高速鉄道2000系

営団05系

うりゃ

ガラス越しだが、思っていたより面白い撮影ができた気がする
電車が構図の右に寄っているのは、線路も撮りたかったためであり、撮影者のセンスがひどいわけではない、ということにしておいてくれ
今後も続けてみようかな
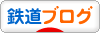 にほんブログ村
にほんブログ村
 鉄道ランキング
鉄道ランキング
できるだけ近くから、生き生きとした電車の姿を撮影してみたいという思いが日に日に強くなってきた
ではどうしたらそんな写真が撮れるのか
電車が最も輝いて見えるのは線路を走っている時だろう
では走行中の電車の中から撮影してみたらどうだろう
どんな撮影になるか分からないが、ものは試しだ
というわけで地下鉄東西線に乗ってみた
東西線は地下鉄ではあるが地上区間がやたらと長い
路線距離30.8km中13.8kmが地上区間だ
地上に出て早速来たのは東京メトロ15000系
最近は桁の多い型番の電車が多いのな

連写でうりゃ

揺れる電車の中での望遠なので構図を決めづらいが、なかなかいいんでないかい
ブレを抑えるためにシャッタースピードを上げたせいでLED表示がうまいこと写っていないのは今後の課題だな
乗ったのはこちら 東西線との直通仕様のE231系

撮影を続ける
東葉高速鉄道2000系

営団05系

うりゃ

ガラス越しだが、思っていたより面白い撮影ができた気がする
電車が構図の右に寄っているのは、線路も撮りたかったためであり、撮影者のセンスがひどいわけではない、ということにしておいてくれ
今後も続けてみようかな
 鉄道ランキング
鉄道ランキング











