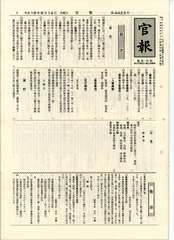2007年8月27日付の読売新聞・夕刊1面の記事に関するお話。
記事内容をまとめると、防衛省は、「企業の若手社員を対象に、
自衛隊に2~3年の期限付きで入隊させる「レンタル移籍制度」の
創設を検討している」とのこと。
読売新聞は、防衛省が「高卒」の若手隊員の人材不足、
「任期制自衛官」の制度での人材募集が難しくなる状況において、
「人材確保策の一環」としての施策であるとしているが、
果たしてそれだけなのかは、疑問である。
表向きには、読売新聞によれば、「背景には自衛隊の若手教育に対する
企業側の期待もある」としているが、実際のところ、「身分は通常の自衛官と同じで、
訓練内容も変わらない」のでは、実質的には、民間企業の社会人の自衛隊
隊員への即応力を調査することもでき、将来の有事に当たって、人員不足が生じた
際に、どれだけの国民を隊員とすることができるのかを調査する目的があるのでは
ないかと、危惧している。というのは私だけだろうか。
どうやら読売新聞の調べでは、企業では現在、「自衛隊人気」があるそうで、
「企業研修に協力する」名目で自衛隊が「3~4日間の社員の体験入隊」を
認めているそうだ。その数も増えつつあり「昨年度の陸自体験入隊は約1万5000人」。
送り出す企業も「団体生活を経験して社員の意識が向上」しているとの効果を
上げているが、これもまた、表向きには企業の研修費の削減と自衛隊の広報活動の
両者の目的がマッチした形であるといえるのだろう。
しかし、実際に企業が国家とくに国防を預かる防衛省に人材を派遣するというのは、
とても不自然な流れであって、どう考えても防衛省のある目的の名の下に
行われている活動の一環に、企業がうまく乗らされてしまっているような
印象が否めない。ぜひとも、企業の人事担当者は、安易に外部に研修を
委託するのではなく、よく考えた上で派遣をしてもらいたい。
<編集後記>
あくまでも個人的な考えで、考え過ぎなのかもしれません。
しかし、ジャーナリストの斎藤貴男氏の講演や著書を読む限りでは、
国家のただならぬ方向性を感じざるを得ず、
このような記事となりました。
次号では、ある本の書評にチャレンジしていますので、
ぜひ、ご覧ください。
~ムッシュ・いけふくろう~
記事内容をまとめると、防衛省は、「企業の若手社員を対象に、
自衛隊に2~3年の期限付きで入隊させる「レンタル移籍制度」の
創設を検討している」とのこと。
読売新聞は、防衛省が「高卒」の若手隊員の人材不足、
「任期制自衛官」の制度での人材募集が難しくなる状況において、
「人材確保策の一環」としての施策であるとしているが、
果たしてそれだけなのかは、疑問である。
表向きには、読売新聞によれば、「背景には自衛隊の若手教育に対する
企業側の期待もある」としているが、実際のところ、「身分は通常の自衛官と同じで、
訓練内容も変わらない」のでは、実質的には、民間企業の社会人の自衛隊
隊員への即応力を調査することもでき、将来の有事に当たって、人員不足が生じた
際に、どれだけの国民を隊員とすることができるのかを調査する目的があるのでは
ないかと、危惧している。というのは私だけだろうか。
どうやら読売新聞の調べでは、企業では現在、「自衛隊人気」があるそうで、
「企業研修に協力する」名目で自衛隊が「3~4日間の社員の体験入隊」を
認めているそうだ。その数も増えつつあり「昨年度の陸自体験入隊は約1万5000人」。
送り出す企業も「団体生活を経験して社員の意識が向上」しているとの効果を
上げているが、これもまた、表向きには企業の研修費の削減と自衛隊の広報活動の
両者の目的がマッチした形であるといえるのだろう。
しかし、実際に企業が国家とくに国防を預かる防衛省に人材を派遣するというのは、
とても不自然な流れであって、どう考えても防衛省のある目的の名の下に
行われている活動の一環に、企業がうまく乗らされてしまっているような
印象が否めない。ぜひとも、企業の人事担当者は、安易に外部に研修を
委託するのではなく、よく考えた上で派遣をしてもらいたい。
<編集後記>
あくまでも個人的な考えで、考え過ぎなのかもしれません。
しかし、ジャーナリストの斎藤貴男氏の講演や著書を読む限りでは、
国家のただならぬ方向性を感じざるを得ず、
このような記事となりました。
次号では、ある本の書評にチャレンジしていますので、
ぜひ、ご覧ください。
~ムッシュ・いけふくろう~