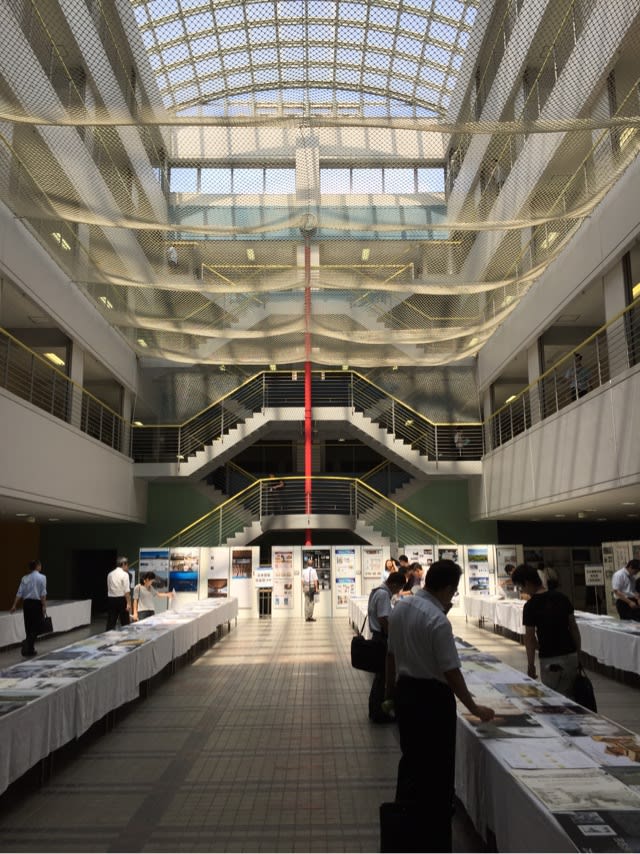2008年に「真のプロフェッショナルの受難」という記事を書いた
「それにしても、耐震偽造事件以降の法改正の動きは何か変だ
現時点で頼りになる老練なプロフェッショナルを切り捨てるような結果になっている
実力のない資格だけの稚拙なえせプロフェッショナルばかりになっては、誰をたよりに設備設計をすればいいのかとまどうばかりだ
問題が社会に重大な影響を与えないうちに見直しを希望してやまない」
それから14年が経とうとしているが、建築設計者のうちの電気設計のプロフェッショナルはだんだんいなくなってきて、まさに風前の灯となっているのではないかと危惧している
ご存知ではない方も多いと思うので事情を説明すると、建築設備の設計者は規模に応じて設備一級建築士という資格を取らないと仕事ができないことになったが、設備設計のうちの電気の設計者は建築系の大学を出た方はほとんどなく、一級建築士を受験できないしできたとしても構造計算など専門外でまず合格できない
対して空調や給排水などの設計者は建築系の大学に研究室がたくさんあるので構造もあるカリキュラムから考えて、空調や給排水の設備設計者は合格可能な方が大勢存在する
電気設計は明らかに建築系のカリキュラムから外れていいて、今いる電気設計のプロフェッショナルは当たり前だが電気系の学校を出ている方がほとんどだ
そのため、電気設計者は空調や給排水が専門の設備一級建築士の下請け的な立場に置かれているのが実情である
この人たちを「設備一級建築士という資格」が取れないことで差別していいのだろうか?電気設計の能力に構造計算は必要なはずがないのに制度は今だに改善されていないことに苛立ちを覚えるのは私だけでないはずだ
このままだと、能力のある電気設計者の技能が伝承されずに建築設計界で大きな問題になるはずで、至急プロフェッショナルを守る資格を作るべきだ
設備一級建築士制度を作った人には見えないかもしれないが、空調設備や給排水設備設計と電気設備設計の分野は全く違うことを認識しなくてはいけないと思う
今からでも遅くないので、至急建築の電気設備設計資格を別途に新設することを願う
「建築電気設備設計士」でどうか?