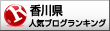昭和8年、香川新報社発行の『勝地讃岐と其産業陣営』に
仁尾の朝日庖刀と大矢根商会という項目がある。
三豊郡仁尾町の特殊生産事業としてその存在を謳われるものに庖刀製造大矢根商会がある。
然して製造の濫觴(らんしょう:起源)と見るべきは、当主大矢根良吉氏の祖父大矢根政右衛門翁の刀剣鍛冶職に発し、同翁は西讃に有名なる刀匠であったが、その後時代は封建を拭って明治維新となり、帯刀廃止令出づるや当時悉ゆる(あらゆる)刀匠は時代に敗残を喞つ(かこつ:不平を言う)やむなきに至った。
爰に(ここに)政右衛門翁はよくその転換の途を考察し、決然煙草截断(せつだん:切断)用の庖刀製造を着創した。刀剣鍛磨に熟練の翁は、愈々(いよいよ)その業に精進すれば製品の声価は謂わずもがな、朝陽の如くであり。
次いで辰次氏その業を継ぎ、更に当主良吉氏父業を継承するに及ぶや明治31年資本金15万円を以て合名会社を組織し、以来一大飛躍を遂げて今日に至って居る。
目下その製品年産二十万枚に上り、専売局製品を主として一部は支那方面への輸出を見ているが、同商会製品朝日庖刀の声価八紘に高きも蓋しこの由緒ある鍛冶によるものであろう。
この記事に見える大矢根商会は、当時の大矢根兄弟商会と思われる。
そして、現在の「大矢根利器製作所」に発展する。
その礎(いしずえ)は、紛れもなく仁尾にある。
参照:
株式会社大矢根利器製作所HP
→
仁尾の朝日庖刀2~大矢根兄弟商会(三豊市仁尾町)
←
第17回仁尾八朔人形まつり~浦島太郎【三豊市仁尾町】
お読み下さり、ありがとうございます。ブログランキングに参加しています。
下のボタンのどれか一つ押して下さればとても嬉しいです。