民事訴訟
民事紛争 (私人間間の財産と身分を規律する)
民事訴訟(裁判手続き)
裁判によって、権利の存否を確定し、解決する
(判決によらずに終了することもある)
判決→→判決
原告(裁判所への判決要求)
手続:一定の目標に向かい人の行為が積み重なっていくこと
判決手続き:当事者や裁判所の行為が・・・・・・
※被告(人)とは言わない
裁判所 最広義:司法部 広義:国法上の裁判所 狭義:事件を担当する裁判官ら(訴訟法上)
第一審(単独制)高裁・最高裁(合議制)右陪席・左陪席
裁判:裁判所が判断を表示する行為
形式/主体/口頭弁論/告知方法/上訴
判決/裁判所/必要的/言い渡し/控訴・上告
決定/裁判所/任意的/相当な方法/抗告
命令/裁判官/任意的/相当な方法/抗告
(1)法による裁判
法的三段論法
法を大前提、事実を小前提、結論を判決
民事訴訟の判決の基準となる法:実体私法 民法など
○○ときには、○○。
(法律要件) (法律効果)権利の発生と消滅
・事実
・要件事実(抽象的)⇔主要事実(具体的)
民事訴訟:要件事実に該当する具体的事実の存否の認定→権利の存否の判断
(2)権利確定手続き
原告:訴にあって、どんな権利を主張するのか、原告は示しておく(請求の確定)
裁判所:請求の権利の存否を判断する
○認める→請求の認容する判断 ○認めない→請求棄却判決
以上は本案判決⇔訴え却下判決(訴えの中身に入らない)
Or 一部認容判決
↓
判決の確定 権利の存否の判断は裁判所も当事者も覆せない(既判力)
◎判決の核心部分にしか生じない
既判力が消滅する場合
※当事者の履行
※時効
※相殺
So;いつの時点の既判力が大切
=事実審の口頭弁論の終結時点=既判力の基準
Ⅱ 民事紛争処理手続きの種類
(1)判決手続き以外
○強制執行
○債務名義(権利の存在を示す文書であり、強制執行に必要)EX 確定判決など
○民事保全手続き(仮差し押さえ、仮処分)
○倒産処理手続き、非訟手続きなど
(2)特別な手続き
○人事訴訟
○行政訴訟
(略式手続)・手形訴訟、小切手訴訟、少額訴訟、督促手続き、簡裁の判決手続きの特則
Ⅲ民事訴訟法
Ⅳ自主的紛争解決(私的自治の法則)
(1)和解
裁判外⇔裁判内
・既決和解(和解調書)→行政執行
(2)調停、仲介
民事調停
家事調停:家事事件手続法 ※調停前置規定 離婚など
↓
調停調書
(3)仲裁:仲裁人(裁判官ではない)紛争解決を委ねる 仲裁法
仲裁判断→執行決定→債務名義になる
(4)裁判外紛争解決手続き(ADR) 米
○民間会社において紛争解決 ADR法
○弁護士会、行政書士会、スポーツ仲裁裁判機構
民事訴訟の概略
■訴え提起=訴状の提出
○必要的記載事項
当事者(=法定代理人)
請求の特定・請求の趣旨(どのような判決が欲しいか)
・請求の原因(主要事実)
■訴え提起の手数料納付
訴額(原告勝訴のときの利益が基準)
事物管轄の基準
管轄 国法上の裁判所間の分担
イ.事物管轄 地方OR簡裁(140万)
ロ.土地管轄 原則被告の住所(普通裁判籍)⇔特別
本人訴訟主義(弁護士代理の原則)
※一定の資格
↑訴訟代理人⇔法定代理人
■(裁判長による)訴状の審査
補正命令、訴状却下命令、訴え却下決定
■訴状の送達
第一回口頭弁論期日の指定、呼出し
期日:時間
答弁書:請求の趣旨に対する被告側の主張
事実に対する否認
■準備書面・答弁書の提出
■口頭弁論(弁論主義)
→争いの無い事実は証拠調べが不要
■訴状の陳述・答弁書の陳述
口頭弁論に上程する意味がある
→裁判所はその事実のみから判断しなければならない
■応答 認める(自白)→裁判所は拘束される
争う A;否認
B;抗弁 (両立する事実をのべる)
■争点および証拠の整理手続き
準備的口頭弁論(弁論準備)非公開
書面による準備手続き
■証拠調べ
証拠の申し出→証拠の採否→証拠調べ
証人尋問、当事者尋問→集中証拠調べの対象
鑑定
書証
検証
◎自由心証主義⇔法定証拠主義
◎証明責任(証拠調べしたがその事実が不明の時)
→その証明ができない責任は証明責任者が負う
■口頭弁論の終結
■第一審判決(第一審の終局判決)
判決書 主文
言い渡し
送達
※調書判決
※仮執行宣言(控訴されても執行できる)
■控訴 2週間(不変期間)
原則 負けた部分がなければならない
■控訴状 原審に提出(原審提出主義)
・原判決に対する不服の当否
事実審:事実についても、法律についても扱う
■上告
法律審:法律について扱う
So;上告審の既判力の基準日は、控訴審の口頭弁論終結時
控訴審の続審主義(第一審の資料を基礎に新たな資料を追加して判断)
CF 覆審、事後審(第一審の証拠のみ) 控訴審の事後審化
控訴審の終結判決
控訴却下 自判が原則 差戻しは例外 WHY 控訴審は証拠調べが可能
⇔上告審 差し戻しが原則
BUT 第一審が簡裁のときではなく、最高裁が上告の時
憲法違反、重要な手続き違反
○上告理由の制限
○裁量上告制;上告受理の申立(法令解釈の重要事項)
EX 判例相反、判例無し 上告受理決定
■判決の確定
A 既判力
B 執行力
C 形成力
再審:確定した判決を取消し、再度審査する
手続保証:誰もが利用できる
6.民事訴訟の基本理念 適正(手続き)、公平(当事者間の公平)、迅速、訴訟経済
→手続きの安定性
→画一的処理の要請 WHY:前の手続きに瑕疵があれば、後の手続きを全て無効にできない
民事訴訟の目的
権利保護説 個人
私的秩序維持説 国家
紛争解決説 通説
訴権 民事訴訟を利用する私人の権能
→公法に基づくもの 抽象的訴権説、具体的訴権説、本案判決請求権説
訴えと請求(訴訟物)
一、訴え=原告の裁判所への判決要求
訴訟行為1、裁判所、2、当事者
○申立 裁判所に対し一定の行為を求める EX訴え
○主張 申し立てを基礎づけるもの EX請求
○挙証
請求認容判決の主文
イ)給付判決:被告人→原告給付を命ずる
(債務名義) ※債権上の給付とは異なる EX 明渡・騒音を出さない(不作為)
◎執行力
ロ)確認判決:権利の存否を確認する
(又は法律関係)略:権利関係⇔事実
※請求棄却判決も含む
ハ)形成判決:法律関係の変動を宣言
(一定の法律要件)
EX離婚→形成要件
A 請求が原告→被告に対する給付請求権の主張
①現在の給付 給付請求権が現存する
②将来の給付
将来現実化すへきもの
(事実審口頭弁論終結時のあと)
B 請求が
①積極的確認 存在確認
②消極的確認 不存在確認
※法律関係の確認=事実確認はできない(原則_
例外;書証の真否確認の訴え
C 訴えを以て裁判所に法律関係の変動を請求できる
意味:判決により、はじめて、変動の効果
EX 契約書の解除は、含まない
○人事訴訟 会社関係訴訟など→対世効があるとされる
CF 既判力は当事者間のみが原則
BECAUSSE 身分関係は社会関係であり、会社関係の影響が広い
後見的国家像→形成判決のこと?
二、請求(訴訟上の) ×訴訟法
原告→被告 権利主張
◎請求権(※異なる)
○支配権
○形成権
これらは民法上の分類=私権
広義:訴訟物=請求
(訴の対象)
狭義:訴訟物→主張する権利関係 ※実務
訴えにおける請求の特定の必要
A 裁判所の審判対象の呈示
B 被告の防御の保証
C 訴訟物理論の問題
イ)実体法説(旧説) 実務
一定の実体権(実体法上の権利・法律関係)の存在
※形成訴訟の訴訟物
形成要件・形成原因毎
ロ)訴訟法説(新設)学者
確認訴訟;一定の実体権の存否
給付訴訟:一定の給付を求める地位
形成訴訟:一定の形成
A 請求権競合
X→所・賃→明け渡せ→Y 実体的に見るか、訴訟法的に見るか?
①所有権(物権的請求権)
②賃借権(債権的)
イ)解除
ロ)明渡
同一の訴訟中に追加した時
旧説:実体権が違うときは、訴訟物が異なるため、二重起訴にならない
バスの運転手と乗客のケガ
①不法行為
②債務不履行
旧説:既判力がおよばない
B ①請求の併合、②訴えの変更、③二重起訴、④既判力
①複数の請求を一つの訴で行うこと(訴えの客観的併合)
②訴訟係属中に請求を変更する
※追加的変更を念頭
③訴訟係属中に、同一の事件につき、別訴を提起することの禁止
=訴状の送達を基点とする考え方
④判決確定後、同一の訴訟物について訴えを提起すると、前訴の確定判決の既判力が後訴におよぶ
旧説: 訴訟物毎
新設: 給付物毎
従って:旧説では、A権で負ければ、B権で戦える
→新説は、紛争の一回的解決(訴訟経済)
WHY 実務は旧説?
既判力の及ぶ範囲は広い(新設)
→再チャレンジできない、裁判所の釈明義務の負担が大きい
民事訴訟の基本原則
行為/当事者主義/職権主義
判断対象の設定/◎処分権主義/職権調査
判断資料の提出/◎弁論主義/職権探知主義
手続きの提出/当事者進行主義/◎職権進行主義
処分権主義
訴訟の開始、修了、対象を当事者の意思に委ねる(私的自治)
終了とは、訴えの却下、和解
A 申立事項=判決事項
ア)裁判所は原告の申し立てた訴訟物に拘束(訴訟物理論)
×A権の訴を、B権の判決
イ)裁判所は原告の申し立てた救済形式に拘束(訴えの類型)
×確認の訴に、給付の判決
ウ)裁判所は原告の申し立てた救済範囲を越えて判決できない
×200万の訴に、300万の判決
B 一部認容判決
原告の意思の尊重=処分権主義
手続き保証(被告の防御)不意打ち防止
○ 200万円の訴に150万の判決(量的一部認容)
○ 無条件の給付要求に、条件付きの判決(質的一部認容判決)
事実抗弁⇔権利抗弁
C 一部請求 分割可能な権利の一部を請求する場合
12億の内1億円を請求
WHY 訴額の減額 相殺の可能性 適法
WHAT 残部の請求が認めらるか?
CASE 明示の一部請求のときの残部請求(明示説)
H10、明示の一部請求を棄却する判決確定後の残部請求
→信義則違反
WHY 一部であっても全部審査している、被告に二重負担
EX 12億中の1億の請求で裁判所は2億の支払い義務があると思っても、1億の判決がMAXとなる
明示説→勝敗に応じて異なる立場
学説:肯定説(処分権主義)、明示説、判例説(訴訟経済)、全面否定説※控訴審で拡張恕
明示の主たる対象は被告
その他問題になる、 時効中断、過失相殺(外側説)⇔内側説 案分説
三、弁論主義
判決の基礎となる事実や資料は、当事者の権能・義務
吾に事実を与えよ、されば、汝に法を与えん
(当事者の義務・権能) (裁判所の権能・専権)
※根拠規無し 人訴20、非訟 職権探知主義(公益に関する事項)
根拠:本質説(私的自治)学説、手段説(真実発券)、多言説(歴史的所産)
機能;不意打ち防止
弁論主義の三原則
①主張責任(裁判所は主張した事実のみ)
②自白の拘束力(争いの無い事実はそのまま判決の基礎となる)
③職権証拠調べの禁止(証拠の問題)
①ア)適用範囲
学説)主要事実(=要件事実に該当する具体的事実)
(=法律効果の判断に直接必要な事項)
CF 間接事実 主要事実を推認するのに役立つ事実
補助事実 証拠の信用性に関する事実
WHY 間接事実は主要事実についての証拠のようなものであり、そこまで裁判所がこうそくされれば、自由心証主義が害さっる
イ)主張責任; 主要事実の主張がない結果、当事者の一方が蒙る不利益
主張責任の分配;証明責任と一致
主張共通の原則;いずれか一方の主張があればよい
why 判決は、裁判所と当事者の問題であり、当事者間の考量不要
ウ)訴訟資料と証拠資料の峻別
証拠調べで分った事実=当事者が主張する事実
(証拠資料) (訴訟資料)
Aを以て、 Bに代えてはいけない
※A 弁論主義
B 訴訟に関する資料(広義)
事実より主張が優先される??
→釈明権
エ)一般条項(規範的要件)の主要事実
(公序良俗、権利濫用、信義則)+過失の主要事実
○過失か、過失の内容か???
スピード違反(間接事実)の主張
飲酒運転(間接事実)で判決
S0 A 過失を主要事実とみれば、判決は正当(弁論主義)
B 過失を内容とみれば、判決は不当 (通説)=主要事実は、内容とみる
WHY 被告にとって不意打ちとなる
→中身に関する事実;評価根拠事実が主要事実である
○釈明権(裁判所)
裁判長の訴訟指揮権
本来、職権進行主義に基づく権能
条文「できる」→しなければならないと解す
釈明権の一部が義務である 釈明;問いただす、立証を促すの意味「求釈明」ともいう
○消極的釈明(不明瞭を問いただす) 義務
○積極的釈明(必要な申立、主張、立証を促す)
(中立性の関係)
弁論主義のゆがんだ適用を、補正修正するために、用いる。
→公正な判決と裁判所の中立
釈明せずに判決したら、釈明義務違反になる
当事者
自己の名で、裁判(判決)を求めるものとこれに対立する相手方(判決の名宛人)
当事者の呼称
原告/被告
控訴人/被控訴人
上告人/被上告人
申立人/相手方
債権者/債務者
二当事者対立の原則(対立当事者の原則)
※共同訴訟 人数は複数だが、対立的
※三面訴訟
二、訴訟上の能力
(1)当事者能力 当事者となることのできる一般的資格
原則;権利能力に一致(民法)
例外;法人でない社団・財団で、代表者・管理人の定めのあるもの
(=権利能力のない社団・財団)
WHAT;民法上の組合の当事者能力
→判例肯定 組合、誰が組合員かという個性が強い
→学説反対
WHAT;当事者能力がないとき
→訴え却下 原則
→訴訟手続きの中断・受け継ぎ
(継続中に当事者が合併、死亡など)
→当事者の交代を予定
訴訟承継という
(2)訴訟能力
原則;行為能力(法律行為を単独でなすことのできる能力)
↓より高度(本人保護)
手続きの安定性、本人保護
A 未成年者、成年被後見人 NO
※法定代理の同意があっても、できない
※民法で、例外に認められる場合を除く
B 被保佐人、被補助人(同意が必要)
応訴の同意は不要
注意)人事訴訟 意思能力があるかぎり、訴訟能力を肯定
C 訴訟能力欠缺の扱い→無効
○無効だが、追認は可能
○訴訟要件ではない(通説)
※訴訟能力の欠缺が訴訟成立過程にあるとき、訴え却下
・絶対的上告理由
・再審事由
係属中に訴訟能力の欠缺:訴訟手続きの中断(訴訟承継はない)
三、当事者適格⇔訴えの利益(この請求でよいのか?)
本案判決を求めることができるかどうか(この当事者でよいのか)
正当な当事者(訴訟追行権)
原告適格 被告適格 ⇔訴訟担当
(一般の場合)
通常は、給付の時、給付請求権を有すると主張⇔原告により義務者
○確認の利益があること、
○形成→当事者になるべきものが法文にさだめてある。
(第三者の訴訟担当)
訴訟物たる権利関係の帰属主体に代り、第三者に、適格が認められるとき、
訴訟担当者が受けた判決の効果は、実質的利益帰属主体にもおよぶ
(被担当者)
代理人とも共通
BUT 代理人は、当事者の名で行う点が異なる
ア) 法定訴訟担当⇔任意的(本人の意思)
A 担当者のための訴訟担当
第三者が、自分の利益のために、管理処分確認を認められ、それに基づき、訴訟担当が認められること
EX 代位訴訟
B 職務上の当事者
実質的利益帰属主体による訴訟追行が困難な時は、この者の利益を保護するべき、職務にあるもの
EX 人事訴訟の検察官、成年後見人、遺言執行者
イ)任意的訴訟担当(本人の意思)
A 明文あり 選定当事者??
B 明文無し
弁護士代理の原則 ※訴訟信託の禁止を回避、潜脱することなく、
民法上の組合(百選13事件)
業務執行組合員
A 組合が当事者となる
B 代表が任的訴訟担当となる
C 組合イン全員の共同訴訟
法人でない社団(権利能力なき社団)の登記請求
社団名義で登記できない
CASE;構成員全員の共有登記、代表者の個人名義の登記は可能
BUT 肩書はNG
権利能力泣き社団の財産は、構成員全員が総有的に帰属する財産
百選11事件 権利能力なき社団の当事者適格の判例
○全員名義(当事者原告)
○現在登記名義人(任意的)
○社団自体が当事者となる
訴訟担当構成→既判力の面から肯定できる
固有適格構成→社団の判決の効力が構成員に及ぶ理屈が難しい
代理人
自己の訴訟行為の効果を他人(当事者)に帰属させるため、他人の名でし、また受けるもの
代理権欠缺の扱い;訴訟能力がないと〃
①法的代理人(本人の意思に基づかない)
主として、訴訟無能力者の保護
当事者に近い地位(訴状の必要的記載事項)
法人の代表者も法定代理の規定
ア)実体法上の法定代理人
イ)訴訟法上の特別代理人??
②任意代理人、
ア)訴訟委任に基づく、訴訟代理人(狭義)
特定の事件ごとに訴訟追行の委任を受け、そのための包括的な代理権を授与される者
A 資格 弁護士の原則
簡裁の許可代理
B 訴訟代理権
訴訟代理権授与;訴訟委任
その範囲;特別委任事項を除き、必要な訴訟追行に制限なく広い
審級代理の原則
○本人の死亡などによる訴訟代理権の不消滅
○訴訟代理人が要る間は、本人の死亡などにより、訴訟は中断しない
訴訟係属;二重起訴の禁止
(1)訴訟係属;特定の請求につき裁判で審理されている状態
ア)発生時;訴状送達時 ※「提出時」説
イ)裁判上の請求による時効中断、期間順守の効果の発生時期;訴訟提出時
(2)二重起訴(重複起訴)の禁止
訴訟物=当事者 同一事件
※近時の有力説は、訴訟物は異なっても主要な争点が共通していれば、二重起訴にあたる??(併合審理)
WHY ①重複審理の不経済
②判決の矛盾による混乱の防止(既判力)
③被告の応訴の煩
(百選㊳事件)
相殺の抗弁 二重起訴の禁止(例外)
注意;相殺
相殺のために主張した請求権の不存在の判断は、相殺のためにもって対抗した額についても既判力をゆうする
WHY 相殺は訴訟物とは無関係にな自動債権を消滅する効果がある。相殺による判断に既判力を認めないと、訴訟物の存否についての存在が自働債権の存否の紛争として、蒸し返される。
二つの裁判で、違った判断がでると、既判力の矛盾の回避の理由からも
→仮に既判力が矛盾した時は、再審の対象である
判例) 別訴の自働債権と相殺の抗弁を許さない
〔別訴先行型〕⇔(抗弁先行型)判例なし
相殺の予備的抗弁
訴訟要件(本案判決をするための要件)
→欠缺 訴え却下
①裁判所;裁判権、管轄権
※渉外事件;国際裁判管轄
管轄違い(移送)
②当事者;実在、当事者能力、当事者適格
③訴えの提起 訴状送達が有効
④訴えの利益
⑤複雑訴訟の要件を満たすこと
⑥訴訟費用の担保提供
国際紛争の場合、妨訴抗弁
※仲裁合意がある、応訴を拒む根拠
審理原則
○職権調査事項
当事者の申立がなくても職権で取り上げることができる⇔処分主義
例外、抗弁事項、仲裁合意、不起訴合意、基礎費用の担保提供
→訴えを不適法として却下する
適法;実体法に照らして判断できる状態
訴訟要件を備えていない時
○職権探知主義
※抗弁事項・任意管轄・ 訴えの利益 当事者適格
○基準時 事実審口頭弁論の終結時
※管轄(起訴時)
民事紛争 (私人間間の財産と身分を規律する)
民事訴訟(裁判手続き)
裁判によって、権利の存否を確定し、解決する
(判決によらずに終了することもある)
判決→→判決
原告(裁判所への判決要求)
手続:一定の目標に向かい人の行為が積み重なっていくこと
判決手続き:当事者や裁判所の行為が・・・・・・
※被告(人)とは言わない
裁判所 最広義:司法部 広義:国法上の裁判所 狭義:事件を担当する裁判官ら(訴訟法上)
第一審(単独制)高裁・最高裁(合議制)右陪席・左陪席
裁判:裁判所が判断を表示する行為
形式/主体/口頭弁論/告知方法/上訴
判決/裁判所/必要的/言い渡し/控訴・上告
決定/裁判所/任意的/相当な方法/抗告
命令/裁判官/任意的/相当な方法/抗告
(1)法による裁判
法的三段論法
法を大前提、事実を小前提、結論を判決
民事訴訟の判決の基準となる法:実体私法 民法など
○○ときには、○○。
(法律要件) (法律効果)権利の発生と消滅
・事実
・要件事実(抽象的)⇔主要事実(具体的)
民事訴訟:要件事実に該当する具体的事実の存否の認定→権利の存否の判断
(2)権利確定手続き
原告:訴にあって、どんな権利を主張するのか、原告は示しておく(請求の確定)
裁判所:請求の権利の存否を判断する
○認める→請求の認容する判断 ○認めない→請求棄却判決
以上は本案判決⇔訴え却下判決(訴えの中身に入らない)
Or 一部認容判決
↓
判決の確定 権利の存否の判断は裁判所も当事者も覆せない(既判力)
◎判決の核心部分にしか生じない
既判力が消滅する場合
※当事者の履行
※時効
※相殺
So;いつの時点の既判力が大切
=事実審の口頭弁論の終結時点=既判力の基準
Ⅱ 民事紛争処理手続きの種類
(1)判決手続き以外
○強制執行
○債務名義(権利の存在を示す文書であり、強制執行に必要)EX 確定判決など
○民事保全手続き(仮差し押さえ、仮処分)
○倒産処理手続き、非訟手続きなど
(2)特別な手続き
○人事訴訟
○行政訴訟
(略式手続)・手形訴訟、小切手訴訟、少額訴訟、督促手続き、簡裁の判決手続きの特則
Ⅲ民事訴訟法
Ⅳ自主的紛争解決(私的自治の法則)
(1)和解
裁判外⇔裁判内
・既決和解(和解調書)→行政執行
(2)調停、仲介
民事調停
家事調停:家事事件手続法 ※調停前置規定 離婚など
↓
調停調書
(3)仲裁:仲裁人(裁判官ではない)紛争解決を委ねる 仲裁法
仲裁判断→執行決定→債務名義になる
(4)裁判外紛争解決手続き(ADR) 米
○民間会社において紛争解決 ADR法
○弁護士会、行政書士会、スポーツ仲裁裁判機構
民事訴訟の概略
■訴え提起=訴状の提出
○必要的記載事項
当事者(=法定代理人)
請求の特定・請求の趣旨(どのような判決が欲しいか)
・請求の原因(主要事実)
■訴え提起の手数料納付
訴額(原告勝訴のときの利益が基準)
事物管轄の基準
管轄 国法上の裁判所間の分担
イ.事物管轄 地方OR簡裁(140万)
ロ.土地管轄 原則被告の住所(普通裁判籍)⇔特別
本人訴訟主義(弁護士代理の原則)
※一定の資格
↑訴訟代理人⇔法定代理人
■(裁判長による)訴状の審査
補正命令、訴状却下命令、訴え却下決定
■訴状の送達
第一回口頭弁論期日の指定、呼出し
期日:時間
答弁書:請求の趣旨に対する被告側の主張
事実に対する否認
■準備書面・答弁書の提出
■口頭弁論(弁論主義)
→争いの無い事実は証拠調べが不要
■訴状の陳述・答弁書の陳述
口頭弁論に上程する意味がある
→裁判所はその事実のみから判断しなければならない
■応答 認める(自白)→裁判所は拘束される
争う A;否認
B;抗弁 (両立する事実をのべる)
■争点および証拠の整理手続き
準備的口頭弁論(弁論準備)非公開
書面による準備手続き
■証拠調べ
証拠の申し出→証拠の採否→証拠調べ
証人尋問、当事者尋問→集中証拠調べの対象
鑑定
書証
検証
◎自由心証主義⇔法定証拠主義
◎証明責任(証拠調べしたがその事実が不明の時)
→その証明ができない責任は証明責任者が負う
■口頭弁論の終結
■第一審判決(第一審の終局判決)
判決書 主文
言い渡し
送達
※調書判決
※仮執行宣言(控訴されても執行できる)
■控訴 2週間(不変期間)
原則 負けた部分がなければならない
■控訴状 原審に提出(原審提出主義)
・原判決に対する不服の当否
事実審:事実についても、法律についても扱う
■上告
法律審:法律について扱う
So;上告審の既判力の基準日は、控訴審の口頭弁論終結時
控訴審の続審主義(第一審の資料を基礎に新たな資料を追加して判断)
CF 覆審、事後審(第一審の証拠のみ) 控訴審の事後審化
控訴審の終結判決
控訴却下 自判が原則 差戻しは例外 WHY 控訴審は証拠調べが可能
⇔上告審 差し戻しが原則
BUT 第一審が簡裁のときではなく、最高裁が上告の時
憲法違反、重要な手続き違反
○上告理由の制限
○裁量上告制;上告受理の申立(法令解釈の重要事項)
EX 判例相反、判例無し 上告受理決定
■判決の確定
A 既判力
B 執行力
C 形成力
再審:確定した判決を取消し、再度審査する
手続保証:誰もが利用できる
6.民事訴訟の基本理念 適正(手続き)、公平(当事者間の公平)、迅速、訴訟経済
→手続きの安定性
→画一的処理の要請 WHY:前の手続きに瑕疵があれば、後の手続きを全て無効にできない
民事訴訟の目的
権利保護説 個人
私的秩序維持説 国家
紛争解決説 通説
訴権 民事訴訟を利用する私人の権能
→公法に基づくもの 抽象的訴権説、具体的訴権説、本案判決請求権説
訴えと請求(訴訟物)
一、訴え=原告の裁判所への判決要求
訴訟行為1、裁判所、2、当事者
○申立 裁判所に対し一定の行為を求める EX訴え
○主張 申し立てを基礎づけるもの EX請求
○挙証
請求認容判決の主文
イ)給付判決:被告人→原告給付を命ずる
(債務名義) ※債権上の給付とは異なる EX 明渡・騒音を出さない(不作為)
◎執行力
ロ)確認判決:権利の存否を確認する
(又は法律関係)略:権利関係⇔事実
※請求棄却判決も含む
ハ)形成判決:法律関係の変動を宣言
(一定の法律要件)
EX離婚→形成要件
A 請求が原告→被告に対する給付請求権の主張
①現在の給付 給付請求権が現存する
②将来の給付
将来現実化すへきもの
(事実審口頭弁論終結時のあと)
B 請求が
①積極的確認 存在確認
②消極的確認 不存在確認
※法律関係の確認=事実確認はできない(原則_
例外;書証の真否確認の訴え
C 訴えを以て裁判所に法律関係の変動を請求できる
意味:判決により、はじめて、変動の効果
EX 契約書の解除は、含まない
○人事訴訟 会社関係訴訟など→対世効があるとされる
CF 既判力は当事者間のみが原則
BECAUSSE 身分関係は社会関係であり、会社関係の影響が広い
後見的国家像→形成判決のこと?
二、請求(訴訟上の) ×訴訟法
原告→被告 権利主張
◎請求権(※異なる)
○支配権
○形成権
これらは民法上の分類=私権
広義:訴訟物=請求
(訴の対象)
狭義:訴訟物→主張する権利関係 ※実務
訴えにおける請求の特定の必要
A 裁判所の審判対象の呈示
B 被告の防御の保証
C 訴訟物理論の問題
イ)実体法説(旧説) 実務
一定の実体権(実体法上の権利・法律関係)の存在
※形成訴訟の訴訟物
形成要件・形成原因毎
ロ)訴訟法説(新設)学者
確認訴訟;一定の実体権の存否
給付訴訟:一定の給付を求める地位
形成訴訟:一定の形成
A 請求権競合
X→所・賃→明け渡せ→Y 実体的に見るか、訴訟法的に見るか?
①所有権(物権的請求権)
②賃借権(債権的)
イ)解除
ロ)明渡
同一の訴訟中に追加した時
旧説:実体権が違うときは、訴訟物が異なるため、二重起訴にならない
バスの運転手と乗客のケガ
①不法行為
②債務不履行
旧説:既判力がおよばない
B ①請求の併合、②訴えの変更、③二重起訴、④既判力
①複数の請求を一つの訴で行うこと(訴えの客観的併合)
②訴訟係属中に請求を変更する
※追加的変更を念頭
③訴訟係属中に、同一の事件につき、別訴を提起することの禁止
=訴状の送達を基点とする考え方
④判決確定後、同一の訴訟物について訴えを提起すると、前訴の確定判決の既判力が後訴におよぶ
旧説: 訴訟物毎
新設: 給付物毎
従って:旧説では、A権で負ければ、B権で戦える
→新説は、紛争の一回的解決(訴訟経済)
WHY 実務は旧説?
既判力の及ぶ範囲は広い(新設)
→再チャレンジできない、裁判所の釈明義務の負担が大きい
民事訴訟の基本原則
行為/当事者主義/職権主義
判断対象の設定/◎処分権主義/職権調査
判断資料の提出/◎弁論主義/職権探知主義
手続きの提出/当事者進行主義/◎職権進行主義
処分権主義
訴訟の開始、修了、対象を当事者の意思に委ねる(私的自治)
終了とは、訴えの却下、和解
A 申立事項=判決事項
ア)裁判所は原告の申し立てた訴訟物に拘束(訴訟物理論)
×A権の訴を、B権の判決
イ)裁判所は原告の申し立てた救済形式に拘束(訴えの類型)
×確認の訴に、給付の判決
ウ)裁判所は原告の申し立てた救済範囲を越えて判決できない
×200万の訴に、300万の判決
B 一部認容判決
原告の意思の尊重=処分権主義
手続き保証(被告の防御)不意打ち防止
○ 200万円の訴に150万の判決(量的一部認容)
○ 無条件の給付要求に、条件付きの判決(質的一部認容判決)
事実抗弁⇔権利抗弁
C 一部請求 分割可能な権利の一部を請求する場合
12億の内1億円を請求
WHY 訴額の減額 相殺の可能性 適法
WHAT 残部の請求が認めらるか?
CASE 明示の一部請求のときの残部請求(明示説)
H10、明示の一部請求を棄却する判決確定後の残部請求
→信義則違反
WHY 一部であっても全部審査している、被告に二重負担
EX 12億中の1億の請求で裁判所は2億の支払い義務があると思っても、1億の判決がMAXとなる
明示説→勝敗に応じて異なる立場
学説:肯定説(処分権主義)、明示説、判例説(訴訟経済)、全面否定説※控訴審で拡張恕
明示の主たる対象は被告
その他問題になる、 時効中断、過失相殺(外側説)⇔内側説 案分説
三、弁論主義
判決の基礎となる事実や資料は、当事者の権能・義務
吾に事実を与えよ、されば、汝に法を与えん
(当事者の義務・権能) (裁判所の権能・専権)
※根拠規無し 人訴20、非訟 職権探知主義(公益に関する事項)
根拠:本質説(私的自治)学説、手段説(真実発券)、多言説(歴史的所産)
機能;不意打ち防止
弁論主義の三原則
①主張責任(裁判所は主張した事実のみ)
②自白の拘束力(争いの無い事実はそのまま判決の基礎となる)
③職権証拠調べの禁止(証拠の問題)
①ア)適用範囲
学説)主要事実(=要件事実に該当する具体的事実)
(=法律効果の判断に直接必要な事項)
CF 間接事実 主要事実を推認するのに役立つ事実
補助事実 証拠の信用性に関する事実
WHY 間接事実は主要事実についての証拠のようなものであり、そこまで裁判所がこうそくされれば、自由心証主義が害さっる
イ)主張責任; 主要事実の主張がない結果、当事者の一方が蒙る不利益
主張責任の分配;証明責任と一致
主張共通の原則;いずれか一方の主張があればよい
why 判決は、裁判所と当事者の問題であり、当事者間の考量不要
ウ)訴訟資料と証拠資料の峻別
証拠調べで分った事実=当事者が主張する事実
(証拠資料) (訴訟資料)
Aを以て、 Bに代えてはいけない
※A 弁論主義
B 訴訟に関する資料(広義)
事実より主張が優先される??
→釈明権
エ)一般条項(規範的要件)の主要事実
(公序良俗、権利濫用、信義則)+過失の主要事実
○過失か、過失の内容か???
スピード違反(間接事実)の主張
飲酒運転(間接事実)で判決
S0 A 過失を主要事実とみれば、判決は正当(弁論主義)
B 過失を内容とみれば、判決は不当 (通説)=主要事実は、内容とみる
WHY 被告にとって不意打ちとなる
→中身に関する事実;評価根拠事実が主要事実である
○釈明権(裁判所)
裁判長の訴訟指揮権
本来、職権進行主義に基づく権能
条文「できる」→しなければならないと解す
釈明権の一部が義務である 釈明;問いただす、立証を促すの意味「求釈明」ともいう
○消極的釈明(不明瞭を問いただす) 義務
○積極的釈明(必要な申立、主張、立証を促す)
(中立性の関係)
弁論主義のゆがんだ適用を、補正修正するために、用いる。
→公正な判決と裁判所の中立
釈明せずに判決したら、釈明義務違反になる
当事者
自己の名で、裁判(判決)を求めるものとこれに対立する相手方(判決の名宛人)
当事者の呼称
原告/被告
控訴人/被控訴人
上告人/被上告人
申立人/相手方
債権者/債務者
二当事者対立の原則(対立当事者の原則)
※共同訴訟 人数は複数だが、対立的
※三面訴訟
二、訴訟上の能力
(1)当事者能力 当事者となることのできる一般的資格
原則;権利能力に一致(民法)
例外;法人でない社団・財団で、代表者・管理人の定めのあるもの
(=権利能力のない社団・財団)
WHAT;民法上の組合の当事者能力
→判例肯定 組合、誰が組合員かという個性が強い
→学説反対
WHAT;当事者能力がないとき
→訴え却下 原則
→訴訟手続きの中断・受け継ぎ
(継続中に当事者が合併、死亡など)
→当事者の交代を予定
訴訟承継という
(2)訴訟能力
原則;行為能力(法律行為を単独でなすことのできる能力)
↓より高度(本人保護)
手続きの安定性、本人保護
A 未成年者、成年被後見人 NO
※法定代理の同意があっても、できない
※民法で、例外に認められる場合を除く
B 被保佐人、被補助人(同意が必要)
応訴の同意は不要
注意)人事訴訟 意思能力があるかぎり、訴訟能力を肯定
C 訴訟能力欠缺の扱い→無効
○無効だが、追認は可能
○訴訟要件ではない(通説)
※訴訟能力の欠缺が訴訟成立過程にあるとき、訴え却下
・絶対的上告理由
・再審事由
係属中に訴訟能力の欠缺:訴訟手続きの中断(訴訟承継はない)
三、当事者適格⇔訴えの利益(この請求でよいのか?)
本案判決を求めることができるかどうか(この当事者でよいのか)
正当な当事者(訴訟追行権)
原告適格 被告適格 ⇔訴訟担当
(一般の場合)
通常は、給付の時、給付請求権を有すると主張⇔原告により義務者
○確認の利益があること、
○形成→当事者になるべきものが法文にさだめてある。
(第三者の訴訟担当)
訴訟物たる権利関係の帰属主体に代り、第三者に、適格が認められるとき、
訴訟担当者が受けた判決の効果は、実質的利益帰属主体にもおよぶ
(被担当者)
代理人とも共通
BUT 代理人は、当事者の名で行う点が異なる
ア) 法定訴訟担当⇔任意的(本人の意思)
A 担当者のための訴訟担当
第三者が、自分の利益のために、管理処分確認を認められ、それに基づき、訴訟担当が認められること
EX 代位訴訟
B 職務上の当事者
実質的利益帰属主体による訴訟追行が困難な時は、この者の利益を保護するべき、職務にあるもの
EX 人事訴訟の検察官、成年後見人、遺言執行者
イ)任意的訴訟担当(本人の意思)
A 明文あり 選定当事者??
B 明文無し
弁護士代理の原則 ※訴訟信託の禁止を回避、潜脱することなく、
民法上の組合(百選13事件)
業務執行組合員
A 組合が当事者となる
B 代表が任的訴訟担当となる
C 組合イン全員の共同訴訟
法人でない社団(権利能力なき社団)の登記請求
社団名義で登記できない
CASE;構成員全員の共有登記、代表者の個人名義の登記は可能
BUT 肩書はNG
権利能力泣き社団の財産は、構成員全員が総有的に帰属する財産
百選11事件 権利能力なき社団の当事者適格の判例
○全員名義(当事者原告)
○現在登記名義人(任意的)
○社団自体が当事者となる
訴訟担当構成→既判力の面から肯定できる
固有適格構成→社団の判決の効力が構成員に及ぶ理屈が難しい
代理人
自己の訴訟行為の効果を他人(当事者)に帰属させるため、他人の名でし、また受けるもの
代理権欠缺の扱い;訴訟能力がないと〃
①法的代理人(本人の意思に基づかない)
主として、訴訟無能力者の保護
当事者に近い地位(訴状の必要的記載事項)
法人の代表者も法定代理の規定
ア)実体法上の法定代理人
イ)訴訟法上の特別代理人??
②任意代理人、
ア)訴訟委任に基づく、訴訟代理人(狭義)
特定の事件ごとに訴訟追行の委任を受け、そのための包括的な代理権を授与される者
A 資格 弁護士の原則
簡裁の許可代理
B 訴訟代理権
訴訟代理権授与;訴訟委任
その範囲;特別委任事項を除き、必要な訴訟追行に制限なく広い
審級代理の原則
○本人の死亡などによる訴訟代理権の不消滅
○訴訟代理人が要る間は、本人の死亡などにより、訴訟は中断しない
訴訟係属;二重起訴の禁止
(1)訴訟係属;特定の請求につき裁判で審理されている状態
ア)発生時;訴状送達時 ※「提出時」説
イ)裁判上の請求による時効中断、期間順守の効果の発生時期;訴訟提出時
(2)二重起訴(重複起訴)の禁止
訴訟物=当事者 同一事件
※近時の有力説は、訴訟物は異なっても主要な争点が共通していれば、二重起訴にあたる??(併合審理)
WHY ①重複審理の不経済
②判決の矛盾による混乱の防止(既判力)
③被告の応訴の煩
(百選㊳事件)
相殺の抗弁 二重起訴の禁止(例外)
注意;相殺
相殺のために主張した請求権の不存在の判断は、相殺のためにもって対抗した額についても既判力をゆうする
WHY 相殺は訴訟物とは無関係にな自動債権を消滅する効果がある。相殺による判断に既判力を認めないと、訴訟物の存否についての存在が自働債権の存否の紛争として、蒸し返される。
二つの裁判で、違った判断がでると、既判力の矛盾の回避の理由からも
→仮に既判力が矛盾した時は、再審の対象である
判例) 別訴の自働債権と相殺の抗弁を許さない
〔別訴先行型〕⇔(抗弁先行型)判例なし
相殺の予備的抗弁
訴訟要件(本案判決をするための要件)
→欠缺 訴え却下
①裁判所;裁判権、管轄権
※渉外事件;国際裁判管轄
管轄違い(移送)
②当事者;実在、当事者能力、当事者適格
③訴えの提起 訴状送達が有効
④訴えの利益
⑤複雑訴訟の要件を満たすこと
⑥訴訟費用の担保提供
国際紛争の場合、妨訴抗弁
※仲裁合意がある、応訴を拒む根拠
審理原則
○職権調査事項
当事者の申立がなくても職権で取り上げることができる⇔処分主義
例外、抗弁事項、仲裁合意、不起訴合意、基礎費用の担保提供
→訴えを不適法として却下する
適法;実体法に照らして判断できる状態
訴訟要件を備えていない時
○職権探知主義
※抗弁事項・任意管轄・ 訴えの利益 当事者適格
○基準時 事実審口頭弁論の終結時
※管轄(起訴時)










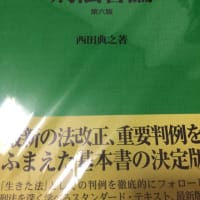
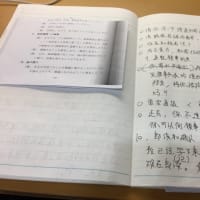
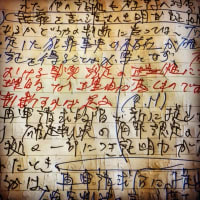

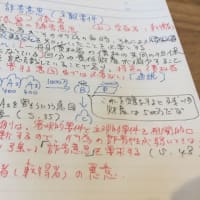
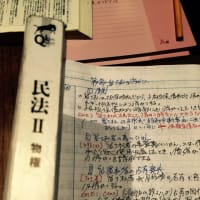
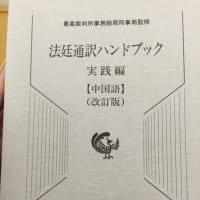
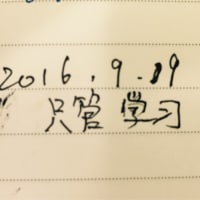

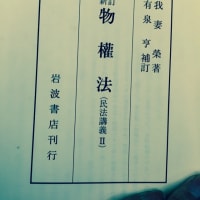
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます