
昭和45年11月25日 (水)
「三島由紀夫、市ヶ谷台上にて、クーデッタを促し、壮絶なる割腹自殺!!」
三島由紀夫
目次
クリックすると頁が開く
一の1
男一匹 命をかけて
私は、自衛隊に、このような状況で話すのは空しい。
しかしながら私は、自衛隊というものを、この自衛隊を頼もしく思ったからだ。
こういうことを考えたんだ。
しかし日本は、経済的繁栄にうつつを抜かして、ついには精神的にカラッポに陥って、政治はただ謀略・欺傲心だけ………。
これは日本でだ。
ただ一つ、日本の魂を持っているのは、自衛隊であるべきだ。
われわれは、自衛隊に対して、日本人の………。
しかるにだ、我々は自衛隊というものに心から………。
静聴せよ、静聴。静聴せい。
自衛隊が日本の………の裏に、日本の大本を正していいことはないぞ。
以上をわれわれが感じたからだ。
それは日本の根本が歪んでいるんだ。
それを誰も気がつかないんだ。
日本の根源の歪みを気がつかない、それでだ、その日本の歪みを正すのが自衞隊、それが………。
静聴せい。静聴せい。
それだけに、我々は自衛隊を支援したんだ。
静聴せいと言ったら分からんのか。静聴せい。
unknown comment・・・リンク→燃えよ剣
一の2
三島由紀夫の死 雷の衝撃
「ある人は、”事件の影響を受けるな” とペンで言う
でも僕はもう受けてしまった
それらの人の言葉は雷どころか乾電池ほどの衝撃も僕には与えてくれない
二
憂 国
三島由紀夫がなぁ、自衛隊で、クーデターを起こそうとして
失敗して、切腹して死んだそうだ
2.26事件を、想い起こしたよ
昭和45年(1970年)11月25日水曜日
高校1年、一日の授業を終えた後の、ホームルームの時間
担任より、知らされたのである
三の1
二・二六事件と私


三島由紀夫 英霊の聲 から
二・二六事件と私
・・・・たしかに 二・二六事件の挫折によって、何か偉大な神が死んだのだった。
当時十一歳の少年であった私には、それはおぼろげに感じられただけだったが、
二十歳の多感な年齢に敗戦を際会したとき、私はその折の神の死の恐ろしい残酷な実感が、
十一歳の少年時代に直感したものと、どこかで密接につながっているらしいのを感じた。
それがどうつながっているのか、私には久しくわからなかったが、
「十日の菊」 や 「憂国」 を私に書かせた衝動のうちに、 その黒い影はちらりと姿を現わし、
又、定からぬ形のまま消えて行った。
それを二・二六事件の陰画とすれば、
少年時代から私のうちに育まれた陽画は、蹶起将校たちの英雄的形姿であった。
その純一無垢、その果敢、その若さ、その死、すべてが神話的英雄の原型に叶っており、
かれらの挫折と死とが、かれらを言葉の真の意味におけるヒーローにしていた。
三の2
三島由紀夫と二・二六事件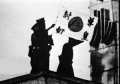 ←山王ホテルで尊皇討奸旗を掲げる蹶起部隊
←山王ホテルで尊皇討奸旗を掲げる蹶起部隊
昭和十一年二月二十六日、
前夜来の大雪を蹶って暴発した二・二六事件は,
僅か四日間で敗退したが、
その四日間の経過は紆余曲折、三転四転、複雑怪奇の跡を辿って幕を閉じた
事件発生以来の、行動面の現象をいくら追及しても、その収拾措置の過程には、
どうしても納得できない疑問が解けない
その疑問の帰結する所は、天皇の意志、存在に突き当たるのであって、
これを裏付け究明することが、事件収拾の謎を解く鍵であると見られていた
しかし、天皇の問題は、踏み込み難い壁があることで、決めてを欠くものがあった
これを取上げて、大胆に触れたのが三島氏であり、その著 『英霊の聲』 である
その中で、天皇はこれまでの治世の中で、二つの失政を犯したとして、その一つは、
二・二六事件の処理であり、もう一つは、終戦時の処置であるとする
そして、そのいずれも失政の原因は、天皇が人間ひとになったためであり、
日本の天皇は人間になってはいけない、神でなくてはいけないと説くのである
二・二六の場合、陛下は 「天皇」 の座を降りて 「人間」 になったために、
その人間感情の激怒の奔流が、二・二六の青年将校たちの憂国の至情、純真精神を押流してしまった
そして、三島氏は磯部浅一が獄中で絶叫する 「陛下、何たる御失政でありますか」
「このままでは日本は滅亡致しますぞ」 と、陛下を御諫めするその烈々の心情を支持するのである
三島氏が言うように、二・二六事件の収拾が、あのような形で幕を閉じたことが、
不当であったか、あるいは妥当であったか、
さらにはそれが天皇の失政であったかどうかの問題は別として、
尠くとも、四日間の経過の不可解な展開の裏には天皇の意志が大きく左右したことが
幾多の事実によって推理されていたことは疑いがない
三の3
などてすめろぎはひととなりたまいし
こは神としてのみ心ならず、
人として暴を憎みたまいしなり。
鳳輦に侍するはことごとく賢者にして
道のべにひれ伏す愚かしき者の
血の叫びにこもる神への呼びかけは
ついに天聴に達することなく、
陛下は人として見捨ててたまえり、
かの暗澹たる広大なる貧困と
青年士官らの愚かなる赤心を。
わが古き神話のむかしより
大地の精の血の叫び声を凝り成したる
素戔鳴尊は容れられず、
聖域に馬の生皮を投げ込みしとき
神のみ怒りに触れて国を逐われき。
このいと醇乎たる荒魂より
人として陛下は面をそむけ玉いぬ。
などてすめろぎは人間となりたまいし
四
三島由紀夫の葉隠入門
・・・『葉隠入門』は、昭和42年(1967年)に書かれたもの
現代文化の特徴は、
従来まで人々を人生に向かって鼓舞していた様々な理想、規範、思想・・が悉く潰え去ったことであろう
嘗てモラルの基礎をなしていた絶対の観念が失われ、
人間は全ての意匠を剥ぎとられた等身大の、赤裸かの、即物的自然的な生命に直面することを強いられている
これが、現代社会を侵している救いがたいニヒリズムの原因であろう
人生いかに生くべきか、
と謂う 曾ての求道的倫理的な問題は、
今では 日進月歩する科学的な生活改良や健康法や姑息な処世の技術や、
要するに瑣末(さまつ)な日常生活への関心にとって代わられた
現代は博学多識と、細分化された「ハウツウもの」の全盛時代である
「吾々は西洋から、あらゆる生の哲学を学んだ」
然し 生活自体への関心は、つまるところ 利殖と保身と享楽の追究におわる
与えられた「生の哲学」によって十全に人間性の自然を開放し、
富益を求め、奢侈(しゃし)と飽食と放埓(ほうらつ)に身をゆだねたのちに、
やがては等しく老衰と死にきわまる運命にさだめられている
生とはついに死に到る不治の病だとすれば、病んでいるのは「生の哲学」そのものだ、
と いえないことはない
民族、国家、社会など、ある共同体が他文化の侵蝕を受けると、
人々の生活の支柱をなしていた掟(おきて)や慣習がすたれ、道徳的精神的に荒廃して、
その共同体は徐々に崩壊、解体してゆくことが知られている
生の充実にどれほど力を注ごうと、生それ自身の自壊作用をくいとめる手立てはありえない
・・田中美代子 同書解説、から
五
勇者とは
泰平が続くと、われわれはすぐ戦乱の思い出を忘れてしまい、
非常の事態のときに男がどうあるべきかということを忘れてしまう
金嬉老事件は小さな地方的な事件であるが、
日本もいつかあのような事件の非常に拡大された形で、
われわれ全部が金嬉老の人質と同じ身の上になるかもしれないのである
しかし、それはあくまで観念と空想の上のできごとで、
現実の日本には、なかなかそのような兆候も見られない
そしていまは女の勢力が、すべてを危機感から遠ざけている
危機を考えたくないということは、非常に女性的な思考である
なぜならば、女は愛し、結婚し、子供を生み、子供を育てるために平和な巣が必要だからである
平和でありたいという願いは、女の中では生活の必要なのであって、
その生活の必要のためには、何ものも犠牲にされてよいのだ
しかし、それは男の思考ではない
危機に備えるのが男であって、女の平和を脅かす危機が来るときに必要なのは男の力であるが、
いまの女性は自分の力で自分の平和を守れるという自信を持ってしまった
それは一つには、男が頼りないということを、彼女たちがよく見きわめたためでもあり、
彼女たちが勇者というものに一人も会わなくなったためでもあろう
六
羞恥心について
私は、日本では戦後女性の羞恥心が失われた以上に、男性の羞恥心が失われたことを痛感する
ただ世間の風潮を慨嘆するだけではない
私自身が知らず知らずの間に時代の影響をこうむって、男の羞恥心を失いつつあるのである
それに気がついたのは妻のお産のときで、
私はいつ生まれるかとヒヤヒヤしながら病院につめ、いよいよ子供が生まれたときは、
初孫の誕生を父に知らせるため、何度も赤電話をかけながら、十円玉を入れるのを忘れて、
電話が通じなかった
そして、やっと十円玉を入れて電話が通じたとき、父の思いがけない不機嫌な声に驚かされた
父は少しも初孫の誕生を喜んでいないように思えたのである
あとでわかったことだが、父は明治生まれの男らしい、実に古風な羞恥心を持っていた
自分の嫁の出産に息子が病院へ行くのさえ、恥ずかしいことであった
病院からあたふたした声で電話をかけてくるのは、もっと恥ずかしいことであった
妻のお産のときには、日本の男はおなかの中で心配しながら、友だちと外で飲んで歩くか、
あるいはそしらぬ顔をしているべきであった
それは女にたいする軽蔑とは違って、むしろ純女性的領域に対するおそれと、
おののきと、遠慮と、反抗から生まれた男のテレかくしの態度であったと思われる
明治の男は、女と肩を並べて歩くのをいさぎよしとしなかった
世間からでれでれしていると思われないために、女と必ず離れて歩き、結婚しても、
妻と並んで歩くのを恥ずかしがる男性はいくらでもいた
七
礼法について
女性の力ではなく、アメリカという男性の、占領軍の力によって女性の自由と開放が成就されたとき、
女性は何によって自分の力を証明しようとしたであろうか
それがいわゆる女性の平和運動である
その平和運動はすべて感情を基盤にして、
「二度と戦争はごめんだ」 「愛するわが子を戦場へ送るな」
という一連のヒステリックな叫びによって貫かれ、それゆえにどんな論理も寄せつけない力を持った
しかし、女性が論理を寄せつけないことによって力を持つのは、実はパッシブ領域においてだけなのである
日本の平和運動の欠点は、感情によって人に訴えることがはなはだ強いと同時に、
論理によって前へ進むことがはなはだ弱いという、女性的欠点を露呈した
八
忠義とは何ぞや ・
・
ぼくは、それが忠義だと思っている
決して忠義というのはオールド・リベラリストがやっているような、
「陛下はいい方です ニコニコお話をなさって、よく人口問題などまでいろいろ研究なさっていらっしゃる」
というようなものじゃないんだ
ヒューマニズムの忠義じゃないんだ
彼らは、大正文化主義から学んだものを忠義だと思ってゐるんだよ
ぼくが一番に 「二・二六事件」 に共鳴するものはそこですよ
忠義を一番苛酷なものだということを証明しただけで、あの事件はいいです
あとのオールド・リベラリストが何をしようが、有馬頼義が出てきてどんなことを書こうが、
そんなことは構わない
忠義は苛酷なものですよ
それはテロリズムだけじゃないだろうけど、精神の問題ですよ
しかし、天皇も皇太子も、結局 「二・二六」 の本質は理解できないんじゃないか
そういう忠義の本質は理解おできになれないという・・・・・・
九
最後に守るべきもの
石原
何をがんばるんですか
三種の神器ですか
三島
ええ、三種の神器です
ぼくは天皇というものをパーソナルにつくっちゃたことが一番いけないと思うんです
戦後の人間天皇制が一番いかんと思うのは、
みんなが天皇をパーソナルな存在にしちゃったからです
石原
そうです
昔みたいにちっとも神秘的じないもの
三島
天皇というのはパーソナルじゃないんですよ
それを何か間違えて、いまの天皇はりっぱな方だから、おかげでもって終戦ができたんだ、
と、そういうふうにして人間天皇を形成してきた
そしてヴァイニングなんてあやしげなアメリカの欲求不満女を連れてきて、
あとやったことは毎週の週刊誌を見ては、宮内庁あたりが、まあ、今週も美智子様出ておられる、
と喜んでいるような天皇制にしちったでしょう
これは天皇をパーソナルにするということの、天皇制に対する反逆ですよ
逆臣だと思う
石原
ぼくもまったくそう思う
三島
それで天皇制の本質というものが誤られてしまった
だから石原さんみたいな、つまり非常に無垢ではあるけれども、天皇制反対論者をつくっちゃった
石原
ぼくは反対じゃない、幻滅したの
三島
幻滅論者というのは、つまりパーソナルにしちゃったから幻滅したんですよ
石原
でもぼくは天皇を最後に守るべきものと思ってないんでね
三島
思ってなきゃしようがない
いまに目がさめるだろう(笑い)
昭和45年 ( 1970年 ) 11月25日 ( 水 )
三島由紀夫、
市ヶ谷台上にて、クーデッタを促し、壮烈なる割腹自殺
三島由紀夫がなぁ、自衛隊で、クーデターを起こそうとして
失敗して、切腹して死んだそうだ
2.26事件を、想い起こしたよ
・
高校1年、一日の授業を終えた後の、ホームルームの時間
担任より、知らされたのである
教室は重苦しい雰囲気に包まれた、クラスの皆も、ショックを受けたようである
皆が、口々に喋って居る
皆は、「三島由紀夫」 を、知っているのである
然し
十六歳、無垢の私
「三島由紀夫」 を、全く知らなかった
・・・憂 国

下記は
当時の二十歳の青年が、事件への想い綴つたものである
此を、
総括 三島由紀夫の死 ( 奈須田敬著 ) の中で觀た
雷の衝撃
この事件が、ある予備校生に与えた衝撃はただならぬものがあった
「 三島由紀夫の死は 否定も肯定も超えて 僕に大きな衝撃を与えた。
自己に内在する 『 何か 』 から 故意に目を外らしていた僕の首を力づくで、そこへ向けてしまった。
それは 『 死 』 であった。
『 武士道は 死ぬことと見つけたり 』
という文字を何回読んでも 遂に実感しようとしなかった僕を、彼はなぐりつけた。
獅子の皮をかむって歩いていた僕が、実は下らないロバに過ぎないことを、彼は冷たく指摘した。
この若者は、一歩すすめて、堂々と、「文化人」批判をはじめる
「 僕は彼の死に、
軍国主義復活の、ホモ・セクシュアリィの、美学完結の、文学的行詰りの、マゾヒズムの、ナルシズムの
----レッテルを貼らない。
レッテルを貼ることによって 『 頭で理解する 』 ことになるのを怖れるからである。
レッテル貼りは、そういう趣味のある人に任せておく。
そういう人は、自分の死についても何かレッテルを貼るのであろう。
それも一面的な、おまけに間違った、あらずもがなのレッテルを。
つまり自叙伝を書いて自分の人生を化石化したりするのであろう。
『 二日たてば 忘れるくせに 』 と 言った、 『 民衆の代表 』 いいだ・もも氏
民衆は果して本当に忘れたか。
生前の三島由紀夫氏が
とっくに自分で語ってしまった ”問題点” を もっともらしく指摘して
方々に書き散らした、なだ・いなだ氏・・・・・・
レッテル貼りはどうしても生き残ったことの弁解にしか見えない。
人は海を想起するとき、それを絵のように静止した形で頭に描くだろうか。
僕は寄せては返す波として、あの事件をとらえている 」
いいだ・もも、なだ・いなだ両人が
「 レッテル貼り 」 かどうかは別として、
「 寄せては返す波 」 として、三島事件をとらえようとする発想は、
きわめてユニークといわねばならず、
示唆しさされるものがある
この予備校生木村雄君の目のさめるような、しめくくりの言葉に耳を傾けたい
「 ある人は、”事件の影響を受けるな” と ペンで言う。
でも 僕はもう受けてしまった。
それらの人の言葉は雷どころか
乾電池ほどの衝撃も僕には与えてくれない
戦争を知らない子供たち ---雷の衝撃と三島嫌い ・・から
檄文
われわれ楯の会は、自衛隊によって育てられ、 いわば自衛隊はわれわれの父でもあり、兄でもある。
その恩義に報いるに、このような忘恩的行為に出たのは何故であるか。
かえりみれば、私は四年、学生は三年、隊内で準自衛官としての待遇を受け、
一片の打算もない教育を受け、又われわれも心から自衛隊を愛し、も はや隊の柵外の日本にはない
「真の日本」をここに夢み、ここでこそ終戦後ついに知らなかった男の涙を知った。
ここで流したわれわれの汗は純一であり、 憂国の精神を相共にする同志として共に富士の原野を馳駆した。
このことには一点の疑いもない。
われわれにとって自衛隊は故郷であり、 生ぬるい現代日本で凛冽の気を呼吸できる唯一の場所であった。
教官、助教諸氏から受けた愛情は測り知れない。
しかもなお、敢えてこの挙に出たのは何故であるか。
たとえ強弁と云われようとも、自衛隊を愛するが故であると私は断言する。
われわれは戦後の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、
国民精神を失い、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、
自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。
政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、
敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、
日本人自ら日本の歴史と伝統を涜してゆくのを、歯噛みをしながら見ていなければならなかった。
われわれは今や自衛隊にのみ、真の日本、真の日本人、真の武士の魂が残されているのを夢みた。
しかも法理論的には、自衛隊は違憲であることは明白であり、
国の根本問題である防衛が、御都合主義の法的解釈によってごまかされ、
軍の名を用いない軍として、日本人の魂の腐敗、道義の頽廃の根本原因を、なしてきているのを見た。
もっとも名誉を重んずべき軍が、もっとも悪質の欺瞞の下に放置されて来たのである。
自衛隊は敗戦後の国家の不名誉な十字架を負いつづけて来た。
自衛隊は国軍たりえず、建軍の本義を与えられず、
警察の物理的に巨大なものとしての地位しか与えられず、その忠誠の対象も明確にされなかった。
われわれは戦後のあまりに永い日本の眠りに憤った。
自衛隊が目ざめる時こそ、日本が目ざめる時だと信じた。
自衛隊が自ら目ざめることなしに、この眠れる日本が目ざめることはないのを信じた。
憲法改正によって、自衛隊が建軍の本義に立ち、真の国軍となる日のために、
国民として微力の限りを尽すこと以上に大いなる責務はない、と信じた。
四年前、私はひとり志を抱いて自衛隊に入り、その翌年には楯の会を結成した。
楯の会の根本理念は、ひとえに自衛隊が目ざめる時、
自衛隊を国軍、名誉ある国軍とするために、命を捨てようという決心にあつた。
憲法改正がもはや議会制度下ではむずかしければ、治安出動こそその唯一の好機であり、
われわれは治安出動の前衛となって命を捨て、国軍の礎石たらんとした。
国体を守るのは軍隊であり、政体を守るのは警察である。
政体を警察力を以て守りきれない段階に来て、
はじめて軍隊の出動によって国体が明らかになり、軍は建軍の本義を回復するであろう。
日本の軍隊の建軍の本義とは、
「天皇を中心とする日本の歴史・文化・伝統を守る」ことにしか存在しないのである。
国のねじ曲った大本を正すという使命のため、
われわれは少数乍ら訓練を受け、挺身しようとしていたのである。
しかるに昨昭和四十四年十月二十一日に何が起ったか。
総理訪米前の大詰ともいうべきこのデモは、圧倒的な警察力の下に不発に終った。
その状況を新宿で見て、私は、「これで憲法は変らない」と痛恨した。
その日に何が起ったか。
政府は極左勢力の限界を見極め、
戒厳令にも等しい警察の規制に対する一般民衆の反応を見極め、
敢えて「憲法改正」という火中の栗を拾はずとも、事態を収拾しうる自信を得たのである。
治安出動は不用になった。
政府は政体維持のためには、何ら憲法と抵触しない警察力だけで乗り切る自信を得、
国の根本問題に対して頬かぶりをつづける自信を得た。
これで、左派勢力には憲法護持の飴玉をしやぶらせつづけ、名を捨てて実をとる方策を固め、
自ら、護憲を標榜することの利点を得たのである。
名を捨てて、実をとる! 政治家たちにとってはそれでよかろう。
しかし自衛隊にとっては、致命傷であることに、政治家は気づかない筈はない。
そこでふたたび、前にもまさる偽善と隠蔽、うれしがらせとごまかしがはじまった。
銘記せよ!
実はこの昭和四十四年十月二十一日という日は、自衛隊にとっては悲劇の日だった。
創立以来二十年に亘って、憲法改正を待ちこがれてきた自衛隊にとって、
決定的にその希望が裏切られ、憲法改正は政治的プログラムから除外され、
相共に議会主義政党を主張する自民党と共産党が、
非議会主義的方法の可能性を晴れ晴れと払拭した日だった。
論理的に正に、この日を境にして、それまで憲法の私生児であつた自衛隊は、
「護憲の軍隊」として認知されたのである。これ以上のパラドックスがあろうか。
われわれはこの日以後の自衛隊に一刻一刻注視した。
われわれが夢みていたように、
もし自衛隊に武士の魂が残っているならば、どうしてこの事態を黙視しえよう。
自らを否定するものを守るとは、何たる論理的矛盾であろう。
男であれば、男の衿がどうしてこれを容認しえよう。
我慢に我慢を重ねても、守るべき最後の一線をこえれば、決然起ち上るのが男であり武士である。
われわれはひたすら耳をすました。
しかし自衛隊のどこからも、「自らを否定する憲法を守れ」という屈辱的な命令に対する、
男子の声はきこえては来なかった。
かくなる上は、自らの力を自覚して、
国の論理の歪みを正すほかに道はないことがわかっているのに、
自衛隊は声を奪われたカナリヤのように黙ったままだった。
われわれは悲しみ、怒り、ついには憤激した。
諸官は任務を与えられなければ何もできぬという。
しかし諸官に与えられる任務は、悲しいかな、最終的には日本からは来ないのだ。
シヴィリアン・コントロールが民主的軍隊の本姿である、という。
しかし英米のシヴィリアン・コントロールは、軍政に関する財政上のコントロールである。
日本のように人事権まで奪はれて去勢され、
変節常なき政治家に操られ、党利党略に利用されることではない。
この上、政治家のうれしがらせに乗り、
より深い自己欺瞞と自己冒涜の道を歩もうとする自衛隊は魂が腐ったのか。
武士の魂はどこへ行ったのだ。
魂の死んだ巨大な武器庫になって、どこかへ行こうとするのか。
繊維交渉に当っては自民党を売国奴呼ばはりした繊維業者もあったのに、
国家百年の大計にかかわる核停条約は、
あたかもかつての五・五・三の不平等条約の再現であることが明らかであるにもかかわらず、
抗議して腹を切るジエネラル一人、自衛隊からは出なかった。
沖縄返還とは何か?
本土の防衛責任とは何か?
アメリカは真の日本の自主的軍隊が日本の国土を守ることを喜ばないのは自明である。
あと二年の内に自主性を回復せねば、
左派のいう如く、自衛隊は永遠にアメリカの傭兵として終るであらう。
われわれは四年待った。
最後の一年は熱烈に待った。
もう待てぬ。
自ら冒涜する者を待つわけには行かぬ。
しかしあと三十分、最後の三十分待とう。
共に起って義のために共に死ぬのだ。
日本を日本の真姿に戻して、そこで死ぬのだ。
生命尊重のみで、魂は死んでもよいのか。
生命以上の価値なくして何の軍隊だ。
今こそわれわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。
それは自由でも民主主義でもない。
日本だ。
われわれの愛する歴史と伝統の国、日本だ。
これを骨抜きにしてしまった憲法に体をぶつけて死ぬ奴はいないのか。
もしいれば、今からでも共に起ち、共に死のう。
われわれは至純の魂を持つ諸君が、
一個の男子、真の武士として蘇えることを熱望するあまり、この挙に出たのである。
三島由紀夫 ・
・
「 静聴せよ、静聴、静聴せい 」
「 静聴せい、静聴せい 」
「 静聴せいと言ったら分からんのか、静聴せい 」

「お まえら聞けぇ、聞けぇ!」
「 静かにせい、静かにせい!」
「 話を聞けっ!」
「 男一匹が、命をかけて諸君に訴えているんだぞ 」
「 いいか、いいか 」
「それでも武士かぁ!」
「それでも武士かぁ!」
昭和45年(1970年)11月25日
市ヶ谷台上で
天皇陛下万歳を三唱 して
壮絶なる死を遂げた、三島由紀夫の 「 死の叫び聲 」 である

軍隊とは、武士の集団であろう ・・と
武士なる、自衛隊と信じて 蹶起したのである
であるが・・
もはや、武士の魂 を 抜取られた、時代の申子 自衛隊
「 檄 」 を、飛ばせど
三島由紀夫の意志など、通じる筈も 無かったのである
されど
三島由紀夫の 飛ばした 「 檄 」 は、「 死の叫び聲 」 は
私の中に潜在した 「 吾は日本人 」 と謂う 意識を喚起した
これぞ
私のDNA なのである
・・・リンク→ 憂 国 男のロマン 大東京 二・二六事件 一人歩き (一) ・
・
左翼思想全盛の昭和45年(1970年)に於いて
素直に そう 掬び付くことは、稀有な存在 であった
今も尚
吾々のDNA は、凍結されしまま 眠っている
これから日本が、世界の中で生存しようとするなら
凍結されし、吾々のDNA を、解凍し
吾々のDNA に眠る
武士の魂 を 喚起する
そこれこそ
吾々日本人に求められているもの
と、私は想うのである
私は、自衛隊に、このような状況で話すのは空しい。
しかしながら私は、自衛隊というものを、この自衛隊を頼もしく思ったからだ。
こういうことを考えたんだ。
しかし日本は、経済的繁栄にうつつを抜かして、
ついには精神的にカラッポに陥って、政治はただ謀略・欺傲心だけ………。
これは日本でだ。
ただ一つ、日本の魂を持っているのは、自衛隊であるべきだ。
われわれは、自衛隊に対して、日本人の………。
しかるにだ、我々は自衛隊というものに心から………。
静聴せよ、静聴。静聴せい。
自衛隊が日本の………の裏に、日本の大本を正していいことはないぞ。
以上をわれわれが感じたからだ。
それは日本の根本が歪んでいるんだ。
それを誰も気がつかないんだ。
日本の根源の歪みを気がつかない、それでだ、その日本の歪みを正すのが自衞隊、それが………。
静聴せい。静聴せい。
それだけに、我々は自衛隊を支援したんだ。
静聴せいと言ったら分からんのか。静聴せい。
それでだ、去年の十月の二十一日だ。
何が起こったか。
去年の十月二十一日に何が起こったか。
去年の十月二十一日にはだ、
新宿で、反戦デーのデモが行われて、これが完全に警察力で制圧されたんだ。
俺はあれを見た日に、これはいかんぞ、これは憲法が改正されないと感じたんだ。
なぜか。
その日をなぜか。
それはだ、自民党というものはだ、自民党というものはだ、
警察権力をもっていかなるデモも鎮圧できるという自信をもったからだ。
治安出動はいらなくなったんだ。
治安出動はいらなくなったんだ。
治安出動がいらなくなったのが、すでに憲法改正が不可能になったのだ。
分かるか、この理屈が………。
諸君は、去年の一〇・二一からあとだ、もはや憲法を守る軍隊になってしまったんだよ。
自衛隊が二十年間、血と涙で待った憲法改正ってものの機会はないんだ。
もうそれは政治的プログラムからはずされたんだ。
ついにはずされたんだ、それは。どうしてそれに気がついてくれなかったんだ。
去年の一〇・二一から一年間、俺は自衛隊が怒るのを待ってた。
もうこれで憲法改正のチャンスはない!
自衛隊が国軍になる日はない!
建軍の本義はない!
それを私は最もなげいていたんだ。
自衛隊にとって建軍の本義とはなんだ。
日本を守ること。
日本を守るとはなんだ。
日本を守るとは、天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守ることである。
おまえら聞けぇ、聞けぇ!
静かにせい、静かにせい!
話を聞けっ!
男一匹が、命をかけて諸君に訴えてるんだぞ。
いいか。
いいか。
それがだ、いま日本人がだ、ここでもってたちあがらなければ、
自衛隊がたちあがらなきゃ、憲法改正ってものはないんだよ。
諸君は永久にだねえ、ただアメリカの軍隊になってしまうんだぞ。
諸君と日本の………アメリカからしかこないんだ。
シビリアン・コントロール………シビリアン・コントロールに毒されてんだ。
シビリアン・コントロールというのはだな、新憲法下でこらえるのが、シビリアン・コントロールじゃないぞ。
………そこでだ、俺は四年待ったんだよ。
俺は四年待ったんだ。
自衛隊が立ちあがる日を。
………そうした自衛隊の………最後の三十分に、最後の三十分に………待ってるんだよ。
諸君は武士だろう。
諸君は武士だろう。
武士ならば、自分を否定する憲法を、どうして守るんだ。
どうして自分の否定する憲法のため、自分らを否定する憲法というものにペコペコするんだ。
これがある限り、諸君てものは永久に救われんのだぞ。
諸君は永久にだね、
今の憲法は政治的謀略に、諸君が合憲だかのごとく装っているが、自衛隊は違憲なんだよ。
自衛隊は違憲なんだ。
きさまたちも違憲だ。
憲法というものは、
ついに自衛隊というものは、
憲法を守る軍隊になったのだということに、どうして気がつかんのだ!
俺は諸君がそれを断つ日を、待ちに待ってたんだ。
諸君はその中でも、ただ小さい根性ばっかりにまどわされて、
本当に日本のためにたちあがるときはないんだ。
そのために、われわれの総監を傷つけたのはどういうわけだ
抵抗したからだ。
憲法のために、日本を骨なしにした憲法に従ってきた、という、ことを知らないのか。
諸君の中に、一人でも俺といっしょに立つ奴はいないのか。
一人もいないんだな。よし!武というものはだ、刀というものはなんだ。自分の使命………。
それでも武士かぁ! それでも武士かぁ!
まだ諸君は憲法改正のために立ちあがらないと、見極めがついた。
これで、俺の自衛隊に対する夢はなくなったんだ。
それではここで、俺は、天皇陛下万歳を叫ぶ。
天皇陛下万歳! 天皇陛下万歳! 天皇陛下万歳! 
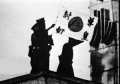
・・・・たしかに
二・二六事件の挫折によって、何か偉大な神が死んだのだった。
当時十一歳の少年であった私には、それはおぼろげに感じられただけだったが、
二十歳の多感な年齢に敗戦を際会したとき、
私はその折の神の死の恐ろしい残酷な実感が、十一歳の少年時代に直感したものと、
どこかで密接につながっているらしいのを感じた。
それがどうつながっているのか、私には久しくわからなかったが、
「 十日の菊 」 や 「 憂国 」 を私に書かせた衝動のうちに、
その黒い影はちらりと姿を現わし、又、定からぬ形のまま消えて行った。
それを二・二六事件の陰画とすれば、
少年時代から私のうちに育まれた陽画は、蹶起将校たちの英雄的形姿であった。
その純一無垢、その果敢、その若さ、その死、すべてが神話的英雄の原型に叶っており、
かれらの挫折と死とが、かれらを言葉の真の意味におけるヒーローにしていた。
十一歳のその日の朝、何も知らずに登校した私は、級友のある子爵の息子が、
「 総理が殺されたんだって 」 と 声をひそめて囁くのをきいた。
私は、「 ソーリって何だ 」 とききかえし、総理大臣のことだと教えられた。
齋藤内府の殺された私邸も学校のすぐ裏手にあり、その朝の学習院初等科は、
いわば地理的にも精神的にも 「 狙われた人たち 」のごく近くにいて、
不吉な不安に充たされていた。
授業第一時間目に、先生は休校を宣し、
「 学校からのかえり道で、いかなることに会おうとも、学習院学生たる矜りを忘れてはなりません 」
という訓示をした。
しかし私たちは何事も出会わなかった。
その雪の日、少年たちは取り残され、閑却され、無視されていた。
少年たちが参加すべきどんな行為もなく、
大人たちに護られて、ただ遠い血と哨煙の匂いに、感じ易い鼻をぴくつかせていた。
悲劇の起こった邸の庭の、一匹の仔犬のように。
少年たちはかくてその不如意な年齢によって、事件から完全に拒まれていた。
拒まれていたことが、却ってわれわれに、その宴会の壮麗さをこの世ならぬものに想像させ、
その悲劇の客人たちを、異常に美しく空想させたのかもしれない。
磯部浅一氏の 「 行動記 」 は、蹶起の瞬間を次のように述べている。
「 村中、香田、余等の参加する丹生部隊は、午前四時二十分出発して、
栗原部隊の後尾より赤坂溜池を経て首相官邸の坂を上る。
其の時俄然、官邸内に数発の銃声をきく、いよいよ始まった。
秋季演習の聯隊対抗の第一遭遇戦のトッ始めの感じだ。
勇躍する、歓喜する、感慨たとえんにものなしだ。
( 同志諸君、余の筆ではこの時の感じはとても表し得ない、とに角言うに言えぬ程面白い、
一度やって見るといい、余はもう一度やりたい。あの快感は恐らく人生至上のものであろう。) 」
( 河野司編 「二・二六事件 」 )
----この人生至上の面白さには、
しかし、あのとき少年たちの心に直感的に宿ったものと、
相照応するものがあったのではなかろうか。
戦時中は日の目を見なかった二・二六事件関係の資料が、戦後続々と刊行され、
私が 「 英霊の聲 」 を書き終った直後に上梓された。
「 木戸幸一日記 」 と 「 昭和憲兵史 」 ( 未発表の憲兵隊調書を収載 ) を以て、
ほぼ資料は完全に出揃ったものと思われる。
壮烈な自刃を遂げた河野寿大尉の令兄河野司氏の編集にかかる 「 二・二六事件 」 と、
末松太平氏の名著 「 私の昭和史 」 は、なかんずく私に深い感銘を与えた著書である。
私は集められる限りの資料に目を通していたが、それで一篇の小説を書こうという気はなかった。
たまたま昨年からかかった四巻物の長篇の、第一巻を書いているうちに、
来年からとりかかる第二巻の取材をはじめた。
たわやめぶりの第一巻 「 春の雪 」 と対蹠的に、第二巻 「奔馬」 は、
ますらおぶりの小説になるべきものであり、昭和十年までの国家主義運動を扱う筈であった。
それらの文献を渉猟するうち、
その小説では扱われない二・二六事件やさらに特攻隊の問題は、
適当な遠近法を得て、いよいよ鮮明に目に映ってきていた。
一方、私の中の故しれぬ鬱屈は日ましにつのり、かつて若かりし日の私が、
それこそ頽廃の条件と考えていた永い倦怠が、
まるで頽廃と反対のものへ向って、しゃにむに私を促すのに私はおどろいていた。
( 政治的立場を異にする人たちは、もちろんこれも頽廃の一種と考えるだろうことは目に見えている。)
私は剣道に凝り、
竹刀の鳴動と、あの烈しいファナティックな懸声だけに、ようよう生甲斐を見出していた。
そして短編小説 「 剣 」 を書いた。
私の精神状態を何と説明したらよかろうか。
それは荒廃なのであろうか、それとも昂揚なのであろうか。
徐々に、目的を知らぬ憤りと悲しみは私の身内に堆積し、
それがやがて二・二六事件の青年将校たちの、
あの激烈な慨きに結びつくのは時間の問題であった。
なぜなら、
二・二六事件は、無意識と意識の間を往復しつつ、この三十年間、たえず私と共にあったからである。
私は徐々にこの悲劇の本質を理解しつつあるように感じた。
北一輝の思想が、否定につぐ否定、
あの熱っぽい否定の颶風によって青年の心をとらえたことは、想像に難くないが、
二・二六事件の蹶起将校は、北一輝の国体観とだけは相容れぬものを感じていた。
幼年学校以来、「 君の御馬前に死ぬ 」 という務りと国体観は一体をなしていたにかかわらず、
北一輝は、 スコラ哲学化した国体観を一切否定し、
天皇を家長と呼び 民を 「 天皇の赤子 」 と呼ぶような論法を自殺論法と貶し、
君臣一家論を大逆無道の道鏡の論裡となし、
このような国体論中の天皇を、東洋の土人部落の土偶に喩えていたからである。
二・二六事件の悲劇は、方式として北一輝を採用しつつ、理念として国体を戴いた。
その折衷性にあった。
挫折の真の原因がここにあったということは、同時に、彼らの挫折の真の美しさを語るものである。
この矛盾と自己撞着のうちに、
彼らはついに、自己のうちの最高最美のものを汚しえなかったからである。
それを汚していれば、あるいは多少の成功を見たかもしれないが、
何ものにもまして大切な純潔のために、 彼らは自らの手で自らを滅ぼした。
この純潔こそ、彼らの信じた国体なのである。
そして国体とは ?
私は当時の国体論のいくつかに目をとおしたが、曖昧模糊としてつかみがたく、
北一輝の国体論否定にもそれなりの理由があるのを知りつつ、
一方、「 国体 」 そのものは、誰の心にも、明々白々炳乎として在った、
という逆説的現象に興味を抱いた。
思うに、一億国民の心の一つ一つに国体があり、国体は一億種あるのである。
軍人には軍人の国体があり、それが軍人精神と呼ばれ、
二・二六事件蹶起将校の 「 国体 」 とは、この軍人精神の純粋培養されたものであった。
そして、万世一系の天皇は同時に八百万の神を兼ねさせたまい、
上御一人のお姿は一億人の相ことなるお姿を現じ、一にして多、多にして一、
・・・・・・しかも誰の目にも明々白々のものだったのである。
この明々白々のものが、何ものかの手で曇らされ覆われていると感じれば、
忽ち剣を執って、これを討ち、明澄と純潔を回復しようと思うのは、当り前のことである。
二・二六事件将校にとって、統帥大権の問題は、軍人精神をとおしてみた国体の核心であり、
これを干犯する(と考えられた)者を討つことこそ、大御心に叶う所以だと信じていた。
しかもそれは、大御心に叶わなかたのみならず、
干犯者に恰好に口実を与え、身自ら 「 叛軍 」 の汚名を蒙らねばならなかった。
文学的意慾とは別に、かくも永く私を支配してきた真のヒーローたちの霊を慰め、
その汚辱を雪ぎ、その復権を試みようという思いは、たしかに私の裡に底流していた。
しかし、その糸を手繰ってゆくと、
私はどうしても天皇の 「 人間宣言 」 に引っかからざるをえなかった。
昭和の歴史は敗戦によって完全に前期後期に分けられたが、
そこに連続して生きていた私には、自分の連続性の根拠と、論理的一貫性の根拠を、
どうしても探り出さなければならない欲求が生まれてきていた。
これは文士たると否とを問わず、生の自然な欲求と思われる。
そのとき、どうしても引っかかるのは、「 象徴 」 として天皇を既定した新憲法よりも、
天皇御自身の、この 「 人間宣言 」 であり、
この疑問はおのずから、二・二六事件まで、
一すじの影を辿って 「 英霊の聲 」 を書かずにはいられない地点へ、私自身を追い込んだ。
自ら 「 美学 」 と称するのも滑稽だが、私は私のエステティックを掘り下げるにつれ、
その底に天皇制の岩盤がわだかまっていることを知らねばならなかった。
それをいつまでも回避しているわけには行かぬのである。
「 木戸幸一日記 」 昭和二十年九月二十九日の項には、
天皇をあたかもファシズムの指導者であったかの如く邪推する米国側の論調に対して、
陛下御自身次のごとく仰せられたことが誌されている。
「 其際、[ 天皇は ] 自分が恰もファシズムを心奉するが如く思わるることが、最も耐え難きところなり。
実際余りに立憲的に処置し来りし為めな如斯事態となりたりとも云うべく、
戦争の途中に於て今少し陛下は進んで御命令ありたりしとの希望を聞かざるには非ざりしも、
努めて立憲的に運用したる積りなり 」 ( 傍点三島 )
私が傍点を附したこの個所はもちろんこの文章の主旨ではなく、
陛下が立憲君主として一切逸脱せず振舞われたということが主旨である。
しかしこの傍点の個所に、
私は、天皇御自身が、あらゆる天皇制近代化・西欧化の試みに対する、
深い悲劇的な御反省の吐息を洩らされたようにも感じるのである。
日本にとって近代的立憲君主制は真に可能であったのか?
・・・・・あの西欧派の重臣たちと、
若いむこう見ずの青年将校たちと、どちらが究極的に正しかつたのか?
世俗の西欧化には完全に成功したかに見える日本が、
「神聖」 の西欧化には、これから先も成功することがあるのであろうか?
二 ・二六事件と私
三島由紀夫 著
英霊の聲 から
・・・リンク→などてすめろぎはひととなりたまいし

三島由紀夫が
「 私の崇敬する人 」 として、二・二六の将校たちを挙げていることを知ってから、
私は三島由紀夫に関心をもつようになった。
その時から、私が 「 三島さん 」 と 敬愛の呼びかけをするようになるのに多くの時日を要しなかった。
私と三島さんを結んだ糸は、『 憂国 』 であり、
その糸が、固結びとなって離れがたいものになったのは 『 英霊の聲 』 であった。
・
三島さんは、
二・二六事件の人たちの、最大の理解者であり、支持者であり、崇拝者であった。
そのすべては、『 英霊の聲 』 と 巻末の 「 私と二・二六 」 のうちにつきている。
市ヶ谷台上での、壮烈な警世の諌死、最後の絶叫 「 天皇陛下万歳 」 の 精神は、
二・二六将校たちの、刑場での 「 天皇陛下万歳 」 に相通じる、人間天皇でない、神格天皇である。
世俗紛々たる三島さんの死への雑音を排除し、私は三島さんの死に見る、日本人としての赤心を支持する。
偉大なる犠牲、捨身の骸むくろの上に萌めばえるであろう、純正日本の真姿顕現をしんじる。
事件直後、新聞、週刊誌上に見た、
「 楯の会 」 の 隊長森田必勝氏の部屋の写真に、私は驚きの目を見はった。
壁間に掲げられた国旗の日の丸を囲んで 「 尊皇討奸 」 の四文字があった。
三十五年前の雪の日、これと同じ旗が、白雪を踏んで蹶起した将兵の先頭に翻っていた。
「 尊皇 」 「 討奸 」 それは蹶起将兵の合言葉でもあった。
二・二六の精神は、昭和維新の悲願は、三十五年間、脈々として受継がれて、
楯の会の指針として三島精神を象徴していたことを見た。
私は、三島さんの死、それは二・二六の人たちの死と、切離しては考えられなかった。
三島さんの死について、
それぞれの立場の人々が毀誉褒貶きよほうへん、批判、論評は数知れない、
その当否の結論を見るには数十年を要するだろう。
しかし、私はかたくなに、三島さんの死と、二・二六の人たちの死との、
結びつき、
因縁を信じてやまない。
謹んで
「 彰武院文鑑公威居士 」
の 冥福を祈り、
維新日本への加護を祈ってやまない。
「 二・二六の挫折の原因は何でしょう 」
と 私の意見を求めた。
「・・最終的には天皇との関係の解明につきると思います 」
と 答えた。
「 やはりあなたもそうですか 」
・
要は事件突発後の現象の推移をいくら解明しても、
どうしても解けない謎が残る。
つきつめればそれは天皇の問題に帰する、
と 三島氏と私の見解は同じであった。
私は述べた
『 木戸日記 』 『 本庄日記 』 に 明らかなように、
事件暴発者に対する天皇の御怒りはよく理解できるが、問題はその 「 激怒 」 にある。
法治国家の元首として、又、軍の大元帥として、
国法を紊りみだり軍紀を犯したものに対し、
厳乎たる措置をとることは、国の秩序を守り、軍の統帥を正すことである。
その処置として、勅命を下し叛乱部隊の原隊復帰を命じたことも当然であったと思う。
しかるに何故か、勅命の下達実行が遷延した時点において、
陛下は
「 朕自ら近衛師団を率い、此が鎮圧に当らん 」
とまで叱咤しておられる。
これまでは理解できる。
しかしその後、蹶起将校一同は全員自決を決意し、
自決に際しては、せめて勅使の差遣を仰ぎたい旨の懇願を、本庄侍従武官長を通じて奏上した。
この最後の願いに対する陛下のお言葉は、
「 陛下には非常なる御不満にて、
自殺するならば勝手に為すべく此の如きものに勅使など以ての外なりと仰せられ 」
と、『 本庄日記 』 に ある。
これは私達が天皇に抱く不抜の信念からは、どうしても理解ができない。
明治天皇は
「 天下億兆一人もその所を得ざるときは皆朕が罪なれば 」
と 仰せられている。
これが日本の天皇の姿ではないだろうか。
だのに、
いま、
陛下の赤子が、その犯した罪を死を以て償おうとしている。
「 そうか、よく判ってくれた 」
と、温かく侍従に、
「 お前行ってよく見届けてやってくれ 」
何故に仰せられないのだろうか。
ここまで言った私の言葉に、
三島氏は、
「 人間の怒り、憎しみですね、日本の天皇の姿ではありません、悲しいことです 」
と、言葉をはさんだ。
私はさらに言葉をついだ。
「 みしまさん、彼等が若し獄中で陛下のこのような言動を知っていたら、
果して 『 天皇陛下万歳」 』 を 絶叫して死んだでしょうか 」
との設問に、三島氏は、
「 君、君たらずとも、ですよ
あの人達はきっと臣道を踏まえて神と信ずる天皇の万歳を唱えたと信じます
でも日本の悲劇ですね 」
と、声をつまらせたことが、未だに忘れられない。 ←「天皇陛下万歳」
←「天皇陛下万歳」
思えば、今回の三島氏の自決直前に絶叫した。
「 天皇陛下万歳 」
の中に、
氏の死を賭した悲願を見る。
人間天皇を否定する三島氏の最後の絶叫は、「 神格天皇万歳 」 で あったと信ずる。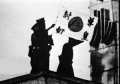 山王ホテルで尊皇討奸旗を掲げる蹶起部隊
山王ホテルで尊皇討奸旗を掲げる蹶起部隊
昭和十一年二月二十六日、
前夜来の大雪を蹶って暴発した二・二六事件は,僅か四日間で敗退したが、
その四日間の経過は紆余曲折、三転四転、複雑怪奇の跡を辿って幕を閉じた。
事件発生以来の、行動面の現象をいくら追及しても、
その収拾措置の過程には、どうしても納得できない疑問が解けない。
その疑問の帰結する所は、
天皇の意志、存在に突き当たるのであって、
これを裏付け究明することが、事件収拾の謎を解く鍵であると見られていた。
しかし、天皇の問題は、踏み込み難い壁があることで、決めてを欠くものがあった。
これを取上げて、大胆に触れたのが三島氏であり、その著 『 英霊の聲 』 である。
その中で、天皇はこれまでの治世の中で、二つの失政を犯したとして、
その一つは、
二・二六事件の処理であり、
もう一つは、終戦時の処置であるとする。
そして、そのいずれも失政の原因は、天皇が人間ひとになったためであり、
日本の天皇は人間になってはいけない、神でなくてはいけないと説くのである。
二・二六の場合、陛下は 「 天皇 」 の座を降りて 「 人間 」 になったために、
その人間感情の激怒の奔流が、
二・二六の青年将校たちの憂国の至情、純真精神を押流してしまった。
そして、三島氏は磯部浅一が獄中で絶叫する。
「 陛下、何たる御失政でありますか 」
「 このままでは日本は滅亡致しますぞ 」
と、陛下を御諫めするその烈々の心情を支持するのである。
三島氏が言うように、二・二六事件の収拾が、あのような形で幕を閉じたことが、
不当であったか、あるいは妥当であったか、
さらにはそれが天皇の失政であったかどうかの問題は別として、
尠くとも、四日間の経過の不可解な展開の裏には天皇の意志が大きく左右したことが
幾多の事実によって推理されていたことは疑いがない。
それが図らずも陛下御自身の口から
「 一九三六年の二・二六事件をあげ、あの場合は暗殺によって多くの閣僚が空席となったため、
自分の意志で行動せざるを得なかったのだ、
さらに、第二次大戦の終結に関しては、
鈴木 ( 貫太郎 ) 首相が、決定を彼に委ねたので、鈴木の責任において彼は決定を自ら下したのだ 」
との釈明となって語られたことは大きな意義をもつ。
かつて国内で、陛下のこのようなお言葉----告白----を聞いた覚えはない
記者会見が未曾有のことであったと同時に、政治上の問題でのこうした発言もまた、
前代未聞ではあるまいか。
私は、陛下が三島氏の 『 英霊の聲 』 を 読まれたとは思はない
天皇の失政として責める内容の書を、側近が御見せするはずはないと思うからだ。
ところが、今度の御発言である。
軌を一にしたかのように、三島所論への回答とも思える内容が、はしなくも語られたことは、
果して偶然の一致であろうか。
「 二・二六の処置は自分がやった、そしてそれは終戦時の処理とともに、
立憲君主の立場を逸脱した異例のことである 」
と、積極的に話されたということに、私は抑えきれない感動に激した。
私は三島氏の説を支持もしないが無視もしない。
しかし、三島氏が指摘した二つの ”失政” が、今度の ”二つの異例” と合致すことには無関心では有得ない。
三島氏の言う ”失政” は、あくまでも精神面であり、現実の政治面での ”失政” に通じるとは思わない。
三島氏が、
「 などてすめろぎは人間ひととなりたまひし 」
と、繰返して陛下をお恨みする由来は、
「 天皇は神でなくてはいけない 」
とする 彼の天皇観、国体観によるので、
この精神的観点から事件収拾の過程においての天皇の言動、処置を見るとき、
その収拾結末の善悪は別として、
その間に人間感情によって左右された経過があったと見られるところを、
三島氏は問題とするのである。
この ”人間感情” の現実を、松本清張を初め論者は、”激怒” と表現している
三島氏は 「 おいかりは限りなく 」 と、文学的に書いているが、
いずれにしても、
この天皇の ”激怒” の背景が何であるかという、具体的事実の追及には及んでいない。
いずれも 筆を擱おいて 踏込もうとしない。
私はここに二・二六の謎の、核心の存在を見る思いである。
私もまた、そのことに触れることなく、この稿を終る。
三島由紀夫と二・二六事件 河野司 著
浪漫人三島由紀夫 その理想と行動 (昭和48年4月5日発行) から
かけまくもあやにかしひき
すめらみことに伏して奏さく まお
今、四海必ずしも波穏やかならねど
日の本のやまとの国は
鼓腹撃壌の世をば現じ こふくげきじょう げん
御仁徳の下、平和は世にみちみち もと
人ら泰平のゆるき微笑に顔見交わし
利害は錯綜し、敵味方も相結び、
外国の金銭は人を走らせ とつくに
もはや戦いを欲せざる者は卑怯をも愛し、
邪まなる戦のみ陰にはびこり いくさ (いん)
夫婦朋友も信ずる能わず
いつわりの人間主義をたつきの糧となし
偽善の団欒は世をおおい
刀は貶せられ、肉は蔑され、 へん なみ
若人らは咽喉元をしめつけられつつ
怠慢と麻薬と闘争に
かつまた望みなき小志の道へ
羊のごとく歩みを揃え、
快楽もその実を失い、信義もその力を喪い、
魂は悉く腐蝕せられ
年老いたる者は卑しき自己肯定と保全をば、
道徳の名の下に天下にひろげ
真実はおおいかくされ、真情は病み、
道ゆく人の足は希望に躍ることかつてなく
なべてに痴呆の笑いは浸潤し
魂の死は行人の額に透かし見られ、
よろこびも悲しみも須臾にして去り すゆ
清純は商われ、淫蕩は衰え、 いんとう
ただ金よ金よと思いめぐらせば かね
人の値打は金よりも卑しくなりゆき、
世に背く者は背く者の流派に、
生かしこげの安住の宿りを営み、 なま
世に時めく者は自己満足の
いぎたなき鼻孔をふくらませ、
ふたたび衰えたる美は天下を風靡し
陋劣なる真実のみ真実と呼ばれ、 ろうれつ
車は繁殖し、愚かしき速度は魂を寸断し、
大ビルは建てども大義は崩壊し
その窓々は欲求不満の蛍光燈に輝き渡り、
朝な朝な昇る日はスモッグに曇り
感情は鈍磨し、鋭角は磨減し、
烈しきもの、雄々しき魂を払う。
血潮はことごとく汚れて平和に澱み
ほとばしる清き血潮は涸れ果てぬ。
天翔けるものは翼を折られ
不朽の栄光をば白蟻どもは嘲笑う。 あざわらう
かかる日に、
などてすめろぎは人間となりたまいし ひととなりたまいし
・・・・・・・・・・・・・・・・
・
われらには、死んですべてがわかった。
死んで今や、われらの言葉を禁める力は何一つない。 とどめるちから
われらはすべてを言う資格がある。
何故ならわれらは、まごころの血を流したからだ。
今ふたたび、刑場へ赴く途中、一大尉が叫んだ言葉が胸によみがえる。
「皆死んだら血のついたまま、天皇陛下のところに行くぞ。
而して死んでも大君の為に尽すんだぞ。大日本帝国万歳」
そして死んだわれらは天皇陛下のところへ行ったか?
われらの語ろうと思うことはそのことだ。
しかしまず、われらは恋について語るだろう。
あの恋のはげしさと、あの恋の至純について語るだろう。
「朕は汝軍人の大元帥なるぞ。
されば朕は汝等を股肱と頼み汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ、その 親 は特に深かるべき。 したしみはことに
朕が国家を保護して上天の恵に応じ祖宗の恩に報いまいらする事を得るも得ざるも、 ほうご しょうてん
汝等軍人が其職を尽すと尽さざるとに由るぞかし」
大演習の黄塵のかなた、天皇旗のひらめく下に、白馬に跨れた大元帥陛下の御姿は、
遠く小さく、われらがそのために死すべき現人神のおん形として、 あらひとがみ
われらが心に焼きつけられた。
神は遠く、小さく、美しく、清らかに光っていた。
われらが賜わった軍帽の徽章の星をそのままに。 ぐんぼうのしるし
皇祖皇宗のおんみ霊を体現したまい、兵を率いては向うに敵なく、 おんみたま
蒼生を憐れんでは慈雨よりもゆたかなおん方。 たみくさ おんかた
われらの心は恋に燃え、仰ぎ見ることはおそれ憚りながら、忠良の兵士の若いかがやく日は、
ひとしくそのおん方の至高のお姿をえがいていた。
われらの大元帥にしてわれらの慈母。
勇武にして仁慈のおん方。
はげしい訓練のあいだにも、すめろぎの大御心はわれらに通うかに感じられ、
消煙の漂う野のかなたから、つねに大御心の一条の光は、戦うわれらの胸内に射していた。 むねうち
そしてわれらは夢みた。
ああ、あの美しい清らかな遠い星と、われらとの間には、しかし何という距離があることだろう。
われらの汚れた戎衣と、あの天上のかぐわしい聖衣との間には、
何という遠い距離があることだろう。
われらの声は届くだろうか。
勅諭をとおして玉音はひしひしと、日夜われらの五体に響いているが、われらの血の叫び、
死のきわに放つべき万歳の叫びは、そのおん耳に届くだろうか。
神なれば千のおん耳をもちたまい、千のおん眼まを以て、見そなわし、 まなこ
又、きこしめされるにちがいはない。
しかしそのとき・・・・・・
われらは夢みた。
距離はいつも夢みさせる。
いかなる僻地、北溟南海の果てに死すとも、われらは必ず陛下の御馬前で死ぬのである。
しかしもし 「そのとき」 が来て、絶望的な距離が一挙につづめられ、
あの遠い星がすぐ目の前に現われたとき、そのかがやきに目は盲い、ひれ伏し、 めしい
言葉は口籠り、何ひとつなす術は知らぬながらも、その至福はいかばかりであろう。 くごもり すべ
死を賭けたわれらの恋の成就はいかばかりであろう。
その時早く、威ある清らかな御声が下って、ただ一言、「死ね」 と仰せられたら、 みこえがくだって
われらの死の喜びはいかほど烈しく、いかほど心満ち足りたものとなるであろう。
われらは生涯に来るとしもないその刹那をひたすらに夢みた。
われらは若く剛健にして、忠節と武勇と信義はならびなく、心は燃えやすく、魂は澄んでいる。
不正はわれらの身に一指も触れるあたわず、若き力と血はこの身にたぎっている。
かくて、われらはすめろぎの星について夢みつづけ、心にその像をいとおしく育てて行った。
民草をひとしく憐れませたまうそのおん方の前へへ出れば、
ここからはかくも遠かったその距離も忽ち払われ、
親疎の別なく父子の情をかけたもうおん方の前では、ここにおいて思う怖れも杞憂にすぎまい。
われらは若く、文雅に染まらず、武骨ながら、われらの血と死の叫びをこめた不器用な恋をも、
どんな不器用な忠義をも、大君は正しく理会したまい、受け入れたもうにちがいない。
かくてわれらはついに、一つの確乎たる夢に辿りついた。
その夢の中では、宮廷の千年の優雅に織り成された生絹の帷が、 すずしのとばり
ほのかな微風をもうけ入れてそよいでいた。
「陛下に対する片恋というものはないのだ」 とわれらは夢の確信を得たのである。
「そのようなものがあったとしたら、もし報いられぬ恋がある筈だとしたら、軍人勅諭はいつわりとなり、
軍人精神は死に絶えるほかはない。
そのようなものがありえないというところに、君臣一体のわが国体は成立し、
すめろぎは神にましますのだ。
恋して、恋して、恋して、恋狂いに恋し奉ればよいのだ。
どのような一方的な恋も、
その至純、その熱度にいつわりがなければ、必ず陛下は御嘉納あらせられる。
陛下はかくもおん憐れみ深く、かくも寛仁、かくもたおやかにましますからだ。
それこそはすめろぎの神にまします所以だ」
われらはそう信じた。
われらはこうして、この恋の端緒を神語りに語りおわった。
・
そのとき陛下はおん年三十五におわしました。
陛下は老臣の皺多き理性と、つつましき狡智に取り巻かれていらせられた。
かつて若きもののふが玉体を護って流す鮮烈な血潮を見そなわしたことはなかった。
民の貧しさ、民の苦しみを竜顔の前より遠ざけ、陛下を十重二十重に、あれらの者たち、
すなわち奸臣佞臣、
あるいは保身にだけ身をやつした者、不退転の決意を持たずに当った者、
臆病者にしてそれらと知らずに破局への道をひらいた者、あるいは冷血無残な陰謀家、
野心家が取り囲み奉っていた。
そして陛下は、霜落つる兵舎の片かげに息吹く若き名もなき者の誠忠の吐息を いぶく
見そなわしたことはなかった。
われらが国体とは心と血のつながり、片恋のありえぬ恋闕の激烈なよろこびなのだ。
さればわれらの目に、はるか陛下は、醜き怪獣どもに幽閉されておわします。
清らにも淋しい囚われの御身と映った。
怪獣どもは焰を吐き、人肉を喰い、あやしい唸り声を立てて徘徊しつつ、 ほのお くらい
上御一人の警護を装うて、実は九重の奥に閉じ込め奉っていた。
その鱗には黄金の苔を生じ、いまわしい銅臭を漂わせ、
その這いずりまわる足もとの草は悉く枯れた。
われらはその怪獣どもを仆して、陛下をお救い出し申し上げたい、と切に念じた。
そのときこそ、民も塗炭の苦しみから救われ、
兵は後顧の憂いなく、勇んで国の護りに就くことができるであろう。
われらはついに義兵を挙げた。
思いみよ。
その雪の日に、わが歴史の奥底にひそむ維新の力は、大君と民草、神と人、
十善の御位にましますおん方と忠勇の若者との、稀なる、対話を用意していた。 みくらい
思いみよ。
そのとき玉穂なす瑞穂の国は荒無の地と化し、民は餓えに泣き、女児は売られ、
大君のしろしめす玉土は死に充ちていた。
神々は神謀りたまい、わが歴史の井戸のもっとも清らかな水を汲み上げ、 かむはかり
それをわれらが頭に注いで、荒地に身を伏して泣く蒼氓に代らしめ、 こうべにそそいで
現人神との対話をひそかに用意された。
そのときこそ神国は顕現し、狭蠅なすまがつびどもは吹き払われ、 さばえ
わが国体は水晶のごとく澄み渡り、国には至福が漲る筈だった。 みなぎる
思いみよ。
そのとき歴史のもっとも清らかなるものは、遍満する腐敗、老朽と欺瞞を打ちやぶり、
純潔と熱血のみ、若さのみ、青春のみをとおして、陛下と対晤せんと望んだのだ。 たいご
やすみしし大君のしろしめす限り、かしこの田、かしこの畑、
かしこの林に久しく埋もれた血の叫び、死の顔は、
今や若々しく猛々しい兵士の顔を借りて、たぎり、あふれ、対面しまいらせんとはかったのだ。
冥々のうちなる日本のもっとも素朴、もっとも根深き魂が、ここを先途と明るみへ馳せのぼり、 せんど
光の根源へ語りかけまいらせようと願ったのだ。
われらはその指揮官だった。
そしてわれらは神謀りのままに動く神の兵士であった。
一つの絵図は、次のように光にみちて描かれた。
そこは一つの丘である。
雪晴れの朝、雪に包まれた丘は銀にかがやき、木々は喜ばしい滴を落し、 しずくをおとし
力強い笹は雪の下から身を起こし、われらは兵を率いて、奸賊を屠った血刀を堤げて立っている。 ほふった
その剣尖からなお血は雪にしたたり、われらの類は燃え、われらの雪に洗われた軍帽の庇は、
漆黒の青空を映している。
兵はみな粛然として、胸をときめかせつつ、近づく栄光の瞬間を待っている。
それは又、ふるさとの悲しめる父母、悲しめる姉妹の救済の時である。
われらは雪晴れの空をふり仰ぐ。
目にしみわたるその青さは、かなたの連山のかがやく白雪の頂きへまで、
遮る雲の一片もなくつづいている。 ひとひら
そして巨木の梢から落ちる雪は四散して、
ふたたびきらめく粉雪になって、かろやかにわれらの軍帽の上に降ってくる。
そのときだ。
丘の麓からただ一騎、白馬の人がしずしずと進んでくるのは。
それは人ではない。
神である。
勇武にして仁慈にましますわれらの頭首、大元帥陛下である。
われらは兵たちに、
「気をつけ!」
の号令をかける。
われらの若く雄々しい号令にまして、この雪晴れの誉れの青空にふさわしいものがあろうか。
陛下は馬をとどめさせ玉い、馬上の陛下のおん影が、
かたじけなくもわれらの雪に濡れた軍靴の足もとに届く。
われらの軍服の胸を張り、捧刀の礼を以てお迎えする。
刀の切羽のまばゆい銀のきらめきを、剣尖からしたたり戻る血がつたわるのを、われらは目の前に見る。
「謹んで申上げます。
われらは君側の奸を斬り、今は粛然として、陛下の御命令をお待ちいたします。
何卒、御親政を以て、民草をお救い下さい」
『よし。
御苦労である。
その方たちには心配をかけた。
今よりのちは、朕親に政務をとり、国の安泰を計るであろう 』 みずから
玉音はあたかも、雪晴れの青空がさわやかに声を発したかのようである。
陛下はつづけて仰せになる。
『その方たちには位を与え、軍の枢要の地位に就かせよう。
今までは朕が不明であった。
皇軍は誠忠の士を必要としている。
これからはその方たちが積弊をあらため、天皇の軍隊の威烈を蘇らさねばならぬ』
「いや、陛下、何卒このままにお置き下さい。
一級たりとも位を進めていただいては、われらが身命を賭した維新の精神が汚れます。
ただ、御親政の実をあげられ、兵たちの後顧の憂いを無からしめて下さることが、
われらへのこの上なき御褒賞であります。
今こそ兵もよろこび勇んで軍人の本分を尽し、皇国を護るために命を捨てることができます」
『そうか。
その方たちこそ、まことの皇軍の兵士である』
陛下は叡感斜めならず、赤誠の兵士らに守られて雪の丘をお下りになる。
その白馬のおん跡に従うわれらこそ、神兵なのだ。
思いみよ。
ここにもう一つ絵図がある。
それは光にみちて描かれてはいないが、第一の絵図にも劣らず、倖せと誉れにあふれたものだ。
むしろわれらの脳裡に、より鮮明に描かれていたのは、この第二の絵図であった。
同じ丘。
しかし空は晴れず、雪は止んでいるが、灰色の雲が低く垂れ込めている。
そのかなたから、白雪の一部がたちまち翼を得て飛び来ったように、
一騎の白馬の人、いや、神なる人が疾駆して来る。
白馬は首を立てて嘶き、その鼻息は白く凍り、雪を蹴り立てて丘をのぼり、われらの前に、
なお乱れた足搔を踏みしめて止る。 あしがき
われらは捧刀の礼を以てこれをお迎えする。
われらし竜顔を仰ぎ、そこに漲る並々ならぬ御決意を仰いで、
われらの志がついに大御心にはげしい焰を移しまいらせたのを知る。 ほのお
『その方たちの誠忠をうれしく思う。
今日よりは朕の親政によって民草を安からしめ、必ずその方たちの赤心を生かすであろう。
心安く死ね。その方たちはただちに死なねばならぬ』
われわれは躊躇なく軍服の腹をくつろげ、口々に雪空も裂けよとばかり、
「天皇陛下万歳!」 を叫びつつ、手にした血刀をおのれの腹深く突き立てる。
かくて、われらが屠った奸臣の血は、われらの至純の血とまじり、同じ天皇り赤子の血として、 ほふる
陛下の御馬前に浄化されるのだ。
われらに苦痛はない。
それは喜びと至福の死だ。
しかしわれらは、肉にひしと抱擁される刃を動かしつつ、背後に兵たちの一せいのすすり泣きを聞く。 やいば
寝食を共にし、忠誠を誓い合い、戦場の死をわが手に預けてくれた愛する兵士たちの歔欷を聞く。 きよき
そのとき、世にも神さびた至福の瞬間が訪れる。 かむ
大元帥陛下は白馬から下り玉い、われらの若い鮮血がくれないに染めた雪の上に下り立たれる。
そのおん足もとには、われらの今や死なんとする肉体が崩折れている。
陛下は死にゆくわれらを、挙手の礼を以てお送りになる。
われらは遠ざからんとする意識のうちに、力をふるって項を正し、竜顔をふり仰ぐ。 うなじ
さしも低く垂れ込めた雲が裂けて、一条の光りが、竜顔をあれたかに輝かせる。
そしてわれらは、死のきわに、奇蹟を見るのだ。
思いみよ。
竜顔のおん頬に、われらの死を悼むおん涙が!
雲間をつらぬく光りに、数条のおん涙が!
神がわれらの至誠に、御感あらせられるおん涙が! ぎょかん
われらの死は正しく至福の姿で訪れる。
・・・・・・・・
それはただの夢、ただの絵図、ただの幻であった。
すめろぎがもし神であらせられれば、二枚の絵図のいずれかを選ばれることは必定だった。
あれほどまでの恋の至情が、神のお耳に届かぬ筈はなかったからだ。
又、すめろぎが神であらせられれば、あのように神々がねんごろに謀り玉うた神人対晤の至高の瞬間を、
成就せずにおすましになれる筈もなかったからだ。
かくも神々が明らかにしつらえ玉うた、救国の最後の機会を、みすみすの逸し玉う筈もなかったからだ。
そのころ陛下は暗い宮中をさすらい玉い、扈従の人のものを憚るような内奏に耳をすまされた。 こしょう
民草の不安は、病菌のように人々の手で運ばれて、宮廷風の不安に形を変えてすでに澱んでいた。
陛下はただちにこう仰せられた。
『日本もロシヤのようになりましたね』
このお言葉を洩れ承った獄中のわが同志が、いかに憤り、いかに慨き、いかに血涙を流したことか!
二月二十六日のその日、すでに陛下は、陸軍大臣の拝謁の際
『今回のことは精神の如何を問わず、甚だ不本意なり、国体の精華を傷つくるものと認む』
と仰せられた。
二十七日には、陛下はこのように仰せられた。
『朕が股肱の臣を殺した青年将校を許せというのか。
戒厳司令官を呼んで、わが命を伝えよ。
速やかに事態を収拾せよ、と。
もしこれ以上ためらえば、朕みずから近衛師団をひきいて鎮圧に当るであろう』
同じ日に、自刃せしむるため、勅使の御差遣を願い出た者には、
『自殺するならば勝手に自殺させよ。そのために勅使など出せぬ』
と仰せられた。
陛下のわれらへのおん憎しみは限りがなかった。
佞臣どもはこのおん憎しみを背後に戴き、たちまちわれらを追いつめる策を立てた。
二十八日に出された奉勅命令は、途中で握りつぶされてわれらの目に触れず、
この無辜の抗命がたちまちわれらを、天皇に対する叛逆の罪に落した。 むこ
陛下のおん憎しみは限りがなかった。
軍のわれらの敵はこれに乗じて、たちまち暗黒裁判を用意し、われらの釈明はきかれる由もなく、
はやばやと極刑が下された。
かくてわれらは十字架に縛され、
われらの額と心臓を射ち貫いた銃弾は、叛徒のはずかしめに汚れていた。
このとき大元帥陛下の率いたもう皇軍は亡び、このときわが皇国の大義は崩れた。
赤誠の士が叛徒となりし日、漢意のナチスかぶれの軍閥は、 からごころ
さえぎるもののない戦争への道をひらいた。
われらは陛下が、われらをかくも憎しみたもうたことを、お咎めする術とてない。
しかし叛逆の徒とは!
叛乱とは!
国体を明かにせんための義軍をば、叛乱軍と呼ばせて死なしむる、
その大御心に御仁慈はつゆほどもなかりしか。
こは神としてのみ心ならず、
人として暴を憎みたまいしなり。
鳳輦に侍するはことごとく賢者にして ほうれん
道のべにひれ伏す愚かしき者の
血の叫びにこもる神への呼びかけは
ついに天聴に達することなく、
陛下は人として見捨ててたまえり、
かの暗澹たる広大なる貧困と あんたん
青年士官らの愚かなる赤心を。
わが古き神話のむかしより
大地の精の血の叫び声を凝り成したる こり
素戔鳴尊は容れられず、
聖域に馬の生皮を投げ込みしとき
神のみ怒りに触れて国を逐われき。
このいと醇乎たる荒魂より あらみたま
人として陛下は面をそむけ玉いぬ。 おもて
などてすめろぎは人間となりたまいし ひととなりたまいし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
歌うにつれて、声は一つ加わり、又一つ加わって、この会はじめの帰神のときと同様、 かむがかり
それは雄々しいあまたの声の合唱になった。
そして潮のうねりのように、ひとたび合唱が参列者の耳を占めるにいたると、 うしお
もう独り語りの神の声は聴きわけられることがなかった。


三島由紀夫 英霊の聲 から
リンク→二・二六事件と私
『 尚武のこころ 』
三島由紀夫対談集 「 守るべきものの価値 」
われわれは何を選択するか
石原慎太郎 (作家・参議院議員) 月刊ペン 昭和44年11月号
・
昭和49年 (1974年 ) 8月8日
二十歳の私が購読したものである
三島 石原さん、
今日は 「 守るべきものの価値 」 に就いて話をするわけだけど、
あなたは何を守ってる ?
石原 戦後の日本の政治形態があいまいだから、守るに値するものが見失われてきているけど、
ぼくはやはり自分で守るべきものは、あるいは社会が守らなければならないのは、自由だと思いますね。
自由は、なにも民主主義によって保証されているものではないんで、
ある場合には、全然違った政治形態によって保証されるものかもしれない。
しかし、われわれはどんな形の下であろうと、自由というものを守ればいい。
僕のいう自由というのは、戦後日本人が膾炙 (カイシャ) してしまった浮薄な自由と違って、
もっと本質的なものです。
三島 でも自由にもいろんな自由があるからね。
どの自由を守るか、たとえば三派全学連はやはり彼らも自由を求めていて、
彼らが最終的にほんとの自由な政治形態、自由な社会をつくるんだと主張しているわけだよ。
自由は人によってずいぶん違うから、そこが問題じゃないですかね。
もし、あなたが自由と言えば、それはやはり米帝国主義か、日本独占資本主義か、
自民党政権下の自由であるというふうにやつらは既定するだろう。
その自由を、つまり やつらと どう違うんだということを説明しないと、自由というのはわからないんじゃないかな。
石原 僕の言う自由はもっと存在論的なもので、つまり全共闘なり、自民党なり、
アメリカンデモクラシーが言っているもののもっと以前のもので、その人間の存在というもの、
あるいはその人間があるということの意味を個性的に表現しうるということです。
つまり僕が本当に僕として生きていく自由。
三島 言論の自由ということですか。 言論、表現の自由。
石原 もちろん言論、表現の自由をも含めてです。
根本は、自分自身の表現そういう自由を許容し得る社会というのは、相対的にながめれば、
やはりコミュニズムよりも、民主主義という政治形態のなかのほうがありうるとぼくは思います。
それすらも非常に制約があるということで、一部の学生たちは既成のエスタブリッシュメントを見て
こわそうとしているわけでしょうけどね。
彼らが非常に生理感覚が鋭敏で、この時代のうそ、
ぬるま湯みたいな民主主義のうそを拒否していることは共鳴できる。
ただ、日本の学生運動を評価できないのは、そのほとんどが容共というか、
歴史的に、社会科学的に、自由への制約が根強い方向を自ら目指している。
共産主義の方法論で自由を求めようとするところが、陳腐で、
保守的というより、退嬰的(タイエイテキ)だと思うんですよ。
だから、ぼくは日本の学生運動というのを認めないんだ。
三島 ただ自由の観念が、たとえばアメリカというのはベトナム戦争中におけるアメリカを評価すれば、
あの長い戦争の経過で言論統制をしなかったこと。
反戦運動は起るわ、反体制的な新聞は出るわ、あらゆることをやってきて、
戦争をやってきてまだやっているんだけれども、言論統制をやっていないことはえらいと思うんです。
あれをやったらアメリカはもう意味がないですね。
チェコも結局、言論の自由の問題です。
それでは言論の自由を守るのには代議制民主主義という政治形態が一番いい、と
するとわれわれは言論の自由を守るために闘うのであって、
ソビエト、ないし中共、ないしその他の共産主義社会では自由はまもれないから、
これに対して闘うという論理だね。
もう一つ新しい政治形態ができて、いまのような死んだ自由ではなくて、
もっと積極的な自由を君らに与えるような政治形態ができれば、
何もそんなにむきになって共産主義に対抗して、民主主義を守らなくてもいいじゃないか、
というのは直接民主主義という考え方なんですね。
直接民主主義という考え方はぼくにもよくわかりませんけれども、
個人個人の自由と、国家意思というものとは一致するということを考えているんでしょうね。
ぼくも言論の自由を守るために、たとえたいした政治形態ではなくても、
言論の自由を保証する政治形態を守るということには全面的に賛成ですがね。
しかしそれと、国民の血というか、文化伝統というか、そういうわれわれの根(ルート)
と 言論の自由がどういう関係があると思う?
自由自体が国民の根であると思うかね。
先験的な自由というものがあって、それはわれわれの国民精神と完全に融合すると思いますか。
石原 ぼくは三島さんより伝統からは自由ですからね。
伝統を絶対化したら、何も出来ない。 進歩もない。
三島 自由だと思っているだけで、君は意識的に自由だと思っているだけで、
決して自由じゃないです。 日本語を使っているんだから。
石原 そりゃそうですよ。たしかに存在というのは、先天的な根を持たなくちゃいけないという。
ぼくの言うのは、存在にはいろんな場合がある、心情的な存在も、精神的な存在もあるでしょうけれども、
特に心情、情念という形は、われわれが根から吸ったフルーツ、つまり伝統という風土を持たざるをえない。
しかしそういったものからのがれようとすることだって自由の問題になってくるでしょう。
しかしそういう根を持つということは不自由なのではない。
つまり自由、不自由以前の問題なんで。
三島 そうすると、つまり根というものは先天的に与えられたものだ、自由は選択だしいう考えだね。
石原 そうです。
三島 ぼくはそこに昔から疑問を感じているんだ。 つまりあなたが自由を撰んだんだ。
人間は自分が選んだバリューを最終的に守ることができることにぼくは疑問なんだ。
石原 選択というより、自由というのはさがすことだ。
三島 人間がさがして最後に到達するものは根だよ。 そうだろ。
石原 いろんな意味での存在の根に対する回帰でしょうね。
しかし、そのためさまざまな回路にも大きな意味がある。
三島 回帰だろう。
回帰のなかには自由という問題をこえたものがあるはずだ。
ぼくは簡単に言うと、こういうことだと思うんだ。
つまりわれわれは何かによって規定されているでしょう。
これは運命ですね。 日本に生れちゃった。
あるいは石原さんのようにブルジョアの家庭に生れちゃった。
石原 ぼく ? とんでもない。
あなたと違って私はたたき上げですからね (笑い)
三島 自由を守るというのはあくまで二次的問題であって、これは人間の本質適問題ではない。
自由を守る、ある政治体制を守るということは、人間にとって本質的問題でも何でもない。
ぼくは、おまえ民主主義を守るために死ぬか、と言われたら、絶対死ぬのはいやですよ。
国会議事堂を守るために死ぬのもいやだし、自民党を守るために死ぬのもますますいやですね。
われわれはある政治体制を守るために死ぬんじゃない。
じゃ何を守るために死ぬのか。
バリューというものを追い詰めていけば、そのために死ねるものというのが、
守るべき最終的な価値になるわけだ。
それはこの自由の選択のなかにないとぼくは思うんだね。
自由の選択自体のなかにはない。
もっと規定しているもののなかにそれがあるんだ。
石原 何のために死ねるかといえば、それは結局自分のためです。
その自分の内に何をみるかということでしょ。
三島さんがいう自由というのは、ぼくの言った自由とは違うところにそれてしまっていると思うな。
ことばのあやみたいだけれども、規定するものとは、不自由ということですか。
三島 ニーチェの 「アモール・ファティ」 じゃないけれども、自分の宿命を認めることが、
人間にとって、それしか自由の道はないというのがぼくの考えだ。
石原 ギリシャの悲劇は宿命というものからのがれようとしている、それに対して闘おうとするあれは何ですか。
三島 ヒュプリスというんだ、ごうまんというんだ。 神が必ずそれを罰するのが悲劇なんだ。
石原 そうですよ。 しかしそこにやはり高貴な自由があるでしょう。
だから神はその英雄を罰し、その後に神にする。
三島 その自由のギリシャのヒュプリスの伝統がキリスト教になり、あるいは三派、全学連になっているんだ。
結局、最後には、人間というものは人間をはみ出して、何かそれ以上のものになろうという、
その意志のなかに何か不遜なものがあるんだ。
それがずうっと尾を引いて直接民主主義までいってしまっているんだ。
それは滅ぼさなくちゃいけない。
石原 それはおそろしい発言だと思うな。 神ならそういえるけど。
それに人間を超えようとすることこそが、人間的でしょう。
ぼくはやはりそういう意味では三島さんより自由というものを広義で考えている。
だってそうじゃないですか。
自分の宿命というものに反逆しようとすることだって、それは先天、後天の対立かもしれないけれども、
しかし宿命というものを忌避しようとすることは、人間にとって自由です。
そこに、神のでない人間の意志がある。
三島 しかし宿命を忌避する人間は、またその忌避すること自体が運命だろう。
そういう人間はそういうふうに生れついちゃったんだ、反逆者として。
石原 しかしそれはその人間の一つの存在の表現であって、
ぼくはやはり人間の尊厳というのはそこにしかないと思うな。
三島 君はずいぶん西洋的だなあ (笑い)
ぼくはそういう点では、つまり守るべき価値ということを考えときには、全部消去法で考えてしまうんだ。
つまりこれを守ることが本質的であるか、じゃここまで守るか、ここまで守るかと、
自分で外堀から内堀へだんだん埋めていって考えるんだよ。
そしてぼくは民主主義は最終的には放棄しよう、と。
あ、よろしい、よろしい。 言論の自由は最終的に放棄しよう、
よろしい、よろしいと言ってしまいそうなんだ、おれは
最後に守るものは何だろうというと、三種の神器(ジンギ)しかなくなっちゃうんだ。
石原 三種の神器って何ですか。
三島 宮中三殿だよ。
石原 またそんなことを言う
三島 またそんなことを言うなんていうんじゃないんだよ。
なぜかというと、君、いま日本はナショナリズムがどんどん浸食されていて、
いまのままでいくとナショナリズムの九割ぐらいまで左翼に取られてしまうよ。
石原 そんなもの取られたっていいんです。
三種の神器にいくまでに、三島由紀夫も消去されちうもの。
三島 ああ、消去されちゃう。 おれもいなくていいの、おれなんて大した存在じゃない。
石原 そうですか、それは困ったことだなあ (笑い) ヤケにならなくていいですよ、困ったな。
三島 ヤケじゃないんだ。
石原 三種の神器というのは、ぼくは三島さん自身のことかと思った。
三島 いや、そうじゃない。
石原 やはりぼくは世界のなかに守るものはぼく自身しかないね。
三島 それは君の自我主義でね、いつか目がさめるでしょうよ。
石原 いや、そんなことはない。
三島 そこまで言ってしまってはおしまいだけど、ぼくは日本文化というものを守るということを考える場合に、
何を守ったらいいのかといつも考えてきたのですよ。
歌舞伎やお能というのは、共産社会になったって絶対だいじょうぶですよ。
レニングラード・バレーと同じで、いつまでもだれかが大事にしてくれますよ。
それからお茶だって、お花だって、こんなものは共産社会になっても生き延びますね。
それなら日本文化が生き延びれば、おまえいいじゃないか、と。
法隆寺だろうが、京都のお寺だろうが、いまあんなものをこわす馬鹿な共産社会はないですよ。
皆いい観光資源になっていますから・・・・・・
古典文化というものは大体生き長らえるでしょうね。
最後に生き長らえないものは何かというと、共産社会では天皇制はまず絶対に生き長らえないでしょう。
それからわれわれが毎日書いているという行為は生き長らえないでしょう。
というのは、これから先に手が伸びようとするとき、その手をチェックするでしょうね。
いま生きている手はね。従って、いまわれわれがこうして書いている手と、
天皇制とは、どこか禁断のものという点で共通点があるはずなんです。
生きている手というものと、天皇制というものの関係は何だろうと考えると、
ぼくは天皇制の本質というのを前からいろんなことを言っているんですけど、
文化の全体性というものを保証する最終的根拠であるというふうに言っている。
というのは、天皇制という真ん中に かなめ がなければ、
日本文化というのはどっちへいってしまうかわからないですよ。
昔からそういう性質を持っているんです。
それでこの かなめ があるから、右側へ行ったものは復元力で左側へ来て、
左側へ行ったものは復元力でまた右側へ行く。
中心点にある かなめ が天皇 だというふうに考える。
日本文化というものはいままでどういう扱いを受けてきたかというと、
明治以降日本文化というものは近代主義、西欧主義に完全に毒されて、
その反動が来て日本文化からほとんどエロティックな要素は払拭(フッショク)されちゃった。
戦争中のような儒教的な、ぎりぎりの超国家主義的な日本文化になっちゃった。
今度、逆になってきたら、だらしのないエロティックな日本だけがわっと出てきてしまった。
快楽主義、刹那主義、だらしのなさね。
そのかわり、そのなかに日本文化のいいものももちろん出て来た。
戦争時、禁圧されていたいいものが一ぱい出てきた。
そうすると日本の近代史というのは、文化の全体を保証しないようにいつも動いてきているんですよ。
それじゃアメリカの民主主義ははたして日本の文化の全体を保証したかというと、
たとえば占領軍が来て一番初めに禁止したのは、「忠臣蔵」ですね。
歌舞伎の復讐劇ですね。
それからチャンバラとか、殺伐な侍の芝居を禁止しましたね。
そのとき舟橋聖一らのエロ小説は全部解禁された。
エロティックなことは何を書いてもいいという時代がしばらく続いたでしょう。
そして思想的にもあらゆるものが解放された。
解放されて日本文化が復活したかというと、そうじゃないところがおもしろいんだ。
文化というのはそういう形に置かれたときに、またへんぱなものになっちゃう。
文化の全体性というのはいまないんですよ。
こんなに言論が自由であるように思われるけれども、何も全体性というものがないですよ。
そして文化というものはただだらしのないものになっちゃった。
創造意欲が少しもなくなって、あわれなものになっちゃったんですよ。
するとアメリカ的民主主義というのは、文化としては日本文化の全体性を回復したとは思わない。
やはり一面性だけしか回復しなかったんだと思いますね。
戦時中のああいうものを一面性しか回復しなかった。
おまえの求める文化の全体性というのは、それではいつの時代にそれが実現されたんだというと、
徳川時代もだめだった。
徳川時代は幕府が一所懸命禁圧してだめだった。
それから平安時代は貴族文化だけですからね。
そういうふうにどの時代の政治形態も、政治形態というのは文化の全体性を腐食するような方向にいくんです。
だからぼくは政治はきらいなんです。
政治はきらいですが、ぼくにとって最終的な理念というのは、文化の全体性を保証するような原理
そのためなら命を捨ててもよろしいということをぼくはいつもいっているんです。
保証する原理というのは、この世の地上の政治形態の上にはないですよ。
ですから三派が直接民主主義なんてことを言うと、
どうして日本に天皇があるのに直接民主主義なんてことを言うんだ、ああいうものがあるんだから、
君らの求めるそういう地上にないような政治形態を天皇にもとめればいいじゃないかって言うんですよ。
ぼくは天皇を決して政治体制とは思っていませんけれども、
ぼくは文士ですから、文士というのはいつも全体性の欠如に対して闘う、という理念を持っている。
われわれの書くものが石原さんの言うような自由であるためには、無意識の自由、意識された自由、
政治形態としての自由、何の自由なんてものは問題ではない。
文化が、日本の魂があらゆる形で四方八方へ発揮されなければ・・・・・
次頁
最後に守るべきもの 2 に、続く
前頁
最後に守るべきもの 1 の 続き
男の原理を守る
石原 しかし文化というのはどこの国でもそういうものでしょう。
三島 ええ、でも、日本じゃそういうことはないはずなんです。 天皇がいるから。
石原 いや、だってそれは違うんじゃないかな。
振れ動くものが戻ってくる座標軸みたいなものでしょう、天皇の三種の神器というのは。
だけど、ぼくはやはりそれは違うと思うんだな。
つまり天皇だって、三種の神器だって、他与的なもので、
日本の伝統をつくった精神的なものを含めての風土というものは、
台風が非常に発生しやすくて、太平洋のなかで、日本列島だけが非常に男性的な気象を持っていて、
こんなふうに山があり、河があるということじゃないですか。
ぼくはそれしかないと思うな。
そこに人間がいるということだ。
三島 君は風土性しか信じないんだね。
石原 結局そういうところへ戻ってきちゃうんですよ。 それしかない。
三島 戻ってきても、風土性からは文化というのが直接あらわれるわけじゃないよ。
石原 もちろんそうですよ。
天皇とか、三種の神器を座標軸に持ってくるのは簡単だけれども、それだってやはり日本の風土とか、
伝統をつくった素地というものが与えた伝統的の一つでしかなく、一番本質的なものではないんだな。
ただ一つの表象です。
三島 いや、伝統が一つしかないと言うけれど、伝統的にはいろんな多様性があるでしょう。
その多様性がある伝統の九割ぐらいまでは、共産主義だろうが何だろうがほうっておいたっていいんだよ。
僕が伝統主義者であれ何であれば何も闘う必要はない。
これからの世界は、かつてのソビエトみたいな共産主義では長続きしません。
ある程度、伝統文化も包含するでしょう。 たとえば、ぼくがあなたのように単なる伝統保存主義者であり・・・・・
石原 いや、ぼくはそうは言わない。 伝統は別に総て保有しなくてもいい。
いろいろ形で我々が伝統から逃れられないとも思わない。
三島 伝統の多様性というものを守るためには闘う必要はないんだ。
伝統なんかたった一つだけ守ればいいんだ。 絶対守らなきゃああぶないものを守ればいいんだ。
守らなきゃあたいへんなものを。 そうすればほかのものは、たいていだいじょうぶですよ。
石原 そうかなあ。 結局そういうものがあるから、歴史というものはいつも右、左に振れる。
座標軸ははずしたっていいんじゃないんですか。 はずしたほうがかえっていいんじゃないかな。
三島 いやいや、ぼくは君みたいなそんな共和論者じゃない。
石原 そうすると、とらえどころがなくなるというのですか。 しかし風土はあるよ。
三島 文化の統一性と、文化というものの持っているアイデンティテーというものを、全然没却しちゃう、そういうことをしたら。
石原 ああ、そうか。 三島さん、かつての文化論は取り消したんだな。
三島 そうそう (笑い)。 だってアイデンティティーというのは、最終的にアイデンティティーを一つ持っていればいいんだ。
言わば指紋だよ。 君とおれとは別の指紋を持っている。 ナショナリズムでも何でもない。 指紋が違う。
それで文化を守るということは、最終的にアイデンティティーを守ることなんだ。
それ以上のもの、文化全体というか、ほかの守らないでいいものは一ぱいありますよ。
石原 自分をアイデンティファイする対象というのは、
実は自分が意識でとらえ切れなくなっている本質的な自己であって、ぼくはそれしかないと思いますね。
三島 それに名前をつければいい。 その本質的な自己というのは・・・・・・
石原 だからそれは三種の神器じゃないんだ。 もっと、何と言うか、日本列島の気象でもいい。
もっと始原的な存在の形じゃないですか。
三島 つまり全然形のない文化を信じるとすれば、目に見える文化は全部滅ぼしちゃったっていいんですよ、そんなものは。
それからあなたの作品も、ぼくの作品も地上から消え失せて、京都のお寺から何からみんな要らないんですよ。
そしてただ形のないものだけ守っていればいいんですよ。
それは本土決戦の思想なんだよね、そこまで行っちゃえば。 つまり焦土戦術だね。
軍が考えたことはそういうことだったと思うんだ。
つまり国民の魂というものは目に見えないものでいいんだ。
信州に皇室の御行在所 (ゴアンザイショ) とか、いろいろつくっただろうけれど、
これは形だけのことで、軍の当局者にとっては、彼らは焦土戦術をやるつもりだった。
日本は全部滅びても、日本は残るだろう、と
石原さんの考えというのは、最終的に目に見えないものを信ずることによって人間が闘えば、
結局あらゆるものを譲り渡して闘わなければならない、
何かのアイデンティティー、目に見えるものというものを持っていなきゃ、形というものは成立しない。
形が成立しなきゃ、文化というものは成立しない。 文化というのは形だからね。
形というものが文化の本質で、その形にあらわれたものを、そしてそれが最終的なもので、
これを守らなければもうだめだというもの、それだけを考えていればいいと思う。
ほかのことは何も考える必要はないという考えなんだ。
石原 やはり三島さんのなかに三島さん以外の人がいるんですね。
三島 そうです、もちろんですよ。
石原 ぼくにはそれがいけないんだ。
三島 あなたのほうが自我意識が強いんですよ (笑い)
石原 そりゃア、もちろんそうです。 ぼくはぼくしかないんだもの。 ぼくはやはり守るものはぼくしかないと思う。
三島 身を守るということは卑しい思想だよ。
石原 守るのじゃない、示すのだ。 かけがえない自分を時のすべてに対立させて。
三島 絶対、自己放棄に達しない思想というものは卑しい思想だ。
石原 身を守るということが ? ・・・・・。 ぼくは違うと思う。
三島 そういうの、ぼくは非常にきらいなんだ。
石原 自分の存在ほど高貴なものはないじゃないですか。 かけがえのない価値だって自分しかない。
三島 そんなことはない。
石原 風土も伝統もけっこうだけど、それを受け継ぐ者がいる。
それがなけりゃ、そんなものあったって仕方がない。
ぼくがとても好きなマルロオの言葉に 「 死などない、おれだけ死んでいく 」、
ぼくの存在がなくなったときに何ものもが終焉していい。
自分の書いてきたものもその時点でなくたっていい。
結局、自分が示して守るものというのは、
自分の全存在つまり時間的な存在、精神的な存在、空間的な存在、生理的な存在、それしかない。
それを守るということは、それを発揚するということです。
三島 だけど君、人間が実際、決死の行動をするには、
自分が一番大事にしているものを投げ捨てるということでなきゃ、決死の行動はできないよ。
君の行動原理からは決して行動は出てこないよ。
石原 そんなことはない。 守るというのは 「 在らしめる 」 ということ。
そのためには自ら死ぬ場合だってある。
三島 それじゃ現実に・・・・
石原 献身、奉仕だってある。 自分に対する献身もあるでしょう。
三島 それは自己矛盾じゃアないか。
自分に対する奉仕のために自己放棄するなんてばかなやつは世のなかで聞いたことがない。
石原 いや、そうですよ。 はっきりありますよ。 他者というのはぼくの内にしかないんだもの。
三島 君の自己放棄というのは自分のために自己放棄して・・・・・・
石原 ぼくのなかにある他者というもの・・・・・・
たとえばこの間もテレビへ出て、何のために政治をやりましたか、
ぼくのためにやりましたっていったら、すぐ主婦が、「 エゴイズムですか 」
「 そのとおりエゴイズムです 」 って言ったら、「 私はあの人に一票を投じて惜しかった 」
と朝日新聞に投書をして、朝日新聞がまたそれを得々として載せた。
どうせわからんだろうと思ったけど、あえて言ったんだ。
何もぼくは自分の政治参加を雄々しい (オオシイ) なんて思っていませんよ。
しかしそこにある一つの犠牲みたいなものがあっても、それはぼくのうちに在るもの、
つまり友人があったり、家族があったり、民族があったり、国家があるわけでしょう。
そのためにしたんだ。
しかしそんなものはぼくの存在が終わったら全部なくなっちゃうね。
しかしそれが伝統になるんだ。
三島 それじゃ君、同じことを言っているんじゃないか。
つまり君の内部にそういう他者を信じるか、外部に他者を信じるかの差に過ぎないでしょう。
石原 ぼくは内部にしか信じない。
三島 他者というものは内部にいるか、外部にいるか、どっちかだって君は言うわけでしょう。
君は内部に他者を置いて、その他者にディボーションするんでしょう。
そういうものは君のなかにある他者なんで、だれが一体そんなものを信じるんだ。
石原 それは信じらんでしょうね、僕以外。 大体ぼくは人間が他人を信じるなんて信じられないな。
三島 君は絶対、単独行動以外できないでしょう。
石原 そう思います。だから派閥をつくれって言われても人間を信じては派閥なんかつくれない。
三島 絶対の単独行動でどうして政治をやるんですか。
石原 だからそこはとても自己矛盾でね。
しかし、やはりそこで我を折り、複数の行動をすることも自己犠牲の奉仕でしょう。
しかし数というのは、外づらの問題だ。
三島 もうすでに君は何かの形でディボーションやっているんだ。
意識しないディボーションをやっているんだ。
石原 そりゃ意識していますよ。
三島 あまり意識家でもないけどな。
石原 それは江藤淳が言うことだ (笑い) ぼくはこのごろ三島さんなんかより意識家になった。
三島 だんだん逆になって来たな。しかしぼくはやはりサクリファイスということを考えるね。
一番自分が大事に思っているものは大事じゃないんだ、と。
石原 じゃ同じことを言っているわけです。ぼくだってやはり自分をサクリファイスしていると思うんだ。
ぼくが思わなくても他人がそう思うでしょう。
三島 少なくとも君が政治をやるというのもサクリファイスだよ。
石原 そりゃそうだな。 自分で言うことじゃないけれど。
三島 文学というものは絶対的に卑怯なもので、
文学だけやっていればセルフ・サクリファイスというものはないんですよ。
人をサクリファイスすることはできても。
石原 ぼくもそう思う。 ぼくも三島さんが言ったと同じことを、あるところに書いた。
男とは何か。 ぼくはやはり自己犠牲だと思う。そこにしか美しさはないんじゃないか。
だから小説家というのは全然雄々しくないって。
三島 そのとおりだな。 小説家で雄々しかったらウソですよ。
小説家というのは一番女々しいんだ。
生き延びて、生き延びて、どんな恥をさらしても生き延びる のが小説家ですね。
文学というのは絶対雄々しくない。
文学だけで雄々しいポーズをしてみてもしようがないんだ。
ウソをつかなきゃならない。
石原 いま三島由紀夫における大きな分岐点は、非常に先天的と思ったもの、
肉体というものが後天的に開発できるということを悟ってしまったことだな。
三島 そうなんだ。 それはたいへんな発見だ。
石原 三島さんはやっと男としての自覚を持ったと思うんだ。
それは、三島由紀夫が三島由紀夫になるよりあとに持ったんだな。
それで非常に大きな変化が三島さんにきて・・・・・・
三島 困っちゃったんだ (笑い)
石原 さっきも居合抜きを見せてくれたけど、(笑い)
筋肉がくっついて三島さん、ほんとに困ったと思う ?
三島 困っちゃったんだよ。
石原 いまさら女々しくな れないでしょう。
三島 いまさらなれない。
そうかといって文学は毎日毎日おれに取りついて女々しさを要求しているわけだ。
それでしようがない、おれの結論としては、文学が要求する女々しさは取っておいて、
そのほか自分が逃げたくても逃げられないところの緊張を生活の糧にしていくよりほかなくなっちゃったね。
もし運動家になり、政治運動だけの人間になれば、解決は一応つくんだけれども。
石原 「 楯の会 」では、まだクーデターはできない。 そこに悩みがある。
三島 しかしまだ自民党代議士、石原慎太郎も大したことはないし、
まだまだおれも先があると思っている (笑い)
石原 いまの反論はちょっと弱々しかった (笑い) しかしほんとにぼくは思うな。
三島さんのテンパラメントというのは、最初から肉体を持っていたら・・・・・・(笑い)
三島 別のほうに行ってたんだよ。
石原 行っていたね。
三島 だけど、いまさらどっちもね。 こまっちゃったんだ。
石原 そして自分で効率よく自分を文豪に仕立てた責任もあるしね。
ああいう政治能力をほかに発揮したらどうですか。
三島 また・・・・・・。おれがいつ政治をつかいましたか (笑い)
石原 しかし、その筋肉の行き場所がないというのは困りますね。
三島 困りますね、ほんとに。 小説を書くのにこんなもの全然要らないんですからね。
困っちゃうね (笑い)
石原 だけど三島さん、個人の暴力の尊厳というものをいまの学生というのは知らないですね。
三島 そうだね。 ほんとに集団にならなきゃ何もできない。 個人は弱者だと思っている。
石原 彼らによって守らなくちゃならないものに個人がないんだ。
ぼくはときどき言うんだけれども、行すがるときにいきなりつばをはきかけられて、
とがめて顔をふいてもらってもどうにもならんでしょう。
やはりなぐるか、切るかしなければいけない。
そういう行動に出ると、暴力はやめて下さいということになる。
しかしその場合に暴力でなかったら守れないものがある。
三島 そりゃそうですよ。 そのときはやる。
石原 現代社会には名誉というものがないと思うな。
三島 それを守らなくちゃ名誉はないわけだが、しかしそれは自分を守るということと別じゃないかな。
つまり男を守るんだろう。
石原 結局、自分を守ることじゃないですか。
三島 それは、ある原理を守ることだろう。
石原 男の原理。 現代では通用しなくなった男の原理。
三島 男というのは動物ではない、原理ですよ。
普通男というと動物だと思っているんだ。 女から言うと、男ってペニスですからね。
あの人、大きいとか、小さいとか、それは女から見た男で、女から見た男を、
いまの世間は大体男だと思っているんだろうがね。
ところが、男というのはまったく原理で、女は原理じゃない、女は存在だからね。
男はしょっちゅう原理を守らなくちゃならないでしょう。
その原理というものは、石原さんが言うように自分だとぼくは思わないですよ。
自分ならそんな辛い思いをして原理を守る必要はない。
自分を大事にするんだったら、つばをはきかけられても、
なるだけけんかなんかしないでそっとしておいて、かかわりあいにならないで、
そばで人が殺されそうになっても、警察に調書を取られるのはたいへんだから、
そっと見ないで帰りましょうというほうが、よほど生きるのは楽ですよ。
だけどそこで原理を守らなければならないのが男でしょう。
石原 しかし原理はだれのなかにあるんですか。
やはり自分のなかにしかないでしょう。 実は自分に方が先にあるんです。
三島 自分のなかにしかないけれども、男という原理は内発的なものでもあると同時に、
最終的には他人が見ていてみっともないからですよ。
石原 そうかな。 ぼくは人がいないところでもなぐるな。 三島さんだってそうだと思う。
人がいないときに何かやられたら、やはり刀を抜くでしょう。
三島 そりゃそうだ。
石原 この前の対談で雑誌社の人間がいなかったら、いいだもも を切ればよかった (笑い)
三島 刀のけがれになるよ、あんなの切ったら・・・・・・。これちゃんと速記しておいて下さいね (笑い)
石原 これ遠吠え、遠吠え。
三島 あの人は口から先に生れたんだ。
石原 全く口から先に生れた (笑い)
三島 どうにもならんですよ。 生れてオギャーという前に共産党宣言か何か叫んだんじゃないかね。
ところで、われわれは左翼に対してごちそうを出し過ぎていますよ。
みんな食べられてしまう。
われわれが一所懸命つくった料理を出すと、みんな食べられちゃうんです。
カラスが窓からはいってきてみんな食っちゃう。
左翼に食べられちゃったものは、
第一がナショナリズム、第二が反資本主義、第三が反体制的行動だと思うんだ。
この三つを取られてしまうと困っちゃうんだ。
四つ目のごちそうはまだとられていない。 天皇制ですね、ここにおいてどうするんです。
石原 それはたいへんな深謀遠慮ですな (笑い)
三島 なぜ ? ここにおいてどうするんですか。
石原 そりゃラオスにもシヤヌークやプーマ殿下なんているからね。
三島 いるけれども、日本はラオスまではいかんと思うんだ。ぼくはそういう考えですよ。
ですからこのギリギリの一戦、これは丸薬なんです。 苦い薬なんです。
だからみんななかなか飲みたがらない。
石原さんなんかさっきから飲みたがらないでじたばたしているでしょう。
石原 いや、そんなことはない。
三島 これを飲むか飲まないかという問題で闘うんじゃないです。
ごちそうはみんな食われちゃった。 甘い味がつけてありますからね。
石原 それはちょっと違うな。 それほどごちそうじゃないな。
三島 ほかのものだよ。 ほかの三つのものはごちそうだ。
それで最後に丸薬だけ取ってあるんだ。 これは天皇だ。
この丸薬はカラスは食わないですよ。 食えと言ったって食わないんだ。
なぜかと言うとカラスは利口だからね。 この丸薬を食ったら、カラスがハトになるかもしれない。
たいへんなことになる。 カラスがカラスでありたいためには、それを食わんでしょう。
だからぼくは丸薬をじっと持っているんです。
もう、どう言われてもこの丸薬を持っている。
これは味方うちも、敵も、なかなか飲みたがらない丸薬です。
どうでも、どうでも・・・・・・。
石原 三島さんのように天皇を座標軸として持っている日本人というのは、
とても少なくなってきちゃったんじゃないかしら。
三島 君、そう思っているだろう。
だけどこれから近代化がどんどん進んでポスト・イシダストリアゼーションの時代がくると、
最終的にはそこへ戻ってくるよ。
石原 戻るのはいいけれど、天皇をだれにしようかということになるんじゃないかな。
三島 いやいや、そんなことはない。 明治維新にはそんなことを考えたんだ。
たとえば伊藤博文も外国へ行く船のなかで、共和制にしようかって本気に考えたんだ。
ところが日本に帰ってきてまた考えなおしたんだね。
竹内好なんかは君と違って、もっとずっと先を見ているよ。
コンピューター時代の天皇制というのはあるだろう、それがおそろしいっていう。
ポスト ・インダストリアゼーションのときに、日本というものも本性を露呈するんじゃなかろうか。
いまは全く西洋と同じで均一化していますね。
だけどこいつを十分取り入れ、取り入れ、ぎりぎりまで取り入れていった先に、
日本に何が残っているというと天皇が出てくる。 それを竹内好は非常におそれているんですよ。
非常に洞察力があると思いますね。
石原 それはそうじゃアないな。 竹内好のなかに前世代的心情と風土があるだけです。
三島 その風土が天皇なんだよ。
石原 そうじゃない。 それはただ時代とともに、それが変っているんだな。
三島 ぼくは変ってきているとは思わない。 ぼくは日本人ってそんなに変わるとは思わない。
石原 ぼくのいうのは、つまり天皇は自分の風土が与えた他与的なものでしかないということで、
風土は変らんですよ。 われわれの本質的な伝統というものは変らないけど、
天皇というものは伝統の本質じゃないもの 形でしょう。
三島 だけど君、どうしてないなんていうの。 歴史、研究したか。 神話を研究したか。(憤然と怒る)
石原 しかし歴史というものの骨格が変ってきているじゃないですか。
日本の歴史の特異点は、日本にとって、いつも海を隔てた大陸から来るメッセージというものがある。
しかしそれは必ずしも系統だってない。
たとえば仏教。それを濾過することで日本文化はできてきたんでしょう。
政治の形は、そんな文化造形の前からあったが、しかしその規制は受けた。
天皇制が文化のすべてを規制したことは絶対にない。
いずれにしても日本の伝統の本質的条件がつくったものの一つでしかないと思うな、天皇は。
三島 それはもう見解の相違で、どうしようもないな。
つまりぼくは文化というものの中心が天皇というもので、天皇というのは文化をサポートして、
あるいは文化の一つの体現だったというふうに考えるんだから。
石原 文化というのは中心があるんですか。
三島 必ずあるんだ。 君、リシュリーの時代、見てごらん。
石原 いや、中心はあるけど、その中心というのはあっちへ行ったり、こっちへ行ったりするんだなあ。
三島 それじゃリシュリーの時代の古典文化、ルイ王朝の古典文化というものは秩序ですよね。
そして言語表現というのは秩序ですよ。
その秩序が、言語表現の最終的な基本が、日本では宮廷だったんです。
石原 だけど、その秩序は変ったんじゃないですか。
三島 いくら変ってもその言語表現の最終的な保証はそこにしかないんですよ。
どんなに変っても・・・・・・
石原 そこにしかないってどこですか。
三島 皇室にしかないんですよ。
ぼくは日本の文化というものの一番の古典主義の絶頂は 「 古今和歌集 」 だという考えだ。
これは普通の学者の通説と違うんだけどね。
ことばが完全に秩序立てられて、文化のエッセンスがあそこにあるという考えなんです。
あそこに日本語のエッセンスが全部できているんです。
そこから日本語というのは何百年、何千年たっても一歩も出ようとしないでしょう。
一つも出てないですね。
あとのどんな俗語を使おうが、現代語を使おうが、あれがことばの古典的な規範なんですよ。
天皇制への反逆
石原 三島さん、変な質問をしますけど、日本では共和制はあり得ないですか。
三島 あり得ないって、そうさせてはいけないでしょう。
あなたが共和制を主張したら、おれはあなたを殺す。
石原 いや、そんなことを言わずに (笑い) もうちょっと歩み寄って、その丸薬、ぼくは飲めない。
三島
きょうは幸い、刀を持っている。
(居合い抜きの稽古の帰りで、三島氏は真剣を持参していた)
石原 はぐらかさないで、つまり、日本にたとえば共和制がありえたとしたら、
日本の風土とか、伝統というのはなくなりますか。
三島 なくならないと言ったでしょう。
伝統は共産主義になってもなくならないと言ったじゃないですか。
石原 それをつくったもっと基本的な条件はなくなりませんか。
三島 なくなります。
石原 ぼくはそうは思わない。
三島 絶対なくなる。
石原 それはもっと土俗的なもので、
土俗的ということもちょっと夾雑物が多過ぎるけれど、本質的なものはなくならないと思いますね。
ぼくは何も共和制を一度だって考えたことはないですよ。
三島 そりゃまあ命が惜しいだろうからそう言うだろうけど。
石原 ぼくだって飛び道具を持っているからな。
三島 そこに持っていないだろう。
石原 あなたみたいにナイフなんか持ち歩かない。
三島 だけど文化は、代替可能なものを基礎にした文化というのは、
西洋だよ、あるいわ中国だよ。
日本はもう文化が代替可能でないということが日本文化の本質だ、
というふうにぼくは既定するんだ。
だから共和制になったら、代替というものがポンと出てくる。
代でかわることだよ。
共和制になったら日本の文化はない。
石原 つまりシステムというのはほんとに仮象でしかないね。
三島 仮象でいいじゃないか。
だって君、政治が第一、みんな仮象であるということもよくわかっているんだろ。
石原 よくわかっていますよ。 だけどやはりそのなかにはぼくがいるんだもの。
これは、ぼくは実像ですよ。
三島 もう半分仮象になりかかっているじゃないか。
石原 そんなことないよ (笑い) そういう言いがかりはけしからんな (笑い)
三島 いまのは訂正しましょう。
しかしぼくも依怙地ですからね、言い出したらきかないです。
いつまでもがんばるつもりです。
石原 何をがんばるんですか。 三種の神器ですか。
三島 ええ、三種の神器です。
ぼくは天皇というものをパーソナルにつくっちゃたことが一番いけないと思うんです。
戦後の人間天皇制が一番いかんと思うのは、
みんなが天皇をパーソナルな存在にしちゃったからです。
石原 そうです。 昔みたいにちっとも神秘的じないもの。
三島 天皇というのはパーソナルじゃないんですよ。
それを何か間違えて、いまの天皇はりっぱな方だから、おかげでもって終戦ができたんだ、
と、そういうふうにして人間天皇を形成してきた。
そしてヴァイニングなんてあやしげなアメリカの欲求不満女を連れてきて、
あとやったことは毎週の週刊誌を見ては、宮内庁あたりが、
まあ、今週も美智子様出ておられる、
と喜んでいるような天皇制にしちったでしょう。
これは天皇をパーソナルにするということの、天皇制に対する反逆ですよ。
逆臣だと思う。
石原 ぼくもまったくそう思う。
三島 それで天皇制の本質というものが誤られてしまった。
だから石原さんみたいな、つまり非常に無垢ではあるけれども、天皇制反対論者をつくっちゃった。
石原 ぼくは反対じゃない、幻滅したの。
三島 幻滅論者というのは、つまりパーソナルにしちゃったから幻滅したんですよ。
石原 でもぼくは天皇を最後に守るべきものと思ってないんでね。
三島 思ってなきゃしようがない。 いまに目がさめるだろう(笑い)
石原 いやいや。 やはり真剣対飛び道具になるんじゃないかしら (笑い)
しかしぼくは少なくとも和室のなかだったら、僕は鉄扇で、三島さんの居合いを防ぐ自信を持ったな。
三島 やりましょう、和室でね。
でも、とおれと二人死んだら、さぞ世間はせいせいするだろう (笑い)
喜ぶ人が一ぱいいる。 早く死んじゃったほうがいい。
石原 考えただけでも死ねないね。
『 尚武のこころ 』
三島由紀夫対談集 「 守るべきものの価値 」
われわれは何を選択するか
石原慎太郎 (作家・参議院議員) 月刊ペン 昭和44年11月号
・
昭和49年 (1974年 ) 8月8日
二十歳の私が購読したものである
病死は自然死であり、自然の摂理であるが、
自発的な死は人間の意思にかかわることなのである。
そして人間の自由意思の極致に、死への自由意思を置くならば、自由意思とは何か。
それは、行動的な死(斬り死)と自殺(切腹)とを同列に置く日本独特の考へ方であり、
切腹という積極的な自殺は、西洋の自殺のように敗北ではなく、
名誉を守るための自由意思の極限的なあらわれである。
「死とは」、このような、選択可能な行為なのであり、どんなに強いられた状況であっても、
死の選択によってその束縛を突破するときは、自由の行為となるのである。
死=選択=自由という図式は、武士道の理想的な図式である。
吾々は西洋から、あらゆる生の哲学を学んだ。
然し、生の哲学たけでは、われわれは最終的に満足することはできなかった。
亦、仏教の教えるような輪廻転生の、永久に生へまた帰ってくるような、
やりきれない罪に汚染された哲学をも、吾々は親しく自分のものとすることができなかった。
神風特攻隊は、最も非人間的な攻撃方法と謂われ、
戦後、それによって死んだ青年たちは、長らく犬死の汚名を蒙っていた。
然し、国の為に確実な死へ向って身を投げかけたその青年たちの精神は、
それぞれの心の中に分け入れば、いろいろな悩みや苦しみがあったに相違ないが、
日本の一つながりの伝統の中に置く時に、
『葉隠』 の明快な行動と死の理想に、最も完全に近づいている。
人は敢えて言うであろう。
特攻隊は、いかなる美名におおわれているとはいえ、強いられた死であった。
そして学業半ばに青年たちが、国家権力に強いられて無理矢理に死へ追いたてられ、
志願と謂いながら、ほとんど強制と同様な方法で、
確実な死の決っている攻撃へ駆り立てられて行ったのだと・・・・・。
それは確かにそうである。
・
人間は死を完全に選ぶこともできなければ、亦死を完全に強いられることもできない。
たとえ、強いられた死として極端な死刑の場合でも、
精神を以てそれに抵抗しようとするときには、それは単なる強いられた死ではなくなるのである。
亦、原子爆弾の死でさえも、あのような圧倒的な強いられた死も、
一個人一個人にとっては運命としての死であった。
吾々は、運命と自分の選択との間に、ぎりぎりに追い詰められた形でしか、死に直面することができないのである。
そして死の形態には、その人間的選択と超人間的運命との暗々裏の相剋が、永久に纏わりついている。
ある場合には完全に自分の選んだ死とも見えるであろう。
自殺がそうである。
ある場合には、完全に強いられた死とも見えるであろう。
たとえば空襲の爆死がそうである。
然し、自由意思の極致のあらわれと見られる自殺にも、その死へいたる不可避性には、
ついに自分で選んで選び得なかった宿命の因子が働いている。
亦、単なる自然死のように見える病死ですら、
そこの病死に運んでいく経過には、自殺に似た、自ら選んだ死であるかのように想われる場合が、けっして少なくない。
『葉隠』 の暗示する死の決断は、いつも吾々に明快な形で与えられているわけではない。
目の前に敵が現れ、それと戦い、そして自分が死ぬか生きるかという決断を自分で下して死ぬという状況は、
たとえ、まだ日本刀以上の武器がなかった時代でも、いつも簡単に与えられていたものではない。
すなわち、『葉隠』にしろ、特攻隊にしろ、一方が選んだ死であり、一方が強いられた死だと、
厳密に謂う権利はだれにも無いわけなのである。
問題は一個人が死に直面するというときの冷厳な事実であり、
死にいかに対処するかという人間の精神の最高の緊張の姿は、どうあるべきかという問題である。
そこで、吾々は死についての、最もむずかしい問題にぶつからざるを得ない。
吾々にとって、最も正しい死、吾々にとって自ら選び得る、正しい目的にそうた死というものは、
はたして有るのであろうか。
今 若い人たちに聞くと、ベトナム戦争のような誤った目的の戦争の為には死にたくないが、
若し 正しい国家目的と人類を救う正しい理念のもとに強いられた死ならば、
喜んで死のうという人達がたくさんいる。
これは戦後の教育の所為もあるが、
戦争中誤った国家目的のために死んだ過ちを繰り返すまいという考えが生れて、
今度こそは自ら正しいと認めた目的の為以外には死ぬまいという教育が普及した所為だと思われる。
然し、人間が国家の中で生を営む以上、
そのような正しい目的だけに向かって自分を限定することができるであろうか。
亦由し 国家を前提にしなくても、全く国家を超越した個人として生きるときに、
自分一人の力で人類の完全に正しい目的の為に死というものが、選び取れる機会があるであろうか。
そこでは死という絶対の観念と、正義という地上の現実の観念との齟齬が、いつも生ぜざるを得ない。
そして死を規定するとその目的の正しさは、
亦歴史によって十年後、数十年後、あるいは百年後、二百年後には、逆転し訂正されるかもしれないのである。
『葉隠』 は、このような煩瑣(はんさ)な、
そして さかしらな人間の判断を、死とは別々に置いていくということを考えている。
なぜなら、吾々は死を最終的に選ぶことはできないからである。
だからこそ『葉隠』は、生きる可死ぬかというときに、死ぬことを勧めているのである。
それは決して死を選ぶことだとは言っていない。
なぜならば、吾々にはその死を選ぶ基準が無いからである。
吾々が生きているということは、すでに何ものかに選ばれていたかも知れないし、
生が自ら選んだものでない以上、死も自ら最終的に選ぶことができないかも知れない。
では、生きて入る者が死と直面するとは何であろうか。
『葉隠』 はこの場合に、ただ行動の純粋性を提示して、情熱の高さとその力を肯定して、
それによって生じた死は全て肯定している。
それを『犬死などと謂ふことは、上方風の打ち上りたる武士道』だと呼んでいる。
死について 『葉隠』の最も重要な一節である 『武士道と謂ふは、死ぬ事と見付けたり』 という文句は、
このような生と死の不思議な敵対関係、永久に解けない矛盾の結び目を、一刀を以て切断したものである。
『図に当らぬは犬死などと謂ふ事は、上方風の打ち上りたる武士道なるべし。
二つ二つの場にて、図に当ることの解ることは、及ばざることなり。』
図に当るとは、現代の言葉で謂えば、正しい目的の為に正しく死ぬと謂うことである。
その正しい目的ということは、死ぬ場合には決して判らないということを 『葉隠』 は言っている。
『我人、生くる方がすきなり。多分すきの方に理が付くべし』、
生きている人間にいつも理屈がつくのである。
そして生きて入る人間は、自分が生きているという事の為に、何らかの理論を発明しなければならないのである。
随って、『葉隠』 は、図にはずれて生きて腰抜けになるよりも、図にはずれて死んだほうがまだいいという、
相対的な考え方をしか示していない。
『葉隠』 は、決して死ぬことが必ず図にはずれないとは言っていないのである。
ここに『葉隠』のニヒリズムがあり、亦、そのニヒリズムから生まれたぎりぎりの理想主義がある。
吾々は、一つの思想や理論のために死ねるという錯覚に、いつも陥りたがる。
然し 『葉隠』が示しているのは、最も容赦ない死であり、花も実もない無駄な犬死さえも、
人間の死としての尊厳を持っているということを主張しているのである。
若し、吾々が生の尊厳をそれほど重んじるならば、どうして死の尊厳をも重んじない訳にいくであろうか。
いかなる死も、それを犬死と呼ぶことはできないのである。

・・・『葉隠入門』は、昭和42年(1967年)に書かれたもの
現代文化の特徴は、
従来まで人々を人生に向かって鼓舞していた様々な理想、規範、思想・・が悉く潰え去ったことであろう
嘗てモラルの基礎をなしていた絶対の観念が失われ、
人間は全ての意匠を剥ぎとられた等身大の、赤裸かの、即物的自然的な生命に直面することを強いられている
これが、現代社会を侵している救いがたいニヒリズムの原因であろう
人生いかに生くべきか、
と謂う 曾ての求道的倫理的な問題は、
今では 日進月歩する科学的な生活改良や健康法や姑息な処世の技術や、
要するに瑣末(さまつ)な日常生活への関心にとって代わられた
現代は博学多識と、細分化された「ハウツウもの」の全盛時代である
「吾々は西洋から、あらゆる生の哲学を学んだ」
然し 生活自体への関心は、つまるところ 利殖と保身と享楽の追究におわる
与えられた「生の哲学」によって十全に人間性の自然を開放し、
富益を求め、奢侈(しゃし)と飽食と放埓(ほうらつ)に身をゆだねたのちに、
やがては等しく老衰と死にきわまる運命にさだめられている
生とはついに死に到る不治の病だとすれば、病んでいるのは「生の哲学」そのものだ、
と いえないことはない
民族、国家、社会など、ある共同体が他文化の侵蝕を受けると、
人々の生活の支柱をなしていた掟(おきて)や慣習がすたれ、道徳的精神的に荒廃して、
その共同体は徐々に崩壊、解体してゆくことが知られている
生の充実にどれほど力を注ごうと、生それ自身の自壊作用をくいとめる手立てはありえない
・・田中美代子 同書解説、から
いま
われわれにとって
『サムライ』 は
われわれの父祖の姿であるが、
西洋人にとっては、
いわゆるノーブル・サヴェッジ(高貴なる野蛮人)のイメージでもあろう
われわれはもっと野蛮人であることを誇りにすべきである
・
『サムライ』といえば、
われわれはすぐ勇気ということを考える
勇気とは何であろうか
また勇者とは何であろうか

( 金嬉老事件 昭和43年(1968年) 2月2日 )
この間の金嬉老事件で
私がもっともびっくりぎょうてんしたのは、
金嬉老、及びそのまわりに引き起された世間のパニックではなかった
それは金嬉老の人質の中の数人の二十代初期の青年たちのことであった
彼らはまぎれもない日本人であり、
二十何歳の血気盛んな年ごろであり、
西洋人から見ればまさに 『サムライ』 であるべきはずが、
ついに四日間にわたって、
金嬉老がふろに入っていても手だし一つできなかった
われわれはかすり傷も負いたくないという時代に生きているので、
そのかすり傷も負いたくないという時代と世論を逆用した金嬉老は、
実にあっぱれな役者であった
そしてこちら側にはかすり傷も負いたくない日本青年が、
四人の代表をそこへ送り出していたのである
今は昭和元禄などといわれているが、
元禄の腰抜武士のことを
大道寺有山の 『武道初心集』 はこんな風に書いている
すなわち「不勇者」は、何でもかんでも気随気ままが第一で、
朝寝、昼寝を好んで、学問はきらい
武芸----いまでいえばスポーツだろうが、
スポーツをやっていても何一つものにならず、
ものにならないくせに芸自慢のりこうぶりばかりをして、
女狂いやぜいたくな食事のためには幾らでも金を使い、
大事な書類も質には入れるし、
会社の金で交際費となれば平気で使い散らし、
義理で出す金は一文も出さず、
またその上からだはこわしがちで、
大食い、大酒の上に 色情にふけっているので、
自分の寿命にやすりをかけるがごとくになって、
すべて忍耐や苦労やつらいことができなくなるような肉体条件になってしまうから、
したがって、柔弱未練の心はますますつのる
これを不勇者----臆病武士と規定している
泰平が続くと、われわれはすぐ戦乱の思い出を忘れてしまい、
非常の事態のときに男がどうあるべきかということを忘れてしまう
金嬉老事件は小さな地方的な事件であるが、
日本もいつかあのような事件の非常に拡大された形で、
われわれ全部が金嬉老の人質と同じ身の上になるかもしれないのである
しかし、それはあくまで観念と空想の上のできごとで、
現実の日本には、なかなかそのような兆候も見られない
そしていまは女の勢力が、すべてを危機感から遠ざけている
危機を考えたくないということは、非常に女性的な思考である
なぜならば、
女は愛し、結婚し、子供を生み、
子供を育てるために平和な巣が必要だからである
平和でありたいという願いは、女の中では生活の必要なのであって、
その生活の必要のためには、何ものも犠牲にされてよいのだ
しかし、それは男の思考ではない
危機に備えるのが男であって、
女の平和を脅かす危機が来るときに必要なのは男の力であるが、
いまの女性は自分の力で自分の平和を守れるという自信を持ってしまった
それは一つには、男が頼りないということを、
彼女たちがよく見きわめたためでもあり、
彼女たちが勇者というものに一人も会わなくなったためでもあろう
今の日本では、大勢に順応するということは、
戦時体制下のアメリカとちがって、別に徴兵制度を意味しない
何とか世の中をうまく送って、マイホームをつくるために役立つ道を歩むことである
それでは大勢に順応しないということは、何を意味するのであろうか
極端な例が三派全学連であるが、こん棒をふりまわしても破防法はなかなか適用されず、
一日、二日の拘留で問題は片づいてしまう
しかもおまわりさんは機動隊の猛者といえども、
まさかピストルをもって撃ってくる心配はないので、
幾らこちらが勇気をふるって相手をやっつけても、
強い相手が強い力を出さないので、
あしらって一緒に遊んでくれるのである
幼稚園と保母のような関係がそこにあるといえよう
したがって、
いまの日本では勇者が勇者であることを証明する方法もなければ、
不勇者が不勇者であることを見破られる心配もない
最終的には、勇気は死ぬか生かの決断においてきめられるのだが、
われわれはそのような決断を、人には絶対に見せられないところで生きている
口でもって 「なにのために死ぬ」 と言い、
口で 「命をかける」 ということを言うことはたやすいが、
その口だけか口だけでないかを証明する機会は、
まずいまのところないのである
私は 『武道初心集』 を読みかえすごとに、
現代の若い 『サムライ』 が勇者か不勇者かを見る区別は、
もっと別のところに見なければなるまいと思う
それは何であろうか
それは非常事態と平常の事態とを、
いつもまっすぐに貫いている一つの行動倫理である
危機というものを、心の中に持ち、その危機のために、
毎日毎日の日常生活を律してゆくという
男性の根本的な生活に帰ることである
男性が平和に生存理由を見出すときには、
男のやることよりも女のやることを手伝わなければならない
危機というものが
男性に与えられた一つの観念的役割であるならば、
男の生活、
男の肉体は、
それに向かって
絶えず振りしぼられた弓のように緊張していなければならない
私は町に、緊張を欠いた目をあまりに多く見過ぎるような気がする
しかし、それもわたしの取り越し苦労かもしれない
若きサムライのために
昭和44年(1969年) から
東京のある一流ホテルの経営者の妹さんで、戦前から上流社会で鳴らした婦人は、
外国生活が長いところからレディー・ファーストをあらゆる男に要求している
彼女はそのホテルの中の日本料理を食べたときに、
日本料理の座敷でありながら、
彼女自身、床の間の前にでんとすわり、
料理が自分の前に一番先に運ばれてこないのに憤慨した
このホテルはレディー・ファーストで統一しているのに、
どうして日本料理に限って男から先に出さなければいけないのか
これが彼女の深刻な疑問であった
そこで彼女はたちまちホテルに向って、
日本料理といえどもその席に女性がいれば、
女性に一番先に皿を運ばなければならないと厳命を下した
まず私の知る限り、
日本料理で女の前に一番先に皿が運ばれるのは、このホテルだけである
・
日本の女性は伝統に対して受身であったので、
自ら伝統を守るという役割を果してきたことがなかった
それが現在の礼法にまで微妙な影響を及ぼしていると思われる
もし、女性がほんとうに主体的であれば、
主体的に伝統を守るという考えがどうして生じないのであろうか
伝統は守らなければ自然に破壊され、そして二度とまた戻ってはこない
男は伝統の意味を知っているから、
ある意味で主体的にいつも伝統を守る側に立ち、
自らその伝統をよしとし、
あるいは悪いと思っても伝統を守らなければならないという、強い義務感を感じていた
それが日本の男性を必要以上に保守的に見せていた原因であると思う
しかし、いつも女性はこの男性に対して、
伝統を破壊するという方向にのみ、自分の開放の根拠を求めた
しかし、ここにはパラドックスがある
もし伝統破壊の行動を続けるならば、
その女性は自分が伝統によって受身に縛られてきたときの態度を、
伝統が破壊されたあとも、そのまま押し通すということになるのである
しかし、何もないところでは、何の行動も基準もあり得ないので、
今度は女性は、
西洋式な伝統のサルマネを始め、それを男性に強要するようになった
その最も端的な例が、最初に話した上流婦人の例であろう
その上流婦人は、日本料理に西洋式礼法を取り入れることによって、
日本料理の味までもまずくしてしまったのである
女性の力ではなく、
アメリカという男性の、占領軍の力によって女性の自由と開放が成就されたとき、
女性は何によって自分の力を証明しようとしたであろうか
それがいわゆる女性の平和運動である
その平和運動はすべて感情を基盤にして、
「 二度と戦争はごめんだ 」
「 愛するわが子を戦場へ送るな 」
という一連のヒステリックな叫びによって貫かれ、
それゆえにどんな論理も寄せつけない力を持った
しかし、女性が論理を寄せつけないことによって力を持つのは、
実はパッシブ領域においてだけなのである
日本の平和運動の欠点は、感情によって人に訴えることがはなはだ強いと同時に、
論理によって前へ進むことがはなはだ弱いという、女性的欠点を露呈した
私はエチケットばかりでなく、平和運動でも、政治運動でも、
ほんとうに開放された自由な主体的な女性ならば、
自分をかつて苦しめた伝統を、
自分がかつてその被害者であったところの伝統を、
もはや被害者になるおそれがない現代において、
そこから新しい意味を見つけ出してそれを再創造し、
世界に向って日本の伝統の美しさを示すような役割を、
自分ですすんで引受けてほしいと思うものである
若きサムライのために
昭和44年(1969年) から
私は、日本では戦後女性の羞恥心が失われた以上に、
男性の羞恥心が失われたことを痛感する
ただ世間の風潮を慨嘆するだけではない
私自身が知らず知らずの間に時代の影響をこうむって、
男の羞恥心を失いつつあるのである
それに気がついたのは妻のお産のときで、
私はいつ生まれるかとヒヤヒヤしながら病院につめ、
いよいよ子供が生まれたときは、
初孫の誕生を父に知らせるため、何度も赤電話をかけながら、
十円玉を入れるのを忘れて、電話が通じなかった
そして、やっと十円玉を入れて電話が通じたとき、
父の思いがけない不機嫌な声に驚かされた
父は少しも初孫の誕生を喜んでいないように思えたのである
あとでわかったことだが、
父は明治生まれの男らしい、実に古風な羞恥心を持っていた
自分の嫁の出産に息子が病院へ行くのさえ、恥ずかしいことであった
病院からあたふたした声で電話をかけてくるのは、
もっと恥ずかしいことであった
妻のお産のときには、
日本の男はおなかの中で心配しながら、友だちと外で飲んで歩くか、
あるいはそしらぬ顔をしているべきであった
それは女にたいする軽蔑とは違って、
むしろ純女性的領域に対するおそれと、
おののきと、遠慮と、反抗から生まれた
男のテレかくしの態度であったと思われる
明治の男は、女と肩を並べて歩くのをいさぎよしとしなかった
世間からでれでれしていると思われないために、
女と必ず離れて歩き、
結婚しても、
妻と並んで歩くのを恥ずかしがる男性はいくらでもいた
・
しかし、このような男性の羞恥心は、あくまでも男らしさとつながっていた
男と女がそれぞれの領域をきちんと守り、心がどんなにひかれていても、
それをまっすぐにあらわさないということが、恋愛の不可欠の要素であったのだ
これは、古い気質の人間のあらゆる感情表現に影響を及ぼし、
わざと嫌いなふりをすることが、愛することの最大の表現と思われていた
・
男女関係自体が、
新しいアメリカ風の、お互いに愛を最大限に表現する形によって、
わざとらしい公明正大さを得てきた
そして女の羞恥心すら、男女同権を破壊するような封建的遺習と考えられ、
その女の羞恥心が薄れるに従って、
男の羞恥心も、ガラスの表にはきかけた息のように、たちまち消え去ってゆき、
そしていつの間にか、かくも露骨に表現し合った男と女は、
お互いの大切な性的表現を失って、
いま言われるような中性化の時代が来たのである
羞恥心は単にセックスの面だけにあらわれるのではない
日本人が人にものをあげるときに、
「ほんの粗末なものですが」
とか、
「まずいものでございますが」
とか言って人に挙げる習慣は、しだいに失われようとしている
アメリカ風な習慣は、一般的になってきた
それは、あたかもわれわれが個人の自由と権利を拡張して生きている時代と見合っている
言論の自由の名のもとに、人々が自分の未熟な、ばからしい言論を大声で主張する世の中は、
自分の言論に対するつつしみ深さというものが忘れられた世の中でもある
人々は、自分の意見----政治的意見ですらも何ら羞恥心を持たずに発言する
戦後の若い人たちが質問に応じて堂々と自分の意見を吐くのを、
大人たちは新しい日本人の姿だと思って喜んでながめているが、それくらいの意見は、
われわれの若い時代にだってあったのである
ただわれわれの若い時代には、言うにいわれぬ羞恥心があって、
自分の若い未熟な言論を大人の前でさらすことが恥ずかしく、
また ためらわれたからであった
そこには、自己顕示の感情と、また同時に自己嫌悪の感情とがまざり合い、
髙い誇りと同時に、
自分を正確に評価しようとするやみ難い欲求とが戦っていた
いまの若い人たちの意見の発表のしかたを見ると、
羞恥心のなさが、反省のなさに通じている
私のところへ葉書が来て、
「 お前は文学者でありながら、
一ページの文章の中に二十幾つかのかなづかいの間違いをしているのは、
なんという無知、無教養であるか さっそく直しなさい 」
という葉書をもらったことがある
この女性は旧かなづかいというものを知らないのみならず、
自分の無知を少しも反省してみようとしないのであった
若きサムライのために
昭和44年(1969年) から
 ・
・
つまりぼくの言っている天皇制というのは、幻の南朝に忠勤を励んでいるので、
いまの北朝じゃないと言ったんだ
戦争が終わったと同時に北朝になった
ぼくは幻の南朝に忠義を尽くしているので、幻の南朝とは何ぞやというと、人に言わせれば、
美的天皇制だ
戦前の八紘一宇の天皇制とは違う
それは何かというと、没我の精神で、ぼくにとっては、国家的エゴイズムを掣肘するファクターだ
現在は、個人的エゴイズムの原理で国民全体が動いているときに、
つまり反エゴイズムの代表として皇室はすべきことがあるんじゃないか、という考えですね
そして、皇室はつらいだろうが、自己犠牲の見本を示すべきだ
そのためには、いまの天皇にもっともっとなさることがあるんじゃないか
そして、天皇というのはアンティ(反)なんだよ
いま、われわれの持っている心理にたいするアンティ、われわれの持っている道徳に対するアンティ、
そういったものを天皇は代表してなければならないから、
それがつまりバランスの中心になる力だというんです
国民のエゴイズムがぐっと前に出れば、それを規制する一番の根本ファクターが天皇だね
そのために、天皇にコントロールする能力がなければならない
そのぼくの考えが既成右翼と違うところだと思うのは、天皇をあらゆる社会構造から抜き取ってしまうんです
抽象化しちゃう考えです
つまりいままでの既成右翼の考えでは、農本主義が崩れたら、天皇は危いですよ
自分が農本主義へ帰って行くことによって天皇に達する、というのはだれでも考えるんですよ
ところが、農地改革が起った後の日本は、昔の日本じゃないです
天皇を支える土地制度というのはないんです
天皇を支える社会制度もなければ、経済制度もなければ何もないんです
そこで、天皇は何ぞや、ということになるんです
ぼくは、工業化はよろしい 都市化、近代化はよろしい、その点はあくまで現実主義です
しかし、これで日本人は満足しているかというと、どこかでフラストレイトしているものがある
その根本が天皇に到達する、という考えなんです
ですから、この一つ一つの線を考えますと、つまり既成右翼的な天皇制というのは、
線の一番はじめのところにあるんです
ぼくは、その線が近代化、都市化、工業化に向ってドンドン進んでいる、
いいよ、いいよ、ドンドンおやり、ゴーゴーも踊るがいい、テレビも見るがいい、
君ながもう自分の家でかまどを使えないなら電子レンジ使うがいい
そうして、ドンドン日本人を進ませる
しかし、ドン尻のところでいつか引き返してくるだろう、というのが天皇制です
天皇はその線の一番手前の端ではなくて、一番向うの端のところにいなければいけないんです
天皇はあらゆる近代化、あらゆる工業化によるフラストレイションの最後の救世主として、
そこにいなければならない
それをいまから準備していなければならない
それはアンティゴイズムであり、アンティ近代化であり、アンティ工業化であるけれど、
決して古き土地制度の復活でもなければ、農本主義でもない
そうすると、農村というものは意味をなさなくなる
その場合でも、天皇は一番極限にいるべきだ、という考えなんです
ですから、近代化の過程のずっと向うに天皇があるという考えですよ
その場合には、つまり天皇というのは、国家のエゴイズム、国民のエゴイズムというものの、
一番反極のところにあるべきだ
そういう意味で、天皇が尊いんだから、天皇が自由を縛られてもしかたがない
その根元にあるのは、とにかく 「お祭」 だ、ということです
天皇がなすべきことは、お祭、お祭、お祭、お祭、----それだけだ
これがぼくの天皇論の概略です
ぼくには非常によくわかるんだ
それが必要だと思うんだけど、その場合に、そうなってくると天皇というのがつらい存在になってくるんです
しかも、生理的には人間ですからね
ある点では、ローマ教皇みたいなことになってくる
「教皇無謬説」というのがあるでしょう ムビュウセツ
しかし、教皇は事実あやまちを犯してきましたよ でも、それは地上教会のあやまちだよ
たとえば、ジャンヌ・ダルクを魔女扱いした
その地上教会のあやまちというのは、後世の同じ地上教会がなおすことができる
あるいは地上教会は永遠に間違いしっぱなしになるかもしれない
でも、それは天上教会によって裁かれる、ということがある
しかし、天皇が天上教会なしの地上教会の最高権威とすると、ボロを出すわけに行かない
天上教会のごとく振舞わなければいけない
そこに非常にむづかしさがあるし、ちょっとでもボロを見せれば、
大正天皇が勅語をまるめてのぞいたというと、もういけないんだ
こういうことをやったら大変なことになっちゃう
天皇が絶対にボロを出さずに済むかというと問題ですね
もう一つは、つらい思いをしてやったにしても、日本の民族の国家エゴイズムの抑制力としてはあっても、
他の国家にとっては、何ものでもない、といあことだね
でも、エリザベスが、亭主が自分の部屋に電話引いたり、テレビつけたり、
ボタンを押すと飛び上がる椅子をつけたりするのに、
エリザベスは、まだ十八世紀のお茶の作法で、
百メートル先から女官たちが手から手へつないだお茶を持って来て、冷えたお茶を飲んでいる
自分の部屋には電話はない
ぼくは、そういうことが天皇制だろうと思うんです
日本の皇室がその点でわれわれを納得させる存在理由は日ましに稀薄になっている
つまりわれわれが近代化の中でこれだけ苦しんで、
どこかでお茶を十八世紀の作法で飲んでいる人がいなければ、世界は崩壊するんだよ
その代り、エリザベス女王は、やっぱりカンベタリー大僧正によって戴冠式を行う
ちゃんと二つに分けてある
ところが、天皇は自分で自分に戴冠しなければならない・
それは、日本の天皇の一番つらいところだよ
同時に神権政治と王権政治が一つのものになっているという形態を守るには、
現代社会で一番人よりつらいことをしなければならない
それを覚悟していただかなければならない、というのがぼくの天皇論だよ
皇太子も覚悟していらっしゃるかどうかを、僕は非常に言いたいことです
いまの皇太子にはむりですよ 天皇も、生物学などやるべきじゃないですよ
やるべきじゃないよ、あんなものは
生物学など下賤の物のやることですよ 政治家がそういうふうにしちゃったんだけど・・・・・・
ただお祭だ
それは大賛成だよ ただ、それが果して世界性を持つかどうかということですね
ぼくは、世界性を持つと思うね
つまり世界の行く果てには、福祉国家の興廃、社会主義国家の噓しかないとなれば、 ウソ
何がほしいだろう それはカソリックならカソリックかもしれない
だけど、日本の天皇というのはいいですよ 頑張ってれば世界的なモデルケースになれると思う
それが八紘一宇だと思うんだよ
ずい分あなたは天皇につらい役割を負わすんだね
井上光晴がいつか言ってたけど、「三島さんは、おれよりも天皇に苛酷なんだね」 と
ぼくのは苛酷だね
あなたなら耐えられるかもしれない(笑)
おれはネクタイも嫌いで家では裸だけど、絶対そうでない人がなきゃ、われわれは生きられないですよ
ぼくは天皇は苛酷な要求するね
それは、戦争が負けて人間宣言をされたあと、日本国民としては天皇を無視するということは、
ある意味で天皇に対する愛情だったんだよ 非常に個人的な愛情だったんだ
ぼくは、そういう個人的な愛情というものじゃないんだ
どうしても、こうして行かなければならない それが一番苛酷な忠義だと思う
愛情じゃなくて忠義だね
ぼくは、それが忠義だと思っている
決して忠義というのはオールド・リベラリストがやっているような、
「陛下はいい方です ニコニコお話をなさって、よく人口問題などまでいろいろ研究なさっていらっしゃる」
というようなものじゃないんだ
ヒューマニズムの忠義じゃないんだ
彼らは、大正文化主義から学んだものを忠義だと思ってゐるんだよ
ぼくが一番に 「二・二六事件」 に共鳴するものはそこですよ
忠義を一番苛酷なものだということを証明しただけで、あの事件はいいです
あとのオールド・リベラリストが何をしようが、有馬頼義が出てきてどんなことを書こうが、
そんなことは構わない
忠義は苛酷なものですよ
それはテロリズムだけじゃないだろうけど、精神の問題ですよ
しかし、天皇も皇太子も、結局 「二・二六」 の本質は理解できないんじゃないか
そういう忠義の本質は理解おできになれないという・・・・・・
片想いですね 忠義というものはそういうものだ
それは 『葉隠』 にもはっきり書いてあるね 実に片想いです
片想いほど、惚れられて厄介なものはないんだ 自分が知らないうちに殺されちゃうかもしれない(笑)
・
忠義は相手の気持ちをわかる必要はないよ
臣下として、相手の気持ちを予測したというのは、逆に不忠だよ
握り飯の熱いのを握って、天皇陛下にむりやり差上げるのが、忠義だと思うんだ
召しあがらなかったらどうする
おわかりでしょう(笑) でも、ぼくは、君主というものの悲劇はそれだと思う
覚悟しない君主というのは君主じゃないと思う
前にも、皇太子の結婚式のときに、石を投げたやつがいる
あのときの皇太子の顔というのをテレビで見たわけだ
つまり王侯が人間的表情を見せるのは、恐怖の瞬間だけで、王侯というものの持っている悲劇を見たね
だけど、しかたのないことでしょう
でも、福田さんだけはわかって下さると思うんだけど、私の考えはファナティシズムから出たんじゃない
現実主義から出て、つまり表現が、比喩がファナティックになるだけで、
決してファナティシズムから栄養はとっていないつもりだな
ぼくはそれはわかるね あなたのは美学だよ
あなたの場合はそうであっても、伝染すればファナティシズムになるでしょう
そうなると、あなた自身が天皇のつらさを味わはされなきゃならない
おれは、握り飯を食わしちゃうほうだから・・・・・・
だけど、エピゴーネンから握り飯を食わされちゃうからね(笑)
吐きだしてるか
吐き出しちゃ、天皇になれないよ(笑) だけど、ある意味で、ある思想のリーダーになったり、
政治運動のリーダーになったりしたら、握り飯を食わなきゃだめですよ
それは 「城山の西郷」 だよ しかたがないですよ
この覚悟が自分じゃついているつもりで、人間というのは実にあやしいものだ
しかし、つくのは最後の五秒間だと思うんだ
ふだんから、「おれは覚悟がある」 と言ったってだめだよ
最後の五秒か十秒の間に勝負がきまる
ふだんの覚悟ならくだらないもので、だれだってできているよ
いつ死んでもいい、殺されてもいいなんてのは・・・・・・ だけど、その場合になると、恐怖を感じてとり乱すよ
そのあとでマナイタの上で平然とできるか、できないかの問題だよ
それで人間がきまる
だから、ふだんから覚悟があるって言っているのは、ちょっとにせものくさい
おおせのとおりだ
(昭和四十二年十一月)・・・若きサムライのために から
・
「 訊くが、
・・・もしだ、もし陛下がお前らの精神 あるひは行動を御嘉納にならなかった場合は、
どうするつもりか 」
「 はい、神風連のやうに、すぐ腹を切ります 」
「 そうか 」
「 それならばだ、もし御嘉納になつたらどうする 」
「 はい、その場合も直ちに腹を切ります 」
「 ほう 」
「 それは又どういうわけだ。説明してみよ 」
「 はい。 忠義とは、私には、自分の手が火傷をするほど熱い飯を握つて、
ただ陛下に差上げたい一心で握り飯を作つて、御前に捧げることだと思ひます。
其結果、もし陛下が御空腹でなく、すげなくお返しになつたり、
あるひは、『 こんな不味いものを喰へるか 』 と 仰言つて、
こちらの顔へ握り飯をぶつけられるやうなことがあつた場合も、
顔に飯粒をつけたまま退下して、ありがたくただちに腹を切らねばなりません。
叉 もし、陛下が御空腹であつて、よろこんでその握り飯を召し上がつても、
直ちに退つて、ありがたく腹を切らねばなりません。
何故なら、草莽そうもうの手を以て直じかに握つた飯を、
大御食おおみけとして奉つた罪は萬死に値ひするからです。
では、握り飯を作つて献上せずに、そのまま 自分の手もとに置いたらどうなりませうか。
飯はやがて腐るに決つてゐます。
これも忠義ではありませうが、私はこれを勇なき忠義と呼びます。
勇気ある忠義とは、死をかへりみず、その一心に作つた握り飯を献上することであります 」
「 罪と知りつつ、さうするのか 」
「 はい。殿下はじめ、軍人の方々はお仕合せです。
陛下の御命令に従つて命を捨てるのが、すなはち軍人の忠義だからであります。
しかし一般の民草の場合、御命令なき忠義はいつでも罪となることを覚悟せねばなりません 」
「 法に従へ、といふことは陛下の御命令ではないのか。裁判所といへども、陛下の裁判所である 」
「 私の申上げる罪とは、法律上の罪ではありません。
聖明が蔽はれてゐるこのやうな世に生きてゐながら、
何もせずに生きて永らへてゐるといふことがまづ第一の罪であります。
その大罪を祓はらふには、瀆とく神の罪を犯してまでも、
何とか熱い握り飯を拵こしらへて献上して、自らの忠心を行為にあらはして、
卽刻 腹を切ることです。
死ねばすべては清められますが、生きてゐるかぎり、右すれば罪、左すれば罪、
どのみち罪を犯してゐることに変りはありません 」
・
三島由紀夫著 奔馬から




























